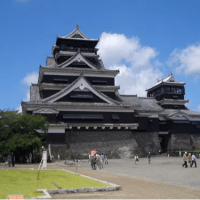動き出したアイデア(原文のまま)
動き出したアイデア(原文のまま)茶道の精神を医療に
「茶道の精神で小児科医療を」という診療姿勢を、たはら小児科医院では掲げている。院内スタッフ全員に茶道の素養がある。院長室は和室にして炉を切り、お茶の道具一式を揃えて、昼休みになると職員のお茶の練習場になる。茶道歴6年の田原正英院長が教えたり、月1回専門の講師を招いて指導してもらう。
「茶道は相手のことを考える思いやりが基本です。そこが医療と同じですが、医療の現場ではなかなか徹底されていないと思います。ドアの閉め方から座り方、話し方、頭の下げ方など、茶道には礼儀作法が凝縮されています」と田原院長。
お茶を点てることで心にゆとりができた。患者さんへの思いやりの気持ちや職員同士のチームワークが強くなった。息抜きにもなる。茶道を取り入れたことは、いろいろな面でメリットがあった。
たはら小児科医院には、畳の部屋の病室が4つある。畳のよいところは、布団を敷いて親子いっしょに寝られること、ベッドを入れたときよりも部屋を広く使えることだ。
「畳の部屋は患者さんの評判は非常にいいのですが、欠点は診察するときの姿勢がちょっときついことです。茶道の作法を生かして、正座して診察していますよ」
たはら小児科医院は、屋根もカーテンも床もスリッパも、お茶をイメージした緑の配色だ。インテリアにも茶道の精神がしみ込んでいる。
(日本アップジョン株式会社発行のSCOPE、1995年4月号より)
この院長室で、日本人以外に、アメリカ人、オーストラリア人、韓国人、ロシア人、ギリシャ人、イタリア人、インドネシア人にも、お茶を点てて差し上げることが出来ました。
又、この自分の茶室の院長室で、現佐伯市医師会長小寺隆先生や、佐伯市に講演で来られた時に、高名な東海大学産婦人科教授の岩崎克彦先生、乳幼児突然死症候群で高名な仁志田博司先生、予防接種で高名な加藤英夫先生に、自分の点てたお茶を差し上げられたことが、今でも、いい思い出になっています。