5月15日文学座アトリエで、ベルトルト・ブレヒト作「肝っ玉おっ母とその子供たち」を見た(訳:岩淵達治、上演台本・演出:西本由香)。

17世紀、ヨーロッパ各国を巻き込んだ30年戦争の戦火の中”肝っ玉おっ母”ことアンナ・フィアリングは三人の子どもたちを連れて
幌車を引いて戦場から戦場へ商売をして暮らしている。
二人の息子は兵隊に取られ、残った娘カトリンとアンナは戦火を潜り抜け逞しく生き抜くが、
平和が訪れれば商売が成り立たず、戦況が悪化すれば逃げ惑う日々。
それでもアンナは幌車を引いていく・・・(チラシより)
谷川道子の翻訳(光文社古典新訳文庫、タイトルは「母アンナの子連れ従軍記」)を読んで臨んだ。
驚いたのは戯曲の充実度。それほど短くはないのに、カットしたくなるような箇所が一つもない。
すべてのセリフが必然性を持ってそこにある。あるべき所に。
その意味で、チェーホフの芝居と似ているかも知れない。
この戯曲は何幕何場ではなく第何景という風に書かれている。
第2景で、アンナ(寺田路恵)が鶏の羽根をむしっている間、コック(上川路啓志)は火を起こし、粉を練って小さいクロワッサンの形みたいなパスタをたくさんこしらえる。
戯曲には書かれていないが、実に興味深い。演出家の面目躍如だ。
第3景で、正直者の次男(武田知久)は軍の会計係になっている。
彼は金庫を預かっており、敵に捕まった後も、それを隠した場所をどうしても言わないので処刑されることになる。
ただ、敵軍の上官に賄賂が効くかも知れないという。
だがアンナは、この切羽詰まった時にも、全財産を差し出すのをためらう。
だって、そうしたら次男の命は助かったとしても、明日から家族全員飢え死にすることになるかも知れないから・・・。
第4景の後、休憩。
第6景のラストでアンナは「戦争はいやだね」と言うが、その後、場面転換なく、すぐに第7景の冒頭のセリフを言う。
そのセリフが「戦争の悪口なんか言わせないよ・・」で、まったく逆のことを口にしている。
演出家はこの2つの場面を意図的につなげている。
第8景で、長男アイリフ(成田次郎)は兵士に連行される。
頭が良くて勇敢な彼は、戦争中、軍隊のための食料を手に入れるために農家を襲い、罪もない農民たちを平気で殺して上官に褒められていた。
だが戦況は刻々と変わり、突然(束の間の)和平が訪れる。
そうなると、前と同じことをすると軍紀違反だということで、今度は処刑されるという。
彼は母親に会いに来るが、あいにくアンナは出かけていていない。
母を待つことも許されない。
彼は最後に酒を一杯飲みたいと言うが、兵士は「そんな時間はない」とすげなく答える。
だがそこに居合わせた従軍牧師(大滝寛)がグラスを手に、もう一人の上官らしい兵士に目で許可を求め、相手がうなづくのを見て
アイリフの口にグラスを当ててワインを飲ませてやる。
アイリフは従軍牧師とコックに、母には、自分は何も変わりはなかったと言ってくれ、と言って連行されるのだった・・・。
第11景で、アンナとカトリン(太田しづか)は新教徒の町ハレを見下ろす山の上の農家に泊まっている。
夜、アンナが町に仕入れに出かけている間に旧教徒の軍隊がやって来る。
彼らはこれからハレの町を攻撃して全滅させようとしている。
農民たちはハレの人々のために祈りを捧げる。
ハレには彼らの親戚の小さな子供たちがいるという。
子供好きなカトリンは、それを聞くと動揺し、幌車から太鼓を取って来て、密かに屋根に登り、はしごを外す。
そして太鼓を叩き始める。
眠っているハレの人々に敵が来たことを知らせようとしたのだ。
敵の兵士たちが慌てて戻って来て止めようとするが、何をしても彼女は叩くのをやめない。
ついに彼らは彼女を銃で撃つ。
だが、カトリンがゆっくり倒れると同時に、町の方から大砲の音が響き始め、急を告げる鐘の音も聞こえて来る。
口のきけない彼女は、自分の命と引き換えにハレの人々を救ったのだった。
ラスト(第12景)で、アンナは兵隊の服のような茶色い上着を着て、茶色い帽子をかぶっている。
その帽子をぬいで、地面に横たえられた娘カトリンの頭の下に敷いてやる。
他に身寄りはいないのか、と尋ねられたアンナは「息子が一人いるよ。アイリフっていうんだ」と笑顔で答える。
その笑顔が胸にこたえる。
三人の子供のうち二人は死んだが、まだ長男が生きている、という思いが彼女を支えている。
アイリフが処刑されたことを彼女は知らない。
息子に再会できるという希望を抱いて、彼女はこれからもたくましく生きていくのだろう。
~~~~~ ~~~~
カットが多いかと心配したが、そんなことはなく、上演台本は原作に忠実で好感が持てた。
とにかく原作が素晴らしい。
ブレヒトはよい芝居の作り方を熟知している。メッセージはもちろんあるが、見ていて面白いので退屈することがない。
アンナをめぐって恋のさや当てを繰り広げるコックと従軍牧師が実に可笑しい。
パウル・デッサウの音楽は、あまり耳にしっくりくるものではなかった。
生演奏の不協和音も、時に耳に痛かった。
役者は皆うまい。
主演の寺田路恵は、最近では2019年9月にやはりアトリエで見た「スリーウィンターズ」での好演が印象に残っている。
コック役の上川路啓志、カトリン役の太田しづか、イヴェット役の山崎美貴も好演。
太田しづかは口のきけない役だが、動きが機敏で的確で良かった。
ブレヒトは聖職者への揶揄、庶民の愚かさとたくましさ、そして愛おしさを、くまなく描き出す。
人間たちを見つめる作者の眼差しは鋭く深い。
ブレヒトの芝居は、これまで「三文オペラ」「ガリレイの生涯」「アルトゥロ・ウイの興隆」「セチュアンの善人」を見てきた。
特に、昔「ガリレイの生涯」で受けた感動を思い出した。

17世紀、ヨーロッパ各国を巻き込んだ30年戦争の戦火の中”肝っ玉おっ母”ことアンナ・フィアリングは三人の子どもたちを連れて
幌車を引いて戦場から戦場へ商売をして暮らしている。
二人の息子は兵隊に取られ、残った娘カトリンとアンナは戦火を潜り抜け逞しく生き抜くが、
平和が訪れれば商売が成り立たず、戦況が悪化すれば逃げ惑う日々。
それでもアンナは幌車を引いていく・・・(チラシより)
谷川道子の翻訳(光文社古典新訳文庫、タイトルは「母アンナの子連れ従軍記」)を読んで臨んだ。
驚いたのは戯曲の充実度。それほど短くはないのに、カットしたくなるような箇所が一つもない。
すべてのセリフが必然性を持ってそこにある。あるべき所に。
その意味で、チェーホフの芝居と似ているかも知れない。
この戯曲は何幕何場ではなく第何景という風に書かれている。
第2景で、アンナ(寺田路恵)が鶏の羽根をむしっている間、コック(上川路啓志)は火を起こし、粉を練って小さいクロワッサンの形みたいなパスタをたくさんこしらえる。
戯曲には書かれていないが、実に興味深い。演出家の面目躍如だ。
第3景で、正直者の次男(武田知久)は軍の会計係になっている。
彼は金庫を預かっており、敵に捕まった後も、それを隠した場所をどうしても言わないので処刑されることになる。
ただ、敵軍の上官に賄賂が効くかも知れないという。
だがアンナは、この切羽詰まった時にも、全財産を差し出すのをためらう。
だって、そうしたら次男の命は助かったとしても、明日から家族全員飢え死にすることになるかも知れないから・・・。
第4景の後、休憩。
第6景のラストでアンナは「戦争はいやだね」と言うが、その後、場面転換なく、すぐに第7景の冒頭のセリフを言う。
そのセリフが「戦争の悪口なんか言わせないよ・・」で、まったく逆のことを口にしている。
演出家はこの2つの場面を意図的につなげている。
第8景で、長男アイリフ(成田次郎)は兵士に連行される。
頭が良くて勇敢な彼は、戦争中、軍隊のための食料を手に入れるために農家を襲い、罪もない農民たちを平気で殺して上官に褒められていた。
だが戦況は刻々と変わり、突然(束の間の)和平が訪れる。
そうなると、前と同じことをすると軍紀違反だということで、今度は処刑されるという。
彼は母親に会いに来るが、あいにくアンナは出かけていていない。
母を待つことも許されない。
彼は最後に酒を一杯飲みたいと言うが、兵士は「そんな時間はない」とすげなく答える。
だがそこに居合わせた従軍牧師(大滝寛)がグラスを手に、もう一人の上官らしい兵士に目で許可を求め、相手がうなづくのを見て
アイリフの口にグラスを当ててワインを飲ませてやる。
アイリフは従軍牧師とコックに、母には、自分は何も変わりはなかったと言ってくれ、と言って連行されるのだった・・・。
第11景で、アンナとカトリン(太田しづか)は新教徒の町ハレを見下ろす山の上の農家に泊まっている。
夜、アンナが町に仕入れに出かけている間に旧教徒の軍隊がやって来る。
彼らはこれからハレの町を攻撃して全滅させようとしている。
農民たちはハレの人々のために祈りを捧げる。
ハレには彼らの親戚の小さな子供たちがいるという。
子供好きなカトリンは、それを聞くと動揺し、幌車から太鼓を取って来て、密かに屋根に登り、はしごを外す。
そして太鼓を叩き始める。
眠っているハレの人々に敵が来たことを知らせようとしたのだ。
敵の兵士たちが慌てて戻って来て止めようとするが、何をしても彼女は叩くのをやめない。
ついに彼らは彼女を銃で撃つ。
だが、カトリンがゆっくり倒れると同時に、町の方から大砲の音が響き始め、急を告げる鐘の音も聞こえて来る。
口のきけない彼女は、自分の命と引き換えにハレの人々を救ったのだった。
ラスト(第12景)で、アンナは兵隊の服のような茶色い上着を着て、茶色い帽子をかぶっている。
その帽子をぬいで、地面に横たえられた娘カトリンの頭の下に敷いてやる。
他に身寄りはいないのか、と尋ねられたアンナは「息子が一人いるよ。アイリフっていうんだ」と笑顔で答える。
その笑顔が胸にこたえる。
三人の子供のうち二人は死んだが、まだ長男が生きている、という思いが彼女を支えている。
アイリフが処刑されたことを彼女は知らない。
息子に再会できるという希望を抱いて、彼女はこれからもたくましく生きていくのだろう。
~~~~~ ~~~~
カットが多いかと心配したが、そんなことはなく、上演台本は原作に忠実で好感が持てた。
とにかく原作が素晴らしい。
ブレヒトはよい芝居の作り方を熟知している。メッセージはもちろんあるが、見ていて面白いので退屈することがない。
アンナをめぐって恋のさや当てを繰り広げるコックと従軍牧師が実に可笑しい。
パウル・デッサウの音楽は、あまり耳にしっくりくるものではなかった。
生演奏の不協和音も、時に耳に痛かった。
役者は皆うまい。
主演の寺田路恵は、最近では2019年9月にやはりアトリエで見た「スリーウィンターズ」での好演が印象に残っている。
コック役の上川路啓志、カトリン役の太田しづか、イヴェット役の山崎美貴も好演。
太田しづかは口のきけない役だが、動きが機敏で的確で良かった。
ブレヒトは聖職者への揶揄、庶民の愚かさとたくましさ、そして愛おしさを、くまなく描き出す。
人間たちを見つめる作者の眼差しは鋭く深い。
ブレヒトの芝居は、これまで「三文オペラ」「ガリレイの生涯」「アルトゥロ・ウイの興隆」「セチュアンの善人」を見てきた。
特に、昔「ガリレイの生涯」で受けた感動を思い出した。













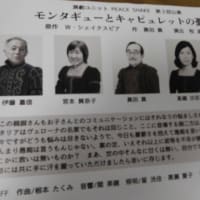

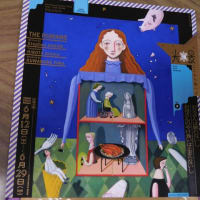
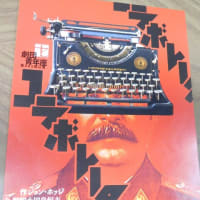


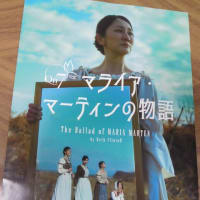






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます