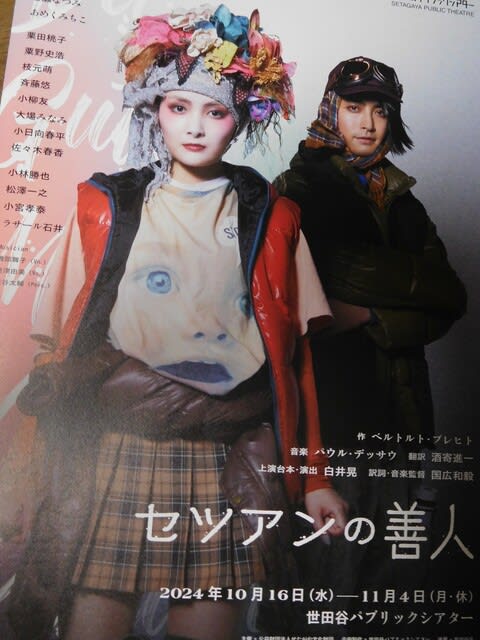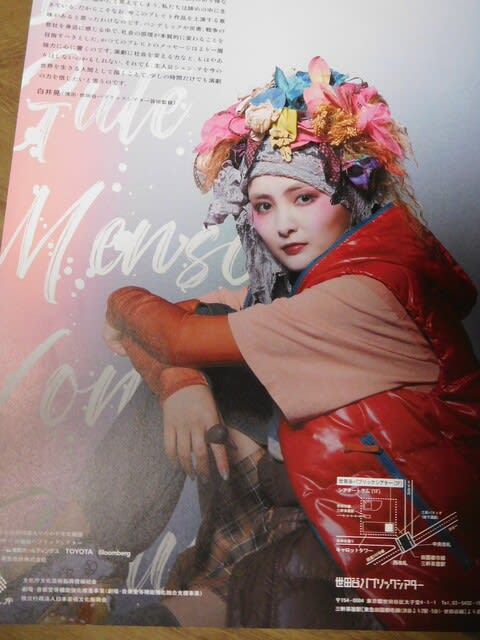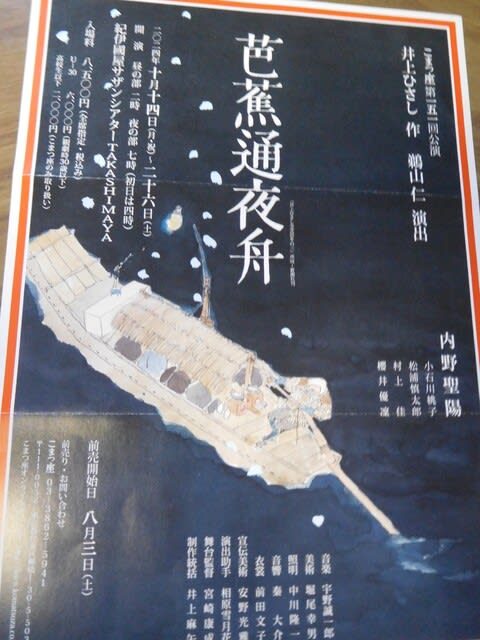5月5日、紀伊國屋サザンシアターで、ドミニカ・フェロー作「リンス・リピート」を見た(演出:稲葉賀恵)。

命が脅かされるほどの摂食障害を抱えていた大学生レイチェル(吉柳咲良)が、施設での治療を経て4ヶ月ぶりに帰宅する。
母ジョーン(寺島しのぶ)と父ピーター(松尾貴史)、そして弟ブロディ(富本惣昭)はレイチェルを迎え入れる。
母は移民として苦労しながら弁護士のキャリアを築いた人で、娘もこの状況を乗り越えて明るい将来をつかみ取ってほしいと期待している。
しかし娘は、セラピストであるブレンダ(名越志保)との会話を思い出しながら、次第に母親の愛情を苦痛に感じ、家族こそが
自分を追い込んだ原因なのではないかと疑問を抱く。
すれ違う母と娘を描き、2019年にオフ・ブロードウェイの話題をさらった作品の本邦初演とのこと。
舞台の背景がおぞましい。独特のピンクで上方がくしゅくしゅと縮れている。不穏で不愉快。
後で知ったが、これは子宮をイメージしているとのこと。
黒子が何人かいて場面転換のたびに家具や物を動かすが、その服装も同じピンクのつなぎ。
レイチェルの帰宅は、週末の「一時帰宅」で、実は「お試し」だった。
その結果を見て、本当に元のように家族と暮らしていけるかどうか判定されるのだ。
優しく穏やかな父親は、今は仕事をやめて主夫をしている。
母は娘の4ヶ月の入院中、一度しか面会に来なかった。
娘は摂食障害ばかりでなく自殺未遂を起こしていた。
弟の彼女は弁護士志望の年上の大学生で母のお気に入り。
娘の「背中を押してあげる」が母の決まり文句。
帰宅2日目の昼、娘は家で母と一緒に映画「エリン・ブロコビッチ」を見る予定だったが、母にクライアントから緊急の連絡が入り、
母は外出を余儀なくされる。あいにく父も弟も外出中で、娘は一人になってしまう。
規則では、食事の時間帯には誰かが必ずレイチェルのそばについていなければいけないのに。
娘は必死で母を引き止めるが、母は事の重大さに気がついていない。
夫か息子に連絡して帰宅してもらえばよかったのだが、それほどのことだとは思わなかったのだろう。
娘は自分が一人になるとどうなるか、どんな行動を取ってしまうか、予想していたのだろう、取り乱し、絶望の叫びを上げる。
家に一人残された彼女は結局、残っていたパンプキンパイを全部食べてしまう。
食べながら、「私はこれを全部食べるだろう、食べたら吐こう」と思っていた。
いつも、後で吐けばいい、と思いながら目一杯食べていた・・・。
娘は短編小説や詩を書いている。
弁護士になるよりそういうものを書く仕事をしたい、という娘の気持ちを知るセラピストは、母にそう言えば、と勧めるが、
詩ならエミリー・ディキンソンくらい(の才能)でないと母は認めてくれない、と娘は答える。
父親は娘の良き理解者だが、妻との力関係が不均衡なため、弱く、娘を守ってやることができない。
かつて浮気をしていた可能性も匂わされ、妻に対して強く出ることができない。
弟はいかにも現代っ子。
姉は彼に「避妊してる?」とダイレクトに、まるで母親のように尋ねるのでドキッとした。
テレビドラマ「ドゥギー・ハウザー」の母親を思い出した。
こんなことを言って二人の関係はどうなるのかと危ぶんだが、弟は意外にもさらりと受け止める。
彼は姉のことをよく理解しており、「弁護士にはなりたくない」と母親にはっきり言ったらいいじゃん、と勧めるのだった。
かつて母の部屋にあり、捨てたはずの体重計は、なぜか冷蔵庫の中にある。これがよく分からない。
体外受精の費用がかかった、と夫が言う。
子供たちは体外受精で生まれたのだろうか。
娘が中学か高校の頃、母は生理がなかった、と、驚くべき事実が明かされる。
タンポンをもらいに部屋に行ったが、なかったという。
実は、母親は極端なダイエットをしているらしい。
母も娘も、食事に関して問題を抱えているのだった・・。
~~~~~ ~~~~~
母原病という言葉があったが、これはまさに、そのことで苦しむ娘の話だ。
自分の娘を自分と同じ立派な仕事につかせようというのは、愛情でも何でもない。
娘は全然別の人生を歩む権利があるのに、本人の意思を無視して枠に押し込もうとするから、良い子ほど病気になってしまう。
レイチェルは、母の期待に応えようと無理して好きでもない法律の勉強を続けたために、体が悲鳴を上げてしまったのだ。
とは言え、さほど単純な話ではないようだ。
よく分からない点もあり、私には難しい芝居だった。
セラピスト役の名越志保が素晴らしい。
この人の強みは何と言ってもその声にある。
穏やかで柔らかみがあり、温かい。
かと思うと、強く鋭い罵声も出せる。
そして、役柄を深く理解する力と、それを表現する力に恵まれている。
常に安定した演技で舞台を支える彼女を、今回も見ることができて嬉しかった。
娘役の吉柳咲良と弟役の富本惣昭も好演。

命が脅かされるほどの摂食障害を抱えていた大学生レイチェル(吉柳咲良)が、施設での治療を経て4ヶ月ぶりに帰宅する。
母ジョーン(寺島しのぶ)と父ピーター(松尾貴史)、そして弟ブロディ(富本惣昭)はレイチェルを迎え入れる。
母は移民として苦労しながら弁護士のキャリアを築いた人で、娘もこの状況を乗り越えて明るい将来をつかみ取ってほしいと期待している。
しかし娘は、セラピストであるブレンダ(名越志保)との会話を思い出しながら、次第に母親の愛情を苦痛に感じ、家族こそが
自分を追い込んだ原因なのではないかと疑問を抱く。
すれ違う母と娘を描き、2019年にオフ・ブロードウェイの話題をさらった作品の本邦初演とのこと。
舞台の背景がおぞましい。独特のピンクで上方がくしゅくしゅと縮れている。不穏で不愉快。
後で知ったが、これは子宮をイメージしているとのこと。
黒子が何人かいて場面転換のたびに家具や物を動かすが、その服装も同じピンクのつなぎ。
レイチェルの帰宅は、週末の「一時帰宅」で、実は「お試し」だった。
その結果を見て、本当に元のように家族と暮らしていけるかどうか判定されるのだ。
優しく穏やかな父親は、今は仕事をやめて主夫をしている。
母は娘の4ヶ月の入院中、一度しか面会に来なかった。
娘は摂食障害ばかりでなく自殺未遂を起こしていた。
弟の彼女は弁護士志望の年上の大学生で母のお気に入り。
娘の「背中を押してあげる」が母の決まり文句。
帰宅2日目の昼、娘は家で母と一緒に映画「エリン・ブロコビッチ」を見る予定だったが、母にクライアントから緊急の連絡が入り、
母は外出を余儀なくされる。あいにく父も弟も外出中で、娘は一人になってしまう。
規則では、食事の時間帯には誰かが必ずレイチェルのそばについていなければいけないのに。
娘は必死で母を引き止めるが、母は事の重大さに気がついていない。
夫か息子に連絡して帰宅してもらえばよかったのだが、それほどのことだとは思わなかったのだろう。
娘は自分が一人になるとどうなるか、どんな行動を取ってしまうか、予想していたのだろう、取り乱し、絶望の叫びを上げる。
家に一人残された彼女は結局、残っていたパンプキンパイを全部食べてしまう。
食べながら、「私はこれを全部食べるだろう、食べたら吐こう」と思っていた。
いつも、後で吐けばいい、と思いながら目一杯食べていた・・・。
娘は短編小説や詩を書いている。
弁護士になるよりそういうものを書く仕事をしたい、という娘の気持ちを知るセラピストは、母にそう言えば、と勧めるが、
詩ならエミリー・ディキンソンくらい(の才能)でないと母は認めてくれない、と娘は答える。
父親は娘の良き理解者だが、妻との力関係が不均衡なため、弱く、娘を守ってやることができない。
かつて浮気をしていた可能性も匂わされ、妻に対して強く出ることができない。
弟はいかにも現代っ子。
姉は彼に「避妊してる?」とダイレクトに、まるで母親のように尋ねるのでドキッとした。
テレビドラマ「ドゥギー・ハウザー」の母親を思い出した。
こんなことを言って二人の関係はどうなるのかと危ぶんだが、弟は意外にもさらりと受け止める。
彼は姉のことをよく理解しており、「弁護士にはなりたくない」と母親にはっきり言ったらいいじゃん、と勧めるのだった。
かつて母の部屋にあり、捨てたはずの体重計は、なぜか冷蔵庫の中にある。これがよく分からない。
体外受精の費用がかかった、と夫が言う。
子供たちは体外受精で生まれたのだろうか。
娘が中学か高校の頃、母は生理がなかった、と、驚くべき事実が明かされる。
タンポンをもらいに部屋に行ったが、なかったという。
実は、母親は極端なダイエットをしているらしい。
母も娘も、食事に関して問題を抱えているのだった・・。
~~~~~ ~~~~~
母原病という言葉があったが、これはまさに、そのことで苦しむ娘の話だ。
自分の娘を自分と同じ立派な仕事につかせようというのは、愛情でも何でもない。
娘は全然別の人生を歩む権利があるのに、本人の意思を無視して枠に押し込もうとするから、良い子ほど病気になってしまう。
レイチェルは、母の期待に応えようと無理して好きでもない法律の勉強を続けたために、体が悲鳴を上げてしまったのだ。
とは言え、さほど単純な話ではないようだ。
よく分からない点もあり、私には難しい芝居だった。
セラピスト役の名越志保が素晴らしい。
この人の強みは何と言ってもその声にある。
穏やかで柔らかみがあり、温かい。
かと思うと、強く鋭い罵声も出せる。
そして、役柄を深く理解する力と、それを表現する力に恵まれている。
常に安定した演技で舞台を支える彼女を、今回も見ることができて嬉しかった。
娘役の吉柳咲良と弟役の富本惣昭も好演。