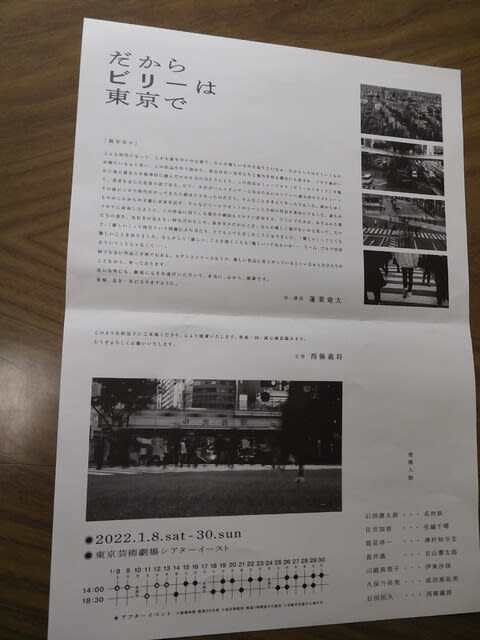2月14日 赤坂 RED/THEATER で、ニール・サイモン作「二番街の囚人」を見た(地人会新社公演、演出:シライケイタ)。

ニューヨークのイーストサイドにある高層マンションの一室に住むメル(村田雄浩)とエドナ(保坂知寿)。
二人の子供を育て上げ、それなりに格好のよい生活を営んでいると信じていた夫婦の目の前にあるのは、薄っぺらな壁と高層ビル群だけ。
ここ数日の夫の不調に気づいていたエドナは、辛抱強くメルの愚痴を聞き不眠の原因を取り除いてあげようとするが、それはあっという間に大喧嘩になり
隣人からの苦情電話を招き、挙句の果てに壁のたたき合いに。なんとメルは会社を首になっていたのだ。その上、空き巣に入られ、家財道具はもちろん、お酒も
薬までも盗まれる始末。それならばと、エドナが働き始める。夫婦逆転の日々は、メルの兄ハリィ(篠田三郎)と三人の姉たち(山口智恵)、広岡由里子、
谷川清美)を巻き込み、大騒動へと発展!?(チラシより)。
この文章を読んだ限りでは、あまり面白そうな印象ではなかったが、一応ニール・サイモンの作品だし、主役の二人を演じるのが保坂知寿と村田雄浩
だというので、見る気になった。1971年の作品。
で、見終わった後、思った。
夫メルに魅力がない。失業したことを妻に打ち明けることができず、夜眠れずマンションの周囲の騒音のせいにして怒鳴りまくる。
あまりにも弱い男だ。それに対して彼の妻エドナは常に前向きで献身的で、出来過ぎた人。二人はあまりにも対照的で、リアリティに欠ける。
インタビューで妻役の保坂知寿が言っているように、これは作者の理想の女性像なのだろう。
妻の美しい愛情に胸打たれたいところだが、残念ながら、かえって引いてしまう。
そして、キャストの問題。
メルの兄ハリィ役は篠田三郎だが、彼は、父が亡くなったため13歳から働き出した苦労人で、姉妹からも大事にされたという楽しい思い出がないという。
だが、篠田三郎はそんな苦労人にはとても見えない。
夫に代わって働きに出るエドナが颯爽として美しい。演じる保坂知寿のスーツ姿は惚れ惚れするほどカッコいい(衣装:伊藤早苗)。
彼女が昼休みに帰宅して、夫のために簡単な昼食を用意しつつおしゃべりしながら自分も慌ただしく食べる場面が楽しい。
半世紀前の、ニューヨークの中年夫婦のランチ風景が興味深い。
だが面白かったのはそこだけ。
メルのきょうだい4人が登場してからの会話は、ただもう退屈なだけで、作家の才能がまるで感じられず驚いた。
ニール・サイモンと言えば、「おかしな二人」「サンシャイン・ボーイズ」などが映画化もされて有名だし、トニー賞、ゴールデングローブ賞、
ピューリッアー賞など多くの受賞歴を誇る喜劇作家だ。
だが、そんな彼の作品の中には、残念ながら、たまにこういうつまらないものもあるということがわかった。
考えてみれば、三谷幸喜だってそうだ。
多作な人がいつも傑作を書いていたら、それはそれで大変かも。

ニューヨークのイーストサイドにある高層マンションの一室に住むメル(村田雄浩)とエドナ(保坂知寿)。
二人の子供を育て上げ、それなりに格好のよい生活を営んでいると信じていた夫婦の目の前にあるのは、薄っぺらな壁と高層ビル群だけ。
ここ数日の夫の不調に気づいていたエドナは、辛抱強くメルの愚痴を聞き不眠の原因を取り除いてあげようとするが、それはあっという間に大喧嘩になり
隣人からの苦情電話を招き、挙句の果てに壁のたたき合いに。なんとメルは会社を首になっていたのだ。その上、空き巣に入られ、家財道具はもちろん、お酒も
薬までも盗まれる始末。それならばと、エドナが働き始める。夫婦逆転の日々は、メルの兄ハリィ(篠田三郎)と三人の姉たち(山口智恵)、広岡由里子、
谷川清美)を巻き込み、大騒動へと発展!?(チラシより)。
この文章を読んだ限りでは、あまり面白そうな印象ではなかったが、一応ニール・サイモンの作品だし、主役の二人を演じるのが保坂知寿と村田雄浩
だというので、見る気になった。1971年の作品。
で、見終わった後、思った。
夫メルに魅力がない。失業したことを妻に打ち明けることができず、夜眠れずマンションの周囲の騒音のせいにして怒鳴りまくる。
あまりにも弱い男だ。それに対して彼の妻エドナは常に前向きで献身的で、出来過ぎた人。二人はあまりにも対照的で、リアリティに欠ける。
インタビューで妻役の保坂知寿が言っているように、これは作者の理想の女性像なのだろう。
妻の美しい愛情に胸打たれたいところだが、残念ながら、かえって引いてしまう。
そして、キャストの問題。
メルの兄ハリィ役は篠田三郎だが、彼は、父が亡くなったため13歳から働き出した苦労人で、姉妹からも大事にされたという楽しい思い出がないという。
だが、篠田三郎はそんな苦労人にはとても見えない。
夫に代わって働きに出るエドナが颯爽として美しい。演じる保坂知寿のスーツ姿は惚れ惚れするほどカッコいい(衣装:伊藤早苗)。
彼女が昼休みに帰宅して、夫のために簡単な昼食を用意しつつおしゃべりしながら自分も慌ただしく食べる場面が楽しい。
半世紀前の、ニューヨークの中年夫婦のランチ風景が興味深い。
だが面白かったのはそこだけ。
メルのきょうだい4人が登場してからの会話は、ただもう退屈なだけで、作家の才能がまるで感じられず驚いた。
ニール・サイモンと言えば、「おかしな二人」「サンシャイン・ボーイズ」などが映画化もされて有名だし、トニー賞、ゴールデングローブ賞、
ピューリッアー賞など多くの受賞歴を誇る喜劇作家だ。
だが、そんな彼の作品の中には、残念ながら、たまにこういうつまらないものもあるということがわかった。
考えてみれば、三谷幸喜だってそうだ。
多作な人がいつも傑作を書いていたら、それはそれで大変かも。