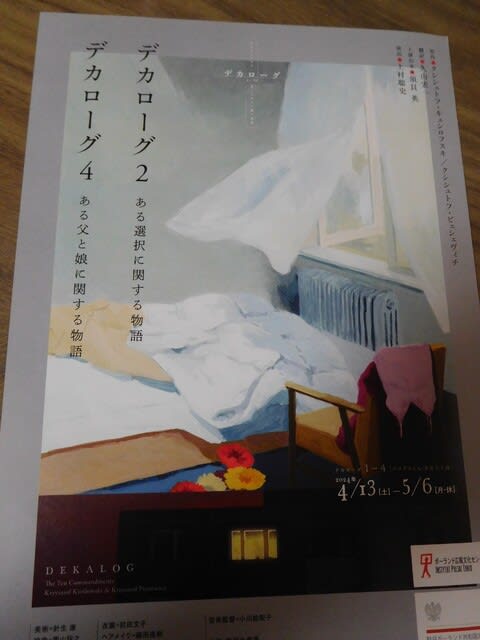4月23日東京芸術劇場シアターイーストで、フロリアン・ゼレール作「母」を見た(演出:ラディスラス・ショラー)。

ゼレールの家族三部作の最後となる作品。
これまで「Le Pere 父」(2019年)と「Le Fils 息子」(2021年)を見た。
「息子」では岡本健一が父親役を、岡本圭人が息子役を、若村麻由美が母親役を演じた。
その三人の関係が、今回そのまま同じというのが面白い。
実は、この「 母」が最初に書かれたそうだ。
2010年パリで初演。今回が日本初演。
アンヌはこれまで自分のすべてを捧げて愛する子どもたちのため、夫のためにと家庭を第一に考えて生きてきた。
それはアンヌにとってかけがえのない悦びで至福の時間であった。
そして年月が過ぎ、子どもたちは成長して彼女のもとから巣立っていってしまった。
息子も娘も、そして今度は夫までも去ろうとしている。
家庭という小さな世界の中で、四方八方から逃げ惑う彼女はそこには自分ひとりしかいないことに気づく。
母は悪夢の中で幸せだった日々を思い出して心の万華鏡を回し続ける・・・(チラシより)。
夫ピエール(岡本健一)が帰宅。「少し遅くなった」
妻アンヌ(若村麻由美)は妙に明るい。「今日はどんな一日だった?」
ずっと会社にいたよ。
さっき会社に電話したのよ。そしたらあなたはいなかった。
・・じゃあ打ち合わせだ。
そう・・。
彼女は夫が浮気していると疑っている。
そしてまた「今日はどんな一日だった?」
さっきも同じことを聞いたよ。
こうして妻は何度もぐるぐると同じ話を繰り返す。
しまいに「・・クソビッチたちとやりまくるがいい」とつぶやく様は、もはや狂気。
だが暗転の後、同じシチュエーションが始まる。
夫が帰宅するが、その後は、前と少し違う。
妻は穏やかで、少し沈んだ様子。
夫「何か変だ」「暗いよ」
朝、緑のドレスを着たアンヌは、明るく生き生きとして、軽やかに動き回る。
飛ぶように朝食の用意をしている。
昨夜遅く、息子ニコラ(岡本圭人)が突然帰って来たのだ。
どうして急に帰って来たんだろう。
(恋人の)エロディと喧嘩したんでしょ。
(エロディは)きっと他の男と寝たんだ・・・。
アンヌの妄想が続く。
アンヌにとって、ニコラの恋人エロディは、自分から息子を奪う悪者なのだ。
ニコラはエロディから連絡がないので、イライラして待っている。
アンヌは新しい赤いドレスを着ている。
どう?私、いくつに見える?
一緒にディナーに行きましょうよ。シーフードのお店でワインを飲んで。
その後、踊りに行きましょ。
親子だなんて思わせない。
年下の若い男と踊ってるって・・。
沈んでいるニコルのそばで、一人はしゃぐアンヌ。
その時、エロディ(伊勢佳代)が来る。
喧嘩していたので、ニコラはどうしようかとためらう。
アンヌは二人の間に割って入り、露骨に邪魔するが、結局二人は抱き合って仲直りし、手を取り合って去る。
赤いドレスを着たままワインを飲み、居間で寝ているアンヌ。
エロディが来る。
ずっとニコラからの連絡を待っている、と言う。
彼女はニコラにメッセージを書き、そのメモを彼に渡してください、とアンヌに頼んで帰る。
アンヌは、もちろんすぐに燃やしてしまう。
ニコラはアンヌに「どうしてメッセージを渡してくれなかったの?」
僕は出て行く。もうここにはいられない。
すがりつく母。
ニコラが出て行くと、舞台は暗くなり、アンヌはテーブルの上の鎮静剤を手に取る・・。
舞台上手の壁が動き、病院の白い壁と白いベッドが出現。
白衣の看護師たちがアンヌに白衣を着せ、ベッドに寝かせようとする。
抵抗するので鎮静剤を打って静かにさせる。
ニコラがそばの椅子に座っている。
アンヌが目を覚ます。
ニコラが手を取ると、喜ぶ。
ここはどこ?
あなたが連れて来たの?
ひと瓶全部飲んだでしょう。それに鎮静剤も。
リビングで倒れてるのを発見されたんだ。
ニコラは上着を脱ぎ、腕まくりする。
これから何をするの?
これからママを抱きしめる。
アンヌは歓喜。
抱きしめてくれるの?
そのあと、両手でママの首を絞める。
そして実行。
アンヌは死ぬ。
ニコラは母に近づき、顔を見て泣く。
そこにピエールとエロディが来る。
エロディ「終わったの?」
ピエール「ああ。あいつがやった」
エロディ「私のために」「幸せな瞬間だわ」
ニコラは二人のそばを通って立ち去る。
ベッドのそばの椅子にピエールがいる。
アンヌが気がつく。
ここはどこ?
私がここにいるってニコラに連絡してくれた?
どうして来ないのかしら。
きっと来るよ。
日曜日に来るよ、きっと・・・。
幕
「父」の時と同様、同じシーンが手を変え品を変え演じられるので、やはり最初は面食らう。
一体どれが事実でどれがアンヌの妄想なのか、観客は翻弄される。
ここで描かれているのは、いわゆる「空の巣症候群」と呼ばれるものだ。
だが、作者が男性のせいだろうか、女性の描き方には素直に賛同しかねる気もする。
今どきこんな女性がいるだろうか。
彼女には娘もいるが、息子にだけ異常に執着し、彼の自然な成長を喜ぶことができないでいる。
こんなことになるよりずっと前から、彼女には仕事も趣味も友人も、何か打ち込めるものも、何もなかったらしい。
そんな人がいるのだろうか?
夫との関係も、あまりに希薄。
もう少ししたら、孫が欲しいとか思う年齢だろうに、彼女には難しいようだ。
アンヌ役の若村麻由美がすごい。
声の微妙な変化。優雅な、あるいはダイナミックな動き。狂気のさま。
他の誰にこんな役ができるだろうか。
他の3人も好演。
繰り返されるシーンは似ているものの、少しずつ微妙に違う。
そのセリフと段取りを間違えないようにするだけでも大変だと思う。
そして今回、例えばこの日は、昼間「母」を上演して夜「息子」をやるという。
「息子」なんて、これ以上にシリアスな芝居なのに・・・。
どうやって切り替えるのだろう。
役者ってすごい、と改めて思った。

ゼレールの家族三部作の最後となる作品。
これまで「Le Pere 父」(2019年)と「Le Fils 息子」(2021年)を見た。
「息子」では岡本健一が父親役を、岡本圭人が息子役を、若村麻由美が母親役を演じた。
その三人の関係が、今回そのまま同じというのが面白い。
実は、この「 母」が最初に書かれたそうだ。
2010年パリで初演。今回が日本初演。
アンヌはこれまで自分のすべてを捧げて愛する子どもたちのため、夫のためにと家庭を第一に考えて生きてきた。
それはアンヌにとってかけがえのない悦びで至福の時間であった。
そして年月が過ぎ、子どもたちは成長して彼女のもとから巣立っていってしまった。
息子も娘も、そして今度は夫までも去ろうとしている。
家庭という小さな世界の中で、四方八方から逃げ惑う彼女はそこには自分ひとりしかいないことに気づく。
母は悪夢の中で幸せだった日々を思い出して心の万華鏡を回し続ける・・・(チラシより)。
夫ピエール(岡本健一)が帰宅。「少し遅くなった」
妻アンヌ(若村麻由美)は妙に明るい。「今日はどんな一日だった?」
ずっと会社にいたよ。
さっき会社に電話したのよ。そしたらあなたはいなかった。
・・じゃあ打ち合わせだ。
そう・・。
彼女は夫が浮気していると疑っている。
そしてまた「今日はどんな一日だった?」
さっきも同じことを聞いたよ。
こうして妻は何度もぐるぐると同じ話を繰り返す。
しまいに「・・クソビッチたちとやりまくるがいい」とつぶやく様は、もはや狂気。
だが暗転の後、同じシチュエーションが始まる。
夫が帰宅するが、その後は、前と少し違う。
妻は穏やかで、少し沈んだ様子。
夫「何か変だ」「暗いよ」
朝、緑のドレスを着たアンヌは、明るく生き生きとして、軽やかに動き回る。
飛ぶように朝食の用意をしている。
昨夜遅く、息子ニコラ(岡本圭人)が突然帰って来たのだ。
どうして急に帰って来たんだろう。
(恋人の)エロディと喧嘩したんでしょ。
(エロディは)きっと他の男と寝たんだ・・・。
アンヌの妄想が続く。
アンヌにとって、ニコラの恋人エロディは、自分から息子を奪う悪者なのだ。
ニコラはエロディから連絡がないので、イライラして待っている。
アンヌは新しい赤いドレスを着ている。
どう?私、いくつに見える?
一緒にディナーに行きましょうよ。シーフードのお店でワインを飲んで。
その後、踊りに行きましょ。
親子だなんて思わせない。
年下の若い男と踊ってるって・・。
沈んでいるニコルのそばで、一人はしゃぐアンヌ。
その時、エロディ(伊勢佳代)が来る。
喧嘩していたので、ニコラはどうしようかとためらう。
アンヌは二人の間に割って入り、露骨に邪魔するが、結局二人は抱き合って仲直りし、手を取り合って去る。
赤いドレスを着たままワインを飲み、居間で寝ているアンヌ。
エロディが来る。
ずっとニコラからの連絡を待っている、と言う。
彼女はニコラにメッセージを書き、そのメモを彼に渡してください、とアンヌに頼んで帰る。
アンヌは、もちろんすぐに燃やしてしまう。
ニコラはアンヌに「どうしてメッセージを渡してくれなかったの?」
僕は出て行く。もうここにはいられない。
すがりつく母。
ニコラが出て行くと、舞台は暗くなり、アンヌはテーブルの上の鎮静剤を手に取る・・。
舞台上手の壁が動き、病院の白い壁と白いベッドが出現。
白衣の看護師たちがアンヌに白衣を着せ、ベッドに寝かせようとする。
抵抗するので鎮静剤を打って静かにさせる。
ニコラがそばの椅子に座っている。
アンヌが目を覚ます。
ニコラが手を取ると、喜ぶ。
ここはどこ?
あなたが連れて来たの?
ひと瓶全部飲んだでしょう。それに鎮静剤も。
リビングで倒れてるのを発見されたんだ。
ニコラは上着を脱ぎ、腕まくりする。
これから何をするの?
これからママを抱きしめる。
アンヌは歓喜。
抱きしめてくれるの?
そのあと、両手でママの首を絞める。
そして実行。
アンヌは死ぬ。
ニコラは母に近づき、顔を見て泣く。
そこにピエールとエロディが来る。
エロディ「終わったの?」
ピエール「ああ。あいつがやった」
エロディ「私のために」「幸せな瞬間だわ」
ニコラは二人のそばを通って立ち去る。
ベッドのそばの椅子にピエールがいる。
アンヌが気がつく。
ここはどこ?
私がここにいるってニコラに連絡してくれた?
どうして来ないのかしら。
きっと来るよ。
日曜日に来るよ、きっと・・・。
幕
「父」の時と同様、同じシーンが手を変え品を変え演じられるので、やはり最初は面食らう。
一体どれが事実でどれがアンヌの妄想なのか、観客は翻弄される。
ここで描かれているのは、いわゆる「空の巣症候群」と呼ばれるものだ。
だが、作者が男性のせいだろうか、女性の描き方には素直に賛同しかねる気もする。
今どきこんな女性がいるだろうか。
彼女には娘もいるが、息子にだけ異常に執着し、彼の自然な成長を喜ぶことができないでいる。
こんなことになるよりずっと前から、彼女には仕事も趣味も友人も、何か打ち込めるものも、何もなかったらしい。
そんな人がいるのだろうか?
夫との関係も、あまりに希薄。
もう少ししたら、孫が欲しいとか思う年齢だろうに、彼女には難しいようだ。
アンヌ役の若村麻由美がすごい。
声の微妙な変化。優雅な、あるいはダイナミックな動き。狂気のさま。
他の誰にこんな役ができるだろうか。
他の3人も好演。
繰り返されるシーンは似ているものの、少しずつ微妙に違う。
そのセリフと段取りを間違えないようにするだけでも大変だと思う。
そして今回、例えばこの日は、昼間「母」を上演して夜「息子」をやるという。
「息子」なんて、これ以上にシリアスな芝居なのに・・・。
どうやって切り替えるのだろう。
役者ってすごい、と改めて思った。