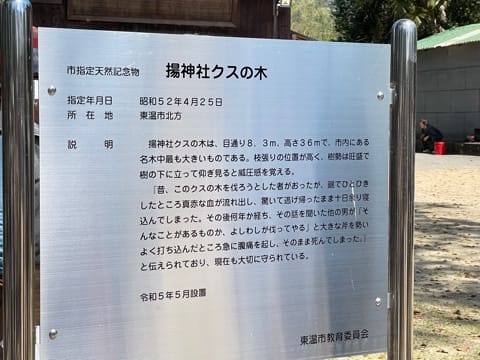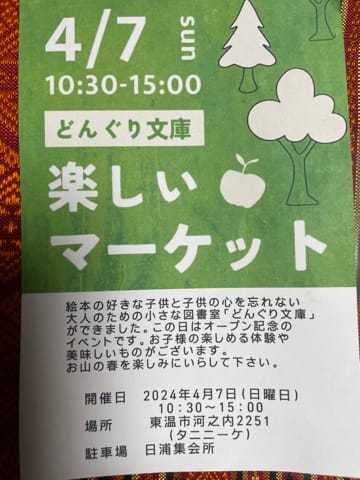あ~ ショック
11月のお出かけを2回にわたってーと書いていたのに消えてしまいました。今は書き直す気力がありません。たまにはタイムリーな話題を書きましょう。
ようやく紅葉の季節がやってきました。例年より10日ばかり遅れているようです。二日ほど前、2時間ほど中途半端な時間の空きができて、ふと思いついて西山興隆寺に行ってみました。西条市の西山興隆寺は紅葉寺と呼ばれる紅葉の名所です。
駐車場が近づいて、あたりが赤く染まっているのが見えました。あれ?あんなところに赤い屋根の建物があったかなあ?
行ってみるとそれは紅葉したカエデだったのです。ここにはカエデの仲間が何種類かあるそうですが、わたしには詳しいことはわかりませんのですべてモミジと書きます。

駐車場の周りは燃えるような木々で囲まれていました。


この木の色が素晴らしく鮮やかで、何人もがカメラを向けていました。と、どこからかトンボがやってきてあらら・・・
あとでこの写真をお見せしておきました。
ただ、駐車場がこんなに色づいているときは、本堂付近はもう散り始めているというのがこのお寺の特徴です。
というのも本堂までの標高差が大きく紅葉は上から下へと進んでくるのです。ああ、ちょっと遅かったかしら。
谷川にかかるみゆるぎ橋。ここから参道が始まると言ってもいいでしょう。
仁王門はまだまだ先。
ところどころ緑の中に燃えるような朱が輝いていました。
やっと仁王門
門を過ぎると、大きな石があります。このお寺は鎌倉時代に源頼朝公の発願によって再建された古い歴史を持っています。再建時資材を運んだ牛が途中で倒れ、牛によく似た石で葬ったのだそうです。白く見えるのは一円玉です。今も供養の草が差し込まれていました。

本堂はまだまだ。 あのモミジあたりに勅使門があって、そのわきをくぐると庫裏とおもてなし用の建物があります。本堂はそれより高いのです。

建物の庭からは扇面の景と呼ばれる景色が見えます。ここは見どころの一つ。二つの山の間から見えるのは道前平野。

次に宝物館の前あたり

さらに行くと石垣と紅葉とが美しいところ。

道はここで直角に曲がり、正面にイチョウの木が見えるようになります。トラオがまだ小さかったころ来たときは葉がはらはらと散っていて、「イチョウが降ってる。」と言ったことを覚えています。今年はまだ緑が残っていました。下の方があんなに紅葉しているのに?ちょっと不思議な感じがしました。

ここをさらに直角に曲がって石段を上るとやっと境内です。左手にはさらに高い石段の上に三重の塔があります。

と、ここまで来て、予想外にモミジがきれいなのに気が付きました。
塔に向かい合うように本堂が建っています。今年も会えたね、お寺犬の?ちゃん。おとなしい柴ちゃんですが、この日は犬連れの参拝者がいて気になるのかずっと吠えていました。でも撫でてあげるとおとなしくなります。

本堂の横に回ると

斜面の下から生えているので、目の前に枝が広がっています。

いつものように、本堂付近はもう散っているかと思ったけど、まだこの鮮やかさ。
良いお天気で一段と紅葉が映えていました。
宝物殿を見下すと、

雪柳も赤い。

石垣のところを見下ろすとみんな必ずここで写真をとっています。

ふと気が付くと、しまった!思わぬ長居をしていました。約束の時間に間に合うかしら。
いつもなら庫裏の横から山道に出てそちらを歩くのですが、急いでもと来た道を帰ることにしました。
たくさんの石段を下りるのはちょっと心配なので、境内にあった杖を借りました。
下りていると続々と人が登ってきました。皆さん息をハアハアさせて。
「あとどのくらいですか?」
上の方で聞かれたときは「もうちょっとですよ、がんばってください。」と言ったのだけど、下の方で聞かれると、 「まだまだ、先ですね。」とついつい本当のことを言ってしまいました。うそでも「もうちょっと」って言ってあげた方がよかったんだろうなと後で反省しました。皆さん結構しんどそうで、とっさに励みになる言葉が見つからなかったの。
こんな山登りみたいなお寺とは思わなかったのでしょうね。
階段途中ですれ違ったおじいさんが、振り向いたら転んでいたり、前を歩いていたおじいさんがつまづいてこけそうになっていたり、「わたし、もうここまででいい。」と弱音を吐くおばあさんがいたり・・・
私もおばあさんですが、私より若そうなおじいさん、おばあさんだったんですよ。
仁王門まで下りてくると門の土台に並んで座っているマダムたち 5,6人。ツアーのお仲間とお見受けしました。早くもギブアップのようでした。私が「杖を貸しましょうか」と言っても「もう、時間がないから」と、動こうとはしませんでした。わたしは心の中で、せっかくのツアー代金が・・・って思ってしまいました。今年のように上まできれいな年はめったにないと思うのです。しかもバッチリ見ごろのこの晴れた日に。あれを見ないなんてもったいない。
考えてみたらいつも別道を下りるので、階段を上ってくる人に会ったことがなかったのです。みんなけっこう苦労して上ってくるのだなあ、と思いました。杖をつかずに上まで上ったわたしって、結構やるじゃん。と自分をほめておきました。



































































































































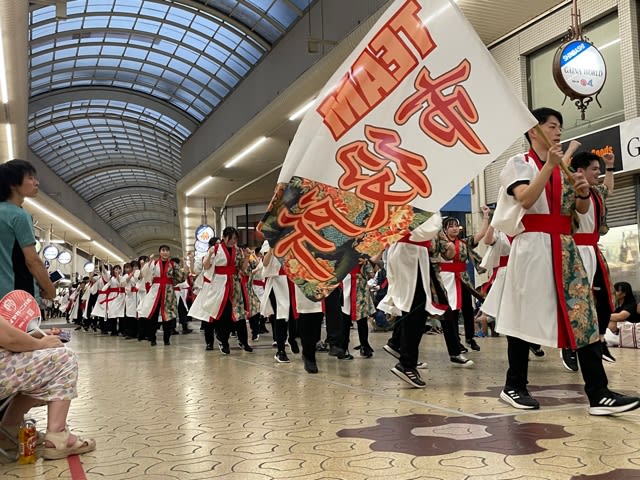




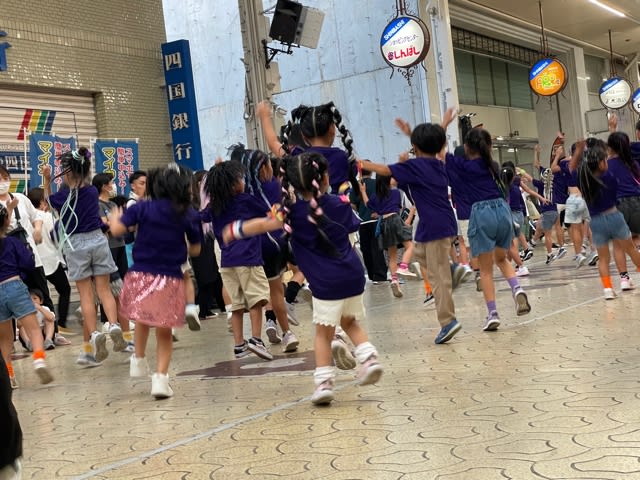






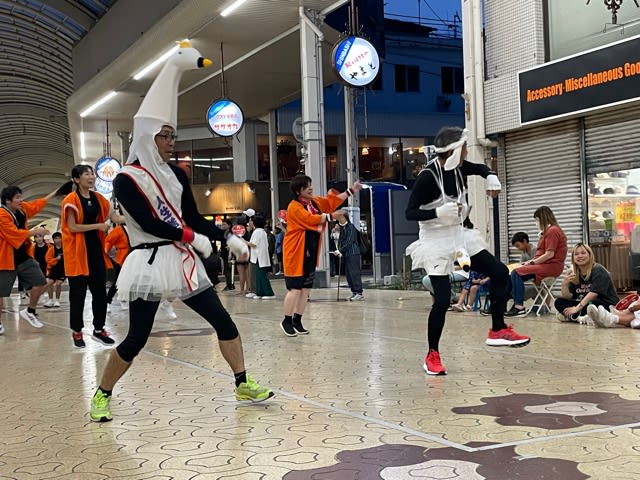








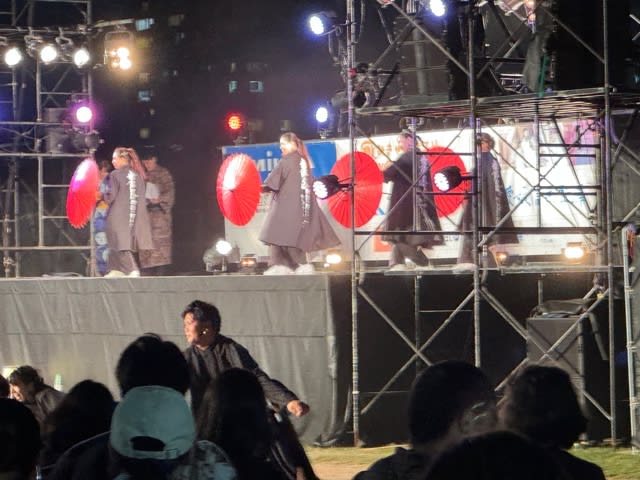
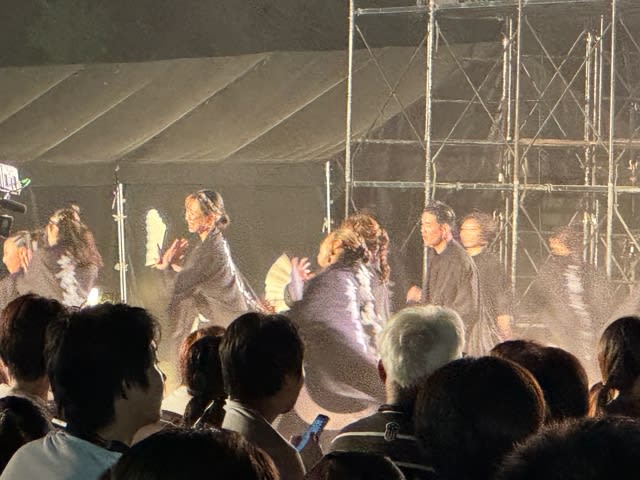
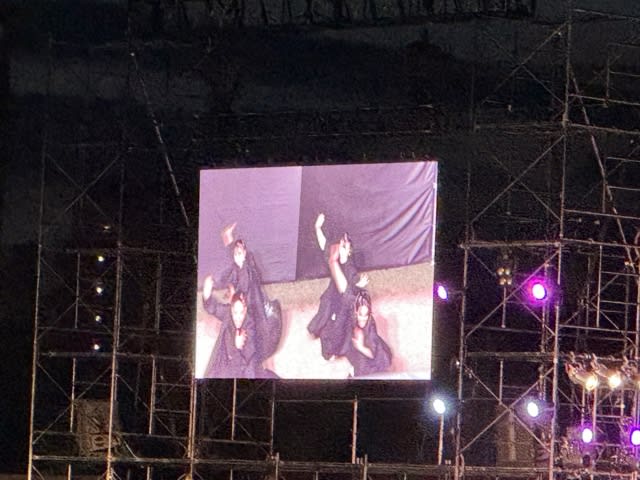

























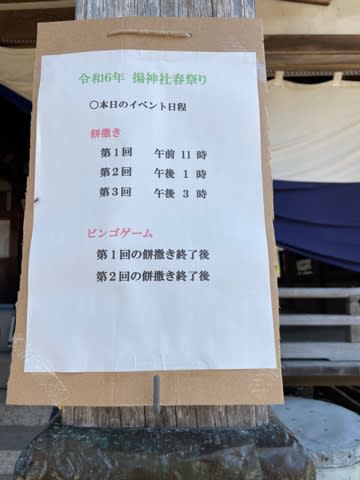 。
。