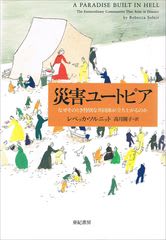災害医療関連の書籍に続き、新刊紹介を頼まれて、日本ホリスティク医学協会の会長で帯津三敬病院の名誉院長である帯津良一医師の『がん 「余命宣告」でも諦めない』と、彦根市立病院緩和ケア科部長で心療内科医でもある黒丸尊治医師の『「心の治癒力」をスイッチON!』を読んだ。
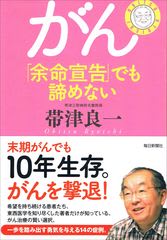
50年以上がん治療に携わってきた帯津先生は、まず「はじめに」で「余命宣告には明確な根拠はない。まだまだ打つ手はあります」と伝えている。
帯津先生は、まだ何の治療もしないうちから、簡単に余命宣告をする西洋医学しかしらない医師には傲りを感じると憤慨し、「ずっと患者さんの心に添うはずなのに、どうして平気で切り捨てるようなことが言えるのか」と嘆いている。
治療はやってみなければ、本当のところ、医師にもわからないこともあり、中でもがんは非常にミステリアスなものだというのだ。
そんながん治療には手術、抗がん剤、放射線治療などの西洋医学と、自然治癒力・免疫力を高める代替療法の両方をバランスよく取り入れた戦略が必要だと、帯津先生は説いている。
本書には、帯津三敬病院の患者さんの中からランダムに選ばれた、さまざまながん患者さんの詳細な治療方法や経過が綴られていた。
たとえ病気が治ったとしても、高額な治療費がその後の生活を圧迫することもあることから、患者さんの経済的なストレスを軽減できるよう、帯津先生が行っている主な代替療法の治療費の目安なども掲載されていて、為になった。
がん治療に王道はなく、治療戦略は患者さん1人ひとり異なる。それは何の病気にも言えることだけれども、1人ひとりに丁寧に対応する統合医療こそ、今後、日本の医療が進むべき道なのではないかなあと思った。
一方、黒丸先生の著書は、「心の治癒力」、つまり自分を癒す力を引き出すコミュニケーションスキルについてまとめられたものだ。

主にセラピストに向けて、クライエントが抱える問題を解決するための質問の仕方や、基本的なコミュニケーションスキルを伝える内容になっているのだけど、セラピーや心療内科の現場だけでなく、誰にでも役に立つ“言葉”の指南書だった。
心と体はつながっているから、心の治癒力が高まれば、体の治癒力も刺激されて、善循環が促されるわけですね。
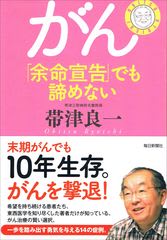
帯津良一(著) 毎日新聞社 1,500円+税
50年以上がん治療に携わってきた帯津先生は、まず「はじめに」で「余命宣告には明確な根拠はない。まだまだ打つ手はあります」と伝えている。
帯津先生は、まだ何の治療もしないうちから、簡単に余命宣告をする西洋医学しかしらない医師には傲りを感じると憤慨し、「ずっと患者さんの心に添うはずなのに、どうして平気で切り捨てるようなことが言えるのか」と嘆いている。
治療はやってみなければ、本当のところ、医師にもわからないこともあり、中でもがんは非常にミステリアスなものだというのだ。
そんながん治療には手術、抗がん剤、放射線治療などの西洋医学と、自然治癒力・免疫力を高める代替療法の両方をバランスよく取り入れた戦略が必要だと、帯津先生は説いている。
本書には、帯津三敬病院の患者さんの中からランダムに選ばれた、さまざまながん患者さんの詳細な治療方法や経過が綴られていた。
たとえ病気が治ったとしても、高額な治療費がその後の生活を圧迫することもあることから、患者さんの経済的なストレスを軽減できるよう、帯津先生が行っている主な代替療法の治療費の目安なども掲載されていて、為になった。
がん治療に王道はなく、治療戦略は患者さん1人ひとり異なる。それは何の病気にも言えることだけれども、1人ひとりに丁寧に対応する統合医療こそ、今後、日本の医療が進むべき道なのではないかなあと思った。
一方、黒丸先生の著書は、「心の治癒力」、つまり自分を癒す力を引き出すコミュニケーションスキルについてまとめられたものだ。

黒丸尊治(著) BABジャパン 1,500円+税
主にセラピストに向けて、クライエントが抱える問題を解決するための質問の仕方や、基本的なコミュニケーションスキルを伝える内容になっているのだけど、セラピーや心療内科の現場だけでなく、誰にでも役に立つ“言葉”の指南書だった。
心と体はつながっているから、心の治癒力が高まれば、体の治癒力も刺激されて、善循環が促されるわけですね。