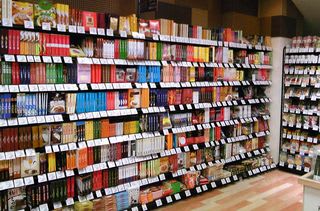この本は、ゲシュタポでナチスの通訳をしながら、多くのユダヤ人を脱走させ、戦後カトリック神父となったダニエル・シュタインの生涯を描いた上下巻の大作です。主人公ダニエルのモデルは実在したユダヤ人のカトリック神父、オスヴァルト・ルフェイセン氏。
オスヴァルト氏はポーランドに生まれ、何度も死を目前にしてながらまるで奇跡のように難を逃れ、ゲシュタポの通訳になって生き延びます。その間、皆殺しにされる直前だったゲットーのユダヤ人300人を、巧みな情報操作によって脱走されることに成功するのです。
ホロコーストを生き延び、カトリックに改宗したのちイスラエルに渡り、ユダヤ人のカトリック神父として人種や宗派の違いを超えた教会の在り方を模索し、その構築に尽力するのですが、ユダヤ教やイスラム教との摩擦もあり、ローマカトリック界から異端的な扱いを受けた彼の足跡を、本人だけでなく彼と関わった人々の日記や書簡、対話、講演会などから浮き彫りにした小説。
外国の人名を覚えるのが苦手なので、「この人、どういう関係の人だっけ」とたびたびページをめくりなおしたりしましたが、読み応え充分。
著者のウリツカヤさんの「彼の教えは、何を信じるかより何をするかが重要、ということです」という言葉に、頭でっかちになりがちな己を振り返り、こうべを垂れたのでありました。
これから分厚い下巻に挑みます。