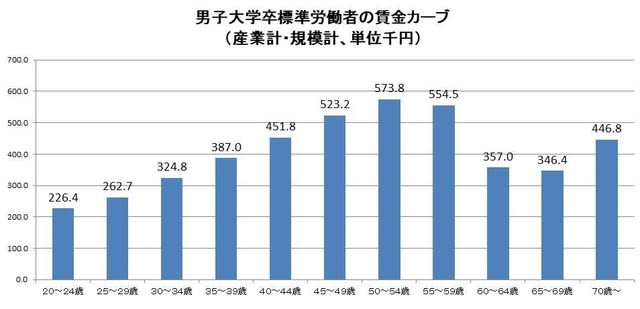正常な動きを始めた毎月勤労統計
昨4月5日、世間から国会までを大騒ぎに巻き込んだ「毎月勤労統計」の平成31年1月確報と2月の速報が発表になりました。
なぜこんなバカげた大騒ぎが起きたかの事実関係は闇の中ですが、統計の信頼性が回復すれば、「まあ」一件落着という事でしょう。
昨年は1~3月、全産業の1人当たり「現金給与総額」の前年同月比上昇率が急に高くなりびっくりしてこのブログに書いたのが5月9日でしたが、今年の2月速報は、景気減速を反映してでしょうか、所定内給与こそマイナス0.1%(前年同月比)ですが、残業などを含む「現金給与総額」は0.8%(同)のマイナスです。
マスコミが指摘しますように物価上昇を差し引いた実質賃金ではマイナス1.1%(同)という残念な結果になっています。
折角統計が正常に機能し始めたのですから、お祝いで少しいい数字が出てくれればいいなと思っても、そんな思いを忖度してくれるほど現実は甘くないという事でしょうか。
ここで「毎月勤労統計」が正常に機能し始めた、とわざわざ指摘していますのは、それなりの理由があると理解しているからで、その点についてちょっと付け加えておきたいと思います。
昨年の1月以降の賃金が、前年に比べてどうも上がりすぎているように感じられるというのが問題の発端で、その原因は一番賃金水準の高い東京都の500人以上の1464事業所の調査について、全数調査と決められているのに、厚労省が独断でほぼ1/3の491事業所を抽出した抽出調査にしたのが平成16年でそれから平成29年まで抽出調査を続けていたのです(厚労省の説明)。これだけの事業所数があれば、抽出調査にしても、統計数理上は問題ないと認識したからでしょう。
もちろん抽出調査の数字を1464社に復元して、1464社の調査結果としていれば問題なかったのですが、調査の結果を集計する際、500人以上の事業所は全数調査という決まりなので、491事業所を「全数」として集計してしまったとのことです(厚労省の説明)。
その結果、残りの973事業所は「存在しない」ことになり、賃金の高い大企業の事業所の集中する東京の500人以上事業所の約1/3が統計から抜け落ちることとなり、全国、全産業の平均賃金が実態より低くなってしまっていたのです。
つまり、平成16年から29年までの毎月勤労統計の数字は、14年間実態より低くなっていたという事で、このあたりが省内でも問題になったのでしょう。平成30年の1月から1464社に復元して出すことにしたのでしょう。結果は統計の中に最も賃金の高い973事業所が入ってきたので、平均が高まり、「え!なんで急に高くなったの」という事で、平成16年からの 統計集計上の「取扱錯誤」がバレてしまったという事なのです。
厚労省の文書では、原データが残っている平成24年以降については復元した「再集計値」を発表していますから、一部は不完全ながら、最近の数字については正常化したと判断できるといっていいのでしょう。
加えて厚労省は、引き続き経緯を調査し、再発防止に努めるといっていますが、何時、誰が、何処でどう間違えたかは多分永久に「不明」という事で終わるのではないでしょうか。なんとなく、そんな気がしています。
昨4月5日、世間から国会までを大騒ぎに巻き込んだ「毎月勤労統計」の平成31年1月確報と2月の速報が発表になりました。
なぜこんなバカげた大騒ぎが起きたかの事実関係は闇の中ですが、統計の信頼性が回復すれば、「まあ」一件落着という事でしょう。
昨年は1~3月、全産業の1人当たり「現金給与総額」の前年同月比上昇率が急に高くなりびっくりしてこのブログに書いたのが5月9日でしたが、今年の2月速報は、景気減速を反映してでしょうか、所定内給与こそマイナス0.1%(前年同月比)ですが、残業などを含む「現金給与総額」は0.8%(同)のマイナスです。
マスコミが指摘しますように物価上昇を差し引いた実質賃金ではマイナス1.1%(同)という残念な結果になっています。
折角統計が正常に機能し始めたのですから、お祝いで少しいい数字が出てくれればいいなと思っても、そんな思いを忖度してくれるほど現実は甘くないという事でしょうか。
ここで「毎月勤労統計」が正常に機能し始めた、とわざわざ指摘していますのは、それなりの理由があると理解しているからで、その点についてちょっと付け加えておきたいと思います。
昨年の1月以降の賃金が、前年に比べてどうも上がりすぎているように感じられるというのが問題の発端で、その原因は一番賃金水準の高い東京都の500人以上の1464事業所の調査について、全数調査と決められているのに、厚労省が独断でほぼ1/3の491事業所を抽出した抽出調査にしたのが平成16年でそれから平成29年まで抽出調査を続けていたのです(厚労省の説明)。これだけの事業所数があれば、抽出調査にしても、統計数理上は問題ないと認識したからでしょう。
もちろん抽出調査の数字を1464社に復元して、1464社の調査結果としていれば問題なかったのですが、調査の結果を集計する際、500人以上の事業所は全数調査という決まりなので、491事業所を「全数」として集計してしまったとのことです(厚労省の説明)。
その結果、残りの973事業所は「存在しない」ことになり、賃金の高い大企業の事業所の集中する東京の500人以上事業所の約1/3が統計から抜け落ちることとなり、全国、全産業の平均賃金が実態より低くなってしまっていたのです。
つまり、平成16年から29年までの毎月勤労統計の数字は、14年間実態より低くなっていたという事で、このあたりが省内でも問題になったのでしょう。平成30年の1月から1464社に復元して出すことにしたのでしょう。結果は統計の中に最も賃金の高い973事業所が入ってきたので、平均が高まり、「え!なんで急に高くなったの」という事で、平成16年からの 統計集計上の「取扱錯誤」がバレてしまったという事なのです。
厚労省の文書では、原データが残っている平成24年以降については復元した「再集計値」を発表していますから、一部は不完全ながら、最近の数字については正常化したと判断できるといっていいのでしょう。
加えて厚労省は、引き続き経緯を調査し、再発防止に努めるといっていますが、何時、誰が、何処でどう間違えたかは多分永久に「不明」という事で終わるのではないでしょうか。なんとなく、そんな気がしています。