《創られた賢治から愛すべき真実の賢治に》
さて、ここまで10年間ほどかけて賢治のことを調べてきた私の主たる理由は何かというと、それは今から約半世紀前に恩師の岩田純蔵教授が、 賢治はあまりにも聖人・君子化され過ぎてしまって、実は私はいろいろなことを知っているのだがそのようなことはおいそれとは喋れなくなってしまった。
という意味のことをある時に嘆いたことである。実は岩田教授は賢治の甥(賢治の妹シゲの長男)であり、しかも私は賢治を尊敬していたから尚のことその嘆きが気になった。とはいえ、仕事に就いている頃の私にはそのようなことを調べるための時間的余裕はなかった。それが10年程前に定年となり、やっとそのための時間を持てるようになって賢治のことを調べることができるようになった。すると、「通説」や「旧校本年譜」(『校本宮澤賢治全集第十四巻』所収「賢治年譜」)等において、常識的に考えればこれはおかしいと思われるところが、特に「羅須地人協会時代」を中心として少なからず見つかるのだった。まず私が最初におかしいと思ったのは、「旧校本年譜」の「大正15年7月25日」の記述、
賢治も承諾の返事を出していたが、この日断わりの使いを出す。使者は下根子桜の家に寝泊りしていた千葉恭で午後六時ごろ講演会会場の仏教会館で白鳥省吾にその旨を伝える。
だった。この「下根子桜の家に寝泊りしていた」という記述に素直によれば、「羅須地人協会時代」の賢治は「独居自炊」とは言い切れないので、「通説」とは異なることになるからだ。そこで、千葉恭のこと調べてみようと思ったのだが、どういうわけかあの膨大な『校本宮澤賢治全集』のどこを探しても恭その人に関しては何も書かれていない。仕方がないから私は自分で調べるしかないということであちこち尋ね廻ったところ、出身地、穀物検査所を辞めた日及び復職した日、賢治から肥料設計をしてもらっていたこと、楽団ではマンドリン担当だったことなども明らかにできた。
また、
〈仮説〉千葉恭が賢治と一緒に暮らし始めたのは大正15年6月22日頃からであり、その後少なくとも昭和2年3月8日までの8ヶ月間余を2人は下根子桜の別宅で一緒に暮らしていた。
を立ててみたところその検証もできたのだった。そして実際、恭は『私が炊事を手傳ひました』とはっきり証言もしていた。したがって、「羅須地人協会時代」の賢治は厳密には「独居自炊」であったとは言い切れない。かてて加えてよくよく調べてみたならば、この時代が「独居自炊」と譬えられるようになったのは『昭和文学全集14宮澤賢治集』(昭和28年)以降であり、奇しくも、高村光太郎のそれこそ『獨居自炊』(昭和26年)の発行を境にしていることもわかった。それ故、「羅須地人協会時代」を「独居自炊」で譬えるのは換骨奪胎の感が否めず、あまり後味のいいものではない。
とまれ、これで厳密には「羅須地人協会時代」は「独居自炊」であったとは言い切れないことを私は実証できたと判断できたから、そうかこれが恩師が嘆いた「いろいろなこと」の一つの具体事例だったのかと、その嘆きの意味を初めて覚った気がした。そして同時に、どうやら私はパンドラの箱を開けてしまったようだと直感したのだった。
そこでそれ以降、賢治関連の事柄、とりわけ「年譜」や「通説」については一度徹底して疑ってみる必要があると私は思うようになっていった。それは、従前から「学問は疑うことから始まる」と私は認識していたし、一般に「賢治に関する論考」等においては、裏付けも取らず、検証もせず、その上典拠を明示せずにいともたやすく断定表現をしている個所が多過ぎるのではなかろうかということを私は危惧していたことがあった上に、この「独居自炊であったとは言い切れない」があったからである。
そこで私は、賢治関連の考察等においては自分で直接原典に当たり、実際自分の足で現地に出かけて行って自分の目で見、そこで直接関係者から取材等をしたりした上で、自分の手と頭で考えるというアプローチの仕方を心掛けてきた。そしてその結果、特に「羅須地人協会時代」の賢治に関してのあやかしや、知られざる「真実」のいくつかを明らかにできたつもりだ。
例えば、先ほどの「独居自炊」のあやかしのみならず、
(1) 「大正15年12月2日上京」の典拠の恣意的な使い方
(2) ヒデリノ時ニ賢治は涙ヲ流サナカッタこと
(3) サムサノ夏に賢治はオロオロ歩ケナカッタこと
(4) 「一九二八年の秋」の「一九二七年の秋」への変更の無茶
(5) 昭和二年の約三ヶ月間の滞京と挫折
(6) 昭和三年六月の農繁期の上京の疑問
(7) 「羅須地人協会時代」終焉の真相
などがそれらである。そこで、私はやはりパンドラの箱を開けてしまったのだと思うしかなかった。
これは見方を変えれば、前掲した、私の恩師で賢治の甥である岩田純蔵教授の先の、
賢治はあまりにも聖人・君子化され過ぎてしまって、実は私はいろいろなことを知っているのだがそのようなことはおいそれとは喋れなくなってしまった。
という意味の嘆きはやはりそのとおりであり、賢治に関する「年譜」や「通説」の中には賢治を「聖人・君子化」するために改竄や捏造された蓋然性が高いものが少なくないということになりそうだ、ということである。そして、冷静になって今までのことを振り返って概観すれば、
賢治に関する「年譜」や「通説」において常識的に考えておかしいと思ったところは、検証してみると殆どの場合やはりおかしいということである。それは、論理的に破綻していると思った場合はもちろんのこと、心理的におかしい思った場合もまた同様であった。
とはいえ、私の検証結果や主張が全て正しいと言い張るつもりはない。所詮それらはいずれも基本的には一つの仮説に過ぎないからだ。だが私が主張しているものはまず仮説を立て、次に、定性的な段階にとどまらずにできるだけ定量的な考察によって検証できたものだ。だから当然、反例が提示されれば私は即その仮説を棄却するし、されなければしない。ましてや、現「賢治年譜」には前掲の「約三ヶ月間の滞京」を始めとしていくつかの反例があり、一方で、それに対応する私の立てた仮説には反例が存在しないとなれば、同年譜は大幅な修訂が不可避だろう。ついては、「賢治研究」の更なる発展のために、現「賢治年譜」のまずは「羅須地人協会時代」を早急に当局には一度検証し直していただきたい。さもないと、「創られた偽りの宮澤賢治像」が未来永劫「宮澤賢治」になってしまう虞があるからだ。
 続きへ。
続きへ。前へ
 。
。 “『「羅須地人協会時代」の真実』の目次”
“『「羅須地人協会時代」の真実』の目次””みちのくの山野草”のトップに戻る。

《鈴木 守著作案内》
◇ この度、拙著『「涙ヲ流サナカッタ」賢治の悔い』(定価 500円、税込)が出来しました。
本書は『宮沢賢治イーハトーブ館』にて販売しております。
あるいは、次の方法でもご購入いただけます。
まず、葉書か電話にて下記にその旨をご連絡していただければ最初に本書を郵送いたします。到着後、その代金として500円、送料180円、計680円分の郵便切手をお送り下さい。
〒025-0068 岩手県花巻市下幅21-11 鈴木 守 電話 0198-24-9813☆『「涙ヲ流サナカッタ」賢治の悔い』 ☆『宮澤賢治と高瀬露』(上田哲との共著)
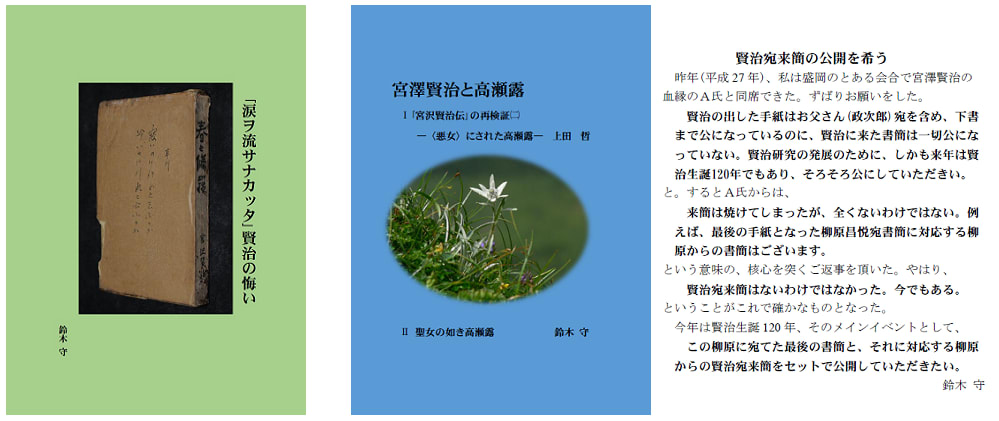
なお、既刊『羅須地人協会の真実―賢治昭和二年の上京―』、『宮澤賢治と高瀬露』につきましても同様ですが、こちらの場合はそれぞれ1,000円分(送料込)の郵便切手をお送り下さい。
☆『賢治と一緒に暮らした男-千葉恭を尋ねて-』 ☆『羅須地人協会の真実-賢治昭和2年の上京-』 ☆『羅須地人協会の終焉-その真実-』
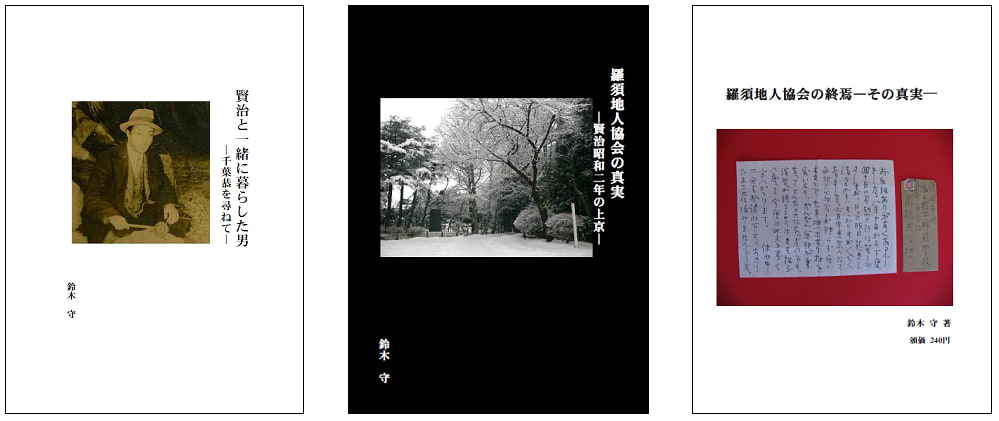
◇ 拙ブログ〝検証「羅須地人協会時代」〟において、各書の中身そのままで掲載をしています。
























