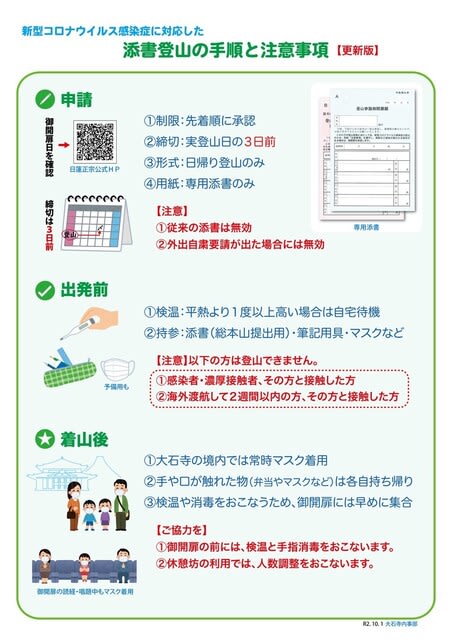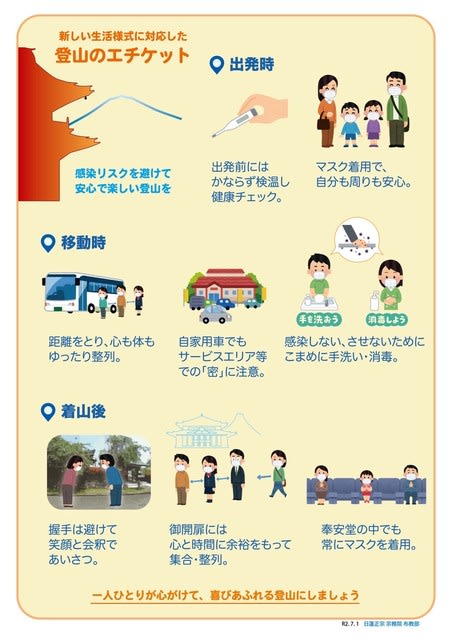正林寺御住職指導(R4.8月 第223号)
現代は、映像により視覚からの情報が主流であります。その目からの情報が多くの人を動かし大きな影響力を持ちます。そして、字幕なども映像と同時に伝わる技術も進歩しています。視覚に障害のある方においても点字により、または聴力を生かした伝え方が発達しています。
日蓮正宗公式HPでも映像を駆使した「バーチャルミュージアム 日蓮大聖人御聖誕800年展」特設サイトが公開されています。是非、ご覧ください。
インターネットが普及し、印刷された新聞等の活字離れが若者の間では起こり、紙媒体から電子媒体になりつつも、文字離れまではしていません。SNSなどは文字がなければ成り立たないツールでしょう。まさに「文字」は人間社会で生きていくための必要不可欠な、絶対になくてはならない大事なものです。
その文字も伝え方一つで、人間関係を円滑にもし、悪くもします。文字を書く場合や入力にも「尊い境涯にたって」不軽菩薩の振る舞いが日々の信行において「実践」すべき信心修行となります。九思一言を心がけて軽率な文字入力等は慎みましょう。
『諸宗問答抄』に曰く、
「文字は是(これ)一切衆生の心法の顕はれたる質(すがた)なり。されば人のかける物を以て其の人の心根を知って相(そう)する事あり。(中略)かきたる物を以て其の人の貧福をも相するなり。」(御書36)
当然ながら、仏の教えも文字が命脈となります。宗祖日蓮大聖人は『蓮盛抄』に、
「仏は文字に依って衆生を度し給ふなり。問ふ、其の証拠如何。答へて云はく、涅槃経十五に云はく『願はくば諸の衆生悉く是(これ)出世の文字を受持せよ』と。像法決疑経(けつぎきょう)に云はく『文字に依るが故に衆生を度し菩提を得る』云云。若し文字を離るれば何を以てか仏事とせん。」(御書28)
と仰せであります。仏様は文字によって人々を幸せにされます。その証拠については、涅槃経に仏様が願うことは一切衆生に釈尊の出世の本懐となる法華経の文字を受け持たせることであり、像法決疑経には仏が説いた文字により人々を救済し煩悩を菩提へと体得することができます。もし、仏説となる文字を離れる教えならば仏事とはならないとのことであります。
また、『諸宗問答抄』に、
「文字は是三世諸仏の気命(いのち)なり」(御書36)
と仰せであります。文字である経文により人々を救済され、文字である経典から離れれば、仏事とはならず救済できず幸せになることはありません。まさに仏が説かれる文字は命であります。己が智分を改めて、その気命(いのち)に帰命(きみょう)することが非常に大事となります。
八月は盂蘭盆会の月に当たります。御塔婆に認められた妙法蓮華経の文字に、故人の戒名等を認めることにより、仏の文字に帰入されて成仏を遂げることができます。同時に回向の意義から願主となられた方にも回りめぐって功徳を積むことになります。
仏が説かれた文字である経文は、爾前諸経ではなく「法華最第一」(法華経325)である法華経です。大聖人は『四条金吾殿御返事』に、
「法華経は釈迦如来の御志を書き顕はして此の音声を文字と成し給ふ。仏の御心はこの文字に備はれり」(御書621)
と仰せであります。釈尊自らの「声仏事を為す」(御書108)、音声を文字とされたのが法華経になります。釈尊入滅後、「経典の結集」(御書127)により弟子たちは一カ所に集まり、教えの散逸を防ぐため、教法を整理して各々が記憶していた釈尊の言葉(音声)を暗誦し合い、編集しました。経典の結集は、釈尊入滅の年に第1回結集、入滅後百年頃に第2回結集、紀元前三世紀頃に第3回結集、二世紀中期には第4回結集が行われました。(※「日蓮正宗入門」経典の結集 P55)
『報恩抄』に、
「阿難と文殊とは八年が間此の法華経の無量の義を一句一偈(げ)一字も残さず聴聞してありしが、仏の滅後に結集(けつじゅう)の時九百九十九人の阿羅漢(あらかん)が筆を染めてありしに、妙法蓮華経とかヽせて次に如是我聞と唱へさせ給ひしは、妙法蓮華経の五字は一部八巻二十八品の肝心にあらずや。」(御書1032)
と、釈尊の無量義を「一字も残さず聴聞(音声)」し「筆を染めて」文字にされたことを御教示であります。
まさに『祈祷抄』には、
「御悟りをば法華経と説きをかせ給へば、此の経の文字は即釈迦如来の御魂(みたま)なり。一々の文字は仏の御魂なれば、此の経を行ぜん人をば釈迦如来我が御眼の如くまぼ(守)り給ふべし。人の身に影のそ(添)へるがごとくそはせ給ふらん。いかでか祈りとならせ給はざるべき。」(御書624)
と仰せであります。その祈りは、まさしく『祈祷抄』に仰せである、
「法華経をもていのらむ祈りは必ず祈りとなるべし。(中略)必ず法華経の行者の祈りをかな(叶)ふべし。」(御書622)
との御指南に通じていきます。この祈りにより『木絵二像開眼の事』には、
「文字と成りて衆生を利益するなり。」(御書637)
と仰せである御利益へとなります。さらにそれは、
「仏の御意(みこころ)あらはれて法華の文字となれり。文字変じて又仏の御意となる。されば法華経をよませ給はむ人は、文字と思(おぼ)し食(め)す事なかれ。すなはち仏の御意なり。」(御書637)
との御指南からであり、「六万九千三百八十四文字の仏」のことでもあります。
その法華経を重んじるためには、法華経に説かれる「正直捨方便」と「不受余経一偈」を心肝に染める日々の信行が不可欠です。
「正直捨方便」は法華経方便品第二(法華経124)に説かれ、釈尊は法華経以前の四十余年間に説いてきた諸経は方便の教えであり、それら全てを捨てて無上の法華経を説かれました。
「不受余経一偈」は法華経譬喩品第三(法華経183)に説かれ、余経とは法華経以外の諸経のことで、真実の法華経のみを信じて、他経の一偈一句をも受持してはならないということであります。
難信難解な法華経は、「正直捨方便」と「不受余経一偈」を心肝に染めることにより以信得入することが可能となります。
以上の心得を信心の原点として『妙一尼御前御返事』に、
「法華経・釈迦・多宝・十方の諸仏菩薩・諸天善神等」(御書1467)
と仰せである、十界互具の御本尊は、まさに末法時代における究極の文字であることを確信し、『経王殿御返事』に仰せである、
「日蓮がたましひ(魂)をすみ(墨)にそめながしてかきて候ぞ、信じさせ給へ。仏の御意は法華経なり。日蓮がたましひは南無妙法蓮華経にすぎたるはなし。」(御書685)との御指南、つまり三大秘法の御本尊の御事であります。その相貌については『日女御前御返事』に、
「末法二百余年の比(ころ)、はじめて法華弘通のはたじるし(旗印)として顕はし奉るなり。是全く日蓮が自作にあらず、多宝塔中(たほうたっちゅう)の大牟尼世尊(だいむにせそん)・分身(ふんじん)の諸仏のすりかたぎ(摺形木)たる本尊なり。されば首題の五字は中央にかゝり、四大天王は宝塔の四方に坐し、釈迦・多宝・本化(ほんげ)の四菩薩肩を並べ、普賢(ふげん)・文殊(もんじゅ)等、舎利弗(しゃりほつ)・目連(もくれん)等座を屈し、(中略)妙法五字の光明(こうみょう)にてらされて本有(ほんぬ)の尊形(そんぎょう)となる。是を本尊とは申すなり」(御書1387)
と末法の正しい御本尊(曼陀羅)を御教示下されております。
『妙法曼陀羅供養事』に、
「此の曼陀羅(まんだら)は文字は五字七字にて候へども、三世諸仏の御師(中略)成仏得道の導師なり」(御書689)
と、さらに、
「末法の時のために、教主釈尊・多宝如来・十方分身(ふんじん)の諸仏を集めさせ給ふて一の仙薬をとヾめ給へり。所謂妙法蓮華経の五の文字なり。此の文字をば法慧(ほうえ)・功徳林(くどくりん)・金剛薩・(さった)・普賢(ふげん)・文殊(もんじゅ)・薬王・観音等にもあつらへさせ給はず。何(いか)に況んや迦葉・舎利弗等をや。上行菩薩等と申して四人の大菩薩まします。此の菩薩は釈迦如来、五百塵点劫(じんでんごう)よりこのかた御弟子とならせ給ひて、一念も仏をわすれずまします大菩薩を召し出だして授けさせ給へり」(御書690)
と、外用上行菩薩に託され、内証久遠元初の御本仏・宗祖日蓮大聖人の胸中に所持あそばす秘法であります。
その三大秘法の力用について『呵責謗法滅罪抄』に、
「法華経の文字の各の御身に入り替はらせ給ひて御助けあるとこそ覚ゆれ。」(御書718)
と仰せのように信力行力の如何により、守護されることを御指南であります。『曽谷入道殿御返事』に、
「経の文字は皆悉く生身(しょうじん)妙覚の御仏なり。(中略)仏は一々の文字を金色(こんじき)の釈尊と御覧有るべきなり。」(御書794)
と、経は単なる文字と思うことなかれ、生身の仏であると仰せであります。『法蓮抄』には、
「『今此三界皆是我有、其中衆生悉是吾子』等云云。教主釈尊は此の功徳を法華経の文字となして一切衆生の口になめさせ給ふ。」(御書815)
と仰せであります。自行においては御本尊への唱題、化他である下種折伏により世の中へ功徳を弘めることができる広宣流布へとつながります。
さらに、
「大音声(おんじょう)を出だして説いて云はく『仮使(たとい)法界に遍く断善の諸の衆生も一たび法華経を聞かば決定して菩提を成ぜん』云云。此の文字の中より大雨降りて無間地獄の炎をけす」(御書817)
と、末法の逆縁成仏、無間の獄にいる人をも救済されることを仰せであります。その所以は、
「法華経の文字は皆生身の仏なり(中略)仏種純熟せる人は仏と見奉る。されば経文に云はく『若し能く持つこと有らば即ち仏身を持つなり』等云云」(御書819)
との境界に至ることにより可能となります。「能く持つこと有らば即ち仏身を持つなり」とは、持つ法第一ならば、持つ人も第一となる信心につながります。
つまり、『妙心尼御前御返事』に、
「妙の文字は花のこのみとなるがごとく、半月の満月となるがごとく、変じて仏とならせ給ふ文字なり。されば経に云はく『能く此の経を持つは則ち仏身を持つなり』と。天台大師の云はく『一々文々是真仏なり』等云云。妙の文字は三十二相八十種好円備せさせ給ふ釈迦如来にておはしますを、我等が眼つたなくして文字とはみまいらせ候なり。譬へば、はちす(蓮)の子(み)の池の中に生(お)ひて候がやうに候。はちすの候を、としよりて候人は眼くらくしてみず。よる(夜)はかげ(影)の候を、やみ(暗)にみざるがごとし。されども此の妙の字は仏にておはし候なり。又、此の妙の文字は月なり、日なり、星なり、かヾみなり、衣なり、食なり、花なり、大地なり、大海なり。一切の功徳を合はせて妙の文字とならせ給ふ。又は如意宝珠のたまなり。かくのごとくしらせ給ふべし。くはしくは又々申すべし。」(御書1120)
と、妙の一字の徳と縁を結ぶ大切さについても御教示であります。
それはまた、法華経の『方便品第二』に、
「是の法は法位に住して(是法住法位)」(法華経119)
と説かれる意味にもつながると拝します。
大聖人の御精神である「立正安国」の文字について、御法主日如上人猊下は、
「総本山第二十六世日寛上人は『立正』の両字について、
『立正の両字は三箇の秘法を含むなり』(御書文段6)
と仰せであります。
すなわち『立正』とは、末法万年の闇を照らし、弘通するところの本門の本尊と戒壇と題目の三大秘法を立つることであり、国土安穏のためには、三大秘法を立つることこそ肝要であると仰せられているのであります。
また『安国』の両字については、
『文は唯日本及び現在に在り、意は閻浮及び未来に通ずべし』(御書文段5)
と仰せられています。
すなわち『国』とは、一往は日本国を指すも、再往は全世界、一閻浮提を指しているのであります。」(大日蓮 第918号 R4.8)
と御指南であります。
七月中は「お題目を一杯唱えていく」唱題行での徳を積み、「信の一字は元品の無明を切るところの利剣」により罪障消滅させていただきました。八月はさらなる「信行の前進」をはかり、改めて「今、求められている信行」を再確認し、「大事中の大事」である三大秘法の御本尊に絶対的確信を堅持し、御法主上人猊下の御指南を根本に精進することが大事であります。
最後に昨今、新興宗教の旧統一教会が話題となっています。世間一般の方には、宗教となれば仏教もすべて同じように錯覚される方もおります。五重相対等の判釈があるように同じではありません。下種折伏には丁寧に違いを教えていくことも必要となります。同時に、入会している人を邪宗邪義による「マインドコントロールからの脱却」をはかることが求められ、一日も早い脱会と「信心と申す」日蓮大聖人の正しい仏法により日蓮正宗の寺院・教会で謗法払いをされ、日々の信行においては三大秘法の御本尊に罪障消滅の祈りと真の救済である折伏行にチャレンジすることが大切であります。
宗祖日蓮大聖人『妙一尼御前御返事』に曰く、
「夫(それ)信心と申すは別にはこれなく候。妻のをとこ(夫)をおしむが如く、をとこの妻に命をすつるが如く、親の子をすてざるが如く、子の母にはなれざるが如くに、法華経・釈迦・多宝・十方の諸仏菩薩・諸天善神等に信を入れ奉りて、南無妙法蓮華経と唱へたてまつるを信心とは申し候なり。しかのみならず『正直捨方便(しょうじきしゃほうべん)、不(ふ)受(じゅ)余経(よきょう)一(いち)偈(げ)』の経文を、女のかゞみ(鏡)をすてざるが如く、男の刀をさすが如く、すこしもす(捨)つる心なく案じ給ふべく候。」(御書1467)