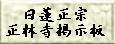年中行事の意義は、総本山富士大石寺に伝わる深遠な仏法を正しく伝えるとともに、僧俗がご報恩の心をもって親しく行事を奉修し、仏縁を深め、もって広宣流布への前進を期し、そして一人ひとりが積功累徳の信心修行をするところにあります。
日蓮大聖人御誕生会は、御本仏日蓮大聖人の末法ご出現をお祝い申し上げ、ご報恩のために奉修される行事です。
釈尊滅後一千年を正法時代、次の一千年を像法時代、その後を末法時代といいます。そして、正像二千年間は釈尊の教えで利益もありますが、末法の時代に入ると、釈尊の仏法は功力がなくなり前時代とは違った全世界的な戦いや不毛な論争が思想を混乱させ、人心が荒廃して濁悪の時代となります。このような時代になると釈尊の仏法では国家・人民・世界は救われなくなるのです。
この末法という時にたいして法華経では、涌出品にあらわれた上行等の地涌の菩薩がふたたび出現して衆生を救済されることが予証されており、神力品に「日月の光明の能く諸の幽冥を除くが如く斯の人世間に行じて能く衆生の闇を滅せん」と、その赫々たる人格、活動を説かれています。
この時に当って釈尊が法華経で説いた後五百歳広宣流布の金言通り、日蓮大聖人が末法万年尽未来際までの一切衆生を救済する御本仏として日本にご誕生になったのです。すなわち、承久の変の翌年、末法に入って一七一年、後堀河天皇の貞応元年(一二二二年)二月十六日に貫名次郎重忠を父とし、梅菊女を母として安房の国(千葉県)長狭郡東条小湊でご誕生あそばされ幼名を善日麿と称されました。
大聖人はご自身の出生を御書の中に「日蓮今生には貧窮下賤の者と生まれ」(佐渡御書)「日蓮は日本国東夷東条安房国、海辺の旃陀羅が子なり。」(佐渡御勘気抄)「民の家より出でて頭をそり袈裟をきたり」(妙法比丘尼御返事)と述べられているように、漁師の子としてご誕生されました。
このことはご自身示同凡夫のお姿として出生され、当時最下級の人民とされていた「旃陀羅」の子を名乗り、みずからが民衆の中に入って、末法濁悪の機根である一切の大衆を救済されるためにほかなりません。この凡夫そのままのお姿で、仏のお姿を示されるということは、他のいかなる宗教の神仏にも優れて大聖人のみが示されるご化導のお姿なのです。
つまり、私たちと同じ凡夫のお姿で、同じ裟婆の大地において、仏道修行の極まるところ仏の境涯があると示されることは、ご自身のお姿を通して私たちもまた、私たちの現在の姿形のまま、御本仏大聖人・御本尊にたいして真剣なる仏道修行により仏の境涯に至ると教えられているのです。
二月十六日は一往大聖人が安房の国に貫名重忠を父とし、梅菊を母としてお生まれになった日と考えますが、再往は久遠元初の御本仏出現の日であり、御本尊すなわち宝塔涌現の日であります。
現在総本山では、毎年二月十六日の大聖人御誕生会には、五重の塔のお塔開きが行なわれ、末寺においてもそれぞれ法要を修し、大聖人のご誕生をお祝い申し上げています。法華経宝塔品において、突然、多宝塔が涌現し、多宝仏が釈尊の説く法華経は皆な是れ真実なりと証明したのは、きわまるところ寿量文底の南無妙法蓮華経すなわち久遠元初名字の妙法蓮華経の真実を証明しているのであり、したがって多宝塔は大曼荼羅の姿でもあります。
この意義のもとに総本山では御法主上人が大衆を随え、御影堂においてご報恩の読経の後、五重の塔の〈お塔開き〉を行なわれ読経唱題してお誕生会を奉修しています。このお塔開きは大聖人の末法ご出現をあらわし、また五重の塔が西の方を向いているのは、大聖人の仏法が中国・インドを経て世界に広宣流布するようすを、太陽が東から昇って西を照らし、全世界に光明をおよぼすという現象になぞらえ、大聖人の仏法が西漸する意義を示しているのです。