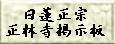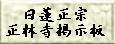創価学会会長・秋谷栄之助氏の目指す宗教改革の欺瞞を破す
時局協議会文書作成班4班
はじめに
池田大作氏ただ一人の慢心に起因する創価学会の仏法改変問題は、既に仏法の核心部分にまで及んでいる。一般会員を宗門から隔離させようとする学会幹部のしたたかな策動も、今や全国的に目立つようになってきた。これら学会幹部を恣意的に操る首謀者は、いうまでもなく学会の実質的権力者たる池田氏その人である。この池田創価学会の習癖は、氏を走狗(そうく)のように取り巻く首脳幹部の言動を考察することによって、より明確に看取(かんしゅ)することができよう。
本宗の僧俗は、彼等が並べ立てている「民主主義」「平和」「文化」「教育」「時代に開かれた」などの美辞麗句の陰に、宗史の改鼠(かいざん)や虚偽・捏造(ねつぞう)、一般学会信徒を酷使して止まない幹部たちの、欺瞞(ぎまん)に満ちた権威主義による権力者然とした姿が存在することを深く了知し、長く宗史に止めるべきである。
以下、『大白蓮華』の巻頭言を元に、創価学会会長・秋谷栄之助氏の発言から、その破法の体質を暴きたい。特に、
そして、お互いに励まし合い、同志の温かい絆を強くしながら、いわば『宗教革命』ともいうべき民衆仏法の大展開を成し遂げたのであります。(『大白蓮華』91年2月号・巻頭言)
と、文は通例の学会自賛の後の言葉ではあるが、氏は池田学会が好んで使う「宗教革命」をここで標榜している。もしこれが、マルチン・ルターの「宗教改革」を擬(なぞら)えていうのであれば、大石寺法門破壊・在家仏教独立の意志があることの自白である。
現今における池田学会の言動は、明らかにこの『ルターの改革構想』を模倣しており、マスメディアを使って、一般会員や世間に対してこれを諷喩(ふうゆ)しているのである。ここでは、その類似性の考察とともに、その欺瞞に満ちた邪義を破折することとする。
1.池田学会の目的
資料1.宗教改革以前
キリスト教におけるカトリシズムは、中世ヨーロッパの封建制度の中において、強大な法義的構造・権力的秩序を構築していた。そこには、唯一、教皇権によって統括された聖職者身分の階層秩序・支配体制のみが法的規定を持つ正統な教義であり、信徒個人の信仰は、神の定めた教会の伝統的諸権威・強制への、内面的な絶対服従を意味し、これに反するあらゆる信仰的内容はすべて「異端」として、世俗の権力の協力のもとに、きびしく禁圧されていた。
池田学会がいう「前時代的」「封建主義的」「開かれた宗門」という語意は、ヨーロッパにおける「宗教改革」以前のカトリシズムを日蓮正宗の伝統の教義に当てはめていうことである。
特に、池田学会においては、当家の「師弟相対の法門」「手続の師匠」が邪魔でならない。創価仏法の本質は、「池田本仏論」による在家仏教教団の構築、もしくは宗門の乗っ取りにある。したがって、当家の「手続の法門」における、
〈御本仏日蓮大聖人→御法主上人猊下→末寺の住職→信徒〉
と正しい筋目・道筋を立てて、本仏の功徳・力用を手中にする教義を、何とか、
〈御本仏日蓮大聖人=池田大作→民衆〉
に置き換える必要がある。しかし、これを露骨に示せば、謗法であることが明らかとなり、一般信徒が正信に目覚めてしまう。そのため、本来、対比すべきでない外道の沿革を、今回の池田発言問題に巧みに絡めて利用し、本宗の「宗教改革」と擬えて諷喩し、徐々に下種の仏法破壊を行ない、会員の洗脳に用いているのである。
本宗においては、宗祖大聖人の身延・池上両相承書がある以上、唯授一人の血脈相承を破失することは全く不可能である。
もし、仏法の本質を見下して、その弟子檀那を指して外道の族(やから)に擬似せしめんという虚構をなすならば、三類の強敵以外の何物でもない。
しかし、氏は、下種仏法を破壊せんがために、宗門の仏法守護の姿勢を、「権威・権力の横暴」とすり替えておいて、中世ヨーロッパ宗教革命当時の外道、キリスト教プロテスタントの者を称賛してやまないのである。いわく、
今日、キリスト教が、世界宗教となりえたのは、現実の生活に閉鎖的な教義に対して生き生きとした人間性回復を目指したルネッサンスの運動があり、そして聖職者の腐敗を糺し、原点たる聖書に戻ろうとした宗教改革など、数え切れないほどの歴史的な試練を経てきたからに他ならないのであります。(『大白蓮華』91年4月号・巻頭言)
『本因妙抄』における「唯授一人の血脈」、『御本尊七箇之相承』の「代代の聖人悉く日蓮」、『化儀抄』の「我に信を取るべし」の御文について、氏がいずれも信解することができないのは、こういった外道礼讃・内外混濁のためである。
故に、氏は次のようにも主張するのである。
宗門は世界どころか狭い宗内に閉じこもり、世間の苦労も知らず、いたずらに難解な教義を説き、信徒を見下す権威主義に陥っている姿は、まことに気の毒という他はなく、その狭量さにはあきれるばかりであります。(『大白蓮華』91年7月号・巻頭言)
氏は、御法主上人に対し、「大聖人の最大深秘の法門を説くな」といっているのである。大石寺門流の弟子檀那として、誰がこれを肯定し得ようか。
2.唯授一人の血脈相承
現今の池田学会における、唯授一人の御相承に対する妄言・邪見を吐く姿は、まさに悪鬼入其身そのものである。ところが、こと血脈相承・御法主上人に対する理解は、実に稚拙である。すなわち、教義の深遠さに対して、実生活上の御利益を重視するあまり、御本尊への信仰と折伏弘教のみをもって信仰のすべてとし、伝統化儀を等閑視している。あるいは、知ってこれを改変しようとするのであろうか。
御法主上人に対する池田学会の理解は、
1.御本尊書写係
2.宗門という僧団・組織の首領
3.現今の天皇制の如き単なる象徴
4.警察や検事の如く謗法逸脱があった時の指摘糾弾係
5.裁判官の如く教義面や行政面で異義論争が起こった時
の判定官
などという、いずれも皮相的、一面的なものでしかない。
仏法とは、本仏の開悟せられた絶対的な甚深の一法を、いかに信受し、かつ久住並びに流布せしめていくかという点にある。そのため、まず本仏本法の法体が、この事相の差別世界において、常住不変でなければならない。この重大な責任を本然的に背負って、生きた人間が流通伝持していかなければならないのである。ここに、相伝の重要性があり、大聖人滅後の僧俗の責任と義務が存するのである。その根本が、唯授一人の法体血脈の相承である。
したがって、「民主の時代」であろうがなかろうが、「新思考」などといって、大聖人の正法の本質を改変せしめるような、新たな根本的な法の創造をしてはならない。また、「民主の時代」だからといって、唯授一人の血脈を、信徒を含めた大衆が共有するのだなどと考えてもならない。
仏の法をあやまたず流伝する必要性から、釈尊は滅後の化導においても、時と機とに従って、それぞれ流通の法が付嘱されている。そのため、付法蔵の24人が定められ、神力嘱累における本化・迹化の付嘱が明示され、生きた社会に流伝するための僧伽の位置付けがなされている。
相承とは、相伝承継の意であり、「相い承る」ことである。これは、法義を未来世に久住せしめ、広宣流布せしめることに目的がある。また、付嘱の語も「付法嘱託」の義で、法を付して後世へ嘱託する意味である。
故に、釈尊の法は摩訶迦葉・阿難に、天台大師は章安に、伝教大師は義真に、それぞれ直授相承せられ、他家においてもその次第を決して蔑(ないがし)ろにすることはない。
当然ながら、当家における付嘱の根源は、外用の辺に約せば多宝塔中における神力品の結要付嘱に存するが、内証本地の辺に約せば久遠元初の結要付嘱に存する。この久遠元初の結要付嘱は、本因妙の教主日蓮大聖人の法体の付嘱の意であるから、具体的に末法においては、『一期弘法付嘱書』に、
「血脈の次第 日蓮日興」(全集1600)
とあるように、宗祖大聖人より日興上人への法体血脈の相承にその根源が存する。以来、嫡々代々の御歴代上人を経て、御当代日顕上人に至る相承を唯授一人の血脈相承というのであり、中途の時期において、他家・俗人から発するものは、絶対に「血脈」とも「相承」ともいわないのである。
この唯授一人という方法を用いられる理由として、『報恩抄送文』には、
「親疎と無く法門と申すは心に入れぬ人にはいはぬ事にて候ぞ御心得候へ」(全集330)
と、法門伝持において、特に根本の法義は器に非ざれば説くものではないと戒められている。ゆえに、三位日順師の『本門心底抄』には、
「願くば門徒の法器を撰して密に面授相伝すべし若し外人他見に及ばば還って誹謗の邪難を加へん、努(ゆ)め努め偏執の族に対して心底を披露すべからざるなり」(富要2-32)
とある。すなわち、法門の深義・内証の面授相伝は、法器を撰び、密かに行なわれるべきであり、門外人・他門・邪見・我慢偏執の徒輩に公開するならば、誹謗の邪難が加えられることが示されている。血脈法水の純粋性を守るためにも、僧団内の異義混乱を招かないためにも、唯授一人の手段にこそ令法久住の枢鍵があるのである。
日寛上人も、『当流行事抄』に、
「六老の次第は受戒の前後に由り、伝法の有無は智徳の浅深に依る」(聖典951)
と仰せられている。
日蓮大聖人がいかに付法伝授に留意あそばされ、血脈相承を重視せられていたかについて、
「当世の学者は血脈相承を習い失なう故に之を知らざるなり故に相構え相構えて秘す可く秘す可き法門なり」(『立正観抄』・全集530)
「此の経は相伝に有らざれば知り難し」(『一代聖教大意』・全集398)
と仰せられ、相伝なくしては仏法の真意を心得ることはできないと御教示されている。
また、付嘱がなければ、たとえ仏法の真意を心得ていたとしても、法の真意を説くことは許されないのである。その規律の一端を『法華行者逢難事』に、
「竜樹・天親は共に千部の論師なり、但権大乗を申べて法
此に口
華経をば心に存して口に吐きたまわず 、天台伝教は
伝有り
之を宣べて本門の本尊と四菩薩と戒壇と南無妙法蓮華経の五字と之を残したもう、所詮一には仏・授与したまわざるが故に」(全集965)
この類文は随所に存するが、たとえこの法義の内容を知っていても、仏より付嘱(相承)がなければ、決してこれを説くことは許されない、というのが仏法の規律である。
総本山第56世日応上人の『弁惑観心抄』の御指南に、
「唯授一人嫡々血脈相承にも別付惣付の二箇あり、其の別付とは則ち法体相承にして、惣付とは法門相承なり、而して法体別付を受け玉ひたる師を真の唯授一人正嫡血脈付法の大導師と云ふべし」(同書211)
「吾大石寺は宗祖・開山より唯授一人法体別付の血脈を紹継するを以て五十有余代の今日に至るも、所信の法体確立して毫も異義を構へたる者一人もなし。而して別付の法体とは則ち吾山に秘蔵する本門戒壇の大御本尊是なり」(同書212)
「金口の記別は彼の書巻授与の如きの比にあらず、此の金口の血脈こそ宗祖の法魂を写し本尊の極意を伝るものなり。之を真の唯授一人と云ふ」(同書219)
と懇切に御教示されるように、代々唯授一人の相承とは、内証法体の相承であり、別付嘱とも称し奉るのである。これこそ、
「宗祖大聖人の御法魂」を写瓶あそばされ、「本尊の極意」を師伝せらるるところの当家の法門の究極であり、御法主上人以外に、全く知ることあたわざる唯仏与仏の奥義なのである。
この御法魂を肉団の胸中に伝持あそばされるがゆえに、宗内の僧俗は、恭敬合掌の礼をもって恭順拝信し奉るのである。故に、『百六箇抄』に、
「上首已下並に末弟等異論無く尽未来際に至るまで予が存日の如く日興嫡嫡付法の上人を以て総貫首と仰ぐ可き者なり」(全集869)
また、『御本尊七箇之相承』にも
「代代の聖人悉く日蓮なりと申す意なり」(聖典379)
と仰せられているのである。
当宗の信仰においては、御法魂を伝持あそばされる御法主上人の御指南に信伏随順し奉り、三秘総在の大御本尊を拝し奉ることこそ成仏の要諦なのである。ここを以て『身延山付嘱書』には、
「背く在家出家どもの輩は非法の衆たるべきなり」(全集1600)
と御制戒あそばされ、第2祖日興上人も、『佐渡国法華講衆御返事』に、
「なをなをこのほうもんは、しでしをたゞしてほとけになり候。しでしだにもちがい候へば、おなじほくゑをたもちまいらせて候へども、むげんぢごくにおち候也」(歴全1-183)
あるいは、また『日興遺誡置文』には、
「衆議為りと雖も仏法に相違有らば貫首之を摧く可き事」(全集1618)
と御指南されている。
総本山第65世日淳上人は、『弁惑観心抄』の序文に、
「由来日蓮大聖人の門流に於ては聖祖は二祖日興上人の血脈相承し玉ひて大導師たるべしと御遺命あり三祖日目上人その跡を承継し玉ひて相承の次第炳乎として明かに今日に至つてをる。よつて此の相承を大宗として各々師弟の関係をしうすれば自ら正統の信行に住することができるのである。然るに中間に於て我慢の徒輩は此れを省みず人情に固執して逸脱をしその結果己義を構へ邪義に堕したのである」
と明快に御教示あそばされている。
すなわち、いかに法華経を持ち、当家の御本尊を受持しても、法体血脈相承を伝持あそばされる御法主上人に対し奉る師弟相対の道を正さないかぎり、成仏はありえない。まさに無間地獄なりとの、厳格にして甚深の御教示である。本宗僧俗の一切は、この師弟の筋目を正すとき、はじめて信心の法水が流れ通うのである。すなわち、当宗においては智解をもって成仏するのではなく、御法主上人に信伏し奉る師弟相対の化儀の上に立脚した信の一字をもって成仏が叶うのである。
『御義口伝』に、
「成仏するより外の神通と秘密とは之れ無きなり、此の無作の三身をば一字を以て得たり所謂信の一字なり」(全集753)
とあり、また日有上人の『化儀抄』にも、
「信と云ひ、血脈と云ひ、法水と云ふ事は同じ事なり信が動ぜざれば其の筋目違ふべからざるなり、違はずんば血脈法水は違ふべからず」(富要1-64)
と御教示である。すなわち、信の一念をもって法体血脈に対する師弟の筋目を正すとき、はじめて末法凡下の我等の生命にも、信心の血脈が通い、法水も流れるのである。その血脈法水を事行の上に御所持あそばされるお方は、いうまでもなく宗祖日蓮大聖人より嫡々付法相承なされた御当代の御法主上人であらせられる。その法体血脈(再往跨節の血脈)に対する信心によって、我々僧俗に流れる血脈は、一往当分の信心の血脈と解しておくべきである。
ところが氏は、これを全く信解できていないのである。いい分の中には、
「民主の時代」にあっては、一人一人が、本当に自由に語り合い、平等に接し、人間として尊敬し合わなくてはならないし、いわんや信仰の世界には何ら差別があってはならないと思うのであります。
大聖人は「今日蓮が弟子檀那又又かくのごとし(中略)若し然れば貴賤上下をえらばず南無妙法蓮華経と・となうるものは我が身宝塔にして我が身又多宝如来なり」(13
04ページ)と仰せであります。(『大白蓮華』91年2月号・巻頭言)
と、常にこのように平気で御書の偏読をして、平等面だけを主張するのである。
氏が引いた『阿仏房御書』は、見宝塔品の多宝塔涌現について、阿仏房の質疑に答えられたものである。また、時期的にいえば、順徳天皇の御陵を護り、日夜朝暮に念仏三昧を行ずること30年に及ぶ阿仏房夫妻が、捨邪帰正し、大聖人に奉侍して間もない文永9年3月13日のもので、大聖人が『開目抄』を著わされた翌月に当たる。すなわち、一切衆生の盲目を開かれるべく、御自身が本地久遠元初の自受用身にましますことを明かされた直後に当たっているのである。
大聖人は、氏が引くところのすぐ上の文において、『法華文句』の証前起後「二重の宝塔」にことを寄せられ、信心未熟の機根に照らし、種脱の決判をされないまま、氏が「(中略)」として読み飛ばした、
「末法に入って法華経を持つ男女の・すがたより外には宝塔なきなり」(全集1304)
と法華経の諸経中王の実義と、諸法実相・十如同体の説法による十界皆成の妙理の開顕を特筆して御教示せられ、もって阿仏房自身の信行倍増を促されんとされた御文なのである。
氏は、この御文をもって「我れ得たり」と思ったのであろうが、深意を拝そうともせず、御本仏の大慈大悲の御教示を利用せんとしたことによる、まことに短絡的な解釈である。
また氏の考えは、正信会の徒輩の考え方そのものでもある。
すなわち、前述の『化儀抄』の一文と、
「仏の行体をなす人は師範たりとも礼儀を致すべし、本寺住持の前に於ては我が取り立ての弟子たりとも等輩の様に申し振舞ふなり、信は公物なるが故なり云云」(富要1-70)
の中の「信は公物」の一文を結び付け、しかも総付嘱の上にいわれた「血脈・法水」を、法体別付の唯授一人相承のものと曲解して、「法主の血脈法水も信と同様に公物だ」と主張し、あたかも御法主上人を一般僧侶と同格同等のように喧伝する短見者と同類と見ることができる。
このような切り文をあちこちに貼り付けて、勝手な解釈を個々まちまちにわめきたてるならば、大聖人御建立の法門の綱格は一瞬にして倒壊してしまう。すなわち、これは邪宗他門の異流義である。
日淳上人は、
「仏法に於て相承の義が重要視されるのは、仏法が惑乱されることを恐れるからであつて、即ち魔族が仏法を破るからである。そのため展転相承を厳にして、それを確実に証明し給ふのである。」(淳全1324)
秋谷氏よ。伏して思慮せよ。「魔族」とは貴殿等のことである。
さらに、日淳上人は、
「日蓮正宗では大聖人の教の奥底を日興上人が承継遊ばされ歴代の上人が順次相伝遊ばされて参つたのであります。一器の水を一器に移すのと同じに相ひ伝へて今に至つてをるわけであります。」(淳全1256)
と御指南なされている。
秋谷氏よ。池田氏はその器ではない。血脈相承もなく、法水の滴(しずく)も受けていないのである。
また『日蓮正宗要義』には、
「大聖人が観心本尊抄に
『前代未聞の故に耳目を驚動し心意を迷惑す。請ふ重
ねて之を説け、委細に之を聞かん』(新定二-九六八)
と重々の請誡を構えられて説き出されたところは五重三
段であり、その究竟目的は文底三段にあった。この文底三
段の正宗と流通の解釈が難解難入であり、諸師百家蘭菊を
競うもほとんど肯綮に当たっていない。『前代未聞』とは
釈尊一代の施化を一括してこれを判釈した天台伝教の未弘
の法を意味する。『心意迷惑』とはこの天台の法門即ち釈
尊の一代化導に眼を奪われる故に、末法出現の大法を聞い
ても心に迷いを生じて、正解に到達できない者が多いこと
を指すのである。その証拠に文書保存の目的をもって本尊
抄を賜った富木常忍自身、大聖人の真意に迷い種々の質問
をなしており、果して終身の時の了解のいかがであったか
も疑わしい。この理由として
一、大聖人の仏法が五段の相対を経て、従浅至深し、漸く
その幽微を拝するに足る深固幽遠無人能到の法義である
こと。
二、大聖人随自意の施化においては本地の幽微下種本因妙
を明確に立てられるも、未だ一宗弘通の初めであるから
一般への賜書においては、その対告の人にしたがって表
現に猶予進退があられたこと。
三、弟子檀那にもそれぞれ機に堪と不堪とあり、もし五段
の相対による本懐の宗旨のすべてを示せば、生疑不信の
恐れあるためあえて体信の弟子の外は肝心をのべられな
かったこと、これは報恩抄送文の
『親疎と無く法門と申すは心に入れぬ人にはいはぬ事
にて候ぞ。御心得候へ』(新定二-一五四五)
の文に明らかに拝されよう。更には三大秘法抄において、
この法門を書いて留めなかったならば、おそらく法門未
熟の遺弟らが誤った讒言を加えるであろうことを配慮さ
れていることからも、令法久住に対して弟子の法門領解
の程度に信頼をおけないものがあったことが看取される。
四、このように弟子の領解も高低様々であって、達者少な
き道理、もし抛置する時は末代に向って大聖人本懐の根
本義を失う恐れあること。
以上の事情により、大聖人が末法万年のためこの正法深
義を後世に誤りなく伝えしめようとお考えになる場合、よ
く大聖人と一体の境地に至って疑いなくその法義を信解す
る弟子を撰び、令法久住のため法門法体の一切を付嘱され
ることはけだし当然である。」
と明確に御教示のように、我等末代の凡夫は、大聖人御内証の法水を伝持あそばされる、時の御法主上人の弟子檀那として、御指南に随順し奉る信念をもって、本門戒壇の大御本尊を拝し奉るとき、はじめて宗祖大聖人の御内証、すなわち元初の一念が我が身心に流れ伝わるのである。ここに即身成仏の境界が開かれるのである。
氏よ、この唯授一人の血脈相承の法門を信解したまえ。
氏は、この宗祖日蓮大聖人究竟の法体を根本本源とする、御開山日興上人、日目上人の流れを汲んだ第9世日有上人の『化儀抄』、第26世日寛上人の『六巻抄』等々の、全ての御歴代御相伝書を破壊霧散したいのであろう。その上で、「民主化」「開かれた宗門」という謳(うた)い文句によって、常住不変たる大聖人の法門を、自分達の都合の良いように、いつでも改変できるようにしたいのであろう。しかし、日蓮正宗の僧侶及び法華講衆は、この根本の法体を破失して、大石寺法門が存続するなどと思っている者はいないのである。
3.キリスト教の「宗教改革」の模倣
資料2.宗教改革の前夜
ヨーロッパ中世末期よりルネッサンスに至る過程において、十字軍の失敗等により、封建貴族・教職は没落し、ローマ教皇権の衰退史となる。一方、十字軍で巨利を占めた市民階級が興起し、それまであまり強くなかった国王が、下層市民階級と結んで、封建貴族・教職を抑え、中央集権的勢力の強大化をはかり、腐敗堕落の底にあった教皇庁の無力化を画策した。その間、仏王フィリップ4世(1294~1303)による教皇のバビロニア捕囚(またはアビニョン捕囚1309~77)が起こり、教皇の権威は失墜、道徳は頽廃し、各地で分裂と闘争が支配した。このような教会の腐敗に対し、ウィリク(1320~84)やフス(1369~1415)のような改革家があらわれて、聖書の教会に帰るように説いた。
既に時局協議会から出された文書により、破折がなされている中野毅氏の「檀家制度の形成とその影響」、あるいは堅樹院日好の異流義を正当化する高岡輝信氏の理論、「神札問題」などにみられる宗門汚濁論の展開の理由とその必要性はここにもある。
池田学会にとって、「宗教改革」を興起せしめるためには、その「改革の証」として、宗内僧侶の汚損が絶対に必要であった。そのためには、末法における本宗僧侶の本質の改変を目指すことになる。すなわち「小乗戒律の宣揚」、および「宗史の改鼠」である。
もし、本宗僧侶が、その意味で腐敗・堕落していたのならば、金欲しさに学会幹部に媚(こ)び諂(へつら)い、教義を改変し、三大秘法を破失していたであろう。しかし、本宗僧侶はそうではない。
日蓮正宗における僧侶存在の意義は、師弟相対の法門化儀を固く持ち、不変不滅の正法を厳護するところに存する。しかも、この僧は、『盂蘭盆御書』における、
「此僧は無戒なり無智なり二百五十戒一戒も持つことなし三千の威儀一も持たず、智慧は牛馬にるいし威儀は猿猴ににて候へども、あをぐところは釈迦仏・信ずる法は法華経なり(中略)父母・祖父・祖母・乃至七代の末までも・とぶらうべき僧」(全集1430)
である。ここにおいて、無戒と破戒とを混同してはならない。宗祖大聖人が、本来本有の名字凡夫位に居して、法華本門の本因妙を弘宣されたように、末法は「教弥実位弥下」であることを案ずべきである。
しかるに、池田学会は、本宗僧侶を爾前権教の人師に類し、あたかも迦葉・阿難等の羅漢の極位に居することが正道であるかのように宣揚している。しかも、それをもって、いかにも宗内僧侶が戒律を破り、権威や権力をもって横暴を極めているように喧伝しているのである。いわく、
残念なことに、宗門は大聖人の仏法を奉じているとはいえ、権威で民衆を見下し、屈服させるような姿であります。これは、大聖人の御精神に背く偽善であり、また人々に迷惑をかけるような数々の社会性に反する行動、非常識な言動は、およそ仏法者の精神に反するものと断じられても止むを得ない状況であります。(『大白蓮華』91年6月号・巻頭言)
残念なことに、宗門はあいも変わらず、権威をかさにきて、正論には耳を傾けず、社会的にみても全く不条理としか思えない独善的な振る舞いを続けており、その姿は常に信徒を思いやられた大聖人のお心に反するものであると断言しておきたい。(『大白蓮華』91年8月号・巻頭言)
と。そして、その責任を過去へ追いやるためと、自らの大義名分のために、池田学会としては、ウィリクやフスのような教権と俗権の分離や教会統治体制の変革、神の掟としての聖書を中心に据え、それに根拠をもたない教会の慣行・教義を批判したとするような改革家がいたことを、捏造してまでも宗門の歴史に存在させる必要があった。
周知のように、平成3年5月15日付『創価新報』に掲載された、驚くべき我意・我見の主張、堅樹院日好の異流義を正当化する創価学会副学生部長高岡輝信氏の妄見がこれである。
これは、「単なる史実の誤認」などという単純な問題ではない。そこには、巧妙にして悪辣なる陰謀が隠されている。
すなわち、本門戒壇の大御本尊を否定した、大謗法の堅樹院日好をわざわざ正当化した理由は、池田氏が主張する御書直結論「経巻相承」や、大聖人・大御本尊直結論「本宗血脈否定論」という邪義を正当化するためである。同時に、いかにも「宗門とは、歴史上宗門内に発生した改革派をことごとに弾圧し、狭量で権威・権力主義は今に始まったことではない」と吹聴して、「これを是正せんとする学会にこそ正義がある」という大義名分を作り上げることが目的だったのである。
池田学会とは、己の邪義・邪見を正当化するためなら、日蓮正宗の宗史をも捏造・改鼠(かいざん)するという、大謗法集団である。
この大謗法の故に、宗門から出された歴史の真実を表わす教導書に、いまだ反論もできないでいる。
今後、氏は、識者と言わず、大学教授といわず、キリスト教プロテスタントの人々に御書の解釈をしてもらい、彼等から血脈を受けたとでもいい出しかねないことを、宗門としては危惧するものである。
資料3.ルターの改革構想
マルティン・ルター(1483~1546)がヴィッテンベルク大学助教授の頃、彼は「ただ恵みにより、信仰により、キリストの故に、人は神の前に義とされる」という宗教改革の根本原理「塔の体験」(1514? 13~19)を体得し、革命への内的用意がなされる。
そして1517年、ルターがヴィッテンベルク城教会の門扉に95箇条の論題を公示し、敢然とローマ教会の贖宥券(免罪符)の販売に反対を表明したことにより、宗教改革は始まった。教皇レオ10世はルターに破門威嚇状を送り、彼は大衆の面前でこれを焼く。新帝カール5世もヴォルムス国会にルターを召喚し、国法でその処罰を決定した。これに対し、ルターは当時急速に発展しつつあった印刷技術を存分に活用し、宗教改革の3大論文その他を矢継ぎばやに発表したのである。
その改革論のうち『ドイツ国民のキリスト教貴族に与う』は、ルターが初めてドイツ国民としての国民意識に立って、ローマ教皇勢力によるあくどい財政的収奪や、そのほか国民生活を圧迫して正しい信仰を損なう悪弊を列挙し、教会当局者が無能を暴露して、貴族に教会生活全般の改革を助けるよう呼び掛けた。そこには一般に特権的な身分としての聖職者の否定、いわゆる「万人祭司主義」(allgemeines Priestertum)の理念が、聖書に基づいて展開されている。
またルターの「信仰義認論」によるところの「自由」とは、『キリスト者の自由』によれば、律法の前で露呈される罪からの開放、キリストの福音への進行のみによって神の前に義とされた、キリスト者の霊的・内的な自由のことであり、肉体的・外的存在としては、自由な魂の慶びにあふれて、隣人への奉仕に身をささげる神の僕と説いている。
さて、件(くだん)の「塔の体験」を、池田学会流に置き換えれば、「ただご利益により、信心により、大聖人の故に、人は御本尊の前に義とされる」ということになるのであろう。氏の、
だれもが等しく「仏に成る」ことができることから、徹底した平等主義、民主主義の思想に貫かれており、そこには宗教的特権を持つ人間が、権威をふるう余地などはありえない。(『大白蓮華』91年8月号・巻頭言)
との言動からも明らかである。
『ヴィッテンベルク城教会の門扉の95箇条の論題』とは、あの虚偽・捏造をもととする、傲慢不遜な9項目の『お伺い』文書に始まる。
また、『贖宥符(しょくゆうふ)』を塔婆供養に当てたことはいうまでもない。
『教皇レオ10世の破門威嚇状』とは、総講頭資格喪失。
『カール5世の国法でその処罰』は、世情を賑(にぎ)わす「絵画不正取引疑惑」等であろう。国法を犯しながら、これを「法難だ、法難だ」といいまくるのは、このためであろう。
そして、当時の印刷技術の応用は、そのまま現代の情報化社会を巧みに操った全国衛生放送、『聖教新聞』『創価新報』その他の謀略情報などであり、信徒の洗脳を図ることである。
そして、『ドイツ国民のキリスト教貴族に与う』の「万人祭司主義」こそは、氏のいう、
また檀家制度を墨守し、あたかも寺院、僧侶中心の儀式こそ、宗教の要であるかのような考え方も、決して大聖人の御精神にかなうものではないと断言しておきたい。これらは、まさに封建時代の残滓であり、今こそ、それを打ち破り、世界宗教にふさわしい宗風を確立する時であります。(『大白蓮華』・91年5月号・巻頭言)
であろう。上記に関して、いずれも既に宗門より破折がなされているので、ここでは言及しない。ただ、氏の発言を考察すると、今回の問題における池田学会の謀略は、ルターの「宗教改革」に擬えたものであることは明白である。本年(平成3年・1991年)1月10日、池田氏自身が、「俺はマルチンルターになる」「日本で宗教革命の歴史はなかった。今これをやるのだ」等の発言をしたといわれているが、これらの発言は、上記の考察よりみて、事実である可能性が濃厚である。
4.52年路線の踏襲
以上のことから、池田学会は10年前の問題に関しても、全く無慚無愧であったとしかいいようがない。その証拠に、当時発覚した『北条文書』『山崎・八尋文書』そのままの言行が、現在もなされているではないか。いわく、
『北条文書』 昭和49年6月18日付
「 報告者 北条 浩
4、情況判断
猊下の心理は、一時的なものではない。今こんな発言を
したら、宗門がメチャメチャになってしまうことも考えな
いのではないか、困るのは学会だと思っているのだろう。
宗門は完全な派閥で、猊下と総監とは主導権争いになって
いるのではないか。
長期的に見れば、うまくわかれる以外にないと思う。本
質は、カソリックとプロテスタントのような違いである。
戦術的には、すぐ決裂状態となることは避けて、早瀬理
事とのパイプ(山崎・八尋が話し易い関係にあります)を
太くするとか、当面猊下の異常心理をしづめ、新しい進路
を開きたいと考えます。
但し、やる時がきたら、徹底的に戦いたいと思います。
以上、甚だ要をえないご報告で恐縮ですが、口頭で申上
る機を賜わらばその時にご報告申上たいと存じます。」
『山崎・八尋文書』 昭和49年4月12日
「 報告者 山崎・八尋
今後の私達の作業の進め方について。
本山の問題については、ほぼ全容をつかみましたが、今
後どのように処理して行くかについて二とおり考えられま
す。一つは、本山とはいずれ関係を清算せざるを得ないか
ら、学会に火の粉がふりかからない範囲で、つまり、向こ
う三年間の安全確保をはかり、その間、学会との関係では
いつでも清算できるようにしておくという方法であり、い
ま一つは、長期にわたる本山管理の仕掛けを今やっておい
て背後を固めるという方法です。
本山管理に介入することは、火中の栗をひろう結果にな
りかねない危険が多分にあります。
しかし、私の考えでは本山、正宗は、党や大学、あるい
は民音以上に学会にとっては存在価値のある外郭だと思わ
れ、これを安定的に引きつけておくことは、広布戦略の上
で欠かせない要素ではないかと思われます。こうした観点
から、後者の路線ですすむしかないように思われます。そ
のための布石としては、
①本山事務機構(法人事務、経理事務の実質的支配)
②財政面の支配(学会依存度を高める)
③渉外面の支配
④信者に対する統率権の支配(宗制・宗規における法華
講総講頭の権限の確立、海外布教権の確立等)
⑤墓地、典礼の執行権の移譲
⑥総代による末寺支配
が必要です。これらのことは機会をとらえながら、さりげ
なく行うことが必要であり今回のことは、①、②、③、を確
立し更に④まで確立できるチャンスではあります。
いずれにせよ、先生の高度の判断によって決せられるべき
と思いますので、ご裁断をあおぐ次第です。」
要するに、現況から判断する限り、52年路線から一歩も脱していない。10年前の懴悔は真っ赤な嘘だったのである。
よって、秋谷氏のいう「宗教革命」の本意には、池田学会の宗門からの独立路線、在家仏教教団の確立、もしくは宗門の乗っ取りの意志があることは明白なのである。
む す び
今現在、日蓮正宗と池田学会との問題は、学会幹部の祭司化(聖職者化)、という化儀破壊の実践によって、もはや後戻りできないところまで来てしまっている。
当然ながら、日蓮正宗は、創価学会の邪義による化儀の破壊行為を、永久に認めるところではない。しかし、池田学会は、今更「学会葬は間違いであった」と、自らの邪法行為を認めるわけにもいかなくなっている。
なぜなら、故人を地獄へと引き堕とす大謗法行為と知りながら、組織を挙げて学会葬を強要したことは、そのまま遺族や会員を騙(だま)したことであり、死者に対するこの上ない愚弄侮蔑だからである。すなわち、この問題により、全国的に、既に学会葬を執行させられてしまった遺族から、慰謝料請求訴訟が起こされる可能性があり、学会とて、これに抗しきれるものではないからである。よって、池田学会は、何が何でもこの破法を正当化せざるを得なくなったのである。
これは、まさに池田大作氏並びに秋谷栄之助氏以下学会首脳幹部の行なってきた、種々の悪業の因縁のしからしむるところである。
この期に及んで、いまだ秋谷氏のように、血脈の正師を忘れ、ただ池田邪師に盲従して、親の成仏よりも、また子の成仏よりも、己の幹部としての地位・名声・物質的欲望の充足を願い望む者がいたならば、その者は池田邪教に諂曲(てんごく)した不知恩・大謗法の輩と断ぜられなければならない。
早く邪法を棄損(きえん)し、信仰の寸心を改めて、速やかに正法正師の正義に信順すべきである。
以 上