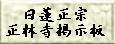(大日蓮H3.11月 第549号転載)
通 告 文
最近、創価学会では、会員のみの同志葬・友人葬と称する僧侶不在の葬儀(以下、学会葬という)を執行するなど、組織を挙げて、本宗伝統の化儀を改変しております。これは、まさに大聖人の仏法と富士の立義を破壊する謗法行為であり、日蓮正宗として、絶対に認めることはできません。
一 日蓮正宗の信仰の根幹は、大聖人・日興上人以来の師弟相対の信心化儀を中心とした、化儀即法体の法門にあります。したがって、本宗の信徒は、下種三宝を帰命の依止処として、師弟相対の信心化儀を修することによって、はじめて所願が成就するのであります。下種三宝とは、仏宝は本仏日蓮大聖人、法宝は本門戒壇の大御本尊、僧宝は第二十六世日寛上人が、
「所謂僧宝とは日興上人を首と為す、是れ則ち秘法伝授の御弟子なるが故なり」
と仰せのごとく、唯我与我の日興上人をはじめとして、唯授一人血脈付法の御歴代上人の全てにわたるのであります。故に、本宗の僧俗は御法主上人を仏法の大師匠として、師弟相対の信心に励まなければなりません。さらに、御法主上人に信伏随従する一般僧侶も僧宝に含まれますから、信徒各位は、所属寺院の住職・主管を血脈法水への手続の師匠と心得なければなりません。
日寛上人は、『当流行事抄』において、
「但吾が富山のみ蓮祖所立の門流なり、故に開山已来化儀・化法四百余年全く蓮師の如し」
とお示しですが、根本行である勤行を中心とする本宗伝統の信心化儀の一切は、その大綱において、唯授一人の法体血脈と、それに基づく総本山の山法山規等によって、大聖人御入滅より七百年を経た現在まで、厳然と伝わっているのであります。したがって、およそ本宗の信徒である以上、必ず宗門の定める化儀作法に従って、信行に励まなければなりません。
二 そもそも本宗における葬儀とは、故人の臨終の一念を扶助し、臨終に正念を遂げた者も遂げられなかった者も、ことごとく、本有の寂光へと導き、本因妙の即身成仏の本懐を遂げしめる重要な儀式であります。すなわち、臨終の正念が各自の信心の厚薄によるのに対し、葬儀は、故人の即身成仏を願う遺族親族等の志によって執行され、下種三宝の当体たる御本尊の徳用によって、その願いが成就するのであります。
この葬儀の式は、他の一切の化儀と同様、正式にせよ略式にせよ、総本山の山法山規に準拠することが宗是ですから、必ず本宗伝統の化儀・化法に則って厳修されなければならないのであります。
葬儀において大切なことは、御本尊と引導師、及び戒名等であります。まず、申すまでもなく、葬儀における御本尊は、古来、御法主上人の特別な御指示による場合以外は、導師御本尊を奉掲するのであります。また、引導師は、僧俗師弟の上から、必ず僧侶がその任に当たるのであります。戒名等については、便宜上、後に述べることといたします。
三 日興上人の『曾禰殿御返事』に、
「なによりは市王殿の御うは(乳母)他界御事申はかり候はす、明日こそ人をもまいらせて御とふらひ申候はめ」
と、当時、僧侶が導師を務めて信徒の葬儀を執行したことを示された記述が存しております。
次に、第三十一世日因上人が、
「私の檀那の筋目之を糺すべき事、此は師檀の因縁を示す檀那は是俗の弟子なり、故に師弟血脈相続なくしては即身成仏に非ず、況や我が師匠に違背せるの檀那は必定堕獄なり乖背は即不信謗法の故なり」
と仰せのごとく、本宗における僧侶と信徒との関係は、師匠と弟子との関係にありますから、信徒は所属寺院の住職・主管を師匠とする師弟相対の信心に住さなければ、即身成仏の本懐を遂げることはできません。この師弟相対の筋目は、本宗信仰の基本でありますから、信徒が亡くなった場合も、必ず所属寺院の住職・主管の引導によって葬儀を執行しなければならないのであります。もし、これに反すれば、下種三宝の血脈法水に対する師弟相対の信心が調いませんから、即身成仏どころか必定堕地獄となります。
本宗僧侶は、本宗規定の化儀に則って修行し、御法主上人より免許を被って法衣を着しますが、この本宗の法衣には、仏法の無量の功徳が具するのであります。日寛上人は、
「出家は身心倶に釈子なり。在家は心の釈子なり」
と御教示ですが、僧侶はこの法衣を着するゆえに身心ともに僧宝の一分に加わり、血脈法水への手続を務めるのであります。したがって、短絡的に、僧侶個人の力用によって、故人が即身成仏を遂げるなどと解するべきではありません。もとより僧宝の一分として葬儀を執行するのでありますから、当然、僧侶はその心構えが大切であります。その心構えについて、日有上人は、
「仏事追善の引導の時の廻向の事、私の心中有るべからず」
と仰せられ、また日亨上人校訂、富士本日奘師編の『興門宗致則』に、
「所詮大強盛の信力を以て欲心余念を絶し偏に下種の三宝を祈るべし一人の霊魂引導の事
は容易にあらず最も貴重なるものなり」
とあります。すなわち、僧侶が僧宝の一分としての立場から、余念を絶し私心なく大聖人以来の血脈法水への手続の引導を務めることによって、故人が下種三宝の当体たる本門の本尊の功徳力用に浴し、ここに本因妙の即身成仏を遂げることができるのであります。
これに対し、本宗伝統の化儀を無視し、創価学会独自に僧侶不在の葬儀を執行するならば、それは下種三宝の意義を欠く化儀となり、決して即身成仏の本懐を遂げることはできません。それどころか、本宗の師弟相対の血脈次第の筋目を無視した罪によって、故人や遺族はもとより、導師を務める者も、必ず謗法堕地獄となるのであります。
四 次に、現在、葬儀において必要とされる戒名と位牌について述べておきます。
戒名とは、仏法の三帰戒を受けた名でありますから、まさに法名と同意であります。本宗においては、大聖人の御父には妙日、御母には妙蓮、総本山開基檀那の南条時光殿には大行という戒名があるごとく、戒名は、大聖人の御在世当時から付けられております。戒名は、生前に付けられる場合もありますが、現在では、死後、葬儀の折に付けられるのが一般となっております。それは、葬儀には、本宗の化儀の上から、戒名が必要不可欠だからであります。日有上人は、葬儀等における戒名の重要性について、
「仏事追善の引導の時の廻向の事(中略)当亡者の戒名を以って無始の罪障を滅して成仏
得道疑ひなし」
と、導師が御本尊の功徳力用を願うとき、戒名に寄せて故人の無始以来の謗法罪障を消滅して、即身成仏の本懐を遂げる意義を仰せであります。したがって、本宗信徒は、御法主上人ないし所属寺院の住職・主管に、戒名の命名を願うべきであります。
また、位牌については、現在、葬儀において、世間一般に広く用いられております。日有上人は、儒家伝来の俗名のみを記した世間通途の位牌は、「理の位牌」であるから用いるべきではないと仰せであります。本宗で用いる位牌は、妙法の題目の下に故人の戒名等を認めることによって、御本尊の示し書に準じて師弟相対の意義を顕した「事の位牌」であります。したがって、日有上人は、通途の位牌を禁じられる一方で、
「又仏なんどをも当宗の仏を立つる時」
と仰せであります。日亨上人がここでいう「仏」を位牌と釈されるごとく、日有上人の当時、既に現在のような、仮の位牌が立てられていたことが示されております。また、日達上人は、
「位牌というものは亡くなった人の姿をそこに顕わすのであります。」
と仰せられております。
現在、本宗で位牌を用いるのは、このような意義に基づくのであります。但し、日常の信行から見れば、過去帳記載までの仮の建立でありますから、決して信仰の対象とはなりません。
五 以上、本宗本来の化儀・化法の上から、葬儀の在り方を述べました。創価学会においても、牧口常三郎初代会長の葬儀は日淳上人(当時、歓喜寮主管)の導師によって、戸田城聖二代会長の葬儀は日淳上人の大導師によって、北条浩四代会長は日顕上人の大導師によって執行されました。その際、それぞれ御法主上人より尊号(戒名)を頂戴しております。また、池田大作名誉会長の母堂いち殿及び次男城久殿が亡くなった際にも、御法主上人より尊号(戒名)をいただき、本宗僧侶の導師によって葬儀を執行されております。このように、従来、学会員の葬儀は、みな本宗伝統の化儀に従って執行されてきたのであります。現に、聖教新聞社文化部編『やさしい冠婚葬祭』や潮出版社の『私たちの冠婚葬祭』では、位牌・戒名等も含め、本宗の化儀に則って日蓮正宗の葬儀を解説しております。
ところが、最近では、僧侶を不要とする学会葬が、全国各地で盛んに執行されております。しかも、そこでは導師御本尊を奉掲せず、当然のことながら本宗の戒名はなく、また位牌があっても本宗の位牌ではありません。本来ならば、このような現状に対し、創価学会は、機関紙や会合等で本宗本来の化儀に立ち返るよう、全会員に指導徹底すべきところであります。
しかし、創価学会では、大聖人の御書中に、信徒の葬儀に関する直接的な記載がないことを奇貨として、むしろ学会葬を奨励しているのであります。御書中にないからといって、僧侶の導師による葬儀が行われなかったとするのは、早計であり、独断であるといわざるをえません。
特に、平成三年八月七日付『創価新報』では、「僧侶ぬきの葬儀では成仏しないとの妄説」「戒名も後の時代に作られた形式」などの見出しを付け、また九月二十六日付『聖教新聞』では、「僧侶の引導により成仏は誤り」などと見出しを付けた上、
「僧侶なしでは成仏できないと不安がる必要はないのです。これまで述べてきたように、葬儀は決してその形式に意味があるのではありません。苦楽を分かち合った遺族と信心の同志による真心からの追善をこそ、故人は最も喜ぶことを知っていただきたいものです。」
と、本宗の化儀・化法と全く正反対の、信徒としては許されない教義上の謬見を述べ、信心を狂わせているのであります。
このように、導師御本尊を奉掲せず、僧侶を不要とし、戒名・位牌等を愚弄する学会葬は、明らかに本宗の血脈師弟義に背いた大謗法であります。
このことは、創価学会の本宗信徒団体としての存立自体に、大きく影響を及ぼす問題であると考えるものであります。
よって、貴殿らには、以上のことを深く反省された上、学会葬の誤りを率直に認め、速かに本宗本来の化儀に改めるべく、その措置を講ぜらるよう、厳に、通告するものであります。
平 成 三 年 十 月 二 十 一 日
日 蓮 正 宗 総 監 藤本日潤
創 価 学 会 会 長 秋谷栄之助殿