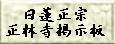『僧俗平等論』の誤りを破す
時局協議会文書作成班5班
創価学会は、宗門より指摘された「第35回本部幹部会」における池田名誉会長のスピーチの不遜さ、傲慢さ、信心のなさを、隠蔽し、問題の焦点をぼかそうとして、さまざまなキャンペーンを連日繰り返している。これらのキャンペーンは、いずれもすり替えや欺瞞に満ちたものであり、無慚極まりないものである。
聖教新聞に掲載された、青年学術者会議からの質問書「宗門に僧俗の基本的認識を問う」も、「総監の珍妙な教学を笑う」も、「化儀抄を拝して」も、全く同趣旨のもので、仏法の本義に迷い、論点をすり替えた見当違いの我見・迷妄をふりまわしているだけに過ぎない。
これらは、形の上では、平成2年12月16日付の、宗務院から学会へ宛てられた「お尋ね」に抗するものである。しかし、一読して、この機会に乗じて、かねてより公に主張したかった、いわゆる宗門無視・宗門不在の「在家仏教の展開」という学会の本音が、その背後に潜んでいることを読み取ることができる。
また、最近の創価学会は、「民主的」という語を頻繁に使用して、いかにも「宗門は非民主的で、学会は民主的である」との印象を、読者に植え付けようとしている。何が民主的で、何が非民主的なのか、その概念さえ明らかに判っていない人たちが、一方的に、自分たちは民主的で宗門は非民主的だと、声を大にして叫ぶこと自体、笑止千万である。
意図的に、本宗の真実の法義を隠蔽して、僧俗平等論を展開している創価学会の狙いはどこにあるのか。衣の下に隠された鎧の存在を、我々は見逃してはならない。独特な情報操作を繰り返し、仏法の尊厳さえも無視するような所業は、破仏法の因縁の最たるものと弾劾するものである。卑劣極まりない池田名誉会長並びに学会首脳の人間性が、宗門に対するあらゆる抗議にそのまま謄写され、日蓮正宗の正法正義に随順する信心の在り方を失った「逆賊の徒」の姿が、創価学会全体に露呈している。宗門をないがしろにする言動は、そのまま正法及びその付嘱の法体に対する誹謗背反に通じるのであるから、このことを深く恐れなければならない。
以下、学会が主張する「僧俗平等論」なるものについて、その昏迷を破すものである。
1. 総監の指摘
創価学会は、幹部が筆を執り、また謗法を信仰する識者たちにまで頼み込んで、総監の指摘に対し猛然と反発をしている。
しかし、「お尋ね」において、藤本総監が学会に指摘したのは、11・16のスピーチにおける池田名誉会長の誤りや慢心であり、「僧俗の上下関係」をことさらに述べたものではない。このことは、「お尋ね」を読めば一目瞭然で、誰にでもすぐ判ることである。
つまり、その中で、藤本総監は池田名誉会長の誤った僧俗観を糺すために、日顕上人の御指南、北条会長の反省と誓い、日有上人の化儀抄などを引用して、僧俗のあるべき姿を述べているのであって、何ら本宗の法義にもとるところはない。
「みんな信者だ、御本尊のよ、坊さんだって。違いますか、坊さんだけほか拝んでんのかよ。」
という池田名誉会長の発言こそ、僧侶に対する蔑視発言以外の何物でもないことを指摘しているのである。在家仏教の推進者として、世間に対し、また会内に対して美辞麗句を並べ、世界をリードする文化人を気取る池田名誉会長の、傲慢性、欺瞞性、偽善性、短見を、藤本総監は指摘しただけなのである。
これに対し、池田名誉会長のスピーチが犯した誤りは、日蓮正宗信徒として致命的なものであることを、本人も学会首脳も熟知しているために、窮余の一策として、焦点ボカシとすり替えのため、かねてよりの野望「宗門支配」のための前段階
として、「僧俗平等論」を、大々的に展開しているといえる。
「平等」「民主」「自由」ということは、基本的人権を最大限尊重することであるが、これらが一番等閑にされているのは、まさに創価学会である──という学会員の声を、しばしば耳にし、ときには悲痛な叫びとして訴えられる。学会自らが達成してもいない「民主化」「平等化」を宗門に要求する。このような手口は、歴史の古今に登場する謀略革命集団の、常に用いる卑劣な手口と全く同じものである。
学会が主張する「僧俗平等論」を破すにあたり、まず創価学会の欺瞞性、独善性を指摘しておく。
創価学会は、今回の問題に関し、さまざまな論陣を張っているが、宗門からの指摘に対して、何一つまともに答えていない。
それどころか、一方的に問題をすり替えて、逆に宗門を非難し、攻撃しているのである。学会が、今主張している僧俗平等論もその例外ではない。
学会側の論点のすり替えを認識するために、藤本総監が「お尋ね」で指摘した内容(大日蓮号外・学会問題の経過と往復文書25~27頁)を、今一度読みなおすべきである。その上で、果たして藤本総監が、聖職者の権威や権力をふりかざし、信徒を軽視し蔑視しているかどうか、しっかりと判断して頂きたいものである。
学会側は、藤本総監の指摘を、「平等観」「民主」という論点にすり替え、おかど違いの非難中傷を繰り返しているに過ぎない。これは、踏まれてもいない足を「踏まれた」「蹴られた」と大騒ぎをしているようなものである。このようなやり方を、「言論の暴力」とか「言論の詐欺」というのであろう。しかも、いかにも宗門の体質が、時代錯誤の「権威・権力至上主義」にあるような印象を、純真な信徒や社会に与えているのである。しかし、このような悪質極まりない魂胆は、今や明白となっている。創価学会も宗教団体を名乗るのであれば、正直を旨として、節度を充分にわきまえる必要がある。
それさえもかなぐり捨てて、宗門を攻撃しなければならなくなったのは、「お尋ね」の指摘が仏法の道理の上から正当であったからであり、創価学会がこれに対して「進退きわまった」からであろう。
2.「僧俗平等論について」
僧俗の立場において、どちらが上でどちらが下かという、きわめて「差別的視点」から論を展開しているのは、実は創価学会である。
日蓮正宗には、もともと差別偏重の教義や意識はない。仏法は空理空論を弄ぶものではなく、真実の妙法を身をもって信受し実践修行していくことである。そこにこそ、本仏の御意に適い、成仏の道が開かれるのである。その見地から、今回の問題を通して、創価学会が喧伝している無軌道な「僧俗平等論」の誤謬を破すものである。
(イ)「僧俗の不二」について
堀日亨上人は「化儀抄註解」に、
「竹に上下の節の有るがごとく其ノ位をば乱せず」
との御文を、僧俗平等の義・差別の義、常同常別・二而不二と釈されている。
日蓮大聖人が説かれた「僧俗の立場」の御教示は、結論を先に述べるならば「二而不二」、すなわち「二にして二ならず」という関係である。立場・役割の現実的な相違は、否定し得ないものであるから「二而」である。また、御本尊に対し奉る信仰面で捉えるならば、「平等」であり「不二」である。
仏法には、このような拝し方をすべき法門が多々存する。例えば、「色心不二」「因果不二」「依正不二」「仏凡不二」など、「二而不二」の義で示され、その立場から拝さなければ、到底真実義に至ることのできない教説は、多岐にわたって存するのである。
藤本総監が、「お尋ね」の中で指摘した「上下関係」は、僧俗の立場について、日有上人が示された「僧俗の礼儀」について述べられたものである。これは、そのまま一般の社会秩序にも通ずるものである。したがって、もしこれを否定するのであれば、社会秩序の崩壊をも招来するのである。
藤本総監は、日有上人の御教示をそのまま紹介されて、池田名誉会長のあまりにも野卑な「僧侶蔑視」の発言を忠告し、たしなめたのである。それに対して開き直り、さらに非難したのが、「総監の珍妙な教学を笑う」という、一連の低俗なシリーズである。これは、創価学会の「狂った教学」と「過剰防衛的体質」を知る上で、格好の材料となるものである。
さて、論の展開上、僧俗の立場における「不二」について、先に記すと、
「久遠実成の釈尊と皆成仏道の法華経と我等衆生との三つ全く差別無しと解りて妙法蓮華経と唱え奉る処を生死一大事の血脈とは云うなり、此の事但日蓮が弟子檀那等の肝要なり法華経を持つとは是なり」(「生死一大事血脈抄」)
と示されるように、御本尊を拝する信心の上で、「僧俗は全く平等」であるということは日蓮正宗の宗是であり、藤本総監も「お尋ね」の中で明確に述べていることである。そのことを、意図的に隠して、学会員や世間の人に、藤本総監が「僧俗上下論」「僧俗差別論」を展開しているようなキャンペーンを張っているのである。このような姿は、正法正義を意図的に隔離して師敵対した「逆路伽耶陀(ぎゃくろがやだ)」外道を想起するのである。仏法をねじ曲げ、破壊しようとする徒輩は、いつも同じ道を辿る。提婆達多が、釈尊に対し、意図的に卑劣・陰険に敵対したこともよく知られるところである。
「お尋ね」以後、学会首脳をはじめとする幹部の言動は、ひとり藤本総監に対する、理不尽な中傷だけではない。すでに正法正義、富士の清流に対する冒涜であり、また陋劣(ろうれつ)にして醜悪な讒言者と化している。池田名誉会長並びに学会首脳は、虚心坦懐に我が身の邪悪さを反省すべきである。
(ロ)「僧俗の二而」について
宗祖大聖人の御書中に、僧俗に対するさまざまな御教示が拝せられる。
その一つに、
「我が弟子等の出家は主上・上皇の師と為らん在家は左右の臣下に列ならん、将又一閻浮提皆此の法門を仰がん、幸甚幸甚」(「諸人御返事」)
〔日本国一同に日蓮が弟子檀那となったときには、出家(僧)は主上・上皇(主権在民の現代では為政者の)師となり、在家は左右の臣下として列なるであろう。そしてまた、(立正安国の姿を見て)世界中がこの法門を尊崇するであろう。これほどの幸いがあろうか。まことにめでたいことである。〕
この御文は、明らかに僧俗の間に、次第のあることを示されたものである。
池田名誉会長は、かつては僧俗の「二而」を正しく認識していたらしく、つぎのように述べている。
「私どもは、全部猊下の家来でございます。このたび家来を代表させていただき、また、日蓮正宗の信徒を代表させていただきまして、日達上人を外護申し上げ、東南アジアの旅行に行ってまいります。」(渡印歓送会 S37・1・23)
「私も猊下の弟子として、法華講員の一員として、広宣流布のために、(中略)そして猊下のお心におこたえ申し上げたい。」(大坊落慶式 S37・3・3)
「遣使還告であられる御法主上人猊下は日蓮大聖人であります。」(第26回本部総会 S38・9・1)
上記発言は、全て池田名誉会長の過去の発言である。この精神があったがゆえに僧俗和合があり、良識ある創価学会員が、池田名誉会長の指導に従ってきたのである。この信心を失った学会には、最早何の魅力もない。みな失望をしている。池田名誉会長並びに学会首脳は、このことを謙虚に反省懺悔すべきである。
藤本総監は、本年2月9日の書面で、
「宿世の福徳によって人間と生れ、大白法にめぐり逢いながら、無慚な 慢心を起こし、多くの会員を巻き添えにして一生を終えたならば、阿鼻大坑に堕ちることは疑いありません。」
と指摘をしているが、この書面を見て、いまだ反省の心が起きないということは、「完全に信心が狂った」「悪鬼入其身」としか言いようがない。多くの純真な創価学会員のことを思うと、慨嘆に耐えないのである。
3.御法主上人と信徒代表の立場の相違について
私どもは、世間の人種差別問題や基本的人権に関して、論を張ろうとしているのではない。人間一人一人は、互いに「自由」であり、「平等」であり、社会形態も「民主」であることに異論もない。むしろ、こういう社会形態であるが故に、「言論の自由」「信教の自由」が守られることを、心から賛同している。今、論じようとしているものは、「日蓮大聖人の仏法を奉ずる日蓮正宗という宗教団体における、僧俗の役目と立場の違いからくる存在意義と筋目の論」なのである。
いかなる組織や団体にも、上下の関係(縦の関係)と平等の関係(横の関係)が存在する。その最も基本的な二つの関係を混同し、否、意図的に無視して論を展開しているのが、現在の創価学会首脳である。これは、まさしく「若悩乱者頭破作七分」の姿と断ずるものである。
学会首脳がとっている因循姑息な宗門攻撃の裏に隠されているものは何か──これを明確にすることが、問題の真実を知り、問題を正当、かつ早期に解決することにつながる。その視点から、「御法主上人」と「信徒の代表であった池田名誉会長」との〔師弟の立場〕・〔上下の関係〕を明確にしておきたい。なぜならば、現在の学会問題は、この義に混乱したために惹起したからであり、また後代において、同じ轍を踏んではならないからである。
さて、創価学会はその会則に、
「この会は、日蓮正宗の教義に基づき、日蓮大聖人を末法の御本仏と仰ぎ、日蓮正宗総本山大石寺に安置せられている弘安二年十月十二日の本門戒壇の大御本尊を根本とする」
と規定している。故に、その原点に立ち返って、今回の問題に関する誤りを糺さなくては、その存立基盤さえ失ってしまうのである。
「此の経は相伝に有らざれば知り難し」
と、宗祖大聖人が説き置かれたことは、日蓮正宗の信仰をする者なら、誰一人知らない者はいない。この仏法の相伝の一切は、御開山日興上人以来、御当代日顕上人に至るまで、「金口嫡々・血脈付法」によって継承されている。
日蓮大聖人、日興上人が御所持あそばされた仏法の一切は、唯授一人の血脈相承により「日顕上人」が御所持あそばされているのである。これを否定する者は、日蓮正宗の信仰を放棄する者である。
「此の相承は日蓮嫡嫡一人の口決・唯授一人の秘伝なり神妙神妙」(「産湯相承事」)
「血脈並に本尊の大事は日蓮嫡嫡座主伝法の書・塔中相承の禀承唯授一人の血脈なり、相構え相構え秘す可し秘す可し」(「本因妙抄」)
宗祖大聖人自ら大事中の大事をこのように示され、さらに、
「背く在家出家どもの輩は非法の衆たるべきなり」(「池上相承書」)
とまで、厳しく訓告あそばされているのである。宗祖大聖人の仏法の一切を継承あそばされる立場から、時の御法主上人が、時代の状況の変化によって起こりくる教義上の諸問題の「裁定権者」たることも当然である。「日蓮正宗宗規」には、
「教義に関して正否を裁定する。」
と規定されている。
宗祖日蓮大聖人の御教示のように、時の御法主上人には、一宗を教導すべき立場と責任がある。したがって、また日蓮正宗の信仰上、一切の僧俗を含めた上で「上一人」の立場にある。御法主上人自らが、「私が一番偉い」などと仰せになられたことは、ただの一度もない。しかし、「唯授一人・上一人」たることは、僧俗一同が拝受すべき厳粛な事実なのである。
池田名誉会長自身も、また創価学会も、仏法の本義の上から、御法主上人を厳然と「師匠」であると拝し、またそうでなければならないと、広く会員に説いてきたのである。その例を幾つか示すと、
「御法主上人猊下は遣使還告で、日蓮大聖人と拝し奉るのです。このことは信心の上からはっきりしたものです。創価学会の会長を過大評価したりしてはいけないのです。」(巻頭言・講義集第3巻184頁、S39・6・12発行)
「あくまでも師匠は日蓮大聖人即御本尊様です。それから『遣使還告』あそばされる代々の御法主上人猊下です。われわれは全部その弟子です。」(学会伝統の「実践の教学」・会長講演集第6巻113頁、S37・7・20発行)
などである。池田名誉会長が指導しているように、いかに功績があろうと、文化人らしき姿で世界と交流し、勲章が幾つあろうと、仏法の次元では、御法主上人と池田名誉会長とは「師匠と弟子の関係」なのである。御法主上人は、代々の会長をはじめとする創価学会員の、広宣流布への偉大な戦い、また総本山外護の功績を、最大限賞賛あそばされてきた。また、日顕上人は、唯授一人のお立場から、過去に多大な誤りを犯した池田名誉会長を護り、宗開両祖の御精神を根本として、令法久住、広宣流布、世界平和の戦いに邁進するよう御教示もされ、願ってもこられたのである。同様に、多くの信徒に対しても、慈悲をもって、誠心誠意、接してこられたことは、宗内の僧俗一同の知るところである。
法体を御所持あそばされ、僧俗一同の師匠である日顕上人に向かって、
「猊下というものは信徒の幸福を考えなきゃあいけない。権力じゃありません。」
「全然、また難しい教義、聞いたって解んないんだ。誰も解らないんだ、ドイツ語聞いているみたいにね。それで『俺偉いんだ。お前ども、信徒ども、信者、信者』って。そんなのありませんよ、この時代に。」
と、まことに無慚極まりないスピーチを、池田名誉会長は現実にしたのである。「猊下というものは……」との箇所は、日達上人のお言葉を敷衍して述べたものであると、強弁して言い逃れようとしているが、そういうすり替えで、全てをごまかそうという姿勢は、やがて会員に伝染する。いや、すでに学会そのものが、こういう無慚な体質になってしまっている、との発言も多く聞く。
血脈付法の御法主上人を見下し、悪しき権力と決め付けた池田名誉会長のスピーチは、本宗信徒としてあるまじき増上慢・不遜の言動である。しかも、指摘を受けながらも開き直る姿には、数々の謗法を犯して、日興上人に敵対した波木井日円の姿が、そのまま重なってくる。波木井日円が、日興上人に宛てた「最後の状・あざけりの状」とも称されている書状に、
「日円は故聖人の御弟子にて候なり、申せば老僧達も同じ同胞にてこそ渡らせ給ひ候に」
とある。自らの初発心の師であり、また宗祖大聖人の付嘱を受けられた日興上人に対し、日円は、
「自分も大聖人の弟子である。言うならば、六老僧も同胞である。大聖人の慈愛に浴することは同等・平等であり、日興上人から訓戒を受けるいわれはない。」
として反逆をしたのである。大聖人の仏法においては、師弟子の道を正してこそ、成仏得道が可能となる。五老僧や波木井日円も、根本の師弟子の道を違えたが故に、謗法と化し、外道に堕したのである。正法正義と根本の師に敵対した池田名誉会長並びに学会首脳は、本来ならば、自ら慚愧の念に堪えないはずである。自らの信心の誤りを反省し、大御本尊にぬかずいてお詫び申し上げねば、阿鼻大坑の苦は免れないことを断言するものである。
4.一般僧侶と信徒
血脈付法の御法主上人と自分たちとは、信心の上で平等・同等ということは、さすがに表立っての表現はしていない。しかし、創価学会としては、その内面では、すでに下剋上の様相を呈していることが窺われる。その一例が「猊下というものは信徒の幸福を考えなきゃあいけない。権力じゃありません。」
とのスピーチである。
御法主上人に対して、このようにいうのであるから、一般僧侶のことになると、最早平等・同等という論は建前論であって、本音は完全に見下しているというのが実態であろう。
卑怯なすり替え・欺瞞をもって、藤本総監をはじめとする僧侶に攻撃をしている姿は、完全に見下し敵視したものである。平等論も、実のところ、「在家が上」との持論展開の伏線と思われるのである。
さて、一般僧侶と在家信徒との関係については、藤本総監が指摘しているように、
「貴賤道俗の差別なく信心の人は妙法蓮華経なる故に何レも同等なり、然レども竹に上下の節の有るがごとく、其ノ位をば乱せず僧俗の礼儀有るべきか」
との化儀抄の御教示は、従来、僧俗ともに何の異論もなく守り、従ってきた条目である。信心の上では、僧俗に全く差別はなく、平等たることは当然である。しかし、仏法守護のため、信徒の信行学増進のため、宗団維持発展のために、竹に上下の節があるように、礼節が必要なのである。この点が大切なところで、前述の「二而不二」の「二而」の義も、実はここにある。
宗門は古来、日興上人の「遺誡置文」の、
「若輩為りと雖も高位の檀那自り末座に居る可からざる事」
との条目を守り、信心の化儀中にあっては、能化・所化、僧俗の分位、初信・後信の前後等から、上下の秩序を保ってきた。これは、日興上人の御教示であり、歴代の御法主上人が堅持せられてきた日蓮正宗の伝統精神である。
今、学会首脳は、一元的に僧俗の平等を主張しているが、それでは在家同士の間柄はどうであろうか。全ての会員は上下の差がなく、平等であるというのであろうか。
判りやすく創価学会の組織にあてはめると、池田名誉会長も、ある一人の本部職員も、末端の学会員も、御本尊に対し奉る信仰の面においては、全く平等で、何ら差別はないはずであり、またあろうはずがない。しかし、組織の維持発展のために、種々の役職が設けられているのは、そこに上下の秩序をたもつことが必要であるからにほかならない。信心の上では平等であるから、「俺にも池田名誉会長と同等の扱いをしてくれ、平等・民主の時代ではないか」「秋谷会長よりも、俺のほうが毎日長時間働いている。俺のほうが、よほど学会に貢献している。会長以上の待遇で報いてくれ」という要求を、創価学会では認めるとでもいうのであろうか。
「民主」「平等」という、誰しもが抗することのできないであろう「語」を悪用し、宗門に刃を向けているが、実質的には、宗門より更に閉鎖的・非民主的な創価学会の在り方に対して、学会内部から刃が向けられる構図が、すでに見えはじめている。「還著於本人」とは、まさにこのことである。
平成3年1月24日、御法主日顕上人は、僧侶の代表に、
「僧俗の関係は『二而不二』である。」
「『二而』にとらわれてもいけないし、『不二』にとらわれてもいけない。」
との御指南をあそばされた。
この「二而不二」の原理が理解できなければ、創価学会の会員は、永遠に大聖人の仏法に敵対するであろうことを戒めておくものである。
5.化儀・化法のとらえかた
創価学会では、日有上人が「化儀抄」に示された、
「竹に上下の節の有るがごとく其ノ位をば乱せず僧俗の礼儀有るべきか」
の条目も、日興上人「遺誡置文」の、
「若輩為りと雖も高位の檀那より末座に居る可からざる事」
の条目も、化儀・化法のうち、化儀に属する教えであり、二次的なもので、宗祖大聖人の教えの根本は僧俗平等、すなわち化法にその根本の「僧俗平等」が説かれている故に、藤本総監の
「したがって、僧俗には大聖人の仏法に即した本来的な差別が存在する」との論は誤りである──と主張している。この点についての誤謬を破すこととする。
化法とは日蓮大聖人の教義であり、たとえ時代や状況の変化があっても、何ら変わるものではない。したがって、絶対改変されてはならないものである。また、化儀とは化導の儀式、化法の現実化であり、宗祖大聖人の教えに照らして違うことがあってはならない。
化法を、時代に即応した形で「指南する大権」を有するのは、時の御法主上人であり、一般僧侶でもなければ、ましてや信徒でもない。その立場から、日有上人が僧俗の立場、上下の関係を規定なされたのが「化儀抄」であり、日興上人の「遺誡置文」の御文でもある。
化儀とは化法に準則して行ぜられるもので、そこには化法の命脈が生きづいていることを知らねばならないのである。化法と化儀を、都合のいいように切り離す妄説は、本宗の教義でも信心でもない。時代に即した化法・化儀の御指南は、唯授一人の御法主上人に相承された「大権」であることを、僧俗一同が深く認識し、片時も忘れてはならないのである。
さて、学会のいう「僧俗平等論」は、御法主上人を除く一般僧侶と在家との平等をいうのか、御法主上人をも含めた僧俗平等をいうのか、現在の段階では、まだ鮮明ではない。しかし、学会員の中には、すでに「御法主上人と池田先生は対等だ」という暴言を吐く人もいる。この点については、すでにその誤りを指摘してあるが、「僧俗平等論」なる陳腐な論を展開した結果、仏法の本義までも破壊し始めた恐ろしい姿がある。天魔外道に魅入られた所為としかいいようがない。
日蓮正宗の化儀は、化法に裏打ちされたもので、化法から独立しての化儀の存在はありえない。いうなれば「二而不二」なのであり、学会がいうような「二次的なもの」として、軽視し侮ってはならないものである。牽強付会の考え方は、次第に正法誹謗に至るしか道がないことを恐れるべきである。
藤本総監が、1月12日付文書で記した、
「これは権威主義などというものではなく、仏法に定められた規範として、仏法流通の上の、僧侶に備わる本来のあ
るべき姿であります。したがって、僧俗には大聖人の仏法に即した本来的な差別が存するのは当然であります。」
という僧俗の関係は、上述した意義を含んでのものであり、大聖人の仏法に即した僧俗論として、僧俗ともに素直に受け止めるべき内容のものなのである。さらに、
「平等面のみを見て差別面を排するところには、九界即仏界も、差別即平等も一切なくなってしまいます。」
と、本宗の法義に照らして、理路整然と教示されているのであるから、一切の我見を捨てて再読し、藤本総監に、衷心より詫びるべきである。
6.識者の声について
聖教新聞において、宗門を批判したり、池田名誉会長を誉め讃えたりするとき、「ある著名人は……」と書きだすことは、学会の常套手段であった。ところが、今回は、いよいよそれら著名人らしき人たちが、実名で登場するようになったのである。それにしても、これらの人たちは、学会側の主張だけは、よく理解されているようである。
ただし、ここに登場する識者は、日蓮正宗の信心とは、今のところ無縁の人たちである。これらの人が、実際、どのような宗旨の信仰をされているのか、念仏宗か、真言宗か、キリスト教か、はたまた無神論者であるのか、定かではないが、日蓮正宗の信心をしていない人が、この問題を正しく認識することは不可能である。
「民主化を阻む宗教の権威主義」「前世紀の遺物か宗門の古い感覚」「適正な手続きを欠く非民主的な宗門」「宗門に民衆救う精神が欠落」等々、学会擁護の論を展開しているが、肝心の池田名誉会長のスピーチに関して言及したものはひとつもない。ここに信心している者と信心していない者との、考え方の大きな差がある。あえて避けたのかも知れないが、今回の問題の発端であり、根本である三宝破壊につながる池田名誉会長の発言は、信心をしていない人にとっては、大きな意味を持たないのであろう。いずれにしても、謗法の学者まで動員して、宗門攻撃をする無慚無愧な姿は、まことに哀れを誘うものがある。
日蓮正宗において、御法主上人は、大聖人以来の血脈法水を相承され、一身に所持あそばされている唯一人の御方である。したがって、御法主上人は、その権能の上から一宗を総理し、つねに令法久住、広宣流布への方途を示されるのである。故に、僧俗は挙って御法主上人の御指南を拝し、信行に邁進していくことが、日蓮正宗の信心の根幹をなすのである。
このような尊い血脈法水を所持される御法主上人を、侮蔑した池田名誉会長の発言は、日蓮正宗の信心をする者にとって、到底見逃すことができない重大問題である。その重大問題は、大聖人の仏法を受持し、御本尊の功徳を心から信じ求める人でなければ、決して理解できるはずがないのである。
「非民主的」「非近代的」「閉鎖的」「権威主義的」等々と宗門を批判しているが、宗門が民主主義を拒否し、また社会情勢などを何も知らないで、ただ古い体制に固執しているとでも思っているのであろうか。
宗門は過去七百年の間、あらゆる時代のそれぞれの社会に適応しながら、日蓮大聖人の仏法と伝統を守り続けてきたのである。そして、そのための努力は、今後も、未来永遠に続けていかなければならないものなのである。ただ権威をふりかざしているだけでは、七百年の歴史を積み重ねることすらできるものではない。
学会は、宗門が非民主的であると決め付け、社会に開かれた民主的な宗門となるよう、主張している。民主主義は大いに結構であり、決して否定するものではない。ただし、数をもって正義や真実の、全てを決することができないことも事実である。むしろ、愚かな多数決は、ときに正義を覆い隠し、真実をねじ曲げることさえある。日蓮正宗では、すでに七百年前、日興上人が、数を頼んで仏法を決することの非を御教示されている。
日興上人の「遺誡置文」の、
「衆議為りと雖も仏法に相違有らば貫首之を摧く可き事」
の条文である。最近、学会では、同じ「遺戒置文」の、「時の貫首為りと雖も仏法に相違して己義を構えば之を用う可からざる事」
との条文のみを、曲げて用いたがっているようであるが、この二つの条文は、合わせて拝していくところに、日興上人の御意があると拝すべきである。
何かというと「一千万信徒が……」といって、数こそ正義とばかりに、宗門に圧力をかけようとするが、数は必ずしも正義とはなり得ない。
今回もそうであるが、池田名誉会長並びに学会首脳は、自分たちがいかに立派であるかを知らしめるために、世界の著名人、知識人を使うことを常套手段としている。池田名誉会長と多くの著名人との会話が、単なるプロパガンダ(宣伝)にすぎないことは、聖教新聞や聖教グラフで、あれほど池田名誉会長や学会を褒めたたえていたそれらの人々が、その後、入信したという話を聞いたことがないことからも明らかである。
同じことは、今回の識者の方々にもいえることである。みな一様に学会の活動を支持し、賛同の意を表しながら、しかもなお信心をしていないのである。
重ねていうが、今回の問題は、いかに知識人といえども、信心をしていない人には、宗祖大聖人が、
「当世の習いそこないの学者ゆめにもしらざる法門なり」(「草木成仏口決」)
と仰せのように、理解できるべくもない事柄である。同時に、このような識者を自慢げに用いる学会の体質が、そのまま「謗法与同」の誤りを重ねていることを知るべきである。
7.正しい僧俗の在り方
問題が惹起してから、学会首脳が犯した正法に対する背反は、余りにも多く、一文をもっては指摘しきれない。日蓮正宗信徒として、余りにも情けない哀れな心根を見せつづけられている学会員や、池田名誉会長や学会組織の弾圧が怖くて、正論を発言できない学会幹部が、多数存在することも熟知している。
しかし、ことは、まことに重大な事態に至っている。会員一人一人の一生成仏か、阿鼻大坑か、いうなれば「生か死か」を選ぶような真剣さで、仏法の正邪を選ばねばならないほどの局面を迎えたからである。
昭和55年11月26日、創価学会創立50周年記念幹部登山の砌、御法主日顕上人は「僧俗の進むべき方途」を、大慈悲心のお立場から御指南された。すなわち、
創価学会創立以来の折伏弘教と総本山・末寺の外護は、偉大な功績を有するもので、感謝し尊敬する。
創価学会50年の広布の歴史を「果」ではなく、人類の幸福のための「因」と捉え、新たなる発足をして戴きたい。
52年路線の「学会の誤り」は、日達上人の御慈悲により、学会の反省と努力を前提に、一切が収束された。
法主は、血脈を継承する上から、一宗を嚮導すべき立場と責任がある。
創価学会に、宗門の宗旨を蔑ろにするような底意はなかったと信ずるが、仏法は正法及びその付嘱の法体に対しての、
信伏随従か誹謗背反かである。誹謗背反は、大謗法・大悪の行為である。
正信会僧侶の処分に関連して、学会にも指導者にも誤りはなかったという発言は許されない。学会に逸脱があったことは事実である。
〔僧俗に関して〕
在家中心の考え、僧侶・寺院軽視の在り方は改めるべきである。令法久住・広宣流布において、僧俗は一体の使命をもつものである。
僧侶は、とくに「令法久住」、在家は「広宣流布」に、それぞれ重大な使命がある。真実の僧俗和合のもとに前進がなされなければならない。
信徒団体としての基本を忠実に守り、その上で適切な会員指導をして戴きたい。
[指導者中心の在り方]
会長中心の団結と組織、会長への信頼と尊敬が大折伏の要因でもあるが、それがいわゆる神格化に繋がっては、当門流の教義からの逸脱となる。今後は、かかることが微塵もないよう徹底し、即身成仏の大直道を、堂々と進んで戴きたい。 (以上取意)
と、宗開両祖の血脈を継承遊ばされる立場から、甚深の御指南をせられたのである。
僧俗が、ともに本分を全うし、仏祖三宝に御報恩謝徳申し上げることこそ、弟子檀那の最高の道であることを御指南下さったのである。しかも、池田名誉会長並びに創価学会の誤りを、
「浅き罪ならば我よりゆるして功徳を得さすべし、重きあやまちならば信心をはげまして消滅さすべし」(「阿仏房尼御前御返事」)
の御文を引かれ、御慈悲溢れる御言葉をもって、教え諭されたのである。
僧侶に対しても、「上求菩提・下化衆生」という厳しい訓戒をつねに説かれて、「祖道の恢復」をはかってこられたのである。従って、我々僧侶も、理想的な僧俗和合は、御当代日顕上人の代にこそ実現を──と、大きな期待をもち、実践に励んできたのである。
池田名誉会長も、御法主上人のこの御指南に先立つこと半年前の4月2日に、「恩師の二十三回忌に思う」との所感を発表し、6・30、11・7を踏まえた、まことに殊勝な反省懺悔と、仏法流布、仏法外護の決意を述べている。すなわち、
戸田会長の日蓮正宗厳護と忠誠、広宣流布への命懸けの戦いの在り方の尊さを賛嘆し、創価学会の宗教法人設立に当
たっての日淳上人、日達上人及び御先師上人の鴻恩に深く感謝申し上げること。
52年路線の問題は自分の指導に発端があったこと。その起因するところは、
1本山に正本堂を御供養申し上げることができたが、全国の会館の整備がいまだしであった。
2在家団体としての基盤確立と、社会に開いた教学の展開をはかった。
3宗門・僧侶が会員を見下したり、信徒を隷属させることのないよう厳しい態度で臨んだ。
このことが、僧侶・寺院の役割を軽視し『学会主・宗門従』の創価学会中心主義的な『独善性』を生んだ。この主客転
倒は、ひとえに我が身の信心未熟故の慢(増上慢)と、大御本尊に心より懺悔申し上げるものである。
代々の御法主上人は唯授一人・遣使還告の御立場であられると尊崇申し上げるものである。
代々の会長の神格化は、絶対あってはならない。とくに私自身、罪業深き、過ち多き身であることをよく知っている。
今日の種々の問題は、私の指導性の不徳のいたすところである。
創価学会の存立基盤に立ち戻り、あくまで外護と布教の根本を主体とし、社会的存在としての文化活動を推進して行きたい。 (以上取意)
と、犯した誤りと、自らの増上慢を反省懺悔するとともに、本宗信仰の命脈たる戒壇の大御本尊と、血脈付法の御法主上人を根本として、信徒として、信徒団体として、その本分を全うすることを誓ったのである。
しかしこの、
1、御本尊への御誓い。
2、御法主上人への御誓い。
3、創価学会員への誓い。
の、その全てを、今回、見事に裏切ったのである。これほどの「虚言」が、宗門史上、かつて存在したであろうか。「第一義天に慙ず」と「法華文句」にあるが、まさに天をも恐れぬ所業とはこのことをいうのであろう。
僧俗の在り方は、すでに御当代日顕上人が、余すところなく御指南せられている。僧俗ともに真摯に拝受し、実践したならば、理想の僧俗和合は、大きく築かれていたであろう。全ての僧俗が望んだ僧俗和合を破壊し、多くの純真な学会員を苦しめた池田名誉会長並びに学会首脳が犯した罪業は、余りにも大きい。
また、唯授一人の御法主上人の御宸襟を悩まし奉った罪障は、我ら凡慮の計り知れないものである。
願わくば、虚心坦懐、潔く反省懺悔し、宗史に残る大汚点をわずかなりとも、洗い浄められんことを。
以 上