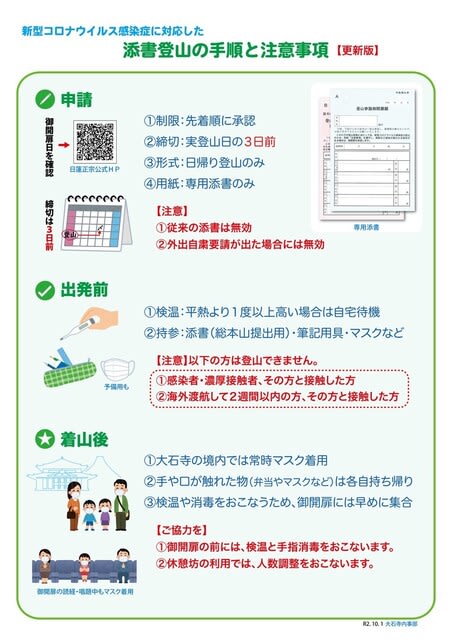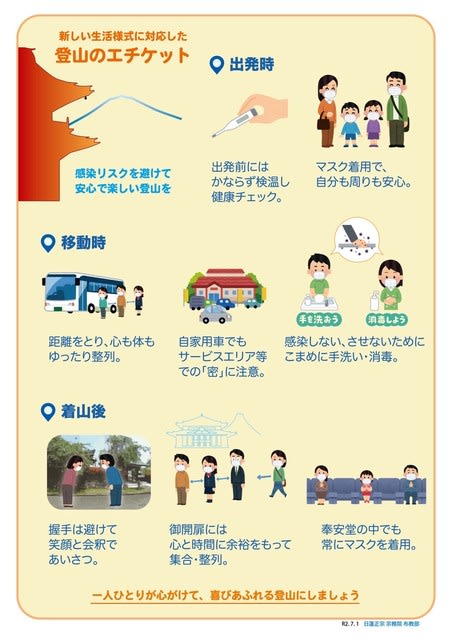令和7年7月度広布唱題会の砌
於 総本山客殿
(大日蓮 令和7年8月号 第954号 転載)
(大白法 令和7年7月16日 第1153号 転載)
本日は広布唱題会に当たりまして、一言申し上げます。
既に皆様には御承知の通り、今月は『立正安国論』上呈の月であります。
すなわち『立正安国論』は、今を去る765年前、文応元(1260)年七月十六日、宗祖日蓮大聖人御年三十九歳の時、宿屋左衛門入道を介して、時の最高権力者・北条時頼に提出された国主への諌暁書であります。
大聖人様は『撰時抄』に、
「外典に云はく、未萠(みぼう)をしるを聖人という。内典に云はく、三世を知るを聖人という。余に三度のかうみゃう(高名)あり」(御書867)
と仰せられ、御一代中に三度、天下国家を諌暁あそばされましたが、その最初の国家諌暁の時に提出されたのが『立正安国論』であります。
ちなみに、二回目は同じく『撰時抄』に、
「二つには去にし文永八年九月十二日申(さる)の時に平左衛門尉に向かって云はく、日蓮は日本国の棟梁(とうりょう)なり。予を失ふは日本国の柱橦(はしら)を倒すなり」(御書867)
と仰せのように、文永八(1271)年九月十二日、竜口の法難の直前に、平左衛門尉頼綱に対して行った時であります。
三回目は、文永十一年四月八日、佐渡赦免直後、平左衛門尉頼綱に見参した時であります。その時、大聖人様は蒙古来襲の時期について尋ねられ、
「天の御気色(みけしき)いかりすくなからず、きう(急)に見へて候。よも今年はすごし候はじ」(御書867)
と「よも今年はすごし候はじ」、つまり「今年中には襲ってくるであろう」と予言されたのであります。しこうして、この予言は的中し、文永の役はその年の十月に起きたのであります。
そこで『立正安国論』御述作の背景について『安国論御勘由来』を拝しますると、
「正嘉(しょうか)元年太歳丁巳八月二十三日戌亥(いぬい)の時、前代に超えたる大地振(じしん)。同二年戊午八月一日大風。同三年己未大飢饉。正元(しょうげん)元年己未大疫病(だいやくびょう)。同二年庚申四季に亘りて大疫已(や)まず。万民既に大半に超えて死を招き了んぬ。而る間国主之に驚き、内外典に仰せ付けて種々の御祈祷(きとう)有り。爾(しか)りと雖も一分の験(しるし)も無く、還りて飢疫等を増長す。日蓮世間の体(てい)を見て粗(ほぼ)一切経を勘(かんが)ふるに、御祈請(きしょう)験無く還りて凶悪を増長するの由(よし)、道理文証之を得了(おわ)んぬ。経(つい)に止(や)むこと無く勘文一通を造り作(な)し其の名を立正安国論と号す。文応(ぶんのう)元年庚申七月十六日辰時、屋戸野(やどや)入道に付し故最明寺入道殿に奏進(そうしん)し了んぬ。此偏(ひとえ)に国土の恩を報ぜんが為なり。(中略)日蓮正嘉の大地震、同じく大風、同じく飢饉、正元元年の大疫等を見て記して云はく、他国より此の国を破るべき先相なりと。自讃に似たりと雖も、若し此の国土を毀壊(きえ)せば復仏法の破滅疑ひ無き者なり」(御書367)
と仰せであります。
大聖人様は天変地夭・飢饉・疫癘、遍く天下に満ち、混沌とした末法濁悪の世相を深く憂えられ、国土退廃の根本原因は、邪義邪宗の謗法の害毒にあると断じられ、邪義邪宗への帰依をやめなければ、自界叛逆難・他国侵逼難の二難をはじめ、様々な難が必ず競い起こると予言され、こうした災難を防ぐためには、
「汝早く信仰の寸心を改めて速やかに実乗の一善に帰せよ」(御書250)
と仰せられ、仏国土を建設するためには一刻も早く謗法の念慮を断ち、「実乗の一善」に帰することであると諫められているのであります。
「実乗の一善」とは、大聖人様の元意は文上の法華経ではなく、法華経文底独一本門の妙法蓮華経のことであり、三大秘法の随一、大御本尊様のことであります。すなわち、大御本尊様に帰依することが、国を安んずる最善の方途であると仰せられているのであります。
よって、総本山第二十六世日寛上人は「立正」の両字について、
「立正の両字は三箇の秘法を含むなり」(御書文段6)
と仰せであります。
すなわち「立正」とは、末法万年の闇を照らし、弘通するところの本門の本尊と戒壇と題目の三大秘法を立つることであり、正法治国、国土安穏のためには、この三大秘法の正法を立つることが、最も肝要であると仰せられているのであります。
また「安国」の両字につきましては、
「文は唯日本及び現在に在り、意は閻浮及び未来に通ずべし」(御書文段5)
と仰せであります。つまり「国」とは、一往は日本国を指すも、再往は全世界、一閻浮提を指しているのであります。
『立正安国論』は、その対告衆は北条時頼であり、予言の大要は自界叛逆難・他国侵逼難の二難でありますが、実には一切衆生に与えられた諌言書であります。また、一往は専ら法然の謗法を破折しておりますが、再往元意の辺は広く諸宗の謗法を破折しておられるのであります。
されば今日、末法濁悪の世相そのままに混沌とした世相を見る時、私どもは改めて『立正安国論』の御聖意を拝し、一日も早く、また一人でも多くの人々に対して折伏を行じていかなければならないのであります。
本年も既に年半ばとなりましたが、どうぞ皆様方には、いよいよ信心強盛に、真の世界平和と全人類の幸せを願い、講中一結・異体同心して、一天広布を目指して折伏に励まれますよう心からお願いし、本日の挨拶といたします。
日蓮正宗公式HP
http://www.nichirenshoshu.or.jp/
正林寺御住職指導(R7.8月 第259号)
盂蘭盆会の時期がまいります。この機会に命終後、未来世の行く末を決定される閻魔法王について、宗祖日蓮大聖人の御教えから拝してまいりましょう。
日蓮大聖人は『弥源太殿御返事』に、
「日蓮必ず閻魔法王にも委しく申すべく候」(御書723)
と仰せあそばされております。
私達の臨終の時、枕経・通夜・葬儀に際して日蓮正宗寺院から僧侶がお供されてくる、導師御本尊に南無妙法蓮華経と唱え奉ることにより、日蓮大聖人は必ず閻魔法王にも一生成仏するように委しく申し上げられる非常に重要な意義が存します。そのためにも月々日々に日頃の信心を真面目に励んで、後生の霊山を願うことが大切であります。
信心を真面目に励むために、第二十六世日寛上人は『寿量品談義』に、
「仏果を成ずることは因行による、因行を励むことは信心による、信心を進むことは法を聞くによるなり。聞かずんば信心生ぜず、信心生ぜずば修行を怠る。修行を怠れば未来何なる処に生るべしや。仍て歩を運んで聴聞肝要なり。聞く裏に信心を生ず、其の間が仏なり。一念信心を生ずれば一念の仏、二念信心生ずれば二念の即仏乃至一時信心を生ずれば一時の仏なり、一日信を生ずれば一日の仏なり乃至云云。信心生ずること必ず聞くに由るなり、縦ひ信心を生ぜざる族ありとも、聞きさへすれば功徳無量なり。」(富要10-183)
と、信心では聴聞の大事を日寛上人は御指南であります。そしてまた、
「命終して閻魔王庁に至る」(富要10-183)
とも御教示あそばされております。令和7年の本年(2025)日寛上人第300回遠忌をお迎え申し上げます。
世間的にも閻魔法王は、仏教において死後の世界で亡者を裁く王として知られています。
最近あまり聞きませんが、昭和時代の頃「嘘をつくと閻魔様に舌を抜かれる」という言い伝えは、この閻魔法王の持つ浄玻璃鏡という鏡に、生前の行いがすべて映し出され、嘘や隠し事は一切通用しないという世間的な教えから来ています。
逝去してから四十九日間の中陰において七回の裁判を受けるとされ、閻魔王は五番目の裁判官として、三十五日目(五七日忌)に重要な審判を下すとされています。そのため葬儀後の初七日から七七日忌までの忌日法要が大事になります。
当宗の化儀による「死する時塔婆を立て」(御書522)との塔婆を建立して成仏を願うことにより「日蓮必ず閻魔法王にも委しく申すべく候」との重要な意味が具わります。
さらに、「日蓮必ず閻魔法王にも委しく申すべく候」との証明として、法華経の文底下種仏法に基づく日蓮正宗の戒名をお付け申し上げます。当宗の戒名は命終して閻魔王庁に至り閻魔法王に大聖人が委しくおっしゃって頂く証拠でもあります。戒名を不要とされる方は、この機会に自問自答されることをお勧めいたします。
臨終に際しての御書は種々拝されます。日蓮大聖人は『上野殿御返事』に、
「御臨終のきざみ、生死の中間に、日蓮かならずむかいにまいり候べし」(御書1361)
と仰せであります。導師御本尊に読経唱題申し上げることにより、臨終に際して故人は迷わないように日蓮大聖人がお迎えに来られたことを意味し、安心して成仏の境界へと導かれていきますとの御書と拝します。つまり「導師」とは、未来世への「案内者」(御書723)のことでもあります。
また大聖人は『弥源太殿御返事』に、
「南無妙法蓮経は死出の山にてはつえはしらとなり給へ。釈迦仏・多宝仏・上行等の四菩薩は手を取り給ふべし。日蓮さきに立ち候はヾ御迎へにまいり候事もやあらんずらん。又さきに行かせ給はヾ、日蓮必ず閻魔法王にも委しく申すべく候。此の事少しもそら事あるべからず。」(御書722)
と仰せでありまして、祭壇に御安置申し上げられた導師御本尊に御題目の南無妙法蓮華経を唱えたことで故人に死出の険しい山道を越えるための杖や柱を施したことになります。導師でいらっしゃる日蓮大聖人から故人への死後の道案内を賜り閻魔大王にも成仏するように仰ってくださるということです。導師御本尊には、特別に常住御本尊と異なり唯授一人血脈相承の上から閻魔法王が認めあそばされます。日蓮大聖人が閻魔大王に故人は成仏するようにと仰る非常に重要な意義があると拝されます。また死後の行方を決定される閻魔大王に対しまして恵まれた環境に生まれますよう後生善処を願う大事な意味もあります。
未入信の方には祭壇の御本尊は、墨で書かれただけの書き物と見えている場合もあります。そのような方には折伏育成の意義から『経王殿御返事』に仰せの、
「日蓮がたましひ(魂)をすみ(墨)にそめながしてかきて候ぞ」(御書685)
と、御指南でいらっしゃる究極の御本尊であることを教えていきます。
その御本尊に御題目を唱えるところ『妙法尼御前御返事』に、
「しかれば故聖霊、最後臨終に南無妙法蓮華経ととなへさせ給ひしかば、一生乃至無始の悪業変じて仏の種となり給ふ。煩悩即菩提、生死即涅槃、即身成仏と申す法門なり。」(御書1483)
と御指南であります。最後臨終に当たり、導師御本尊に南無妙法蓮華経の御題目を唱えたことで、生まれてから臨終を迎えるまでの身心に縁された、様々な人生の辛さ、苦労そして病をも全て洗い流され、新たな人生である成仏の境界へと、導師御本尊の力用により導かれていきます。それが日蓮大聖人の説かれた一生成仏であります。
導師御本尊の「導師」には、大切な意義が当宗には存すると拝信申し上げます。その意義からも臨終に際して、特別に導師御本尊を奉掲申し上げます。
その導師について、大聖人は『真言諸宗違目』に、
「導師は但日蓮一人なるのみ」(御書600)
と仰せであります。導師御本尊の真意につながる御指南と拝します。
また同抄に、
「日蓮は日本国の人の為には賢父(けんぷ)なり、聖親(せいしん)なり、導師なり」(御書600)
とも仰せあそばされております。
そして『諸法実相抄』に、
「地涌の菩薩のさきがけ日蓮一人なり、(中略)一切衆生のためには大導師にてあるべし」(御書666)
と、
さらに同抄には、
「南無妙法蓮華経と唱へて日本国の男女をみちびかんとおもへばなり。経に云はく『一名上行、乃至唱導師』とは説かれ候はぬか」(御書668)
と、命終に当たり導師御本尊へ南無妙法蓮華経を唱えられた男女は導かれていくとの意義が拝される「唱導師」を御指南と拝信いたします。
葬儀に際して一心に永眠された方の誘引化導を願い即身成仏するために「引導」をお渡しいたします。『妙法曼陀羅供養事』に、
「此の曼陀羅(まんだら)は文字は五字七字にて候へども、三世諸仏の御師、一切の女人の成仏の印文なり。冥途(めいど)にはともしびとなり、死出(しで)の山にては良馬となり、天には日月の如し、地には須弥山(しゅみせん)の如し。生死海の船なり。成仏得道の導師なり」(御書689)
と、日蓮正宗の化儀において臨終には成仏得道の導師である「此の曼陀羅」導師御本尊に、一生成仏を願うことが必要であります。当宗の「引導文」は導師御本尊に御報恩申し上げて、精霊を決定菩提の信心に安住させ即身成仏の本懐を得るための大事な化儀であります。
人は生まれれば、必ず最後の臨終である死を迎えなくてはなりません。そのためにも信心は必要になります。
人が生きると書いて人生と読みますが、人が生きる人生には必然的に苦しみを伴います。時には楽しい人生もありますが、決して長続きしないものであり、いつの日にか辛い日々を送ることがあります。これは娑婆世界に生きる私達の定業です。
大聖人は『聖人御難事』に、
「よからんは不思議、わるからんは一定」(御書1398)
と御指南下されております。
自己の限られた人生観、経験や知識だけでは決して苦しみから逃れられないのが人生であります。仏法では苦しみを四苦八苦といわれる八つの苦しみを説いており、生きる苦しみ、年をとる苦しみ、病気になる苦しみ、死を迎える苦しみ、愛する人と別れる苦しみ、会いたくない人と会わなければいけない苦しみ、手に入れようとしても手に入らない苦しみ、そして最後に私達の心と体を悩ます無数の苦しみがあります。それを四苦八苦と申します。貪瞋癡の三毒である、貪る気持ち・怒る気持ち・愚癡を言う愚かな気持ちが苦しみの根源であると説きます。この三つの悪い要素が生活の中で複雑に変化し私達の心身を悩ませ病等を引き起こします。
以上の苦しみは私達の限られた人生経験では解決しがたいことがあります。不幸になる間違った解決策を選択しないために、本当の幸せのため信心が必要となります。
他の宗派でも御題目を唱えるところがあります。極理の師伝から拝された御書に日蓮大聖人が仰せになる七百数十年来、相伝に有らざれば知り難しとの日蓮正宗総本山大石寺に伝わり伝統ある御題目を当宗では唱えて追善供養させて頂きます。
その追善供養のもとに閻魔法王の存在を通して、日蓮大聖人の大慈大悲と師弟の信心について拝することが大切です。
閻魔法王は、サンスクリット語のヤマ(Yama)に由来し、仏教において死後の世界で亡者を裁く王として知られています。
文永11年(1274年)2月21日、日蓮大聖人は重病に臥す北条弥源太殿に宛てた御書の中で、
「又さきに行かせ給はゞ、日蓮必ず閻魔法王にも委しく申すべく候。」(御書723)
との仰せは、「もしあなたが先に亡くなられたなら、私が必ず閻魔法王にも詳しく申し上げましょう」という非常に有り難い意味です。この御文には、深い慈悲と師弟の絆が込められている御書と拝します。大聖人は、弟子檀那が死後の世界で困ることがないよう、ご自身が閻魔法王に直接取り次ぐことを約束されたのです。
御書から、真の師弟関係の姿を学ぶことができます。
第一に、師匠は弟子を生涯にわたって、さらに死後に至るまで見守り続けて下さるということです。大聖人は、弟子の現世での苦悩だけでなく、来世での安心まで配慮してくださる有り難い御書であります。
第二に、師匠の慈悲は、どんな困難な状況をも乗り越える力を持つということです。たとえ冥界の王である閻魔法王であっても、大聖人は弟子のために堂々と進言くださり、弟子の功徳を証明なさると約束された御教示です。
第三に、この約束は、弟子に対する絶対的な信頼と慈悲の表れです。大聖人は弟子の信心を信じ、その功徳を確信されていらしたからこそ、このような約束が果たされます。
この教えは現代を生きる私たちにとって、どのような意味を持つのか思考することも大事です。
まずは、死への不安を乗り越える力についてです。人間である以上、誰しも死に対する恐れを抱きます。しかし、御本尊への絶対信と真の師弟相対の信心に生きる人は、死後の世界においても御本尊に師匠に見守られているという安心感を持つことができます。師匠とは申すまでもなく、日蓮大聖人であり、第二祖日興上人をはじめとする僧宝の御歴代上人です。現在は御法主日如上人猊下を師匠として拝信申し上げることであります。
次に、信心の確信についてです。大聖人が閻魔法王に取り次ぐと約束されたのは、弟子の信心の功徳を確信されていたからです。私たちも、日々の信心修行を通じて、自分自身の仏性を磨き、確固たる信念を築いていくことが大切です。
そして、慈悲の実践についてです。大聖人の慈悲に学び、私たちも周りの人々に対して、同じような思いやりと配慮を持って接することが重要でしょう。まさに、下種折伏活動です。
閻魔法王の教えは、死後の世界の恐怖を説くものではありません。むしろ、師弟相対の信心の尊さ、信心の功徳の確実性、そして慈悲の深さを教えてくださる、希望に満ちた教えであります。
改めて、大聖人の大慈大悲を拝し奉り、師弟相対の信心を築き、大御本尊への絶対的確信のもと日々を歩んでいくことができます。その結果、現世においても来世においても、安心して人生を全うすることができることを確信いたしましょう。
最後に、閻魔法王の教えを通じて、師弟相対の信心の尊さを活動充実の年に相応しく、さらなる信心を目指していただければ幸いであります。
宗祖日蓮大聖人『弥源太殿御返事』に曰く、
「南無妙法蓮華経は死出の山にてはつえはしらとなり給へ。釈迦仏・多宝仏・上行等の四菩薩は手を取り給ふべし。日蓮さきに立ち候はゞ御迎へにまいり候事もやあらんずらん。又さきに行かせ給はゞ、日蓮必ず閻魔法王にも委しく申すべく候。此の事少しもそら事あるべからず。日蓮法華経の文の如くならば通塞の案内者なり。只一心に信心おはして霊山を期し給へ。」(御書722)
一、令和7年の年間方針・『活動充実の年』
二、令和7年の年間実践テーマ
①勤行・唱題で果敢に折伏
②登山推進と寺院参詣で講中の活性化
③活発な座談会で人材育成
大日蓮転載
(破折文書)群馬布教区有志一同
時局協議会シリーズ
平成3年(1991年)12月25日
日蓮正宗時局協議会
日蓮正宗と戦争責任
時局協議会資料収集班1班
http://monnbutuji.la.coocan.jp/jikyoku/sennjise.html
御書五大部手引
正を立てて国を安んずる「立正安国論」
人本尊開顕の書「開目抄」
日蓮当身の大事「観心本尊抄」
末法の時を撰ぶ「撰時抄」
三大秘法への知恩報恩が大事「報恩抄」
http://blog.goo.ne.jp/shourinzi1972/
※支部組織の充実強化に活用ください。
発行 日蓮正宗宗務院
年回表(御法事)
【本日の御聖訓】(メール配信)
正林寺支部掲示板(正林寺支部講中のみなさんへ連絡事項等)
https://www.facebook.com/shourinzi
法華講正林寺支部 E-mailアドレス
nsys1562@yahoo.co.jp