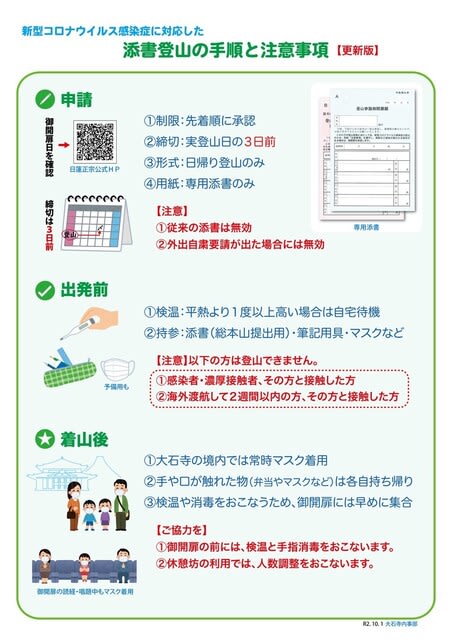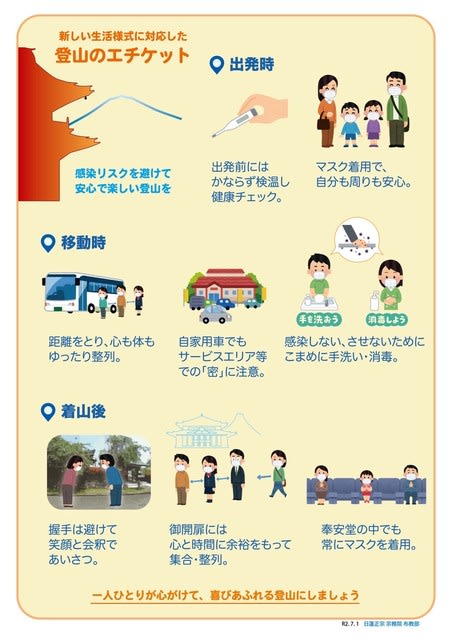正林寺御住職指導(R4.6月 第221号)
学校の成績やスポーツでの順位、企業においても一番になることが求められて評価される社会であります。社会全体が一番となることに、最高の評価基準を置き判断する傾向があります。それに向けて一生懸命に努力して生きている人は世界中に大勢います。
同時に一番を目指すことには、知らぬ間に一番と一番ではない人との間には差別感(格差)を生み出し、人間関係に歪みが生じて想定外な問題、争いへと発展するリスクも潜んでいます。まさに、闘諍堅固の時代に生まれた衆生(本未有善)の習気です。一番を追求すると同時に、差別感や人間関係の歪みを改善・回避すべき方途をも備える人が、真の一番といえるでしょう。
それはまた、ネットの世界でも同じことです。それぞれサイトの分野にランキングがあります。検索ランキングなど列挙すれば切りがありません。まさに、その分野での一番を目指すことに生きがいを感じ、生活においても優雅で安定感があるように見え目指している人もおり、フォロワーが何十万・何百万と共感し達成された時の感激は体験した人でなければ分からない、自受法楽とは明らかに異なる「喜ぶは天」(御書647)との六道輪回の世界でしょう。ネットの世界は優雅な反面、問題として改善すべき闇サイトや裏アカウントなど犯罪・いじめにつながり、差別感と人間関係を壊しかねない温床があります。
宗祖日蓮大聖人の仏法からは、その感激等は八風の四順に、温床等は四違にあたり扱い方により未来が思わぬ方向へ進む場合があります。まさに、差別感や人間関係の歪みのことであり、慢の一字にも用心が必要です。元来、人間の身は草の上の露のため、思わぬ展開になりやすい立場にあります。八風に翻弄されて草の上から転げ落ちないように、身心のバランス感覚を信心で日々磨くことが重要であります。
『御義口伝』に、
「第三 身心遍(へん)歓喜(かんぎ)の事
御義口伝に云はく、身とは生死即涅槃(しょうじそくねはん)なり。心とは煩悩即菩提(ぼんのうそくぼだい)なり、遍とは十界同時なり、歓喜とは法界同時の歓喜なり。此の歓喜の内には三世諸仏の歓喜納まるなり。今日蓮等の類南無妙法蓮華経と唱へ奉れば、我則歓喜とて釈尊歓喜し玉ふなり。歓喜とは善悪共に歓喜するなり。十界同時なり。深く之を思ふべし云云」(御書1748)
と。
仏法の世界では、差別平等一如といわれ一番であっても一番ではなくても自受法楽の境界から八風の扱いに精通する術を身に付け、謗法厳誡が条件のもと平等に成仏できるよう救済する教えであります。その上から、法華の行者は上中下根あれども、信心の厚薄により、持つ法第一ならば、持つ人も第一となります。信心をしなければ、世間的な一番でも、残念ながら第一の法を持たない限りは、第一の人とはなりません。
持つ法第一とは、釈尊が末法に託された上行菩薩の日蓮大聖人が所持され顕された一閻浮提第一の御本尊のことであります。
それは総本山大石寺の奉安堂に御安置の本門戒壇の大御本尊であり、大御本尊を信じて題目を唱える人は、老若男女・貴賎上下を選ばずに第一となります。当然ながら日蓮正宗寺院から御下付頂いた御本尊を受持することは同じです。むしろ、各自において当宗の御本尊を受持して信行しなければ、厳格に、持つ法第一ならば、持つ人も第一とはなりません。内得信仰の方は、御本尊をお迎えできるように精進しましょう。顕正会で主張する遙拝勤行なるものは、当然ながら、現実に受持することはできず、実体として持つ法(御本尊)がないため、持つ人第一とはなりません。確認ですが、広告文も法ではありません。広告文を大事に持参・所持したところで、持つ人第一とはならないのです。論外である他宗の「本尊に迷へり」(御書554)と大聖人が断定された本尊は、第一の法ではありません。
この持つ法第一ならば、持つ人も第一なりとの確信のもとに生きるところ、世法的評判(名声・ランキング)を気にせず、世間的一番ではない、大御本尊への絶対的確信を堅持し、大聖人からお誉めを賜ること、つまり、有り難い功徳を積み御利益を頂くことができる、第一の人となります。まさに、第一の人の身とは、「五尺の身は妙法蓮華経の五字なり」(御書1728)であり、『法華題目抄』に、「水五尺の身に近づかず」(御書354)との御利益となります。さらに講中では異体同心へと広げて、折伏により依正不二の原理から常寂光土へと実現します。
第一の人となるべき条件、講中での心がけがあります。
①大いに御題目を唱え、力強く動いていくこと。まさに、持つ法第一ならば、持つ人も第一となる信心のことであり、『経王殿御返事』に、「あひかまへて御信心を出だし此の御本尊に祈念せしめ給へ。何事か成就せざるべき」(御書685)と。
②体制を整えていくこと。
各部・各班は、所属されている講員を総点検し、家庭訪問・育成に力を入れていく。講中一結・異体同心の確立。『生死一大事血脈抄』に、「剰(あまつさ)へ日蓮が弟子の中に異体異心の者之有れば、例せば城者として城を破るが如し。」(御書514)と。
③歓喜あふれる信行を確立していくこと。
大事な時こそ、内外の魔も盛んになって来るため、一歩も退くことなく月々日々に信行を前進させていく。
今起こる種々のことは、大前進の前の小事と捉える。『衆生心身御書』に、「小事のつもりて大事となる。何(いか)に況(いわ)んや此の事は最大事なり」(御書1216)と。
④真剣な祈りと実践。
中途半端な信心では、一向に進んでいかない。全力で遮二無二、不軽菩薩の振る舞いで動く。『崇峻天皇御書』に、「法華経の修行の肝心は不軽品にて候なり。不軽菩薩の人を敬ひしはいかなる事ぞ。教主釈尊の出世の本懐は人の振る舞ひにて候けるぞ」(御書1174)と。
⑤有縁の方と共に動くこと。
今の時ほど、大きく前進する時はない。『生死一大事血脈抄』に、「総じて日蓮が弟子檀那等自他彼此(じたひし)の心なく、水魚の思ひを成して異体同心にして南無妙法蓮華経と唱へ奉る処を、生死一大事の血脈とは云ふなり。然も今日蓮が弘通する処の所詮是なり」(御書514)と。
一年の中盤、講中挙げて折伏下種・育成・結集に励んで参りましょう。
さらに、持つ法第一ならば、持つ人も第一となるためには、以下の御書を心肝に染めていく信行が大切です。
日蓮大聖人は『持妙法華問答抄』に、
「されば持たるゝ法だに第一ならば、持つ人随って第一なるべし」(御書298)
と仰せであります。この「持つ人随って第一なるべし」との御文は『富木殿御返事』に、
「経に云はく『法華最第一なり』と。又云はく『能く是の経典を受持すること有らん者も、亦復是くの如し。一切衆生の中に於て亦為れ第一なり』と」(御書1578)
の文証からと拝します。
その道理から、持つ法第一ならば、持つ人も第一となります。『四条金吾殿女房御返事』に、
「されば此の世の中の男女僧尼は嫌ふべからず、法華経を持(たも)たせ給ふ人は一切衆生のしう(主)とこそ仏は御らん(覧)候らめ、梵王・帝釈はあを(仰)がせ給ふらめとうれしさ申すばかりなし。又この経文を昼夜に案じ朝夕によみ候ヘば、常の法華経の行者にては候はぬにはん(侍)ベり。」(御書756)と。
御法主日如上人猊下は、
「一閻浮提第一の御本尊を持つ者こそ、一切衆生のなかにおいて第一の者である(中略)一閻浮提第一の本門戒壇の大御本尊様が在すことを心肝に染め、たとえいかなる障魔が惹起しようとも恐れることなく、一意専心、折伏に励むところに必ず大御本尊様の御照覧があることを確信し、講中一結・異体同心して折伏に励んでいくことが今、最も大事であります。」(大日蓮 第915号 R4.5)
と御指南であり、持つ法第一とは一閻浮提第一の御本尊のことであります。
『祈祷抄』に仰せの、
「法華経の行者の祈りのかな(叶)はぬ事はあるべからず」(御書630)
との御教えには、持つ法第一ならば、持つ人も第一であるとの自覚が必要です。
この持つ法第一ならば、持つ人も第一となる信心には、「持つ法」の「法」については申すまでもなく「法華最第一なり」である一閻浮提第一の御本尊・本門戒壇の大御本尊であります。
さらに、帰入・会入の意義からは、「治生産業」(御書79)の教えのもと世間法(憲法・法律等)にも順応する意味から、「持つ法」の「法」に含まれると拝すことも大事です。世界広布を目指し一天四海広宣流布を祈念する、法華経の行者の祈りの叶はぬ事はあるべからずには、日本での治生産業と国外においての治生産業をも考慮する必要性があるでしょう。
最後に、御法主日如上人猊下は、
「本年、宗門は『今こそ 折伏の時』の標語のもとに、僧俗一致して前進をしておりますが、その行く手にはあらゆる障魔が競い起こることは必定であります。しかし、(中略)魔が競い起きた時こそ、信心決定の絶好の機会と捉え、一人ひとりが妙法受持の大功徳を確信して、決然と魔と対決し、粉砕していくことが大事であります。」(大日蓮 第916号 R4.6)
と御指南です。「一人ひとりが妙法受持」の「受持」とは、まさに持つ法第一である妙法を受け持つこと、つまり、一閻浮提第一の本門戒壇の大御本尊であると拝します。そして、持つ人も第一となる信心には、魔が競い起きた時こそ、信心決定の絶好の機会と捉え、決然と魔と対決し、粉砕していくことができる法華講衆は、持つ人も第一となります。
宗祖日蓮大聖人『祈祷抄』に曰く、
「大地はさゝばはづるゝとも、虚空をつなぐ者はありとも、潮のみ(満)ちひ(干)ぬ事はありとも、日は西より出づるとも、法華経の行者の祈りのかな(叶)はぬ事はあるべからず。法華経の行者を諸の菩薩・人天・八部等、二聖・二天・十羅刹等、千に一も来たりてまぼ(守)り給はぬ事侍らば、上は釈迦諸仏をあなづり奉り、下は九界をたぼらかす失(とが)あり。行者は必ず不実なりとも智慧はをろかなりとも身は不浄なりとも戒徳は備へずとも南無妙法蓮華経と申さば必ず守護し給ふべし。」(御書630)