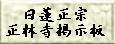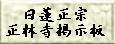正本堂の御指南に対する創価学会の『再お伺い書』の問難を破す(※転載)
(一) 正本堂と創価学会
「昭和四十三年十月の会長発言が、正本堂を三大秘法抄等の御遺命戒壇そのものと断定した典型の発言なのか」に答える
御法主日顕上人猊下は去る一月六日・十日の教師指導会において、池田名誉会長の昨年十一月十六日の傲慢(ごうまん)極まりないスピ-チに関連して、次のように御指南された。
「五十二年の問題の折に、『二度とこのようなことのないようにする』と誓ったにもかかわらず、十年たってまた法主・宗門批判が起こったのは、池田氏は大聖人の仏法を全部つかんでおり、今後の広宣流布の上で、法主の指示・指南を受ける必要はない、というような考えを元としている故であり、その源は昭和四十三年の正本堂着工大法要において、大聖人の御遺命の達成であるという意味で、正本堂を『三大秘法抄』の戒壇であると言い切ったような信徒としての慢心の体質に由来する」(趣意)
この御指南は、池田氏に法主誹謗等の破和合僧の言動が見られるのは、過去における慢心の体質にその源が存することを述べられたものであり、特に昭和四十三年の正本堂着工大法要の氏の挨拶が、信徒として、重大なる御遺命軽視の発言であったと指摘されたものである。
その後、日顕上人はこの御指南を『大日蓮』に掲載する際、二カ所の時期的な訂正をされた。
これに対し学会は二月二十七日付『お伺い書』において、日顕上人が二カ所の訂正をされたことを取り上げて、
①昭和四十三年十月の池田名誉会長の挨拶が、『三大秘法抄』を用いて正本堂を御遺命の戒壇と定義した最初とか、独断的発言とはいえない。
②それを根拠に池田氏に「慢心」があり、それが今日の問題を生んだ根源との御説法は成り立たない。
③正本堂着工大法要での池田会長の挨拶を対象に論じた猊下の御説法は、二カ所の訂正により成り立たない。よって正本堂の意義に関する部分等は撤回されるべきである。との理由で詰問(きつもん)してきたのである。
この学会の『お伺い書』に対し、御法主上人は三月九日付の『御指南』において、
①『大日蓮』での訂正とは、昭和四十三年の池田氏の発言以前に、『三大秘法抄』等を引用しての、正本堂に関する日達上人のお言葉があったという時期的な意味の訂正であり、「正本堂=三大秘法抄の戒壇」と断定したのは池田氏の発言である。よってこれらの論難は当たらない。
②正本堂建立に関しては、創価学会が広宣流布成就を願うあまり、大聖人の御遺命の戒壇を建立したという意識をもち、その意識から強まった「慢心」が正本堂の意義づけに関する問題、五十二年路線の問題、そして今回の問題を生んだ根源となっている。
③最初の発言が誰であるかということとは関係なく、着工大法要の際の池田氏の言葉は誤りであるから、正本堂建立発願者という責任ある立場からも、進んで大聖人様にお詫び奉り、それを宗内に公表すべきである。(趣意)
と仰せられている。
〔学会の問難の要約〕
(一)段においては、初めに池田氏の昭和四十三年十月、正本堂着工大法要における、「日蓮大聖人の三大秘法抄のご遺命にいわく『霊山浄土に似たらん最勝の地を尋ねて戒壇を建立す可き者か時を待つ可きのみ事の戒法と申すは是なり、三国並に一閻浮提の人・懺悔滅罪の戒法のみならず大梵天王・帝釈等も来下して踏み給うべき戒壇なり』云々。この法華本門の戒壇たる正本堂の着工大法要を血脈付法第六十六世日達上人猊下の御導師により、無事終了することができました。本日参加された皆さま方に対し、厚く御礼申し上げると共に、皆さま方の栄光を心よりお祈り致します。大変にありがとうございました」
との挨拶を全文挙げている。
つづけて(学会側は)御法主上人の三月九日付『御指南』を要約して、正本堂を『三大秘法抄』の意義に関連して論じたのは、時期的な点からは池田氏が最初ではなかったので、その意味で訂正をしたが、内容の上から、正本堂を直ちに『三大秘法抄』の戒壇と断定したのは池田氏であり、その発言の不遜性(ふそんせい)はいささかも崩れないとの認識であろうとし、
「猊下の、この会長発言へのご認識は、果たして昭和四十三年十月以前の宗内僧俗の、正本堂の意義に関する発言の上から妥当なのでありましょうか」
と述べて、以下のごとく三項目にわたり問難を掲げている。
〔「宗門の正本堂に関する発言等」についての要約〕
この項では日達上人・日顕上人を含め奉り、当時の宗門僧侶の正本堂に関する二十五の発言例を挙げたのちに、
「池田会長が昭和四十三年十月の着工大法要で、三大秘法抄の文を引いて『この法華本門の戒壇たる正本堂』と述べた発言など、その存在と印象が薄くなるほど、宗門内では昭和四十年二月以降、正本堂=ご遺命の戒壇の実現、というストレートな発言が支配的であったということが分かります」
と述べ、池田氏の四十三年着工大法要の挨拶内容が、当時の宗門の正本堂に関する意義づけを逸脱してはいないという。
〔「正本堂の意義に関する正しい経過史」についての要約〕
この項においては、前項の検証により、正本堂の意義づけは日達上人の御指南が根本であることが歴史的な事実であるとし、昭和四十年二月十六日の、第一回正本堂建設委員会における、日達上人の御指南に則(のっと)って作成されたとする『御供養趣意書』に、「実質的な戒壇建立、広宣流布の達成」との文があることは、以前から宗内で、日達上人が正本堂建立が実質の戒壇建立、広宣流布の達成であるとのお考えをもっておられたことを証明するものであり、これを踏まえ、正本堂が実質的な本門戒壇であり、御遺命の達成であるとの考えかたが、宗内に浸透されていったのが事実経過であるという。
また昭和四十年九月十二日の『訓諭』と『院達』は、正本堂が御遺命の戒壇であり、広宣流布がいよいよ事実の上で成就されるということを、宗内の僧俗に徹底したものであり、この意義のもとに、正本堂の御供養をよびかけたのであって、故にこの『訓諭』・『院達』の見解を後から安易に変更することは、御供養に参加した八百万信徒を欺(あざむ)くものであり、社会的・道義的責任は免(まぬが)れないという。
そして正本堂の意義については、以上の流れの中でその意義の基本骨格が完全に定まったとしている。
〔「突出していない四十三年会長発言」についての要約〕
池田氏の、昭和四十一年の『立正安国論講義』中には、正本堂を三大秘法の完結としたストレートな表現もあったが、その他の池田氏の発言は言い過ぎたものではないとし、その例として、昭和四十二年の『発誓願文』中の文言を挙げ、それは正本堂の建立と広布達成時の本門戒壇とを、ただちに結びつけた発言ではないという。
すなわち宗内の僧侶に、三秘抄の本門戒壇建立、とのズバリ発言が見られる中で、発願主の池田氏は、意義の完結を未来のこととして論じているのであり、四十三年十月の着工大法要の挨拶も、この認識のもとになされているという。その証拠として、前日の十月十二日の聖教新聞に前年の『発誓願文』を再掲載していることを挙げ、よって池田氏の発言は、『発誓願文』に込められた、正本堂と広布の未来における本門戒壇の完結、という認識のもとに発言されたものであることは明らかであり、故に着工大法要における池田氏の発言は、宗内で突出したものではないというのである。
〔「ご回答」への「お伺い」〕
次に学会側はここで(イ)~(へ)までの六箇の質問を構えているが、これについては反論とともに後述する。
〔本段における学会の問難を破す〕
学会は本段において、前記のような「検証」を行っているが、その主張の要点は、「正本堂を『三大秘法抄』等の御遺命の戒壇なりと最初に定義したのは池田氏ではない。したがってその責任を池田氏にありとして、氏の慢心の表れとした猊下の御指南は、事実誤認である」とするところにあるといえよう。
確かに今回、日顕上人が訂正されたごとく、正本堂建設当初に、その意義に関して、日達上人の御指南が存したことは事実である。しかしながら、昭和四十年の第一回正本堂建設委員会における日達上人の御指南が、正本堂の意義に関する一切の根本であり、それ以前には、学会には戒壇に関して何の方針も、責任も存在しないかのごとき学会側の主張は、正当とはいえないのである。
ここで創価学会が本宗の戒壇論、及び正本堂建立にどのようにかかわってきたかについて、戦後における本宗の戒壇論議の流れを検証したい。
〔奉安殿建立と国立戒壇〕
戦後、本宗は創価学会の破竹の折伏大行進により、教勢の急激な進展をみた。その結果、昭和三十年十一月二十三日、学会の寄進により総本山に奉安殿が建立され、戒壇大御本尊の御遷座が行われた。すなわち大御本尊は昭和四十七年十月の正本堂建立までの十七年間、奉安殿にましましたのである。
この奉安殿建立に関し、当時創価学会青年部参謀室長であった池田氏は、昭和三十一年四月の『大白蓮華』五十九号に、「奉安殿建立とその意義」と題する一文を寄せ、
「戒壇御本尊奉安殿設置は正しく広宣流布への第一実証を意味するのであります。国立戒壇の建立こそ、悠遠六百七十有余年来の日蓮正宗の宿願であり、また創価学会の唯一の大目的なのであります。即ち三大秘法抄に云く、『戒壇とは王法仏法に冥じ(中略)時を待つべきのみ事の戒法と申すは是なり』云云」
と述べ、つづいて、
「なかんずく『時をまつべきのみ』と御予言なされて六百七十星霜・今ここに奉安殿建立とともに化儀の広宣流布の歴史的第一頁の段階に入ったわけであります」
と述べて、奉安殿建立が明確に国立戒壇建立の第一歩であるとし、化儀の広宣流布の時が到来したことを述べている。さらに『三大秘法抄』の、
「三国並に一閻浮提の人(中略)踏みたもうべき戒壇なり」
の文、及び『富士一跡門徒存知事』の、
「日興云く(中略)本門寺を建立すべき由奏聞し畢んぬ。仍って広宣流布の時至り国主此の法門を用いらるるの時は必ず富士山に立てらるべきなり」
の両文を引文した後に、
「しかして創価学会こそ、その仏意仏勅を蒙り(中略)闘争を成しゆく団体なのであります」
と述べている。このような発言から見て、「創価学会」においては、昭和三十年当時において、自らを主体的に国立戒壇の建立主と自覚し、『三大秘法抄』等の御遺命の戒壇建立を志したことが看取(かんしゅ)されるのである。
奉安殿はその立場における化儀の広宣流布の第一段階であり、さらにこの意思の具体的展開が、十七年後の正本堂建立であったのである。
ともあれここでは、奉安殿建立時にすでに「国立戒壇建立を学会が行う」との強固な意識があったことを指摘しておく。
〔戸田会長は戒壇建立を重視〕
次に創価学会第二代会長、戸田城聖氏の講演中に、本宗の戒壇に関する発言がある。これは当時、すでに本宗最大の信徒団体となっていた、学会の長としての発言であり、また後の第三代池田会長の戒壇に関する認識とも、密接な関係をもつ上から、重要な意義を含むものである。すなわち創価学会の弘教活動の目的として当時公けに強調されていたのが、「化儀の折伏・国立戒壇の建立」ということであった。
すなわちこれにつき戸田会長は、
「化儀の広宣流布とは国立戒壇の建立である」(巻頭言集・昭和三十一年二月一日)「国立戒壇の建立は、日蓮門下の重大使命であることを論じた。しかし重大使命であるとしても、もし、国立戒壇が、現在の状態で建立されたとしたら、どんな結果になるであろうか。一般大衆は無信仰であり、無理解である。単に国家がこれを尊重するとするならば、現今の皇大神宮や明治神宮の如き扱いを受けるであろう。しからば『かかる日蓮を用いぬるとも、あしく敬はば国亡ぶべし』との御聖言のように、国に災難がおこるであろう。ゆえに、国立戒壇の大前提として、本尊流布が徹底的になされなければならぬ。日本全国の津々浦々まで、この御本尊が流布せられ(中略)最後の国立戒壇の建立、すなわち三大秘法の本門の戒壇の建立は、本尊流布の遂行とともに、当然完成されることは、いうまでもないと信ずる。また、このことは至難事中の至難事であることも、いうまでもない」(傍線筆者) (巻頭言集・昭和三十一年五月一日)
「われらが政治に関心をもつゆえんは(中略)国立戒壇の建立だけが目的なのである。ゆえに政治に対しては、三大秘法禀承事における戒壇論が、日蓮大聖人の至上命令であると、われわれは確信するものである」(傍線筆者) (巻頭言集・昭和三十一年八月一日)
「国立戒壇建立こそ遣使還告の役目であり、地涌の菩薩のなすべきことと自覚するならば、化他にわたる題目こそ、唯一無二の大事なことになるのではなかろうか。そこに折伏の意義があり、学会の使命があるのである」(傍線筆者) (巻頭言集・昭和三十二年六月一日)
以上の戸田会長の戒壇に関する発言からは、化儀の広宣流布、すなわち「御本尊流布」と「戒壇建立」こそが学会の至上の目的・使命であると会員に説いたことが明らかである。しかしそれと共に、時至らぬのに戒壇を建立すれば、国に難が起こる故に、徹底的に津々浦々まで「御本尊」の流布がなされねばならない、との言辞があることに注目すべきである。
すなわち、たとえ宗祖の御遺命たる「戒壇建立」が重大事ではあっても、その戒壇建立の条件、すなわち、「事の戒法」としての「王仏冥合・広宣流布」がなされなければ、戒壇建立を行うべきでないと述べていることである。
これによれば、戸田会長は「国立戒壇」建立を唯一無二の学会の使命とはしながらも、その実現に関しては、宗祖の御意思を慎重に拝しておられたことが窺われるのである。
〔池田会長も当初は戒壇重視〕
昭和三十四年一月一日付の『国立戒壇の建立と学会員の前途』と題する池田氏の総務時代の発言を見るに、
「あくまで、本門の戒壇建立とは、大聖人様の至上命令である。そして、わが日蓮正宗創価学会のただひとつの目的であることは、論をまたない」(傍線筆者)
「この戒壇こそ、末法万年にわたり、民衆を救済するものであると思う。したがって国立の戒壇建立は、全民衆の要望によって成就されるものであることを忘れてはならない」(傍線筆者)
「国立戒壇建立の際には、大御本尊様が奉安殿より正本堂へお出ましになることは必定と思う」(傍線筆者)
「宗教にあっても、最高の宗教が国民の幸福のために、国立戒壇として建立されることは、必然でなくてはならぬ」
と述べている。この時点における池田氏の戒壇論は戸田会長と同様、国立戒壇建立が宗祖の至上命令であり、仏法上の重大事であるとするものであるが、この発言中で特に注目されることは、国立戒壇建立の時は大御本尊が「正本堂」へお出ましになると述べていることである。因みに、「正本堂」という語句の出所は定かではないが、時期的に最も早く見られるのは、この池田氏の発言である。
またこの時点における氏の戒壇建立に対する意識は、戸田会長と同じく、戒壇は広宣流布の暁に建立されるというものであり、それは、「全民衆の要望によって成就される」との語句からも推定し得るのである。
〔正本堂へお出ましの時が広宣流布〕
次の正本堂に関する記述は、昭和三十四年八月五日の、やはり池田氏の「創価学会の歴史と確信」との講義に見られる。ここで池田氏は、
「さらに御法主上人様の深い御構想で、やがては正本堂と、どういう名前になるかわかりませんが(中略)そこへ奉安殿の御本尊様がおでましになるのです。そのときが広宣流布の姿、儀式なのです。そんなに遠くないような気もいたしますが、仏智はかりがたしです。それこそ、もうひとふんばり、ふたふんばりですね」(傍線筆者)
と述べ、先の一月一日の発言においては、正本堂へ大御本尊がおでましになるのは「国立戒壇建立の時」と言っていたものを、ここでは逆に「正本堂へ大御本尊がおでましになる」その時が「広宣流布」との考えに変わっている。そしてその時期も、「そんなに遠くないような気がする」と述べているのである。ここに創価学会における、戒壇建立の時期と条件に関する微妙な変化が看取されるのである。
〔正本堂と本門戒壇堂を分離〕
また昭和三十五年四月四日付の「戸田先生の三大誓願」と題する講演で、池田氏は大客殿の建立に関し、
「『それが終わったならば、すぐに正本堂を造りなさい。いまの御影堂の裏に世界各国の粋を集めて世紀の建築をしなさい』と、このようにも(戸田)会長先生は御遺言なされております。とともに、戒壇建立のときには戒壇堂もでき上がるものと考えられます」(傍線筆者)
と発言している。
これにより、学会としては、大御本尊が奉安殿からおでましになる本堂を「正本堂」と呼称していたことが判る。
と共に昭和三十四年一月までは「国立戒壇」を「正本堂」と見なしていたものが、翌三十五年四月には「正本堂建立」と「戒壇建立」とを別個のものとする考えに変わったことが明らかである。ここに戒壇建立の意義に関する重要な変化の萌(きざ)しが見られるのである。
また同三十五年六月の『大白蓮華』百九号には、「戒壇の研究」と題する記事が掲載された。これは仏教史における戒壇の史実と事跡が述べられ、さらに末法の本門戒壇を論じた二十六頁に及ぶ特集である。ここには、
「今日の戦の仕上げは、戒の流布、すなわち、国立戒壇の実現であると決定された。ここに初めて、あと二十年後には、大聖人の仏法も完成をみんとするわけである」
「創価学会は、今や、第三代会長池田先生のもとに、あと十九年、ひたすら国立戒壇建立に前進をつづけている(中略)正本堂と戒壇堂とはどんな関係におかれるのか」 (傍線筆者)
との文がある。「二十年後に国立戒壇が実現、大聖人の仏法が完成」「あと十九年にて国立戒壇建立」等の文が何を意味しているか。同研究の内容によれば、いうところの国立戒壇とは、『三大秘法抄』『一期弘法抄』における「御遺命の戒壇」であることが明白である。とすれば、国立戒壇を二十年後に建立するということは、取りも直さず、二十年後に御遺命の戒壇を建立するということに他ならない。
御遺命の戒壇建立を行うべく広布に精進するという、その志は尊いものであるが故に、代々の御法主上人には、深く学会を護られ、激励なされたお言葉が存するのである。
しかし、「自ら」や「自らの団体」が、戒壇の建立主であることに固執(こしゅう)することは、我執と言うべきではないだろうか。後年において、日達上人や御当代上人の、一切を勘案(かんあん)されての御指南に素直に従えない原因は、この我執に存すると考えざるを得ないのである。
〔正本堂建立のよびかけ〕
正本堂に関しての発言としては、大客殿建立直後の昭和三十九年五月三日、創価学会本部総会の講演で池田氏は、恩師戸田城聖氏から、
「大客殿の建立が終わったならば、ひきつづいて、すぐに正本堂の建立をしなさい」との遺言があった旨を述べ、さらに、
「正本堂の建立は、事実上、本山における広宣流布の体制としてはこれが最後なのであります。したがってあとは本門戒壇堂の建立を待つばかりとなります」
と述べている。
これは正本堂建立御供養を、具体的に会員に呼びかけた最初の発言であり、正本堂の意義づけに関して、重要な意味をもつものである。ここで池田氏のいう、「本山の体制としては正本堂が最後」、あるいは「あとは本門戒壇堂の建立を待つばかり」との発言が何を意味しているか。それは翌月に明らかとなるのである。
〔池田会長による戒壇矮小化(わいしょうか)〕
池田氏は昭和三十九年六月三十日の学生部第二十七回総会の講演において、国立戒壇論を否定し、続いて、
「戒壇建立ということはほんの形式にすぎない。実質は全民衆が、全大衆がしあわせになることであります。その結論としてそういう、ひとつの石碑みたいな、しるしとして置くのが戒壇建立にすぎません。したがって、従の従の問題、形式の形式の問題と考えてさしつかえないわけでございます」
と発言している(三、「戒壇建立は従の従云云」の段、参照)。
すなわち、この学生部総会の池田氏の発言と、前月の本部総会での「正本堂建立は事実上、本山における広布の体制としては最後」との趣旨の発言と照らし合わせてみれば、池田氏が正本堂重視、戒壇建立軽視の考えを持っていたことが明らかである。
また、このたびの御法主上人の『御指南』のごとく、この池田氏の発言が、大聖人一期の大事たる戒壇の御法門を軽んずるものであることはいうまでもない。
〔着工大法要に至る流れ〕
以上の創価学会における「正本堂」及び「戒壇」に関する発言、定義づけの流れを概観する時、そこに含まれる問題はまさに重大なものと言わねばならない。すなわち池田氏の昭和三十九年五月三日の総会における講演、さらに一カ月後の六月三十日の学生部総会における講演は、まさしく正本堂をもって、事実上の御遺命の戒壇建立とする方針を示したものである。
奉安殿建立以来の準備期間を経たのち、昭和四十年、正本堂建設が具体化するにともない、池田氏の発言も、いよいよ御遺命達成の意義を明確にしていった。
すなわち昭和四十年五月三日の総会では、日達上人より同年二月十六日の第一回正本堂建設委員会で賜った御説法であるとして、
「正本堂の建立は実質的な戒壇建立であり、広宣流布の達成を意義づけるもの」
と述べ、さらに昭和四十一年の『立正安国論講義』においては、正本堂が『三大秘法抄』等の御遺命の戒壇である意義が、直截的(ちょくさいてき)に述べられている。
そしてこのような一連の発言の帰結として、昭和四十三年十月十二日の着工大法要における「断定発言」となったものである。
これらの経過の中で、昭和四十二年の「発願式」を中心として、宗門の僧侶が正本堂建立に関して、精神的高揚(こうよう)により、「御遺命達成」に近い発言、なかにはそのものズバリの発言があったことは学会の指摘の通りであるが、これらの一連の戒壇に関する流れを概観すれば、正本堂の建立及びその意義について、最初に言及(げんきゅう)したのは宗門側ではなく、むしろ戦後の広布の展開の上において、学会側が強い意思により、建立を推進したものであることが文献的に明らかである。
すなわち、当初学会側において、奉安殿建立を第一歩とする「戒壇建立」路線が志されたことを想起すべきであろう。
昭和四十年二月十六日の、第一回正本堂建設委員会における日達上人の御指南は、このような日昇上人・日淳上人時代以来の学会の方針を、大慈悲により包容されたものであることが明らかである。
したがって正本堂を御遺命の戒壇なりと最初に指南されたのは日達上人であり、正本堂建立に関する一切の責任が、日達上人にあられたかのごとき、学会側の主張は、単に表面的な姿を述べたものに過ぎない。
当時の圧倒的な勢力を背景に、宗内に正本堂即御遺命の戒壇、との風潮を作り出したのは、池田氏・創価学会であることは、御本人が一番よく知っておられよう。
〔両上人の御指南について〕
御先師日達上人、御当代日顕上人の、戒壇に関する御真意は、『三大秘法抄』『一期弘法抄』に示される御遺命の戒壇建立は、未来の目標として拝すべきであるとのお立場であり、それが両上人のご信念であられることは、『訓諭』『御指南』等に明らかである。
先師日達上人は、このようなお立場を基本とされながらも、池田氏並びに創価学会を中心とする全信徒の、広宣流布に対する大情熱を激励されるために、その戒壇建立に関する教義解釈については、厳粛・寛容自在の御指南をなされたのであり、これは御仏意による尊い御教導と拝さなければならない。
しかして今日、日顕上人は、同様に御仏意の上から、今日の広宣流布の実情に即して、創価学会の慢心のもととなっている独善的体質を矯正(きょうせい)されるため、厳愛の御指南をされているのである。
先にも述べたが、本宗の信心においては、その時々の御法主上人を師匠と仰ぐべきことが基本である。自らをお褒(ほ)め下さった猊下に対して、感謝し奉ることは当然であろう。
しかしながら、御法主から賜(たまわ)る、称賛・叱責両様の御指南に対しては、いずれにしても信伏随従し奉ることが信心の基本である。本来であれば、かりに創価学会にとって厳しい御指南を賜ったとしても、これを信心で受け止めることが当然なのである。そのような、本宗の信徒であれば誰でも弁(わきま)えるべきことを忘れてしまう程、創価学会の驕(おご)り、昂(たかぶ)りはすでに常軌を逸してしまっていると言わねばならない。ましてや今回のごとく、御法主上人に対し奉り、あらんかぎりの悪口・誹謗の刃(やいば)を向けることは、「悪鬼入其身」と言わずして何であろう。
御法主上人に誹謗の限りを尽くす、悪逆の破門団体と何処が違うというのか、よくよく自問自答してみるべきであろう。
宗祖大聖人は戒壇建立の時に有徳王・覚徳比丘の姿が現出することを、『三大秘法抄』に、
「有徳王覚徳比丘の其の乃往を末法濁悪の未来に移さん時」
と御教示されている。学会首脳部は、この有徳王が覚徳比丘を外道の攻撃から護るために、全身に矢を浴びて戦ったことを想起すべきである。末法の三宝を護持あられるところの、僧宝たる御法主上人に攻撃の矢を向けるような有徳王があろう筈はない。
今日の「発願主」の姿からみても、正本堂が直ちに『三大秘法抄』の戒壇と断定できるものではないと言うべきであろう。
しかし、正本堂は三大秘法惣在の大御本尊まします、本門事の戒壇としての大殿堂であり、この建立に寄与した八百万信徒の功徳は、いささかも変化なく大御本尊の御嘉賞(かしょう)を賜り、未来永劫に称(たた)えられるべきである。
戒壇に関する猊下の深甚(しんじん)なる御指南に対し、「欺(あざむ)く」などということが、如何に無慚(むざん)なことかに気づかねばならないのである。御法主上人の御教導は常に本宗僧俗一同を正しく導くためになされるのであり、特に今回の正本堂に関する日達上人・日顕上人の御指南も同様の意義をもつのである。これをあえて宗門と八百万信徒を分離対立させて、あたかも御法主上人が「信徒を欺いた」かのような非難をすることは、無道心極まりないものと言わねばならない。
〔問難に対する破折〕
ここで以上の経過を踏まえて、問難の破折をしたいと思う。
学会側は、「宗門の正本堂に関する発言例」と題し、池田氏よりも早い時期の僧侶の発言として二十五例をあげ、それをもって、池田氏の昭和四十三年の着工大法要における発言を正当なものと主張するのであるが、たとえ池田氏発言の以前に僧侶の発言例があったとしても、御遺命の戒壇建立が学会の奉安殿建立時以来の方針であったことは先にのべた通りである。
このたび日顕上人は、どちらが先に言いだしたかという時期的な責任論ではなく、正本堂建設の主体的責任者たる建立発願主の立場において、大聖人の仏法の本義に照らし、その発言の誤りを、責任をもって反省されるよう仰せられているのである。池田氏はこの日顕上人の御指南を虚心坦懐(きょしんたんかい)に拝信し、深く反省すべきであろう。
次に学会側は、「正本堂の意義に関する正しい経過史」と題して、正本堂の意義づけは、日達上人の第一回建設委員会の御指南が根本であり、その御指南に基づいて作成されたところの『御供養趣意書』も日達上人のお考えであるとするが、その第一回建設委員会の御指南とは、『一期弘法抄』の「本門寺戒壇建立」の文を挙げられた後に、
①御在世においては大御本尊は本堂に御安置されており、故に今日においても大御本尊は戒壇堂ではなく正本堂に御安置することが正しい。
②正本堂とは言っても未だ謗法が多いため、広宣流布の時まで蔵の形とする。
との趣旨の御説法をなされたものである。
しかるに、この日達上人の御指南に基づいて作成されたとする『御供養趣意書』には、「かねてより、正本堂建立は、実質的な戒壇建立であり、広宣流布の達成であるとうけたまわっていたことが、ここに明らかとなったのであります」
との文がある。この文中の「広宣流布達成」の語は、日達上人の御指南に相違していると言わねばならない。なぜなら、御指南には、「正本堂といっても未だ謗法が多いため、広宣流布の時まで蔵の形云云」と仰せられ、正本堂建立が直ちに広宣流布達成を意味しないことを御指南されているのである。
それに対し、この『御供養趣意書』は、正本堂建立を直ちに広宣流布達成と称し、あたかも日達上人が、正本堂建立の時が直ちに広宣流布の達成である、と常々仰せられていたかの如く思わせる文面となっている。しかるに、日達上人の御真意がそこにはあられないことは、先の二・一六の『御指南』からも、また昭和四十七年の『訓諭』からも拝せられるのであって、その御指南は終始一貫されているのである。
故にこの『御供養趣意書』は、宗門の承認があったことも事実であるが、昭和三十年代以来の戒壇建立路線にのっとり、まさしく創価学会が主導した内容であったことは否めない。
またこの『御供養趣意書』の中の、
「御遺命の戒壇建立・広宣流布の達成」
等の文言を日達上人が了承されたとしても、正本堂に関する御本意は、昭和四十五年の御指南、昭和四十七年の『訓諭』にあられると拝すべきであり、日顕上人は日達上人の御本意を深く鑑(かんが)みられ、内省の意を込めて、今回の『訓諭』に関する補足的御指南をなされたのである。
また学会では、正本堂の御供養に関する『御供養趣意書』『訓諭』『院達』等の意義を後になって変更することは、御供養に参加した信徒を欺くものであり、社会的、道義的責任は免れないという。
しかし日顕上人は今回の『御指南』において、
「宗祖大聖人の御遺命の戒壇の重要性を考えるとき、本当の戒壇の正義に立ち還ることが、仏子としてもっとも大切であると思うからです」
と率直に御胸中を開陳(かいちん)されている。
この日顕上人の御指南は、一切衆生の成仏を願い、過去の一切の経緯(いきさつ)を総括し、戒壇の本義を率直に示されたものである。これに対し日達上人・日顕上人の御指南を証文として持ち出し、社会的道義的な責任等を云々することは、信仰を失い、世法に偏した言動と言わねばならない。
またさらには、現今の社会に於ける本宗僧俗の状態を見ても、一体何処に広宣流布達成の姿があるといえようか。結局は『御供養趣意書』の「正本堂建立は広宣流布達成」の言が誤りであったことを、道理文証よりも現証によって示しているのが現実の姿であることを知り、深く反省して、一日も早く僧俗異体同心して広宣流布に向かうべきなのである。
次に学会側は「突出していない四十三年会長発言」として、昭和四十三年の池田氏の「正本堂=三秘抄戒壇」発言につき、正本堂の意義の完結は未来のこととして述べた証拠として、前年の発願式における『発誓願文』を、着工大法要の前日の聖教新聞に、再度掲載していることを挙げている。しかし同願文が、たとえストレートに三大秘法の完結との表現をしていなくても、何故そのことが翌日の「完結発言」を弱めていると言えるのであろうか。むしろ翌日に「完結発言」をしたということは、逆に前日の『発誓願文』も完結の意味で解釈していることとなるではないか。
池田氏の着工大法要の発言をこのまま放置すれば、本宗の歴史の上で、それが戒壇に関する正式見解となる恐れがある。そこに今回、御法主上人が時を感じて御指南された理由があると拝さなければならないのである。
当時の宗門僧侶の正本堂に関する発言だけをみると、昭和四十三年の会長発言が特に突出したものではないように思えるし、また池田会長が正本堂を『三大秘法抄』の戒壇と確定したのでもないように見える。しかし、昭和三十年代からの学会の戒壇建立の方針を検証するとき、事の真相は学会側の強い願望と働きかけにより、宗内に広宣流布達成、戒壇建立の世論が熟成されたことが明らかである。それらの中で、一連の僧侶の発言が起こったのちに、正本堂建立の発願者という責任ある立場の身として、公けの席でその意義を断定したのが、着工大法要の挨拶だったのである。
このような断定発言は、池田氏及び学会の自己中心的な体質を、如実(にょじつ)に示すものであり、まさしく御法主上人が指摘なされるように、「慢心」をその根底においた仏法軽視の発言であったということが、爾後(じご)二十数年を経て、今日明らかになったものといわねばならない。
そして本段の最後に、「『ご回答』への『お伺い』」として、次のような質問を設けている。これまでの考証で論じたものもあるので、概括的に回答する。
(イ)「本文で見てきた通り、昭和四十三年十月以前に、三大秘法抄、一期弘法抄の文を挙げて正本堂が御遺命の戒壇の建立といった、日顕猊下の言われるところの〝ズバリ〟の発言をした僧侶が多数おられますが、日顕猊下はこれらの発言についてどのように思われますか」
この件に関しては、たしかに昭和四十二年前後に宗門僧侶の発言があったが、しかし、そのはるか以前から、池田氏・創価学会は正本堂建立を推進したのであり、宗内にその意義づけが徹底されていった事実を踏まえて判断しなければ、僧侶発言の意味を正しく認識することはできないであろう。
宗門僧侶の発言は、戦後の未曾有の広宣流布の進展と、壮大なる規模の正本堂建立を目の当たりにして、まさしく御遺命達成の近いことを確信して述べた讃歎の言葉であり、その責任を云々されるべき筋合いではないのである。ただし今回、日顕上人にはそれらの僧侶の発言を代表し、大聖人の仏法の深義に照らして、適当な発言でなかったと深く反省されたのである。その御心こそ尊く拝すべきであろう。
(ロ)「そのような多くの発言をみると、昭和四十三年の会長発言だけが特に突出したいわゆる〝ズバリ〟発言ではないし、ましてや池田会長が正本堂を三大秘法抄の戒壇と確定したということにはならないと存じますが、いかがでしょうか」
との質問については、池田氏・創価学会は奉安殿建立時から、創価学会が戒壇を建立する、国立戒壇建立こそ創価学会の唯一の使命、と考えていたことが明らかであり、さらに正本堂を御遺命の戒壇としたいとの意思をもって、建設を準備し実行したことが資料により明白なのである。池田氏の発言は、このような正本堂建立発願主の立場における「断定発言」であって、その特殊性が考慮されねばならない。
(ハ)「日達上人の昭和四十七年の『訓諭』で、昭和四十三年十月の会長発言が誤りであったことになり、訂正し、反省しなければならなくなったとするならば、日達上人や日顕猊下は、池田名誉会長に対し、そのような要請をなさったことがありますか。具体的にお示しいただきたいと存じます」
この質問に関しては、まず「要請」という言葉であるが、師匠が弟子にするのは指南であって要請ではない。そのような仏法の基本すら失っているところに現在の学会の増上慢そのものの体質があるといえよう。
御法主の信徒に対する教導は、甚深の御境界、すなわち御仏意によってなされるものであり、したがってその指南の時期を決められるのも御仏意によるのである。開創七百一年を迎えた今日の、日顕上人の御指南こそ、その時期が到来した故になされたものと拝するのが正しい信心の姿勢であろう。
(ニ)「結論的にいうならば、昭和四十三年十月の会長発言はその前後の宗内の正本堂に関する発言等や、それ以後二十数年間に及ぶ経過に照らして、日顕猊下が言われるような誤った発言であると考えることは出来ませんし、まして、それが池田名誉会長の慢心のあらわれであるとして非難するなどということは、到底できないと存じますが、いかがでしょうか」
との文においては、学会側は、池田氏の断定発言と、その前後の僧俗の発言とを同列に論じて、池田氏に責任がない論拠としている。しかし池田氏の発言と、他の僧俗の発言とには、正本堂建立発願者としての言と、賛同的発言との厳然たる相違がある。まして池田氏の「断定発言」は、奉安殿建立以来の、創価学会の戒壇建立路線にのっとっているのであるから、戒壇建立を主体的に推進した経過の上の発言として、他の僧俗の発言と同列に論ずべきでないことはいうまでもない。
今日の問題に付随して、御法主上人には僧侶を代表して、自らの過去の行き過ぎた発言を反省遊ばされたのである。大聖人の仏法の深義に照らして、〝誤りである〟との御法主上人猊下の裁定を賜ったのであるから、責任ある立場の身として、池田氏も、慢心の発言を反省すべきことは当然なのである。
また池田氏の「断定発言」以来、二十数年が経過し、その間何の異議もなかったとの言は、時期的な面からはたしかにその通りである。しかし、宗祖の門下に対する御化導には、時機を鑑(かんが)みられての慎重な御配慮があられるところであり、御法主上人が信徒を教導されるのも御仏意によるものなのである。
池田氏の「断定発言」から、今回の御指南までの時間経過が長期であったことをもって、池田氏の発言を正当化する根拠とはならないことは言うまでもない。このことを日顕上人は三月九日付『御指南』において、「全ては、時の経過によって風化させてしまえばよいと考え、他人の真摯な反省も茶番劇と嗤う無慚さを憐れむものであります」と仰せられている。
創価学会が戦後草創の頃より懐いた戒壇建立の素志は、信徒として純粋なものであったと信ずる。しかし、自らの手で建立する正本堂について、御遺命の戒壇の「意義」を含むもの、との日達上人の御指南を超えて、信徒の立場において、『三大秘法抄』の戒壇そのものであると断定することは、「慢心」以外の何物でもない。
いま日顕上人は、どちらが先に言ったなどという責任のなすりあいをすることなく、その発言そのものが重大な誤りであったが故に、その「慢心」の発言を反省するよう仰せられたのである。
(ホ)「猊下は一月六日、十日のご説法では、当時の宗内僧侶の発言についても一応、配慮されていますが、それを当時の宗内の〝空気〟のせいにしようとされ、特に十日のご説法ではそうした空気を作った『一番の元』が、昭和四十三年十月の会長発言であるとされています。それが間違いと分かり『大日蓮』では『一番の元』を『(その)ような経過の中で大事なこと(は)』と言い換えられましたが、このように変更しても間違いは全く直っていないと思いますが、いかがでしょうか」
との質問であるが、結論から言えば、猊下の御指南は少しも間違っていない。猊下の指摘された、当時の宗内の空気こそ、池田氏・創価学会が主導し醸成(じょうせい)したものであり、池田氏の昭和四十三年の「断定発言」は、その御遺命戒壇建立との風潮が蔓延する中でなされた、諸々の「断定発言」の締めくくりともいえるものであった。猊下が「一番の元」を「そのような経過の中で大事なこと」と訂正されたのは、「一番の元」の語句が、単に時期的に、「一番始め」との意味に誤って理解される恐れがあり、それは昭和四十三年以前の正本堂建立に関する様々な事実経過の上から誤解を招く恐れがある故である。しかし宗門を、御遺命戒壇建立の方向へ誘導した「一番の元の人」が池田氏であることは事実であり、日顕上人の御指南の本来の意味は少しも損なわれていないのである。
(ヘ)「どのように考えても、昭和四十三年の会長発言が決定的であるということを前提にされた、一月六日、十日のご説法は成り立ちません。したがって、是非、正本堂に関する部分のご説法を全面的に撤回されるよう再度求めるものでありますが、いかがでしょうか」
前に詳述したごとく、昭和四十三年の池田氏の発言は、日達上人の御指南から一歩突出したところの、所謂「断定発言」であることは明らかである。またこの「断定発言」は、創価学会による、戦後の戒壇建立路線の延長線上になされたものであり、しかも正本堂着工大法要という、公けの儀式の中での言葉であって、その「断定」の意味の重大性は言うまでもなく、決定的といっても差し支えないものである。
今回、日顕上人はこの池田氏の発言が、宗祖大聖人の仏法の深義を信徒の立場において規定しようとした、「慢心」の表われであったことを御指南されたのである。本来、甚深なる宗祖の法義に関する裁定は御法主上人の権能であられる。その裁定にのっとられた御指南に対し、「撤回するように」などということは、まさしく悩乱の暴言である。ただちに懺悔し、恭順の心をもって拝信すべきであろう。
以上のように、学会は、正本堂に関する池田氏の発言には、何ら問題がないかのごとく、傲(おご)り高ぶった抗議をしてきたが、資料によって、池田氏・創価学会が、正本堂建立に関して、頑(かたく)なに御遺命戒壇に固執した事実経過は明白である。
この固執が自己中心的な体質と相まって展開されたところに、「断定発言」という「慢心」が生じたものであろう。したがって、池田氏の昭和四十三年十月十二日の、正本堂着工大法要における発言こそ、氏の「慢心」を示す典型と指摘された、御法主上人の御指南は、全く適正なものであったことを再度確認して本段の回答とする。
※「(二) 広布達成の意識と慢心」へつづく