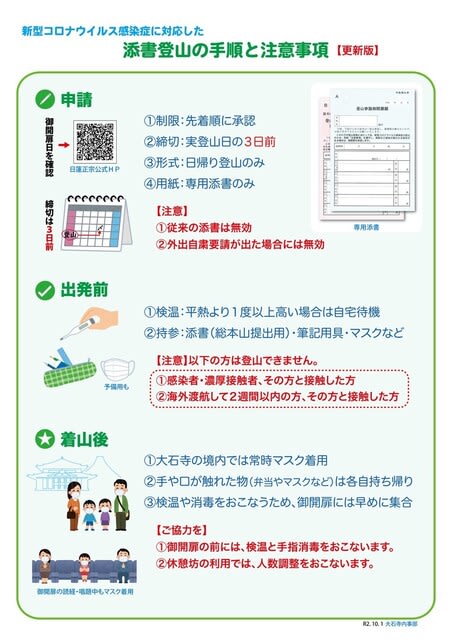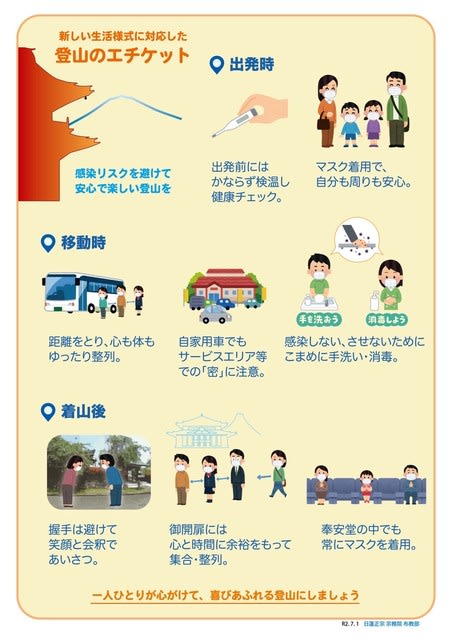正林寺御住職指導(R5.2月 第229号)
御法主日如上人猊下から「令和5(2023)年1月度 広布唱題会の砌」に、『開目抄』のお言葉を賜りました。『開目抄』について研鑚いたしましょう。
宗祖日蓮大聖人御聖誕八百年記念に出版された「日蓮大聖人略伝」には、
「『開目抄』は、文永九(1272)年の二月、塚原三昧堂において著された。この書は、大聖人こそが末法の法華経の行者、すなわち主師親の三徳兼備の御本仏であることを明かされた〔人本尊開顕の書〕である」(大聖人略伝36)
と、佐渡期の御著作の項に明記されております。『開目抄』は日蓮大聖人が佐渡に配流された時、塚原問答の翌月にお認めあそばされました。末法の人々へ「目を開きなさい」(信行要文199)と御指南である御書であります。御書五大部の一書であり、『開目抄』は、当宗で人本尊開顕の書と言われ、『観心本尊抄』は、法本尊開顕の書と言われております。
日蓮大聖人は『種々御振舞御書』に、
「去年の十一月より勘へたる開目抄と申す文二巻造りたり。頚切らるヽならば日蓮が不思議とヾ(留)めんと思ひて勘へたり。此の文の心は日蓮によりて日本国の有無はあるべし」(御書1065)
と御指南であります。
『日蓮大聖人正伝』には、
「文永八(1271)年十一月から深く勘案された不思議の境界、すなわち頸の座における久遠元初自受用報身として発迹顕本された仏の生命を、紙も乏しい極寒の塚原三昧堂で認められ、竜口に供奉した四条金吾を通じて門下一般に与えられた『開目抄』は、まさに日蓮が〔かたみ(形見)〕(御書563)であった。また当抄は、末法万年の民衆を救済し成仏せしめる永劫不変の根本的指南書であり、〔未来日本国、当世をうつし給ふ明鏡〕(御書563)であると、大聖人御自身仰せられている。」(改訂版232)
と記述されています。
『日蓮大聖人のご生涯と正法伝持』には、
「『開目抄』と『観心本尊抄』
日蓮大聖人は、佐渡配流中に50篇を越える御書を著された。その中でも『開目抄』と『観心本尊抄』はご一代を代表する最重要書である。」(絵と写真で見る46)
と、写本と同時に記載されています。
総本山第二十六世日寛上人は『開目抄文段』をお認めあそばされ、『開目抄』と題する所以について、盲目を開く意味であると御教示であります。その意味は、真実の三徳兼備の久遠元初の御本仏を知らない一切衆生の盲目を開かせるために『開目抄』と名づけられました。(御書文段54※取意)
日蓮大聖人は『開目抄』に、
「夫一切衆生の尊敬すべき者三つあり。所謂、主・師・親これなり」(御書523)
と、「主・師・親」である三徳の主徳・師徳・親徳を一切衆生は尊敬すべきことを仰せであります。また大聖人は、
「日蓮は日本国の諸人に主師父母なり」(御書577)
と種脱相対判から三徳兼備の御本仏を御自ら御指南であります。
ゆえに、日寛上人は『文底秘沈抄』に、
「人の本尊とは、即ち是れ久遠元初の自受用報身の再誕、末法下種の主師親、本因妙の教主大慈大悲の南無日蓮大聖人是れなり」(六巻抄48)
と御指南あそばされております。
『開目抄』には非常に大事な教え「文底秘沈」について説かれております。日寛上人は「当流深秘の大事なり」(六巻抄4)と御教示であります。
大聖人は、
「一念三千の法門は但法華経の本門寿量品の文の底にしづめたり」(御書526)
と仰せであり、釈尊が説かれた法華経には文上の法華経と文底の法華経があることを御指南であります。末法は釈尊が説かれた文上の法華経では白法隠没となり利益は無く、法華経の行者・外用上行菩薩で御内証は久遠元初の御本仏・日蓮大聖人が説かれる文底の法華経・三大秘法の南無妙法蓮華経により利益があることを教えられております。この文底の法華経・三大秘法の南無妙法蓮華経に目を開いて見るように『開目抄』をお書きになりました。
大聖人は同抄に、
「我並びに我が弟子、諸難ありとも疑ふ心なくば、自然に仏界にいたるべし」(御書574)
と仰せのように、諸難ありとも疑うことなく目を開いて三大秘法の南無妙法蓮華経を信行するところ自然と絶対的幸福の仏界へと境界を開くことができます。つまり、「正を立てて国を安んずる」実現につながります。
では、目(肉眼)を開いて自然と絶対的幸福の仏界へと境界を開くため、『開目抄』に御指南である御教えを見てまいりましょう。
はじめに、
「仏法を学せん人、知恩報恩なかるべしや。仏弟子は必ず四恩をしって知恩報恩をいたすべし」(御書530)
信行学の「学」について、教学を学ぶには必ず三宝の恩を重んじた恩を知り恩を報じることを心肝に染めた姿勢が根底になければなりません。知恩報恩により自然と絶対的幸福の仏界へと境界を開くことができるとの教えです。
二番目に、
「本門にいたりて、始成正覚をやぶれば、四教の果をやぶる。四教の果をやぶれば、四教の因やぶれぬ。爾前(にぜん)迹門の十界の因果を打ちやぶって、本門十界の因果をとき顕はす。此即ち本因本果の法門なり。九界も無始の仏界に具し、仏界も無始の九界に備はりて、真の十界互具・百界千如・一念三千なるべし」(御書536)
法華経の本門(久遠実成)と迹門(始成正覚)の違い本迹相対について御指南であります。『治病大小権実違目』に「本迹の相違は水火・天地の違目(いもく)なり」(御書1236)と。本門と迹門に違いがあることを知ることで、自然と絶対的幸福の仏界へと境界を開くことができるとの教えです。
三番目に、
「諸宗の学者等、近くは自宗に迷ひ、遠くは法華経の寿量品をしらず」(御書536)
「十九出家三十成道」(御書91)である始成正覚の釈尊を尊崇するあまり「師弟の遠近」(御書839)に迷い、仏の本地身が説かれる法華経寿量品の深意を知らない仏教学者が多いことを御指南であります。まさに「十方の土」と「爪上の土」の違いが末法当初(数百年)には歴然とあります。違いを理解することで、自然と絶対的幸福の仏界へと境界を開くことができるとの教えです。
四番目に、
「世間の罪に依って悪道に堕つる者は爪上の土、仏法によって悪道に堕つる者は十方の土。俗より僧、女より尼多く悪道に堕つべし」(御書538)
御本仏大聖人の御境界から達観あそばされた、世間的罪と仏法的な罪により悪道に堕す衆生の様子を御指南であります。達観された様子を知ることにより、仏界へと境界を開くことができるとの教えです。
五番目に、
「一言も申し出だすならば父母・兄弟・師匠に国主の王難必ず来たるべし。いわずば慈悲なきににたりと思惟(しゆい)するに、法華経・涅槃(ねはん)経等に此の二辺を合はせ見るに、いわずば今生は事なくとも、後生は必ず無間地獄に堕つべし。いうならば三障四魔必ず競(きそ)ひ起こるべしとし(知)りぬ」(御書538)
折伏にあたり、実践する場合と実践しない場合についての現実と果報について御指南であります。着実に実践することにより、仏界へと境界を開くことができるとの教えです。
六番目に
「少々の難はかずしらず、大事の難四度なり。二度はしばらくをく、王難すでに二度にをよぶ」(御書539)
ただひとり日蓮大聖人が法華経の行者として色読あそばされた事を知り、昭和時代の高度成長期に突如出現した第二の法華経の行者は有名無実であり存在しないことを理解することで、仏界へと境界を開くことができるとの教えです。
七番目に、
「日蓮が法華経の智解は天台伝教には千万が一分も及ぶ事なけれども、難を忍び慈悲のすぐれたる事はをそれをもいだきぬべし」(御書540)
「三国四師」(御書679)について、像法時代の正師と末法時代の正師の違いについて知ることにより、境界を開くことができるとの教えです。
八番目に、
「当世、法華の三類の強敵なくば誰か仏説を信受せん。日蓮なくば誰をか法華経の行者として仏語をたすけん」(御書541)
「法華経の行者あらば必ず三類の怨敵あるべし」(御書570)
当世末法において、法華経の行者として文証理証現証の三証から三類の強敵を現実に顕されたのは日蓮大聖人のみであり、大聖人の所作なくして法華経を語ることはできないと知ることで、境界を開くことができるとの教えです。
九番目に、
「諸の声聞、法華をはなれさせ給ひなば、魚の水をはなれ、猿の木をはなれ、小児の乳をはなれ、民の王をはなれたるがごとし。いかでか法華経の行者をすて給ふべき」(御書543)
御法門的に難解な法門であるため譬喩をもちいられて、法華経から離れることがなければ、境界を開くことができるとの教えです。
十番目に、
「法華経方便品の略開三顕一の時、仏略して一念三千心中の本懐を宣べ給ふ」(御書547)
まさに、法華経が真実本懐であることを迹門に略されて説かれ、法華経以外は「方便力を以てす。四十余年には未だ真実を顕さず」(法華経23)と御指南あそばされたことを知ることにより、開くことができるとの教えです。
十一番目に、
「一切経の中に此の寿量品ましまさずば、天に日月の無く、国に大王の無く、山河に珠の無く、人に神(たましい)のなからんがごとく」(御書553)
さらに法華経が真実本懐である真髄について、寿量品は「たましい」であることを知ることにより、開くことができるとの教えです。
十二番目に、
「諸宗は本尊にまどえり」(御書554)
寿量品は「たましい」であるとの理由には、三大秘法の御本尊が寿量品の文底に秘沈されており、多くの宗派は本尊に迷っていることを知ることにより、開くことができるとの教えです。
十三番目に、
「仏をさげ経を下だす。此(これ)皆、本尊に迷へり」(御書554)
具体的に諸宗の本尊に迷っている姿について御指南であり、法華経を見下し文底に秘沈された三大秘法をも下す宗派は、まさに本尊に迷う宗派であると知ることで、開くことができるとの教えです。
十四番目に、
「寿量品をしらざる諸宗の者は畜に同じ。不知恩の者なり」(御書554)
先の二番目から十三番目まで信じることのできない方は、知恩報恩ではない、不知恩の者であるとの厳しい御指南であります。
十五番目に、
「寿量品の仏をしらざる者は父統(ふとう)の邦(くに)に迷へる才能ある畜生とかけるなり」(御書554)
十四番目に続き、補足あそばされた御指南を知ることにより、開くことができるとの教えです。
十六番目に、
「法門を説き給ふとも経を手ににぎらざらんをば用(もち)ゆべからず」(御書558)
法華経の文底に秘沈された教えを下す「迷へる才能」の諸宗の学者は信用してはならないと知ることにより、開くことができるとの教えです。
十七番目に、
「法華経に云はく『已今当(いこんとう)』等云云。妙楽云はく『縦(たと)ひ経有って諸経の王と云ふとも、已今当説最為第一と云はず』等云云」(御書559)
法華経以外に王であるという経は、已今当説を理解されていないため信用してはならないと御指南であります。法華経は「法華最第一」(法華経325)三説超過です。
十八番目に、
「教の浅深をしらざれば理の浅深弁ふものなし」(御書561)
仏教はすべて釈尊が説かれた教えであるため、どれも同じとお考えになる方への大事な御指南であります。一代五十年の説教に浅い深いを弁えることにより、開くことができるとの教えです。
十九番目に、
「当世、日本国に第一に富める者は日蓮なるべし。命は法華経にたてまつる。名をば後代に留(とど)むべし」(御書562)
迷へる才能の諸宗の学者とは明らかに違う、法華経の行者について知り三大秘法の御本尊に帰命し奉ることにより、開くことができるとの教えです。
二十番目に、
「竜女が成仏、此一人にはあらず、一切の女人の成仏をあらわす。法華経已前の諸の小乗経には、女人の成仏をゆるさず。諸の大乗経には、成仏往生をゆるすやうなれども、或は改転の成仏にして、一念三千の成仏にあらざれば、有名無実の成仏往生なり。挙一例諸(こいちれいしょ)と申して、竜女が成仏は、末代の女人の成仏往生の道をふみあけたるなるべし。儒家の孝養は今生にかぎる。未来の父母を扶(たす)けざれば、外家の聖賢は有名無実なり。外道は過未をしれども父母を扶くる道なし。仏道こそ父母の後世を扶くれば聖賢の名はあるべけれ。しかれども法華経已前等の大小乗の経宗は、自身の得道猶(なお)かなひがたし。何に況んや父母をや。但文のみあって義なし。今、法華経の時こそ、女人成仏の時、悲母の成仏も顕はれ、達多の悪人成仏の時、慈父の成仏も顕はるれ。此の経は内典の孝経なり。二箇のいさ(諫)め了んぬ。」(御書563)
法華経は、唯一、女人成仏と悪人成仏が説かれる教えであります。爾前諸経は許されません。
二十一番目に、
「日蓮といゐし者は、去年九月十二日子丑(ねうし)の時に頚(くび)はねられぬ。此は魂魄(こんぱく)佐土の国にいたりて、返る年の二月雪中にしるして、有縁の弟子へをくれば、をそ(怖)ろしくてをそ(恐怖)ろしからず。み(見)ん人、いかにを(怖)ぢぬらむ」(御書563)
発迹顕本あそばされた大事な御指南であります。
二十二番目に、
「順次生(じゅんじしょう)に必ず地獄に堕つべき者は、重罪を造るとも現罰なし。一闡提人これなり」(御書571)
「上品の一闡提人になりぬれば、順次生に必ず無間獄に堕つべきゆへに現罰なし」(御書571)
迷へる才能を有する諸宗の学者により三類と化した正法誹謗者についての未来世を御指南であります。
二十三番目に、
「善に付け悪につけ法華経をすつるは地獄の業なるべし」(御書572)
「始めから終わりまで信心を」心得ていくための大切な御指南になります。
二十四番目に、
「過去の宿習としらむ。答へて云はく、銅鏡は色形を顕はす。秦王験偽の鏡は現在の罪を顕はす。仏法の鏡は過去の業因を現ず。般泥洹経に云はく『善男子、過去に曾て、無量の諸罪、種々の悪業を作るに是の諸の罪報は、或は軽易せられ、或は形状醜陋、衣服足らず、飲食麁疎、財を求るに利あらず、貧賤の家、邪見の家に生まれ、或は王難に遭ひ、及び余の種々の人間の苦報あらん。現世に軽く受くるは、斯れ護法の功徳力に由るが故なり。』」(御書572)
現在、思い当たる境涯であれば、過去世の業因によります。御本尊に祈り罪障消滅を真剣に願いましょう。「諸の罪報は」目を開くことなく謗法与同罪を侵す人、正法誹謗者の順次生(未来世)の「人間の苦報」でもあります。
ゆえに「過去の因を知らんと欲せば、其の現在の果を見よ。未来の果を知らんと欲せば、其の現在の因を見よ」(御書571)と。
二十五番目に、
「『三障四魔紛然として競ひ起こる』等云云。我無始よりこのかた悪王と生まれて、法華経の行者の衣食田畠等を奪ひとりせしこと、かずしらず。当世、日本国の諸人の、法華経の山寺をたうすがごとし。又法華経の行者の首を刎ねること其の数をしらず。此等の重罪はたせるもあり、いまだはたさゞるもあるらん。果たすも余残いまだつきず。生死を離るゝ時は、必ず此の重罪をけしはてゝ出離すべし。功徳は浅軽なり。此等の罪は深重なり。権経を行ぜしには、此の重罪いまだをこらず。鉄を熱にいたうきたわざればきず隠れてみえず。度々せむればきずあらわる。麻子をしぼるにつよくせめざれば油少なきがごとし。今、日蓮、強盛に国土の謗法を責むれば、此の大難の来たるは過去の重罪の今生の護法に招き出だせるなるべし」(御書573)
護法の功徳力についての御指南であり、「功徳は浅軽なり(中略)罪は深重なり」との御指南を肝に銘じるべきでしょう。
二十六番目に、
「天の加護なき事を疑はざれ。現世の安穏ならざる事をなげかざれ。我が弟子に朝夕教へしかども、疑ひををこして皆すてけん。つたなき者のならひは、約束せし事を、まことの時はわするゝなるべし」(御書574)
「憶持不忘」(御書775)についての御指南であります。
二十七番目に、
「夫、摂受・折伏と申す法門は、水火のごとし。火は水をいとう、水は火をにくむ。摂受の者は折伏をわらう、折伏の者は摂受をかなしむ。無智・悪人の国土に充満の時は摂受を前とす、安楽行品のごとし。邪智・謗法の者の多き時は折伏を前とす、常不軽品のごとし」(御書575)
御法主日如上人猊下は、
「まさしく今、末法は『邪智・謗法の者の多き時』にして、この時は摂受ではなく、折伏をもってすることが肝要であるとの御教示であります。この御指南を改めて拝し、講中一同、決意も新たに異体同心して一意専心、折伏を行じていくことが肝要であります。」(大日蓮 第524号 R5.2)
と御指南あそばされております。本年の「折伏躍動の年」では銘記すべき非常に大事な『開目抄』の一説であります。
二十八番目に、
「末法に摂受・折伏あるべし。所謂、悪国・破法の両国あるべきゆへなり。日本国の当世は悪国か、破法の国かとしるべし」(御書576)
広宣流布を目指す過程で、一往付文の辺では日本と拝し、再往元意の辺では世界広布を見据えた御指南であると拝します。時として「法は必ず国をかゞ(鑑)みて弘むべし。彼の国によ(良)かりし法なれば必ず此の国によかるべしとは思ふべからず」(御書324)を心得ていく姿勢が世界広布には必要であります。
二十九番目に、
「設ひ山林にまじわって、一念三千の観をこらすとも、空閑にして三密の油をこぼさずとも、時機をしらず、摂折の二門を弁へずば、いかでか生死を離るべき」(御書576)
「摂折の二門」について第六十五世日淳上人は、
「仏法に於ては弘経の方軌に摂受と折伏との二門があって摂受は摂引容受で、仮りに誤ってゐるものでも之れを許容して寧ろ良い面を見て導いてゆくといふ方法であり折伏は破折屈伏せしめるの意で誤りを糺明し悪を除くといふやり方であります。この二つの化導の行き方は摂折の二門として立てられてをりますが、摂受は法華経の安楽行品等が此の方軌であり、折伏は本門の常不軽品涅槃経等に説かれるところであります。此の二門が立てられる理由は時、国、教の流布される順序次第と人々の機根等の相違によって教益を生ぜしめる上に、その化導の方法と適切ならしめる必要があるためであります。そこで此等の上から末法今の時を判断致しますと時は末法悪世であり人は悪機鈍根であります。此れ等の衆生に対しては折伏を以て臨まねばならない。此れが日蓮大聖人の判決であります。」(淳全910)
と御指南あそばされております。
三十番目に、
「愚人にほめられたるは第一のはぢなり」(御書577)
愚人に誉められて名聞名利を貪るような心根では、一番の恥であるとの御指南であります。「名聞名利は今生(こんじょう)のかざり」(御書296)であり、「法華経の功徳はほむれば弥功徳まさる」(御書969)ことを心がけましょう。
三十一番目に、
「仏法は時によるべし。日蓮が流罪は今生の小苦なれば、なげかしからず。後生には大楽をうくべければ大いに悦ばし」(御書578)
三時弘教の次第を知り、転重軽受と自受法楽の境界を成就できることを御指南であります。
以上、『開目抄』の要文を1ヶ月間(31日)、拝読させていただけるように、はじめから三十一番まで心肝に染めて、自然と絶対的幸福の仏界へと境界を開くことができますことを心から念願いたします。さらに、下種折伏において「一闡提も未来に眼の開くべき縁を結ぶ事、是偏に妙の一字の徳なり」(御書357)との御指南を実践され、目を開いて三大秘法の御本尊への信行に精進されて勧めることが大切であります。そして、時の御法主上人猊下に信伏随従申し上げる信心です。
最後に、伝統の二月といわれる当宗の理由にはさらに、日蓮大聖人を御本仏と拝し奉る人本尊開顕の書『開目抄』の御著述も存すると拝信申し上げます。同時にインド応誕の釈尊入滅(2/15 ※御書733)と大聖人(2/16)の御誕生が重なる月であり、釈尊の正像時代の御化導から末法の御本仏大聖人の御化導へと移行される大事な月が、「富士の立義」伝統の二月との意義も存すると拝します。
宗祖日蓮大聖人『持妙法華問答抄』に曰く、
「只(ただ) 須(すべから)く汝仏にならんと思はゞ、慢のはたほこ(幢)をたをし、忿(いか)りの杖をすてゝ偏(ひとえ)に一乗に帰すべし。名聞名利は今生(こんじょう)のかざり、我慢(がまん)偏執(へんしゅう)は後生のほだし(紲)なり。嗚呼(ああ)、恥づべし恥づべし、恐るべし恐るべし。」(御書296)