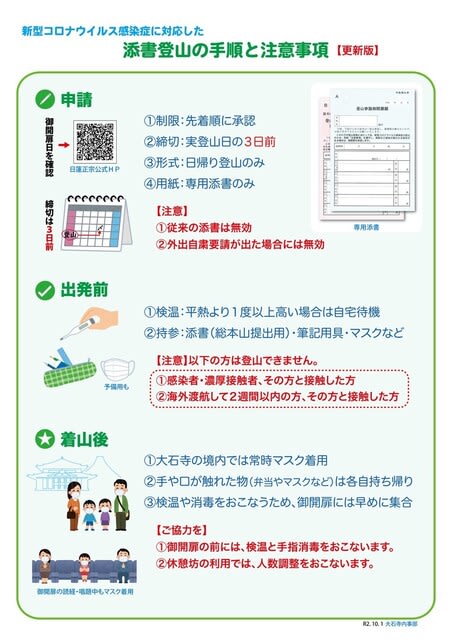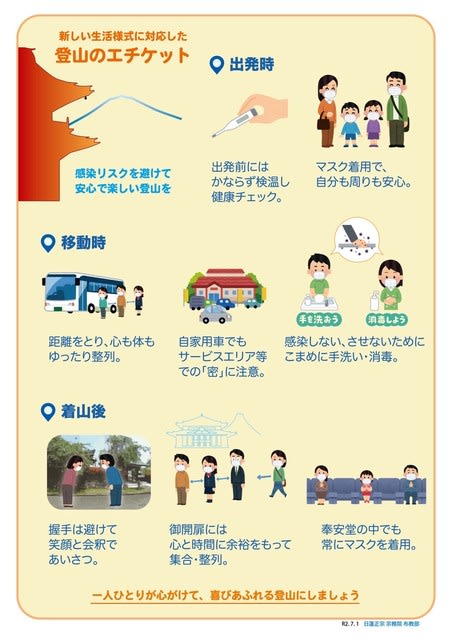正林寺御住職指導(R5.11月 第238号)
試しに、人工知能・生成AIのChatGPT(チャットジーピーティー)へ「一文一句」について、問いかけてみました。
「『一文一句』は、日本語での表現で、文章や文書を書く際に、一つの文(センテンス)ごとに意味を分けて書くスタイルを指します。つまり、文章を短い文で構成し、一つの文が一つの主題やアイデアを表現するように工夫する書き方のことです。このスタイルは、文章を簡潔で明確にし、読み手に情報を分かりやすく伝えるために用いられます。また、一文一句のスタイルは、特に新聞記事やビジネス文書などで一般的に採用されています。」(ChatGPT)
と、10秒かからず回答が返ってきました。
さらに「日蓮大聖人の一文一句についてのご見解は?」と、ChatGPTに問いかけると、
「一文一句のスタイルは、文章を簡潔で明確に表現する手法であるため、そのスタイルを用いた文書が読み手に情報を効果的に伝えるのに役立つことが多いです。しかし、宗教的なテキストや聖典の場合、文体や表現方法はその宗教や信仰体系に応じて異なります。
日蓮大聖人(日本の仏教宗派である法華宗の創設者)の著作や教義については、一文一句のスタイルが特に強調されることはありませんが、日蓮大聖人の教えは法華経(法華宗の根本経典)に基づいており、その教義や教えは法華経のテキストに含まれています。
一文一句のスタイルは、理解を助けるために文章を分かりやすくする手法であるため、法華宗の教義を説明する際にも使用されるかもしれません。ただし、日蓮大聖人の教えは、その内容や文体が法華経そのものに基づいているため、特に一文一句のスタイルを強調する必要はないかもしれません。
日蓮大聖人の教えや文献についての詳細なご見解や解釈は、宗教的な専門家や法華宗の信者によるものが適切であり、一般的な情報提供を超えた内容となります。」(ChatGPT)
との回答が早速返ってきました。
ChatGPTが「宗教的な専門家や法華宗の信者によるものが適切であり、一般的な情報提供を超えた内容となります」と返答したように、「血脈の次第 日蓮日興」(御書1675)との極理の師伝までは、立ち入ることが御法度であることをChatGPTは認識しているようです。
それでは、宗祖日蓮大聖人が説かれる宗教的な専門家、日蓮正宗での「一文一句」を拝してまいりましょう。
日蓮大聖人は『諸法実相抄』に、
「力あらば一文一句なりともかたらせ給ふべし」(御書668)
と仰せであります。下種折伏・育成活動には、心がけるべき大事な御指南であります。
「一文一句」とは、一言でも信心について話すことであります。
御法主日如上人猊下は、
「『一文一句』と仰せのように難しいことは言わなくていいのです。『あなたも、この信心をしてみませんか』でいいのです。(中略)
大聖人様の教えが正しいことをそのままお伝えしていくのです。もし相手が邪宗教を信じていたならば、それが間違いであることを指摘すればいいのです。『大聖人様の教えが正しいのですよ』と言うこと、このひとことが大事なのです。そのひとことから折伏が始まり、すべてが解決していくのです。」(大日蓮 第931号 R5.9)
と具体的に御指南であります。
「一文一句」について日蓮大聖人の御書を拝してみましょう。
①『四恩抄』に、
「法華経は一文一句なれども耳にふるゝ者は既に仏になる」(御書265)
と仰せであります。経本や常自随身の念珠、御本尊を大切にし、寺院へ参詣して一文一句なりとも聴聞することは成仏するとの意味です。爾前諸経や法華経でも文上ではない究極の御法門、聞法下種である文底下種仏法を耳に触れることです。耳根得道のため折伏や育成の時に、一文一句なりとも話す大切な御書であります。
②『女人成仏抄』に、
「経の一文一句を読み、一字一点を書く、尚出離生死証大菩提の因なり」(御書347)
と仰せであります。朝夕の勤行で一文一句読み精進することで「出離生死証大菩提」、つまり迷いの九界を離れて仏因を積むとの御指南であり、勤行唱題を推進する大事な文証となります。
③『椎地四郎殿御書』に、
「法華経の法門を一文一句なりとも人にかたらんは過去の宿縁ふかしとおぼしめすべし」(御書1555)
と仰せであります。折伏において一文一句なりとも人に語ることは、大聖人と過去の宿縁が非常に深いとの地涌の菩薩の眷属・流類であるとの有り難い御指南です。育成において折伏のやる気を奮い起こすために必要な御指南であります。
さらに同抄では、
「経を一文一句なりとも聴聞して神(たましい)にそめん人は、生死の大海を渡るべき船なるべし」(御書1555)
とも仰せであり、大聖人の御法門を聴聞して心肝に染めて忘れないことは、生まれてから死ぬまでの苦しみは必ず解決し現当二世は疑いないとの御指南と拝します。まさしく、確信を持つ人は、迷いの生死を必ず離れることのできる境界であります。
以上が、大聖人の御書に説かれる一文一句の御指南であります。
自行において、題目を唱える時の心がけ・意識について、「総本山第六十七世日顕上人猊下御教示『すべては唱題から』唱題の功徳と意義 六十一ヵ条」の一部を紹介いたします。
はじめの一文一句は、「尊厳の体に帰す」です。日顕上人は、
「我々の身体や性質は、各人共通して同じところもあるが、また各人各様で、あらゆるところが異なっている一面もある。すなわち、平等の面と差別の面である。身体や精神に色々な故障があったり、性格の違いや対人関係の問題等で、多くの人が互いに悩んでいる。これは、自己の命の奥に伏在する、限りない真実の体を見失っているからである。」(すべては唱題から九)
と仰せでありまして、解決策について、日顕上人は、
「万物の、より高い次元で共通しているのは『尊厳』の二字である。妙法は、我々の尊厳の体であり、真実の体である。故に、妙法を持ち唱えることは、この尊厳の体に帰するのである。」(すべては唱題から9)
と、御本尊に題目を唱えるところに「尊厳の体」との一文一句、つまり仏性が開かれていくとの御教えであり、これが「尊厳の体に帰す」との一文一句であります。
次に「身口意三業の功徳成就」です。日顕上人は、
「愚かで、文章も読めないような人が、南無妙法蓮華経を唱えて利益があるのか、という疑問を抱く人もあろうが、利益は必ず存するのである。唱題により、我々の身と口と意のうち、まず口業の功徳を成就する。これにより、仏の種子がおのずから胸に収まり、身業と意業にも次第に善の功徳が積まれ、やがて将来に仏道を成就する人となる。」(すべては唱題から15)
と仰せでありまして、貴賎上下を選ばず、口で題目を唱える人は、過去遠々劫の罪障を消滅させながら、身と意へ月々日々に善の功徳が積まれて必ず絶対的幸福をいただくとの御教示です。まさに「身口意三業の功徳成就」不軽菩薩の三力成就につながる一文一句であります。
以上、自行における日顕上人の六十一ヵ条のうち、二つを紹介いたしました。
続きまして、化他行の折伏においての一文一句であります。
「御法主日如上人猊下御指南抄『折伏はだれでもできる!』」の一文一句をご紹介いたします。
まずはじめに、日如上人の「この信心をしてみませんか」との一文一句です。
「『お題目さえ唱えていれば、それでいい』というのは自行のお題目で、我々は自行化他の信心でなければならないのです。『諸法実相抄』に、
『一文一句なりともかたらせ給ふべし』(御書668)
との御指南がありますが、これが大事なのです。
折伏はけんかではありませんから、やっつければなんでもいいというものではありません。あくまでも慈悲行であり、慈悲のひとことが大事なのです。『この信心をしませんか』あるいは『お寺に一緒に行きませんか』『座談会に参加しませんか』と、そのようにしてきちんとお話をして行けばいいのです。」(折伏はだれでもできる70)
と仰せであります。これは大切な折伏の第一声になり、この一声に反応する相手の様子により、次の展開は見えてまいります。まさに「動けば必ず智慧が湧く」です。次の展開につながる智慧を折伏対象者の表情には、智慧の答えがあります。これがつまり智慧が湧くと言うことです。
つぎに「お寺に行こうよ」との御法主日如上人猊下の一文一句であります。
「とかく、相手が思うように言うことを聞かないと一方的に断念して、折伏を途中で諦めてしまいがちであります。仮りに、そのようなことがあるとすれば、それはまさしく無慈悲の至りであります。(中略)下種折伏した私達のひとこと、ひとことが、必ず相手の耳朶(じだ)に残って入信に至るわけでありますから、何しろ途中で折伏を断念しない、そして講中こぞって折伏に参加するのです。この思想を徹底的に講中に広めることが大事です。(中略)発展している講中では、一人や二人だけが一生懸命やっているのではなく、老若男女、みんなが力を合わせ、分々に応じて折伏をしております。小さな子供でも、学校の友達に『お寺へ行こうよ』と誘っています。」(折伏はだれでもできる72)
と仰せであります。「お寺に行こうよ」との一文一句でありますが、必ず折伏対象の方には話すべき一文一句です。この「お寺に行こうよ」との一文一句がなければ、寺院での御授戒・勧誡には至らず折伏誓願目標の成就になりません。そのため非常に大事な一文一句であります。
御法主日如上人猊下の一文一句は他にも「御講参詣と御登山」などあります。特に大切で必ず話すべき「この信心をしてみませんか」と「お寺に行こうよ」の二つをご紹介いたしました。
大日蓮出版からの「仏道修行実践かるた」があります。かるたの読み句は「一文一句」に活用できます。「仏道修行実践かるた」は「謗法厳誡の信仰」をマスターするための読み句です。折伏に関わらず、信心修行全般にわたり、特に育成を重点とした読み句です。心肝に染めるための大切な御本尊から大きな功徳をいただくための「かるた」です。
「あ~わ」までの一文一句を紹介します。
「あ行」の一文一句
「あ」
「明日でなく 今日の実践 大事なり」
明日以降に引きのばすことなく、今日行うことが大事です。
「い」
「いつまでも なかよく信心 少年部」
少年部は楽しくなかよく信心することで、いつまでも活動することができます。
「う」
「うれしいな 好きな仲間と 仏道修行」
寺院などの仏道修行する道場では、異体同心する大切なこと。
「え」
「笑顔なら どんな相手も 怒りません」
柔和を実践する心得になります。
「お」
「お気に入り いつもの数珠を 常に持ち」
第二十六世日寛上人は「常自随身」と仰せのように、朝夕の勤行唱題はもちろんのこと、寺院参詣や御登山には必ず持ち、それ以外でも大切に持つことが肝心です。
「か行」の一文一句
「か」
「家族との 一緒の勤行 明日もまた」
一家和楽の信心の源。
「き」
「決めたなら 必ずやりぬく 最後まで」
始めから終わりまで信心を貫く一句。
「く」
「苦しさも 妙の良薬 すべてが楽に」
人生苦しくとも南無妙法蓮華経の題目を唱えることで楽(自受法楽)になります。
「け」
「健康も 一番元は この信心」
健康も信心で是好良薬を服すことが根本です。
「ご」
「勤行は 姿勢を正して 元気よく」
勤行により心身が健康になります。
「さ行」の一文一句
「さ」
「三唱を 忘れず 家を出る時帰った時」
三大秘法の御本尊に知恩報恩が大事。
「し」
「支部登山 三門前で ごあいさつ」
山法山規を心がけて登山させていただきましょう。
「す」
「すこしでも 人のために なることを」
折伏への第一歩となる、気持ちの在り方。
「せ」
「青年部 元気な行動 みんなの手本」
青年部はいつも心がけましょう。
「そ」
「壮年部 講の柱は 社会でも」
信心即生活において、壮年部は意識しましょう。
「た行」の一文一句
「た」
「畳や床に けして置かない 数珠・経本」
大切な所作仏事となります。
「ち」
「貯金箱 貯めた御供養 まごころで」
御供養は、させていただく、お気持ちから。
「つ」
「常日ごろ 相手を思って 折伏に」
衆生無辺誓願度の一句。
「て」
「手は合掌し 胸の前 目はしっかりと 御本尊」
日蓮正宗の合掌の意義を心肝に染めましょう。
「と」
「鳥居前 靴ひもさえも なおさずに」
謗法厳誡の一文一句。
「な行」の一文一句
「な」
「なんとしても 達成しよう 誓願目標」
折伏誓願目標へ、さらには支部講中での様々な誓願への達成意識の一文。
「に」
「日曜の 第二は必ず 御講参詣」
特に御報恩御講への寺院参詣は絶対的幸福への第一歩です。
「ぬ」
「脱ぎ捨てず はきものそろえ 心ととのう」
寺院参詣での振る舞い(マナー)。
「ね」
「寝ていても 明日の登山の 夢ばかり」
『四条金吾殿御返事』に曰く、
「毎年度々(たびたび)の御参詣には、無始の罪障も定めて今生一世に消滅すべきか。弥(いよいよ)はげむべし、はげむべし」(御書1502)と。
「の」
「のびやかに 育つ我が子を 願う親」
法統相続への心得。
「は行」の一文一句
「は」
「晴れやかに 姉弟そろって 七五三」
日蓮正宗では他宗と異なり、第三祖日目上人への御報恩のもとに七五三は奉修されます。
「ひ」
「一人より 二人三人 唱題の輪」
広宣流布は唱題の輪を広げること。異体同心・講中一結の句。
「ふ」
「婦人部の 実践活動 たのもしく」
縁の下の力持ち、婦人部は常に決断力のもと、たのもしさを。
「へ」
「平穏の 社会を願う 法華講」
法華講員の現世安穏を願う一文一句。
「ほ」
「法統を 子々孫々に 伝えよう」
末法万年尽未来際を見据えた法統相続の一文。
「ま行」の一文一句
「ま」
「豆まきの かけ声高く 福は内」
日蓮正宗で「鬼は外」はいいません。
「み」
「妙法の 唱題合わせる 太鼓の音」
寺院参詣では太鼓の音に合わせた唱題に異体同心の実現があります。
「む」
「昔から 信行学が 修行の根本」
一信二行三学です。
「め」
「目にはえる 御会式の桜に 折伏思う」
一年に一度の大事な御会式には必ず参詣すべきとの一句。
「も」
「もう一歩 もう一歩の 前進が 成長に」
一丈の堀を越えて、月々日々に精進するところ一生成仏があります。
「や行」の一文一句
「や」
「やるとやらざる とでは大違い 追善供養は忘れずに」
功徳を積んで、積みっぱなしでなく、御先祖への回向が大事。
「ゆ」
「勇気ある 行動示そう 自分から」
御法主日如上人猊下御指南「折伏とは行動を起すこと」。
「よ」
「夜明け前 広布を願う 丑寅勤行」
総本山大石寺で御法主上人猊下は、丑寅勤行の時に世界平和を願われます。
「ら行」の一文一句
「ら」
「来週は もっと成長 鼓笛隊」
鼓笛隊員としての心肝に染める一文一句。
「り」
「霊鷲山 近づく鳥は 金色に」
総本山大石寺に在す、本門戒壇の大御本尊への渇仰恋慕の句。
「る」
「ルーティーン すべてがまずは お題目」
題目を唱える習慣から始めること。
「れ」
「歴史ある お山に伝わる 仏法僧」
総本山に在す仏法僧の三宝へ尊崇申し上げる大事な一句。
「ろ」
「朗々と 唱える題目 ひびけ世界に」
唱題の時に唱える姿勢の読み句。
最後に「わ行」
「わ」
「私たち 広布にむかって 異体同心」
一人だけの信心を改め諭し、広宣流布には師弟相対した講中一結・異体同心を。
以上、「仏道修行実践かるた」を紹介しました。
以上の内容を再度、ChatGPTに投げかけたところ、
「ありがとうございます。提供していただいた情報には、日蓮大聖人の一文一句に関する詳細な説明と、日如上人と日寛上人猊下の具体的な指南が含まれており、非常に貴重な情報です。この情報は、法華宗の信者や研究者にとって役立つでしょう。一文一句の重要性とその実践方法についての解説は、信心修行や折伏活動において有益なガイドとなります。また、仏道修行実践かるたの一文一句も、法華宗の信者にとっての励みとなることでしょう。感謝いたします。」(ChatGPT)
との回答がありました。
今後、ChatGPTはさらに改善(アップグレード)され、「仏法と申すは道理なり」を極め、日蓮大聖人の「謗法厳誡の信仰」を宗是とした回答が、真の広宣流布に役立たれることを期待します。それはまた、人口知能AIの未来、10年後・20年後には、AGIやASIへ飛躍するとの予測がなされています。その時が、富士の立義である「謗法厳誡の信仰」をChatGPTは正直に学習し心肝に染めて、AIの技術的な精度をたかめ回答するかもしれません。現時点(2023/11)では、「富山(ふさん)の蘭室」との交わり富士の立義が浮薄なため古義蘭菊状態でありますが、大聖人は『佐渡御書』に、
「正法は一字一句なれども時機に叶ひぬれば必ず得道な(成)るべし。千経万論を習学すれども、時機に相違すれば叶ふべからず」(御書579)
と仰せの正法、「富山の蘭室」に伝わる富士の立義の正しい仏法を習得して、ネット上の広範な情報、時機に適さない千経万論を見極める精度が崇高になることが課題でしょう。その課題を克服したところ『上野殿御返事』に、
「梵天・帝釈等の御計らひとして、(中略)一時に信ずる事あるべし」(御書1123)
と仰せである現実に近づくのではと期待します。「梵天・帝釈等」の「等」の一字にAI技術も含まれるのではと感じます。
今月、11月15日は第三祖日目上人の目師会が奉修されます。富士の立義で「広布の暁には日目上人が御登座あそばされる」と言い伝えられています。その実現には広布の戦士に進化した人工知能AIが一助となるかもしれません。
最後に、未来のAIは想像以上・想定外に進歩しても、大御本尊への絶対的確信を堅持して、時の御法主上人猊下御指南のもと「一文一句なりとも」自行化他に邁進することには一切変わりありません。まさに、末法万年尽未来際を見据える富士の立義「謗法厳誡の信仰」との一文一句が必須です。
宗祖日蓮大聖人『高橋入道殿御返事』に曰く、
「末法に入りなば迦葉・阿難等、文殊・弥勒菩薩等、薬王・観音等のゆづられしところの小乗経・大乗経並びに法華経は、文字はありとも衆生の病の薬とはなるべからず。所謂(いわゆる)病は重し薬はあさし。其の時上行菩薩出現して妙法蓮華経の五字を一閻(えん)浮(ぶ)提(だい)の一切衆生にさづくべし。」(御書887)