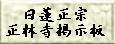創価学会の52年路線とその破綻
時局協議会文書作成班5班
創価学会の、いわゆる「52年路線」については、問題とすべき多くの要素があり、様々な角度から検討しなければならない。
以下、それらについて述べるに当たり、まずはじめに、その問題点の本質を指摘されたともいうべき、昭和55年4月6日の、御代替奉告法要における御法主日顕上人のお言葉を示しておく。
「創価学会の余りにも急激な広布への展開の中には、古来の宗門伝統の思想や形式にたいし種々の特殊性があり、違和的な問題を包藏していたことも事実と思われます。それが正本堂建立以後に於て顕著に現れ、宗門対創価学会の間に様々の不協和を生じました。その主要原因として、本来根本である宗門を外護しつつ広宣流布を推進する信徒団体であるべき立場を更に超え、広布の為には学会主、宗門従という本末顛倒の指向性が特に現われた時から、様々の問題が一時に噴出した感があります。
従ってその頃の学会の方針や指導には確かに行き過ぎがあったと云えます。」
すなわち、52年路線は、学会の「学会主、宗門従」という本末顛倒の強い指向性があって、そこから宗門の伝統教義からの逸脱等、様々な問題が派生したものである。
1.創価学会の宗教法人設立時の宗門に対する約束
本来、日蓮正宗の信徒団体である創価学会が、独自の宗教法人を設立するということは、同一宗内に二つの宗教法人ということになり、まことに不自然な形態となる。しかし、それにもかかわらず、創価学会の法人設立が、宗門から許可されたのである。その法人設立の意図について、戸田第二代会長が、以下のように説明している。
「我々の折伏活動が全国的活動となり、邪宗との決戦に至る時の大難を予想し、本山を守護し、諸難を会長の一身に受けるの覚悟に他ならない、ということ。二つには、将来の折伏活動の便宜の上から宗教法人でなければならない。」
(『聖教新聞』S26.12.20)
以上の理由によって、学会の宗教法人設立は、宗門から許可されたのである。ただし、この時、学会は宗門に対して、以下の3項目を遵守することを約束したのである。
折伏した人は、信徒として各寺院に所属させること。
当山の教義を守ること。
三宝(仏、法、僧)を守ること。
この3項目は、以後、宗門に対して、学会が絶対に破ってはならない原則として、約束されたのである。そして、この3項目は、昭和47年の正本堂建立の時までは、著しい違背もなく、守られてきたのである。しかし、正本堂建立以後、学会の体質は大きく変わり始め、日蓮正宗の信徒団体としてのあるべき姿から、大きく逸脱し始めたのである。そして、そのピークにあったのが52年路線である。
創価学会の52年路線とは、守ると約束した3項目の原則を、様々な方面から、色々な方法で、ことごとく破った路線であるといえる。
2.創価学会の52年路線
いわゆる学会の昭和52年路線が、既に昭和47年の正本堂建立の時に始まっていたことは、昭和53年2月9日の、第1回時事懇談会における日達上人のお言葉から明らかである。
「昭和四十七年に正本堂が建立せられた。その直後から非常に学会の態度がおかしくなってきた。大変僧侶も馬鹿にするし、また教義上に於いても非常に変化が多いように思う。そのつど私も種々な時にそれを指摘して、そういうことはいけない、日蓮正宗の教義に違うと指摘してきたつもりでございます。」
ここには、教義上の誤りのみならず、大変僧侶を侮蔑していたことも明かされている。
また、52年路線の問題が表面化する3年前の昭和49年6月18日に、日達上人は、既に次のように述べられて憂慮の意を表明されている。
「この辺でも、最近、ある書(『人間革命』)が御書だということを盛んに言われてきております。私の耳にもしばしば入ってきています。また、だれそれが仏であるという言葉も、この近所で聞かれるのであって、私は非常に憂慮しています。(中略)どうか、地方においてそういう間違った言葉を聞いたならば、大いにこれを破折して、日蓮正宗の教義を宣べて頂きたいと思います。
日蓮正宗の教義が、一閻浮提に敷衍していってこそ、広宣流布であるべきであります。日蓮正宗の教義でないものが一閻浮提に広がっても、それは広宣流布とは言えないのであります。」
このお言葉には、『人間革命』は現代の御書、「池田会長は御本仏」というようなことが、既にこの時期、学会の組織の中で、公然といわれていたことが、明らかに述べられているのである。
そして、このような学会の在り方に、危惧を抱いた宗内の一部の若手僧侶が、日達上人の意を体して、少しずつその誤りを指摘し始めたのである。やがて、その波は宗内に徐々に波及していき、昭和52年1月15日の、第9回教学部大会における、池田会長の「仏教史観を語る」と題した講演が発表されるや、ついにその運動はピークに達したのである。これ以後、この問題は、宗門全体の問題として、全宗門の僧侶が強い問題意識をもって、監視するようになった。 なお、「仏教史観を語る」については、後に詳述する。
こうして、宗内の若手僧侶によつて、学会の教義逸脱に対する指摘が、徐々に激しくなり、またその運動が、全国的に拡大の様相をみせるようになると、次第に学会内に動揺が起こり、さすがに学会本部としても、これを黙視することができず、昭和52年11月14日、宗門に対して「僧俗一致の原則(5箇条)」と、それに付随する「7箇条」の案を提出してきたのである。ただし、この時は、反学会僧侶11名の処分要求書も併せて提出し、威圧的な姿勢を崩さなかったのである。
この学会からの「案」を巡って、昭和53年2月9日と2月23日の2度にわたり、宗門の代表者、及び多数の傍聴者が集まって、時事懇談会が開催された。この懇談会の結論として、学会へは回答をしない、ということが決定したのである。
また、この時、「学会とは袂を分かつべし」との意見もあったが、日達上人より、「池田会長が謝罪してきたので、学会と手を切るということではなく、いかに協調していくかを検討するように」とのお言葉があり、協調の方向で、宗内から多数の意見が出されたのである。
このような経過を踏まえて、同年6月19日、「教学上の基本問題について」として、34箇条の質問が、宗門より学会に提出されたのである。
3.「教学上の基本問題」(6・30)について
宗門からの34箇条の質問に対し、学会はその回答を、6月30日付『聖教新聞』の4面に掲載した。ただし、宗門からの質問は掲載されず、学会の回答のみを、それも4面という目立たない個所に掲載するという不誠実なものであった。したがって、事情を知らない一般会員には、問題の意味が、ほとんど理解されなかったのである。また、それが学会の狙いだったのである。すなわち、訂正謝罪は、本来、一般会員に対してもなされるべきであったが、あくまでも宗門向けのみの形式的なものでしかなかったのである。
以下、その内容に触れていく。
質問は、全部で34箇条にわたっているが、それらは以下の9項目に大別され、括られている。
(1)戸田会長の悟達・創価仏法の原点
(2)血脈・途中の人師論師・大聖人直結
(3)人間革命は御書
(4)帰命・主師親三徳・大導師・久遠の師
(5)寺院と会館を混同・寺軽視
(6)謗法容認
(7)供養
(8)僧俗
(9)その他
この9項目を順を追ってみていくと、当時、学会が日蓮正宗を語りながら、実は独自に別の方向を目指していたことが、鮮明に浮き彫りにされてくるのである。すなわち、「社会に仏法を応用展開するため」という大義のもとに、後に触れる「創価仏法」という言葉を使用し、日蓮正宗とは、はっきりと一線を画した、独自の在家教団を目指していたということである。
まず、日蓮正宗には、700年の間、血脈付法の歴代の御法主上人によって、大聖人の仏法の全てが受け継がれてきたという、正しい伝統がある。創価学会では、これに対抗するため、学会の伝統的意義付として、
「初代牧口会長、二代戸田会長が、ただ一人唱えはじめられ、そこから二人、三人と唱えつたえて現在にいたった」
とか、
「戸田会長は獄中において『仏とは生命なり』と悟達した」
「創価仏法の原点は戸田会長の悟達にある」
等のことを述べたのである。
また、宗門の血脈相承に対して、明らかにこれを否定した表現がなされている。
「途中の人師、論師ではない」
「血脈相承とは、既成宗教などのように、神秘的に高僧から高僧へ儀式を踏まえて流れるものではない」
等の、宗門の血脈否定の発言である。しかし、一方、学会では、
「大聖人直結」
「信心の血脈相承」
等といって、学会にのみ大聖人の血脈が流れているような表現をしたのである。これらの教義逸脱は、最大の目標である池田会長本仏論への伏線となっていたのである。
「人間革命は現代の御書」
「師への帰命」
「久遠の師・池田会長」
「主、師、親、三徳具備の池田先生」
「池田先生こそ本門弘通の大導師」
これらは、直接、池田会長を本仏と断定していない。しかし、大聖人の御徳を顕わすときにのみ使用される言葉を用いて、全て池田会長の徳であると表現していたのである。そして、池田会長と大聖人をダブらせて、巧みに会長本仏論を作り上げようとしたのである。
こうして、理論上の、いわゆる「創価仏法」を作り上げ、また実践面において、少しずつ一般会員と末寺との離間工作を謀ったのである。
「大聖人は、一生涯、既成仏教のような寺院は持たれなかった」
「儀式だけを行ない、我が身の研鑚もしない、大衆のなかへ入って布教するわけでもない既成の寺院の姿は、修行者の集まる場所でもなければ、ましてや道場であるわけは絶対にない」
等々、あたかも既成仏教を非難しているようにいいながら、宗門寺院や僧侶を非難したのである。それは、また当時の女子部の、次のような発言と関連付けてみれば、さらに理解できよう。
「いわゆる正宗の寺院は、授戒とか葬式とか法事などの儀式の場であります。社会のためとか、広宣流布とか人間革命という御本仏直結の脈動の場は、もはや現代においては創価学会しかないのです。」(藤田栄著『女子部と私』)
こうした指導によって、会員をなるべく寺院から遠ざけるようにしたのである。そして各会館には、あたかも寺院のように山号をつけ、盆や彼岸には先祖供養を行ない、時に法事や結婚式も行なったのである。このような指導の一つに、問題となった「在家の身でも供養を受けられる」という、池田会長の指導もあったのである。
以下、「6・30」の34箇条の中から、主な項目について、宗門からの質問と、問題となった言論資料、及び学会の回答を挙げてみる。
(1)戸田会長の悟達・創価仏法の原点
[宗門からの質問]
「大聖人がただお一人唱え初められたお題目であるにも関らず初代会長・二代会長が唱えはじめられたというのは僭越ではないでしょうか。」
[言論資料]
「創価学会は、初代会長・牧口先生が、まずお一人、立ち上がられ唱えはじめられたところから二人、三人と『唱えつたえ』、約三千人にまでなった。
戦後は、第二代会長・戸田先生が、東京の焼け野原に立って、一人、唱えはじめられ、そこから、二人、三人、百人と『唱えつたえ』て、現在の一千万人以上にまでなったのであります。」(池田会長「諸法実相抄講義」・『聖教新聞』S52.1.5)
[学会からの答え]
「『諸法実相抄』の『日蓮一人はじめは南無妙法蓮華経と唱えしが…』の御文を講義する際、学会において初代会長、二代会長が唱えはじめられたとの表現がありましたが、現時点における、学会における歴史的事実を述べたものでありました。しかし、こうした論述をする際も、大聖人がただお一人唱えはじめられたお題目であることを銘記し、僭越にならぬように注意してまいりたいと思います。」
[宗門からの質問]
「創価仏法とは何ですか。日蓮正宗の仏法の外にあるのですか。」
[言論資料]
「創価仏法の原点はいうまでもなく戸田前会長の悟達にあります。」(池田会長てい談「法華経の展開」・『大白蓮華』S49.4号)
[学会からの答え]
「学会は、実践の教学として社会に仏法を応用展開してきましたが、それを急ぐあまり、宗門伝統の教学に対し、配慮のいたらない部分がありました。この点は、今後十分留意していきたいと思います。
『創価仏法』という表現を使ったことがありますが、これは折伏弘教のうえでの社会への展開という側面でありました。すなわち、実践の教学の意味が込められていました。ものごとには一つのことをさまざまに表現する場合があります。いわば創価というのは幸福ということであり、幸福の仏法という意味で用いたのであります。
また、仏法の展開に際しては、さまざまな現代の哲学、科学上の成果をふまえなければなりません。そのためには、多少の試行錯誤もあることは、当然、覚悟しなければならないことです。むしろ現代人にわかりやすいように、外護の責任のうえから、ある意味のクッションをおいた形が、後々のために望ましいと考えました。しかし『創価仏法』という表現自体は避けるようにします。」
(2)血脈・途中の人師論師・大聖人直結
[宗門からの質問]
「途中の人師論師とは誰を指すのですか。」
[言論資料]
「『先師の御弘通』の『先師』とは、御本仏日蓮大聖人のことであります。したがって『日蓮大聖人の御弘通』そのままにということになるのであります。すなわち日蓮大聖人の正真正銘の門下であるならば、日蓮大聖人の振る舞いと、その精神を根本にすべきなのであります。それは、途中の人師、論師ではないということなのであります。途中の人師、論師が根本でないということは、人師論師の場合には、いろいろな時代背景のもとに、生き延びなければならなかったが故に、令法久住を願ってさまざま様々な知恵をめぐらした場合があるからであります。」(池田会長講演・『聖教新聞』S52.2.17)
[学会からの答え]
「『途中の人師、論師を根本とすべきでない』と表現したことについては、この人師、論師は唯授一人血脈付法の御法主上人猊下の御内証のことではありません。
我ら末弟は『日興遺誡置文』の『富士の立義聊も先師の御弘通に違せざる事』と仰せのごとく、御本仏日蓮大聖人の御弘通のままにということを強調する意味でありました。その日蓮大聖人の仏法の正統の流れは、第二祖日興上人、第三祖日目上人、そして第六十六世の御法主日達上人猊下の御内証に流れていることはいうまでもないことであります。
したがって、こうした唯授一人の血脈に触れずに論ずるような表現は決して使わないようにしたいと存じます。」
[宗門からの質問]
「ここでは既成宗教に血脈相承があることをのべ、かつ大聖人の仏法の本義はそんなところ(高僧から高僧への血脈相承)にあるのではないと論じられているが、それは日蓮正宗に血脈相承があることを否定することともとれますがその意味なのですか。他宗でも血脈ということは言うが血脈相承とは言いません。また、法体の血脈相承と生死一大事の信心の血脈とはその意味に違いがあります。
しかるに学会で大聖人直結の血脈というところに、おのずから本宗の唯授一人の血脈を否定するかのようです。
そこであえて質問いたしますが、学会では生死一大事の血脈のみを血脈として、身延相承書の『血脈の次第日蓮日興』の文義を否定するのですか。」
[言論資料]
「血脈相承といえば、よく既成宗教などにみられるように、神秘的に高僧から高僧へ、深遠甚深の儀式を踏まえて流れるものであると思われがちであります。事実、最蓮房もそのように思っていたにちがいない。しかし、大聖人の仏法の本義はそんなところにあるのではない。我が己心の厳粛な信心のなかにこそあるといわれているのです。
大聖人の生命にある生死一大事の血脈を、私たちはどうすれば相承できるか。大聖人ご自身はすでにおられません。だが、大聖人は人法一箇の当体たる御本尊を残してくださっております。この御本尊から生死一大事の血脈を受けるのでありますが、それは剣道の免許皆伝の儀式のような、学校の卒業証書のような、そうしたものがあるわけではない。ただ、唱題という方程式によって、大御本尊の生命を我が生命に移すのです。というよりも、我が生命の中にある大聖人のご生命、仏界の生命を涌現させる以外にないのです。」(池田会長「生死一大事血脈抄講義」・『大白蓮華』S52.6号)
[学会の答え]
「血脈については、法体の血脈と信心の血脈等があります。御書に『生死一大事血脈抄』があります。その冒頭に『夫れ生死一大事血脈とは所謂妙法蓮華経是なり』と仰せであります。これは別しては日蓮大聖人の御内証そのものであられる南無妙法蓮華経の法体が生死一大事血脈の究極であるとの意味であります。
この別しての法体の血脈相承は『身延相承書』に『血脈の次第 日蓮日興』と仰せのごとく、第二祖日興上人にすべて受け継がれ、以後、血脈付法唯授一人の御法主上人が伝持あそばされるところであります。同抄に『総じて日蓮が弟子檀那等・自他彼此の心なく水魚の思を成して異体同心にして南無妙法蓮華経と唱え奉る処を生死一大事の血脈とは云うなり』の御文は『別して』の法体の血脈を大前提としての『総じて』の信心の血脈を仰せなのであります。ゆえに、代々の御法主上人猊下の御内証によってお認めの御本尊を受持していくことが正しい信心の在り方であり、総じての生死一大事の信心の血脈となるのであります。
ゆえに、別しての法体の血脈相承と、総じての生死一大事の信心の血脈とは、その意味に違いがあることを確認しておきたいと思います。
一昨年、発表された第三代会長の『生死一大事血脈抄講義』は、こうした原理をふまえたうえで、総じての仏法実践のうえでの生死一大事の信心の血脈を中心に、一般社会に展開したものでありますが、別しての法体の血脈相承について深く論ずることをしなかったために、誤解を生ぜしめる点もありました。これについては、第三代会長からの意向もあり、一部訂正して改訂版を発行しましたのでご了承をお願い申し上げます。」
(3)人間革命は御書
[宗門からの質問]
「前進の 204では大聖人の教えの真髄は御本尊と御書であるといっている。が、ここでは人間革命が御書であるとしています。それでは人間革命が大聖人の教えの真髄ということになりますが、そうお考えなのですか。」
[言論資料]
「私は再び繰り返したい。『人間革命』は現代の御書である。『人間革命』を通して御書を拝読すると、大聖人の大精神がより鮮明に、私の心を打つ。更に御書を通して『人間革命』を読むと、学会精神が体内により強烈に脈打ってくる。
御書から『人間革命』へ、そして『人間革命』から御書へと。この往復の中に、信行学の揺がぬ確立があるのではなかろうか。
『人間革命』はそのような一書である。大聖人との不可思議な血脈の相承がある。確かに不思議な書といわざるをえない。」(福島源次郎述・文集『教学と私』第1巻)
[学会からの答え]
「『人間革命は現代の御書』という発言については、第三代会長もすでに明確にしているように、明らかに誤りであります。」
(4)帰命・主師親三徳・大導師・久遠の師
[宗門からの質問]
「文中『久遠の師池田会長』とありますが、本宗で久遠の師とは大聖人のことであります。故に池田会長が久遠の師なら池田会長は即ち大聖人ということですか?
また本宗で帰命とは人法一箇の本門の本尊への帰命ですが文中でいうように池田会長の振舞いが法でありそれに帰命するということは日蓮正宗の教えと全く違っているように思いますがいかがですか。」
[言論資料]
「一、この決意に対して、ただ今拝読されましたごとく、久遠の師・池田会長より、メッセージが寄せられたのであります。」(北風清松九州長談・『ひのくに』11号)
「一、まさしく、現代における“人”への帰命とは師匠への帰命であり、池田会長への帰命となる。また、池田会長が大聖人の御書を寸分違わず、身に移し実践されていることから考えても、必然的にそうなるのである。」(村野宏論文・『ひのくに』10号)
[学会よりの答え]
「第三代会長に関して『久遠の師』という言葉を使った場合がありますが、これは師弟の縁が深いことを述べようとするあまり行き過ぎた表現でありました。正宗では久遠の師とは大聖人のことであり、今後、こういう表現を用いないことにします。
一、『帰命』という言葉は、正宗では仏に対してのみ使う言葉であります。当初は『妙法への帰命』を大前提として『師への帰命』といっておりましたが、それが一部で「人への帰命」といった表現にまでエスカレートして、会長が本仏であるかのような使われ方がなされました。これは誤りであり、帰命という言葉を安直に使用しては絶対にならないものであります。」
(5)寺院と会館を混同・寺軽視
[宗門からの質問]
「文中『葬式だけを行い我が身の研鑽もしない…』とあり、こういう言い方は当然日蓮正宗僧侶を目しているものと思われますが、しからば我々僧侶が我が身の研鑽もしていないと見られるのはいかなる理由によるのですか。
次に大聖人が一生寺院を持たなかったとの浜田某の論文にたいしこちらは破折してあります。これについてそちらからもう一度意見を出して下さい。
また正宗の寺院が修行者の集まる場所でなく、道場でもないという理由をあげて下さい。」
[言論資料]
「寺院を別名『道場』ともいうのは、その意味からであります。儀式だけを行ない、我が身の研鑽もしない、大衆のなかへ入って布教するわけでもない既成の寺院の姿は、修行者の集まる場所でもなければ、ましてや道場であるわけは絶対にない。(中略)また近くは末法の御本仏日蓮大聖人も、一生涯、既成仏教のような寺院は持たれなかった。お亡くなりになるまで草庵であります。折伏弘教の指導をとられ、また自ら布教のために歩く拠点としての庵室を持たれたのみであります。」(池田会長講演「仏教史観を語る」・『大白蓮華』S52.3号)
[学会からの答え]
「この講演の文中『葬式だけを行い我が身の研鑽もしない…』とあるのは、日蓮正宗僧侶を目して述べたものではなく、日蓮正宗以外の一般仏教界の多くの姿を語ったものであります。したがって『既成の寺院の姿は、修行者の集まる場所でなく、道場でもない』というのも、正宗の寺院を言ったものではないことをご了承願いたいと思います。しかしそういう印象を与えたとすれば、まことに遺憾であります。
なお、寺院の存在についてでありますが、日蓮大聖人は、お亡くなりになる前年の弘安4年には、身延に十間四面の堂宇を建てられ、これを久遠寺と命名されました。そして『池上相承書』においては『身延山久遠寺の別当たるべきなり』と日興上人へ遺付されています。さらに日興上人は身延離山の後、正応三年、南条時光の寄進を得て、大石寺の基を築かれたことは、周知の事実であります。」
(6)供養
[宗門からの質問]
「維摩詰が供養を受けたことは法華経で観世音菩薩が受けたのと同じく、仏に捧げる意味であります。
ことに維摩詰は在家であり、供養を受ける資格があるとはいえません。経文に応供とあるのは仏のことで、供養を受ける資格があるのは仏以外にない。
在家はどこまでも資生産業にはげみ、仏に供養するべきであります。」
[言論資料]
「更に、この供養について、若干、歴史的なことを申し上げますと前にもお話しした維摩詰は、在家の身でありながら供養を受けた事実が『維摩詰経』に記されております。(中略)つまり、供養とはあくまで仏法のためになすのであります。その供養が仏法流布に生かされるならば、在家の身であっても供養を受けられるという思想があります。」
(池田会長講演「仏教史観を語る」・『大白蓮華』S52.3号)
[学会からの答え]
「維摩詰が供養を受けたことは法華経で観世音菩薩が受けたのと同じく仏に捧げる意味であります。ことに維摩詰は在家であり、供養を受ける資格があるとはいえません。経文に応供とあるのは仏のことで、供養を受ける資格があるのは仏以外はないのであります。したがって、在家が供養を受ける資格があるという記述は改めます。」
以上、主立った項目について、[宗門からの質問][問題となった言論資料][学会からの答え]の順で列記してきたが、紙数の都合上、以下には「問題となった言論資料」のみを挙げ、それらが宗門からの指摘によって、反省の上に訂正されたことを記しておく。
(7)謗法容認
[言論資料]
「ただし、悪鬼乱入の寺社に関係するのであるから、それ自体“謗法”であることは否定できない。ただ広布のためという目的観と、御本尊への信仰によって、これを超える善根を積み、帳消しにするのである。その意味で、それが謗法であると自覚できる人ならば、自らの責任において、あえて、これを犯してよいともいえる。」(雪山居士述・『大白蓮華』S49.7号)
(8) 僧俗
[言論資料]
「しかし、その仏教も、時代を経るにつれて、出家僧侶を中心とする一部のエリートたちの独占物となっていくのであります。在家の供養で支えられた僧院の中で、学問的に語られるにすぎないものとなっていったことは、皆さんもよくご承知のところでしょう。(中略)これによると、在家はもっぱら唱題に励み、供養し、そのうえ、力にしたがって仏法を語るべきであるとされているのであります。僧侶がもっぱら折伏に徹し、三類の敵人と戦い、広宣流布するのに対して、在家は自身の成仏のため唱題し側面から僧侶を応援する立場である。その本義に立てば、現代において創価学会は在家、出家の両方に通ずる役割を果たしているといえましょう。(中略)私ども学会員は、形は在俗であろうとも、その精神においては出世間の使命感をもって誇りも高く…。」(池田会長講演「仏教史観を語る」・『聖教新聞』S52.1.17)
[言論資料]
「やる気になってからの学会の座談会での指導は、鮮烈なまでに私の命をゆさぶった。ああ、惰眠をむさぼったこと二十八年。
何んといいかげんな、日蓮正宗の信徒であったか。このような慚愧の念は、ますます私を折伏、座談会、そして教学にかりたてていった。
たしかに念仏を唱えるよりは、南無妙法蓮華経と唱えれば功徳はある。しかし、本当の宿命転換という大功徳は、創価学会に入って信心しなければ得られないのだ。これが、私の信仰体験である。従って私の入信は、昭和二十六年六月十五日。入信前の宗教、日蓮正宗なのである。」(北条浩述・文集『私の入信動機』)
(9) その他
[言論資料]
「私は戸田前会長と十年間、師弟の道を歩んできた。たとえ師匠が地獄へ落ちようと、師匠のそばへ行くと決めていた。それを自分の人生と決め、だまされても、師匠と一緒なら、それでいい。これが師弟相対だと決めていた。」
(池田会長著・『指導メモ』)
4.全国教師総会・創価学会創立48周年
記念代表登山会(11・7)
「教学上の基本問題について」(6・30)と題した学会の教義逸脱問題の訂正は、先に触れたように、『聖教新聞』の4面に、しかも宗門からの質問は載せず、学会の回答のみを掲載しただけの不誠実なものであったため、多くの学会員はその内容をよく理解しきれなかった。
そのような、学会側の不誠実な対応ぶりは、かえって宗門僧侶や、学会を脱会した檀徒達の反発を招き、事態はさらに混迷の度を増していったのである。
そうした状況の中で、同年8月には、日達上人御臨席のもと、第1回全国檀徒大会が開催され、180名の僧侶と6000名の檀徒が総本山に結集し、学会の教義逸脱と、その不誠実な姿勢を糾弾したのである。
こうして宗内には、日を追うごとに反学会の気運が高まり、その事態を収拾するために、11月7日、通称「お詫び登山」(11・7)といわれる、学会の代表幹部会が、総本山の大講堂で、全国の僧侶を招いて開催されたのである。
席上、北条理事長、辻武寿副会長、池田会長がそれぞれ陳謝の意を表明した。
[北条理事長]
「私ども創価学会といたしまして、以下の二点を率直に認めるものであります。すなわち、第一に、学会のここ数年の指導、進み方、教学の展開のなかに、正宗の信徒団体としての基本がおろそかになっていたこと、第二に、昨年のような学会の行き方は行き過ぎがあったこと、以上の二点を私ども学会は、とくにわれわれ執行部は、深く反省するものであります。
その認識に立ち、戦後再建の時から今日に至る、宗門と学会との三十年余りに及ぶ関係を顧みたうえで、創価学会は昭和二十七年の宗教法人設立時の三原則を遵守し、日蓮正宗の信徒団体としての性格を、いっそう明確にしてまいる方針であります。(中略)さらに加えて申し上げれば、私どもは信徒として、寺院参詣の重要性を指導してまいります。寺院は経文に当詣道場とあるごとく、信徒としての参詣の道場であります。(中略)また、寺院行事を尊重する意味から、各地にあっては、御講や彼岸法要など、寺院の行事に影響を与えないよう、学会行事、会合の開催を考慮してまいります。そのためにも、春秋彼岸会、盂蘭盆会の学会としての開催は、学会本部ならびに各県中心会館では行う場合はありますが、地方では、いっさい行わないようにいたします。」
[辻武寿 副会長]
「ただいま、北条理事長より、信徒団体としての基本について確認がありましたが、私からは、これをふまえて、私どもが留意すべき点について申し上げます。
それはまず第一に、戒壇の大御本尊根本の信心に立ち、総本山大石寺こそ、信仰の根本道場であることを、ふたたび原点に戻って確認したいのであります。戒壇の大御本尊を離れて、われわれの信仰はありません。(中略)この戒壇の大御本尊を厳護するためにこそ、日蓮正宗の厳粛なる化儀、伝統があるのであり、その点われわれ信徒は、よく認識していかねばなりません。
その意味からも、不用意にご謹刻申し上げた御本尊については、重ねて猊下の御指南をうけ、奉安殿にご奉納申し上げました。今後御本尊に関しては、こうしたことも含めて、お取り扱い、手続きなどは、宗風を重んじ、一段と厳格に臨んでまいりたいと思います。
第二には、唯授一人、血脈付法の猊下のご指南に従い、正宗の法義を尊重してまいりたいと思います。(中略)日蓮大聖人の法体、御法門は、すべて現法主日達上人猊下に受け継がれております。ゆえに創価学会は広布を目指し、社会に仏法を弘通、展開していくにしても、その大前提として、猊下のご指南にいっさい従っていくことを、忘れてはならないのであります。
第三に、学会員の心情には、長い歴史のなかで、しぜんに会長への敬愛の念が培われてきましたが、また、それは当然であるとしても、その心情を表すのに、行き過ぎた表現は避けなければなりません。(中略)この三点に基づき、広宣流布を目指す学会の教学の展開についてふれれば、その大原則は、六月三十日付聖教新聞に掲載した『教学上の基本問題について』に明らかであります。これは、猊下のご指南を得て発表したものであり、今後の展開の規範として、さらに学習してまいる方針でありますので、よろしくお願いいたします。」
[池田会長]
「先程来、理事長、副会長から、僧俗和合の路線の確認、その他の問題について、いろいろと話がありましたが、これは総務会議、県長会議、各部最高会議の全員一致による決定であり、また私の決意であります。
この方針に従って、私どもは、一段と広宣流布と正法外護のご奉公に励む所存でございますので、御宗門の先生方、くれぐれも凡下なわれわれを厳しくも温かく、今後ともご指導くださいますよう心より御願い申し上げます。(中略)なお、これまで、いろいろな問題について行き過ぎがあり、宗内をお騒がせし、また、その収拾にあたっても、不本意ながら十分な手を尽くせなかったことは、総講頭の立場にある身として、この席で、深くおわびいたします。(中略)また、その過程にあっては、幾多の大難にもあいましたが、そのつど、御宗門におかせられましては、つねに学会を守りに守ってくださいました。そのご恩を私どもは、永久に忘れず、一段と御宗門へのご奉公を尽くしてまいる決意でございます。」
以上の池田会長、北条理事長、辻副会長の3人の陳謝の言葉を受けて、日達上人は次のような御指南をされたのである。
「先程来、学会幹部の方々から種々とお話を承りました。たしかに、この数年、宗門と学会の間に種々な不協和の点がありまして、さわぎにもなりましたが、こういう状態が続くことは宗開両祖の御精神に照らして憂慮すべきであることはいうまでもありません。こうした状態をいつまでも続けていることは、世間の物笑いになり、我が宗団を破壊することにもなり兼ねないといつも心配しておりました。幸い、学会においてその点に気付かれて今後の改善のために、反省すべき点は率直に反省し、改めるべき点を明確に改める決意をされたことは、まことに喜ばしいことであります。(中略)もっともたよるべき信徒が寺院を非難中傷し、圧迫するようなことがあれば、僧侶はまことに悲しい思いをいたして、否応なく反論しなくてはならないのであります。(中略)この30年間、学会はまことに奇跡的な大発展をとげられた、そのために今日の我が宗門の繁栄が築かれたことは歴史的事実であり、その功績は仏教史に残るべき、まことに輝かしいものであります。
しかし、その陰に、宗門の僧侶の挙っての支援と協力があったことを忘れないでいただきたいのです。(中略)とにかく大聖人以来、七百年間守りつづけてきた伝統と教義の根本はあくまで守り伝えなくてはならないのであります。これを踏まえなかったならば仮りにこれからいくら勢力が増しても、広宣流布は見せかけのものであったかとの後世の批判を免れることはできないのではないかと心配いたします。
私は法主として、正しい信心を全信徒に持ってもらうよう最大の努力をする責任があります。その立場から老婆心ながら、この点をあえて協調しなくてはならないのであります。(中略)今日、私が申し上げたことを、ここに確認された学会の路線が正しく実現されるということの上で、これまでのさわぎについてはすべて此処に終止符をつけて、相手の悪口、中傷をいい合うことなく理想的な僧俗一致の実現をめざしてがんばっていただきたいのであります。」