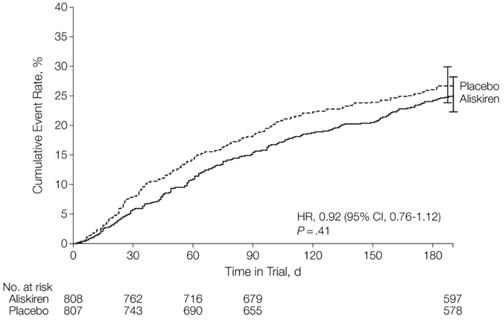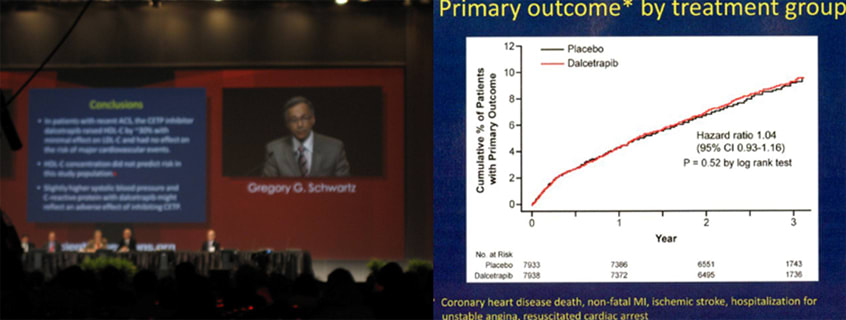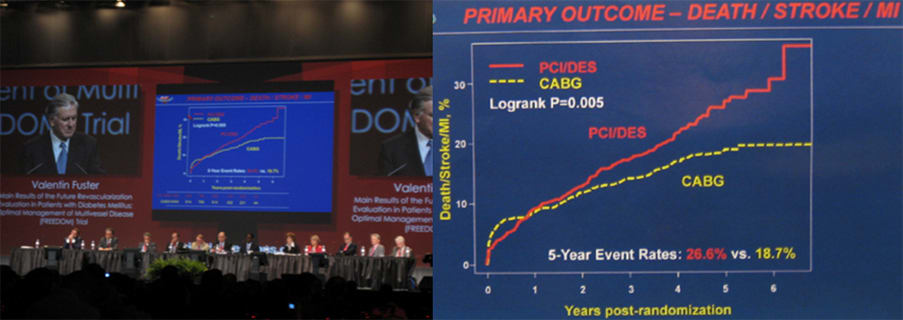学会で発表するためにシカゴに来ています。昼間でも気温はマイナス5度と非常に寒いです。
今回も興味深い臨床研究が発表されました。
Effect of Screening for Coronary Artery Disease Using CT Angiography on Mortality and Cardiac Events in High-Risk Patients With Diabetes: The FACTOR-64 Randomized Clinical Trial.
JAMA. 2014 Nov 17. doi: 10.1001/jama.2014.15825. [Epub ahead of print]
(インパクトファクター★★★★★、研究対象人数★★★★☆)
糖尿病患者は痛みの神経も障害されていることが多く心臓が血液不足になっても胸の痛みが出現することがない場合が多いです。また、糖尿病は心臓の血管の動脈硬化を起こしやすく、症状がないまま血管が細くなっていることも多いです。そのような2つの状態をを想定して、「症状のない」糖尿病患者にあえて血管が細くなっているかを調べる冠動脈CTを行うのが有益であるのかを検討した意義深い臨床研究です。
900人の症状のない、少なくとも3~5年以上糖尿病に罹患している患者が、冠動脈CTを行う群と行わない群に無作為に割り当てられ、その後4~7年間、動脈硬化性の心臓病の発症が比較されました。ただし、両群とも糖尿病の重症度を表すHbA1cは7.0%以下、悪玉コレステロールは100mg/dl以下、血圧は130mmHg以下にするように努力されました。そして冠動脈CTを行った群で、治療が必要なほど動脈が細くなっていた場合には、その状態に応じて適切に治療されました。
結果は、両群で動脈硬化性の心臓病の発症に違いは認められませんでした。
これは非常に興味深い結果だと思います。つまり、症状のない糖尿病患者に対して、糖尿病では動脈硬化が多いからといって、冠動脈の細さの程度を調べるCT検査を行っても、患者の予後は変わらないという事です。
これは何を意味するかというと、糖尿病患者では心臓病で寿命が決まる以外に、例えば腎臓病であったり、脳血管疾患であったり、別の疾患が影響を与えているので、動脈硬化性心臓病だけを症状のない段階で早期に見つけても、患者の寿命を改善することは出来ないということです。
しかし、悪玉コレステロールは100mg/dl以下、血圧は130mmHg以下にはできても、HbA1cを7.0%以下にコントロールするのは容易ではありません。
↓なるほどなぁ~と思われた方!ここをポチッ、応援よろしくお願いいたします。
「ブログランキング」
今回も興味深い臨床研究が発表されました。
Effect of Screening for Coronary Artery Disease Using CT Angiography on Mortality and Cardiac Events in High-Risk Patients With Diabetes: The FACTOR-64 Randomized Clinical Trial.
JAMA. 2014 Nov 17. doi: 10.1001/jama.2014.15825. [Epub ahead of print]
(インパクトファクター★★★★★、研究対象人数★★★★☆)
糖尿病患者は痛みの神経も障害されていることが多く心臓が血液不足になっても胸の痛みが出現することがない場合が多いです。また、糖尿病は心臓の血管の動脈硬化を起こしやすく、症状がないまま血管が細くなっていることも多いです。そのような2つの状態をを想定して、「症状のない」糖尿病患者にあえて血管が細くなっているかを調べる冠動脈CTを行うのが有益であるのかを検討した意義深い臨床研究です。
900人の症状のない、少なくとも3~5年以上糖尿病に罹患している患者が、冠動脈CTを行う群と行わない群に無作為に割り当てられ、その後4~7年間、動脈硬化性の心臓病の発症が比較されました。ただし、両群とも糖尿病の重症度を表すHbA1cは7.0%以下、悪玉コレステロールは100mg/dl以下、血圧は130mmHg以下にするように努力されました。そして冠動脈CTを行った群で、治療が必要なほど動脈が細くなっていた場合には、その状態に応じて適切に治療されました。
結果は、両群で動脈硬化性の心臓病の発症に違いは認められませんでした。
これは非常に興味深い結果だと思います。つまり、症状のない糖尿病患者に対して、糖尿病では動脈硬化が多いからといって、冠動脈の細さの程度を調べるCT検査を行っても、患者の予後は変わらないという事です。
これは何を意味するかというと、糖尿病患者では心臓病で寿命が決まる以外に、例えば腎臓病であったり、脳血管疾患であったり、別の疾患が影響を与えているので、動脈硬化性心臓病だけを症状のない段階で早期に見つけても、患者の寿命を改善することは出来ないということです。
しかし、悪玉コレステロールは100mg/dl以下、血圧は130mmHg以下にはできても、HbA1cを7.0%以下にコントロールするのは容易ではありません。
↓なるほどなぁ~と思われた方!ここをポチッ、応援よろしくお願いいたします。
「ブログランキング」