前回まで、ロケットとのコスト比較をしてきましたが、あと1回比較を行ってみたいと思います。テーマは(1)環境汚染 (2)安全性ですが、今回は、先に軌道エレベーターについて述べたいと思います。
(1) 環境汚染
ものすごく偏った昨今のエコ思想は好きではありませんが、多くの人にとって環境問題は関心の高いテーマです。軌道エレベーターは、電動が前提なので、排気ガスなどによる大気汚染はないと思われます。この電気を火力や原子力で賄うのであれば考えモノですが、前回述べたようにエネルギーの一部は回収できますし、宇宙空間での太陽光発電にも期待したいところです。ただし、建造のためにどこかの土地なり海洋なりの開発、環境改変は避けられないでしょう。
(2) 安全性
昇降機の落下はもちろん、テロや武力攻撃で軌道エレベーターが損壊したら、大きさからいって大惨事になりえますね。ただし旅客機も手榴弾1個持ち込まれて上空で爆発したら一巻の終わりなわけで、空港でのセキュリティチェックが生命線です。軌道エレベーターにも同様の体制が必要でしょう。
どこまで措置を講じれば信頼性を得られるのか、線引きは難しいと思われますが、少なくとも、エレベーターが(機能や耐荷重、安全設備の充実、セキュリティの確保など多面で)十分な規模に達するまでは、一般の有人運用は控えるべきではないでしょうか。
私的には、昇降機の落下もエレベーターの倒壊も、色々対処の仕方があるだろうと考えているのですが、証明材料に乏しいので、機会を改めて述べたいと思います。しかし、後述するような理由で、全体としてはロケットよりははるかに安全であろうというのが結論です。
では、軌道エレベーターに比してロケットの環境面への影響や安全性ですが。。。
 まず(1)の環境汚染については、一部のロケットは、有毒のガスをまき散らして飛んでいることを、ご存じの方も多いでしょう。たとえば、これまでさんざんコキおろしてきた米国のスペースシャトル。SSMEと呼ばれる本体のエンジンは液体の水素と酸素を反応させるもので、生じるのは水蒸気だから無毒。問題は、巨大な茶色い燃料タンクの両脇に付いている固体ロケットブースター(SRB)です。
まず(1)の環境汚染については、一部のロケットは、有毒のガスをまき散らして飛んでいることを、ご存じの方も多いでしょう。たとえば、これまでさんざんコキおろしてきた米国のスペースシャトル。SSMEと呼ばれる本体のエンジンは液体の水素と酸素を反応させるもので、生じるのは水蒸気だから無毒。問題は、巨大な茶色い燃料タンクの両脇に付いている固体ロケットブースター(SRB)です。
SRBの燃料に使われている酸化剤の過塩素酸アンモニウムは毒劇物ですし、燃焼促進剤のアルミ微粉末は呼吸器障害を起こします。こういったものを1回の打ち上げで約1000t反応させ、吐き出しながら飛んでいきます。某作家から聞いた話ですが、ケネディ宇宙センターのシャトル打ち上げ台周辺の土壌は、汚染されて生き物が全然住めないのだとか。
このほか、ロケット燃料の定番とも言えるのがヒドラジン。猛毒です。日本のH-IIA(ただし大気圏外で使用)や中国の長征ロケットなどにもそれぞれ推進剤の一部に使われています。余談ですが、かの国を含む色んな国の弾道ミサイルの推進剤もヒドラジンが混じってます。
ほかにも色々ありますが、このような有毒の燃料が頻繁に使われるのは、これらが個体燃料であり、固体の方が安定していて常温で扱いやすいからです。液体水素は極低温で充填するので、蒸発して機体から漏れ出しやすく、性能はいいけどデリケートらしいです。いずれにせよ、開発において追求されるのは推力や燃焼効率だけで、毒性とかはまったく念頭にないようです。
次に(2)の安全性について。有毒な燃料も危険ですが、何といってもロケットの安全を脅かす最大のファクターは爆発です。しかも「低コストの理由その1」で説明したように、全重量の9割近くを燃料が占めるので、引火事故の時はたいてい大爆発して一瞬で粉々になります。
歴史上、どれだけのロケットが打ち上げに失敗して爆発したのでしょうか。映画「ライトスタッフ」を見るといいです。「これでもか!」と言わんばかりに爆発が連続するシーンがあって、これだけ吹き飛んでもまだ打ち上げる技術者達の根性は、かえってアッパレと言いたくなります。ちなみに最後の一発は爆発せず、笑えるオチになってます(原作によると実話らしい)。
これら爆発事故のうち、最も有名なのは1986年のスペースシャトル「チャレンジャー」の事故でしょう。乗組員の直接の死因は、爆発後に海上に落下した衝撃によるものだそうですが(これも想像するだに恐ろしい)、爆発はSRBの部品が極低温で劣化したのが原因とのこと。結果として7人全員が死亡しました。ついでに言うと、スペースシャトルはSRBの燃焼が終わるまで事実上脱出手段がないのだとか(あってもどれだけあてになるものやら)。
そして、大気圏への再突入がいかに危険かは、前回説明した通りです。少なくともこれらと同種の懸念がないという点だけをとっても、軌道エレベーターはかなりクリーンで安全な乗り物だと言えるのではないでしょうか。
えんえんと欠点をあげつらってきましたが、今のところ、地上と宇宙の間を往復する手段は、現実問題としてロケットしかない以上、ロケットの使用は是とするしかない。良くも悪くも、宇宙開発を支えてきた主役はロケットです。だからここで述べているのはあくまで推定比較であり、ロケットの全否定ではないことをご理解いただければと思います。
それに、軌道エレベーターが完成したら、ロケット開発はますます加速することでしょう。軌道エレベーターの投射機能も利用して、衛星や惑星、太陽系外などへ宇宙船や探査機を送り込む大規模な計画が可能にするはずで、それにはやはりロケットが重要な役割を果たすからです。昨年11月の国際会議で、ロケット技術者らしき人が、軌道エレベーターができたら商売上がったりだ、その辺をどう考えているのかと質問があったのですが、今からそこまで心配しなくても。。。(仮にそうでないとしても、なんで軌道エレベーターの研究者がロケット屋の生活に責任持たなくちゃなくちゃならんのだ。研究をやめろとでも言うのかよう)
軌道エレベーター派は、ロケットの歴史と人類社会への貢献に十分敬意と関心を払った上で、これらロケットを上回る根拠を示して軌道エレベーターの実現を目指します。全身全霊をもって、地上と宇宙の往復手段としてのロケットに引導を渡す。これこそ最大の礼儀というものでありましょう。
ロケットとの比較はこれにて終了。次回からの豆知識は新章に移る予定で、軌道エレベーターの欠点や負の面を紹介していきたいと思います。
(1) 環境汚染
ものすごく偏った昨今のエコ思想は好きではありませんが、多くの人にとって環境問題は関心の高いテーマです。軌道エレベーターは、電動が前提なので、排気ガスなどによる大気汚染はないと思われます。この電気を火力や原子力で賄うのであれば考えモノですが、前回述べたようにエネルギーの一部は回収できますし、宇宙空間での太陽光発電にも期待したいところです。ただし、建造のためにどこかの土地なり海洋なりの開発、環境改変は避けられないでしょう。
(2) 安全性
昇降機の落下はもちろん、テロや武力攻撃で軌道エレベーターが損壊したら、大きさからいって大惨事になりえますね。ただし旅客機も手榴弾1個持ち込まれて上空で爆発したら一巻の終わりなわけで、空港でのセキュリティチェックが生命線です。軌道エレベーターにも同様の体制が必要でしょう。
どこまで措置を講じれば信頼性を得られるのか、線引きは難しいと思われますが、少なくとも、エレベーターが(機能や耐荷重、安全設備の充実、セキュリティの確保など多面で)十分な規模に達するまでは、一般の有人運用は控えるべきではないでしょうか。
私的には、昇降機の落下もエレベーターの倒壊も、色々対処の仕方があるだろうと考えているのですが、証明材料に乏しいので、機会を改めて述べたいと思います。しかし、後述するような理由で、全体としてはロケットよりははるかに安全であろうというのが結論です。
では、軌道エレベーターに比してロケットの環境面への影響や安全性ですが。。。
 まず(1)の環境汚染については、一部のロケットは、有毒のガスをまき散らして飛んでいることを、ご存じの方も多いでしょう。たとえば、これまでさんざんコキおろしてきた米国のスペースシャトル。SSMEと呼ばれる本体のエンジンは液体の水素と酸素を反応させるもので、生じるのは水蒸気だから無毒。問題は、巨大な茶色い燃料タンクの両脇に付いている固体ロケットブースター(SRB)です。
まず(1)の環境汚染については、一部のロケットは、有毒のガスをまき散らして飛んでいることを、ご存じの方も多いでしょう。たとえば、これまでさんざんコキおろしてきた米国のスペースシャトル。SSMEと呼ばれる本体のエンジンは液体の水素と酸素を反応させるもので、生じるのは水蒸気だから無毒。問題は、巨大な茶色い燃料タンクの両脇に付いている固体ロケットブースター(SRB)です。SRBの燃料に使われている酸化剤の過塩素酸アンモニウムは毒劇物ですし、燃焼促進剤のアルミ微粉末は呼吸器障害を起こします。こういったものを1回の打ち上げで約1000t反応させ、吐き出しながら飛んでいきます。某作家から聞いた話ですが、ケネディ宇宙センターのシャトル打ち上げ台周辺の土壌は、汚染されて生き物が全然住めないのだとか。
このほか、ロケット燃料の定番とも言えるのがヒドラジン。猛毒です。日本のH-IIA(ただし大気圏外で使用)や中国の長征ロケットなどにもそれぞれ推進剤の一部に使われています。余談ですが、かの国を含む色んな国の弾道ミサイルの推進剤もヒドラジンが混じってます。
ほかにも色々ありますが、このような有毒の燃料が頻繁に使われるのは、これらが個体燃料であり、固体の方が安定していて常温で扱いやすいからです。液体水素は極低温で充填するので、蒸発して機体から漏れ出しやすく、性能はいいけどデリケートらしいです。いずれにせよ、開発において追求されるのは推力や燃焼効率だけで、毒性とかはまったく念頭にないようです。
次に(2)の安全性について。有毒な燃料も危険ですが、何といってもロケットの安全を脅かす最大のファクターは爆発です。しかも「低コストの理由その1」で説明したように、全重量の9割近くを燃料が占めるので、引火事故の時はたいてい大爆発して一瞬で粉々になります。
歴史上、どれだけのロケットが打ち上げに失敗して爆発したのでしょうか。映画「ライトスタッフ」を見るといいです。「これでもか!」と言わんばかりに爆発が連続するシーンがあって、これだけ吹き飛んでもまだ打ち上げる技術者達の根性は、かえってアッパレと言いたくなります。ちなみに最後の一発は爆発せず、笑えるオチになってます(原作によると実話らしい)。
これら爆発事故のうち、最も有名なのは1986年のスペースシャトル「チャレンジャー」の事故でしょう。乗組員の直接の死因は、爆発後に海上に落下した衝撃によるものだそうですが(これも想像するだに恐ろしい)、爆発はSRBの部品が極低温で劣化したのが原因とのこと。結果として7人全員が死亡しました。ついでに言うと、スペースシャトルはSRBの燃焼が終わるまで事実上脱出手段がないのだとか(あってもどれだけあてになるものやら)。
そして、大気圏への再突入がいかに危険かは、前回説明した通りです。少なくともこれらと同種の懸念がないという点だけをとっても、軌道エレベーターはかなりクリーンで安全な乗り物だと言えるのではないでしょうか。
えんえんと欠点をあげつらってきましたが、今のところ、地上と宇宙の間を往復する手段は、現実問題としてロケットしかない以上、ロケットの使用は是とするしかない。良くも悪くも、宇宙開発を支えてきた主役はロケットです。だからここで述べているのはあくまで推定比較であり、ロケットの全否定ではないことをご理解いただければと思います。
それに、軌道エレベーターが完成したら、ロケット開発はますます加速することでしょう。軌道エレベーターの投射機能も利用して、衛星や惑星、太陽系外などへ宇宙船や探査機を送り込む大規模な計画が可能にするはずで、それにはやはりロケットが重要な役割を果たすからです。昨年11月の国際会議で、ロケット技術者らしき人が、軌道エレベーターができたら商売上がったりだ、その辺をどう考えているのかと質問があったのですが、今からそこまで心配しなくても。。。(仮にそうでないとしても、なんで軌道エレベーターの研究者がロケット屋の生活に責任持たなくちゃなくちゃならんのだ。研究をやめろとでも言うのかよう)
軌道エレベーター派は、ロケットの歴史と人類社会への貢献に十分敬意と関心を払った上で、これらロケットを上回る根拠を示して軌道エレベーターの実現を目指します。全身全霊をもって、地上と宇宙の往復手段としてのロケットに引導を渡す。これこそ最大の礼儀というものでありましょう。
ロケットとの比較はこれにて終了。次回からの豆知識は新章に移る予定で、軌道エレベーターの欠点や負の面を紹介していきたいと思います。










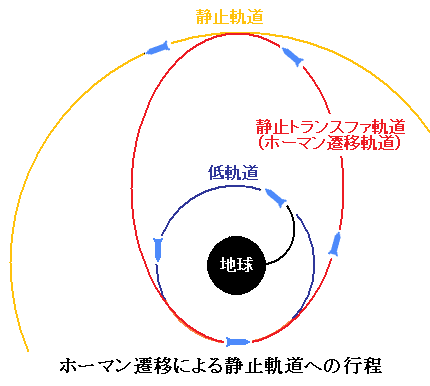

 実際には3倍どころでは済みません。たとえば日本のH-IIAは静止軌道まで最大約6tの質量を持ち上げられる能力を持っていますが、全重量約230tのうち、実に85%の約197tを燃料が占めます。米国のスペースシャトルなんざ、せいぜい高度600kmくらいの低軌道までしか上がれないのに、80t弱のオービターと最大約29tのペイロードを軌道に乗せるのに1200t以上(
実際には3倍どころでは済みません。たとえば日本のH-IIAは静止軌道まで最大約6tの質量を持ち上げられる能力を持っていますが、全重量約230tのうち、実に85%の約197tを燃料が占めます。米国のスペースシャトルなんざ、せいぜい高度600kmくらいの低軌道までしか上がれないのに、80t弱のオービターと最大約29tのペイロードを軌道に乗せるのに1200t以上( この時「軌道」だった理由について、先日お会いした際に金子氏にじかに質問をぶつけてみたのですが、「最初にそう呼んだのは誰なのかなあ?」と、詳しくご存じないようでした。
この時「軌道」だった理由について、先日お会いした際に金子氏にじかに質問をぶつけてみたのですが、「最初にそう呼んだのは誰なのかなあ?」と、詳しくご存じないようでした。
 iPhoneおよびiPod touch/iPad用アプリの電子書籍 "Space Elevator Pocketbook"(軌道エレベーターポケットブック)発売中。日英2か国語で動画付きです。
iPhoneおよびiPod touch/iPad用アプリの電子書籍 "Space Elevator Pocketbook"(軌道エレベーターポケットブック)発売中。日英2か国語で動画付きです。


