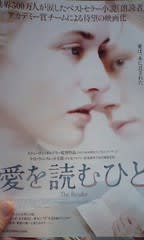
賞レースで名だたる名女優をおさえ、主演のケイト・ウインスレットが賞を総なめにした
「愛を読む人」。
ドイツ人の法律学の大学教授ベルンハルト・シュリンク氏が1995年に発表した原作は、、
世界で500万人が涙したベストセラーだとか。
日本でもミリオンセラーを記録したって、全く知りませんでした。
それじゃあ、映画を見る前に原作を読み終えるぞ~と読んでから見ることに・・・。
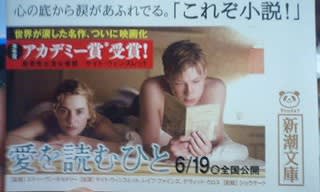









朗読者 DER VORLESER
愛を読む人 THE READER









< ストーリー>
15歳のぼく(マイケル)は母親といってもおかしくないほど年上の女性(ハンナ)と恋に落ちた。
ハンナはなぜかいつも本を朗読して欲しいと求める。人知れず逢瀬を重ねる二人。
だが、彼女は突然失踪してしまう。
数年後、法学専攻の大学生になったマイケルは、ユダヤ人収容所の看守だったことで被告として
裁判を受けるハンナと再会するが・・・。
どんなストーリーか全く知らないまま読み始めたので、
第一部の「こんなことが表ざたになったら『淫行』でハンナは逮捕されるんじゃない?」という
年の差カップルの危ない恋愛ドラマ?にビックリ!続く第二部・三部の驚くような展開に涙し、
引き込まれ、最後まで一気に読み終わりました。
映画では泣かなかったのですが、本を読んでいる時に2度ほど涙があふれました。
電車の中で最後のシーンに差し掛かり、「あか~ん、このまま読んだら泣く」と思い、
本を閉じ、家に帰ってから続きを読んだ次第です。
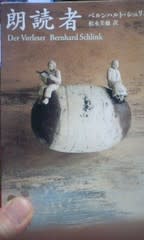

原作本と原作者のシュリンク氏
最初は本の感想を書こうと思ったのですが、考えが纏まらないまま映画の公開となり、
原作を引きずったまま映画を見て益々混乱し、時間がかかってしまいました。
文章か?映像か?
映画はやはりハンナとマイケルの関係を中心に、ハンナを引きずり続け、
助けられなかった罪の意識からテープを送り続けるマイケルを描いていますが、
原作ではマイケル(ミヒャエル)と父の関係、戦中派と戦後派の世代間の葛藤など
他のテーマにも触れています。
本を読んだ直後に見たからかもしれませんが、
本を読んだ時の方が裁判の緊張感やマイケルの心情がより迫ってきた気がします。
果たして原作を読んでいない人はどの時点でハンナの秘密に気付くのでしょう?
本では、裁判の最中、マイケルがハンナの言動や過去の記憶をたどって秘密に気付く場面で、
マイケル同様私まで驚きで息を呑みました。
「えー!そういうことだったの・・・」
映画では描かれていない自転車旅行での何気ないエピソードが秘密を知る決めてでした。
本でハンナの秘密を知って見ていたので、どこで、どんな風にマイケルは気付くのか?
そこに興味が集中してしまい、あの程度の描写で気付くかな?と疑問に思ってしまいました。
映画だけだったら、私は最後まで気付かなかったかも?
本をお読みでない方、どこで秘密に気付いたか、御教えいただければ嬉しいです。
映画の宣伝では、美しいケイトの脱ぎっぷりや、二人の秘密の関係に注目が集まりがちですが、
本の第一部での二人の関係は、過去のハンナの行動を思い出すことで裁判の行方の握る秘密に
マイケルのみが思い至るための伏線であるとともに、
ハンナの真面目で勤勉な人となりを知る上でも必要なんだなと感じました。
ハンナはその秘密ゆえ同年代の男性とは勿論のこと、
女性とも踏み込んだ友人関係を築くことはできなかったでしょう。
真面目な働きぶりで普通なら喜ばしい昇進話も、秘密を守るため別の地へ移らざるを得ない孤独の中で、20ほども年の離れたマイケルになら秘密を知られることなく付き合うことができるということだったのでしょうか?
裁判中の緊迫した言葉のやり取りの中、誤解され、一人で責任を背負わされ、
一人無期懲役を宣告されるも守り通した秘密。
一方、秘密に気付いたマイケルは減刑を得る為に秘密を明らかにすべきかどうか苦悩する。
本の中で、看守の仕事を履行したことで殺人罪にあたるとして問い詰める裁判長に
「あなただったらどうしましたか?」というハンナの問いかけが重い。
その質問に答えた裁判長の言葉、
「この世には、関わり合いになってはいけない事柄があり、
命の危険がない限り、遠ざけておくべき事柄もあるのです」は、
その状況にいなかった第三者だから言える言葉だよなぁ。
このような裁判は、ドイツ人の手でかつての収容所の看守達の戦争犯罪を裁くため1960年代半ばに実際に行われそうです。
ドイツでは、戦後20年経ってもこのような裁判が行われていたということに驚きました。
日本では、戦勝国による裁判はあったけれど、日本人が日本人戦犯を裁くことはなかったんじゃあないでしょうか?
ナチスの幹部が南米で発見され裁判なんてニュースは何度か耳にしましたが、
ドイツも、敗戦国として重いものを抱えているのだなということを改めて実感しました。

「何ができるかを見せるのではなく、何ができないかを隠すために闘ってきた」ハンナ。
強い知識欲を示していた彼女に、教育を受ける機会があったなら・・・と思わずにはいられません。
因みに・・・
『シュミット』というハンナの苗字、かつて西ドイツの首相もいらっしゃいましたが
英語では『スミス』で「鍛冶屋」を意味するそうです。
「硫黄島からの手紙」を見た時、こういう映画を日本で作んなきゃなぁ~と思ったように、
この映画もハリウッドでなくドイツでできなかったんでしょうか?
ドイツの俳優さんはあまり知らないけれど、
「マーサの幸せレシピ」や「善き人のためのソナタ」で主演したマルティナ・ゲデックさんに
ハンナを演じて欲しかったなぁ。(決してケイトに不満があるというわけではありません)
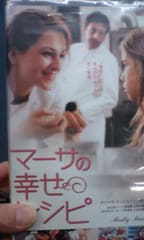

「幸せのレシピ」としてハリウッドでリメイクされましたがこちらの方が好き!
アカデミー賞にノミネートされる俳優さんは、どなたもこなたも実力者ぞろい。
ここで差が出るのは、やっぱり、美しい人の特殊メイクなんでしょうか?
(二コールしかり、シャーリーズ・セロンしかり・・・)
平井堅の歌は好きだけど・・・この映画のテーマ曲としては、全く合ってません。
なんでわざわざイメージソングなんてつけるんだろう?
「愛を読む人」というタイトルも如何なもの?「愛」つけりゃあいいってもんじゃあないよ!
「運命の衝撃が、ひと夏の恋を永遠の<愛>に変える」「少年に日の恋が、無償の愛へと変わるまで」
って「愛」のコピーが躍っているけれど、
マイケルがテープを送り続けたのは、秘密を知りながら救えなかったことへの償いなんじゃぁないのかなぁ。
少年時代のマイケルを演じたドイツの新人俳優デヴィッド・クロスは上手い~。
15歳というのはちと・・・いえ、かなり無理があるけれど(本当は何歳?)、
大学生になった時には明らかに大人になったという雰囲気が出ていて目を見張りました。
最後にアンソニー・ミンゲラ氏とシドニー・ポラック氏への追悼の言葉が・・・
亡くなったお二人がこの映画のプロデューサーだったのですね。 合掌。

*** 見た 映画 ***
6月23日 「愛を読む人」@TOHOシネマズ海老名
6月29日 「夏時間の庭」@銀座テアトル フランス映画
「TELL NO ONE」@有楽町 フランスのサスペンス映画
「愛を読む人」。
ドイツ人の法律学の大学教授ベルンハルト・シュリンク氏が1995年に発表した原作は、、
世界で500万人が涙したベストセラーだとか。
日本でもミリオンセラーを記録したって、全く知りませんでした。
それじゃあ、映画を見る前に原作を読み終えるぞ~と読んでから見ることに・・・。
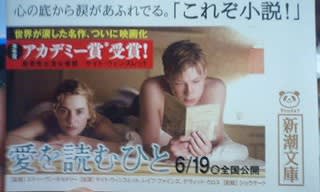









朗読者 DER VORLESER
愛を読む人 THE READER









< ストーリー>
15歳のぼく(マイケル)は母親といってもおかしくないほど年上の女性(ハンナ)と恋に落ちた。
ハンナはなぜかいつも本を朗読して欲しいと求める。人知れず逢瀬を重ねる二人。
だが、彼女は突然失踪してしまう。
数年後、法学専攻の大学生になったマイケルは、ユダヤ人収容所の看守だったことで被告として
裁判を受けるハンナと再会するが・・・。
どんなストーリーか全く知らないまま読み始めたので、
第一部の「こんなことが表ざたになったら『淫行』でハンナは逮捕されるんじゃない?」という
年の差カップルの危ない恋愛ドラマ?にビックリ!続く第二部・三部の驚くような展開に涙し、
引き込まれ、最後まで一気に読み終わりました。
映画では泣かなかったのですが、本を読んでいる時に2度ほど涙があふれました。
電車の中で最後のシーンに差し掛かり、「あか~ん、このまま読んだら泣く」と思い、
本を閉じ、家に帰ってから続きを読んだ次第です。
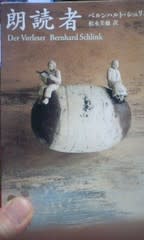

原作本と原作者のシュリンク氏
最初は本の感想を書こうと思ったのですが、考えが纏まらないまま映画の公開となり、
原作を引きずったまま映画を見て益々混乱し、時間がかかってしまいました。
文章か?映像か?
映画はやはりハンナとマイケルの関係を中心に、ハンナを引きずり続け、
助けられなかった罪の意識からテープを送り続けるマイケルを描いていますが、
原作ではマイケル(ミヒャエル)と父の関係、戦中派と戦後派の世代間の葛藤など
他のテーマにも触れています。
本を読んだ直後に見たからかもしれませんが、
本を読んだ時の方が裁判の緊張感やマイケルの心情がより迫ってきた気がします。
果たして原作を読んでいない人はどの時点でハンナの秘密に気付くのでしょう?
本では、裁判の最中、マイケルがハンナの言動や過去の記憶をたどって秘密に気付く場面で、
マイケル同様私まで驚きで息を呑みました。
「えー!そういうことだったの・・・」
映画では描かれていない自転車旅行での何気ないエピソードが秘密を知る決めてでした。
本でハンナの秘密を知って見ていたので、どこで、どんな風にマイケルは気付くのか?
そこに興味が集中してしまい、あの程度の描写で気付くかな?と疑問に思ってしまいました。
映画だけだったら、私は最後まで気付かなかったかも?
本をお読みでない方、どこで秘密に気付いたか、御教えいただければ嬉しいです。
映画の宣伝では、美しいケイトの脱ぎっぷりや、二人の秘密の関係に注目が集まりがちですが、
本の第一部での二人の関係は、過去のハンナの行動を思い出すことで裁判の行方の握る秘密に
マイケルのみが思い至るための伏線であるとともに、
ハンナの真面目で勤勉な人となりを知る上でも必要なんだなと感じました。
ハンナはその秘密ゆえ同年代の男性とは勿論のこと、
女性とも踏み込んだ友人関係を築くことはできなかったでしょう。
真面目な働きぶりで普通なら喜ばしい昇進話も、秘密を守るため別の地へ移らざるを得ない孤独の中で、20ほども年の離れたマイケルになら秘密を知られることなく付き合うことができるということだったのでしょうか?
裁判中の緊迫した言葉のやり取りの中、誤解され、一人で責任を背負わされ、
一人無期懲役を宣告されるも守り通した秘密。
一方、秘密に気付いたマイケルは減刑を得る為に秘密を明らかにすべきかどうか苦悩する。
本の中で、看守の仕事を履行したことで殺人罪にあたるとして問い詰める裁判長に
「あなただったらどうしましたか?」というハンナの問いかけが重い。
その質問に答えた裁判長の言葉、
「この世には、関わり合いになってはいけない事柄があり、
命の危険がない限り、遠ざけておくべき事柄もあるのです」は、
その状況にいなかった第三者だから言える言葉だよなぁ。
このような裁判は、ドイツ人の手でかつての収容所の看守達の戦争犯罪を裁くため1960年代半ばに実際に行われそうです。
ドイツでは、戦後20年経ってもこのような裁判が行われていたということに驚きました。
日本では、戦勝国による裁判はあったけれど、日本人が日本人戦犯を裁くことはなかったんじゃあないでしょうか?
ナチスの幹部が南米で発見され裁判なんてニュースは何度か耳にしましたが、
ドイツも、敗戦国として重いものを抱えているのだなということを改めて実感しました。

「何ができるかを見せるのではなく、何ができないかを隠すために闘ってきた」ハンナ。
強い知識欲を示していた彼女に、教育を受ける機会があったなら・・・と思わずにはいられません。
因みに・・・
『シュミット』というハンナの苗字、かつて西ドイツの首相もいらっしゃいましたが
英語では『スミス』で「鍛冶屋」を意味するそうです。
「硫黄島からの手紙」を見た時、こういう映画を日本で作んなきゃなぁ~と思ったように、
この映画もハリウッドでなくドイツでできなかったんでしょうか?
ドイツの俳優さんはあまり知らないけれど、
「マーサの幸せレシピ」や「善き人のためのソナタ」で主演したマルティナ・ゲデックさんに
ハンナを演じて欲しかったなぁ。(決してケイトに不満があるというわけではありません)
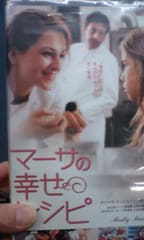

「幸せのレシピ」としてハリウッドでリメイクされましたがこちらの方が好き!
アカデミー賞にノミネートされる俳優さんは、どなたもこなたも実力者ぞろい。
ここで差が出るのは、やっぱり、美しい人の特殊メイクなんでしょうか?
(二コールしかり、シャーリーズ・セロンしかり・・・)
平井堅の歌は好きだけど・・・この映画のテーマ曲としては、全く合ってません。
なんでわざわざイメージソングなんてつけるんだろう?
「愛を読む人」というタイトルも如何なもの?「愛」つけりゃあいいってもんじゃあないよ!
「運命の衝撃が、ひと夏の恋を永遠の<愛>に変える」「少年に日の恋が、無償の愛へと変わるまで」
って「愛」のコピーが躍っているけれど、
マイケルがテープを送り続けたのは、秘密を知りながら救えなかったことへの償いなんじゃぁないのかなぁ。
少年時代のマイケルを演じたドイツの新人俳優デヴィッド・クロスは上手い~。
15歳というのはちと・・・いえ、かなり無理があるけれど(本当は何歳?)、
大学生になった時には明らかに大人になったという雰囲気が出ていて目を見張りました。
最後にアンソニー・ミンゲラ氏とシドニー・ポラック氏への追悼の言葉が・・・
亡くなったお二人がこの映画のプロデューサーだったのですね。 合掌。
*** 見た 映画 ***
6月23日 「愛を読む人」@TOHOシネマズ海老名
6月29日 「夏時間の庭」@銀座テアトル フランス映画
「TELL NO ONE」@有楽町 フランスのサスペンス映画










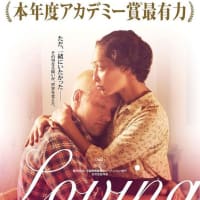









裁判ではみんな冤罪だって知ってるのに、終盤では本を読んだ人は彼女が重ーい罪を犯したと思い込んでしまっている。
生き残った娘も、責任者の顔は覚えていなくて、本を読ませる変な人は覚えているのだから、その変な人が責任者でないことを知っているはずなのに・・・。
「彼女を許すようでお金は受け取れません」といいました。
そんなに怒りが強いのなら、なぜ裁判のときに他の被告人を許したのでしょう?
主人公も面会のときに「たっぷり反省したか?」というような意味の問いかけをしていますが、冤罪のひとには普通は「大変だったね、お疲れ様」ではないでしょうか?
なんだか変な物語です。
コメントありがとうございます。
裁判ではマイケル以外の人はハンナが文盲であることを誰も知りません。
だから収容所でハンナに呼ばれた少女達が本を読まされていたとは思わず、良からぬ目的で夜な夜な呼んだ上、アウシュビッツのガス室に送り込んだひどい奴だと誤解しています。(マイケル・ジャクソンが少年をネバーランドに呼んで・・・という憶測と同じです)
そこで益々ハンナに対する憎悪が膨れ上がるわけです。
生き残った娘も当時は幼子で(友人に本を貸してしまって手元にないので何歳だったは正確にはわからないのですが、4~5歳だったのでは?この裁判は戦後20年経過していています)、責任者が誰であったかは知らなかったでしょう。
ただ自分の周りでハンナに呼ばれた子がその後いなくなったという記憶だけだったでしょう。
本では裁判でマイケルだけが冤罪であることに気付き、仕事を執行しただけでどうすればよかったのか?と正直に問うハンナに、他の被告達はこれ幸いと彼女を責任者に仕立て上げ罪を逃れようとするのです。
この裁判のきっかけは、生き残った娘が収容所でのことを本に書き出版したのが発端で、字の読めないハンナには告発内容もよくわかったいませんでした。
他の被告人たちも許されたのではなく、全員5年ほどの懲役刑を言い渡されましたが、責任者に仕立て上げられたハンナは終身刑/無期刑となりました。判決を言い渡したのはドイツの司法たる裁判官です。
生き残った娘は彼女達を刑に服させることでいくらか溜飲を下げたでしょうが、一生許すことはないでしょう。ユダヤ人組織は最近まで逃亡したナチの幹部を追っています。
知り合いのイスラエル人(戦争を知らない世代です)に、祖父母たちはポーランドで財産を没収(はっきり盗まれたと言ってました)されたと苦々しい口調で聞かされたことがあります。
>主人公も面会のときに「たっぷり反省したか?」というような意味の問いかけ
こんなシーンありましたっけ?ニュアンスが違うような気がします。テープを送り続け、出所後の面倒も見ようとしていたマイケルは、秘密を知りながら助けることができなかった自分の無力に負い目を感じて、だからこそ手紙に返事を書けなかったように感じました。
映画ではハンナの手紙はたどたどしい文字でしたが、本では読み書きを覚え、ナチス関連の本など難しい本を読みこなすまでになっていたようでした。
戦中派たるハンナと戦後派のマイケル、戦後ドイツの中で戦争責任をめぐる世代間の葛藤があり、溝が深かったようです。
因みに、エンディング等のマイケルと彼の娘との関係は本では全く出てきません。
これで、とおりすがりさんへの質問の答えになっているかどうか分かりませんが、短編ですので、是非本を読んでいただきたいなと思います。
上手くいえませんが、恋愛ドラマではなく、もっと深い、とても良い本でした。
マイケルも最初はハンナの秘密を知らず、裁判が進む中、過去の出来事を思い出し、ハッと彼女が文盲なのでは?気がつくのです。
そうすると、全てのことに思い至るという衝撃のシーンでした。
映画ではその辺がいま一つだったかなと、そこで、本を読んでいない方はいったいどこで秘密に気付くのか?と思いました。
コメントありがとうございました。
そうです。
Wikiediaによれば、デヴィッド・クロスは1990年7月4日生まれだそうです。
今は19歳ですけど、撮影当時は18歳ですね。
日本で言えば高校3年生ですが、日本の高校生でああいうベッドシーンはなかなか演じられないのではないでしょうか?
そういう意味では凄いと思いますね!
原作での設定は15歳ですが、18歳にあの役をやらせるって・・・。アメリカって未成年者の映画視聴の目安(レイティング)とか結構細かくうるさいのに、18歳を過ぎたら、見るのも演じるのもOKなんでしょうか?ドイツではどうなんでしょう?
この映画、私は手放しで好きだと言い切れませんが、ずっと後を引いてます。
原作は未読です。
映画を観る前に、騒がれてたハンナの秘密がまさか『それ』だとは思いませんでした。
私は、ハンナがマイケルに本の朗読をねだる最初のところで「あれ?」と思い、食事のメニューの件にて、はっきり分かりました。
自分のところでは書いてませんが、彼女のように識字力が低い人が身近に居たのです~あんなすごい美人ではありませんでしが(笑)
そう、ハンナと彼女をかなり重ねて見てました。
でも彼女は、家庭を築き友人もあったのが大きな違いでしょうか。
幼少より働きづめで文字を知らない悔しさを語るが、その中、家族を養い生き延びてきたという、彼女のあのプライドの高さの理由を、ハンナを見て初めて知っ
た気がします。そんな自分が情けなかったりもしました。あ、人様のとこで、こんな個人的なことを長々と書いて申し訳ございません。
ほんと、この映画って後引くわ~。
それ、よいですね。 私も彼女は好きです。
今度『クララ・シューマン』で主役なので、これも楽しみにしています。
ドイツ語だとなおよかった・・・ 確かに。そう思いました。
食事のメニューで確信をって、りでるさんするどいです。映画の描写では衝撃的に秘密を知るって感じではなかったので本を読んでいなかったら私は気付かなかったかもしれません。
身近にそういう方がいて、ハンデを跳ね返して頑張っておられる姿をご覧になっておられたということでより一層迫ってくるものがあるでしょうね。
貴重なお話ありがとうございます。
同じ映画を見ても、各々経験や感じ方が違うので身近に感じられたり、理解できなかったりってことありますものね。
>この映画って後引くわ~。
ほんとに考えさせられる深いストーリーだなぁと思います。私もいまだに引きずってます。
マルティナ・ゲデックさん、ピッタリですよね。
「クララ・シューマン 愛の協奏曲」ですね。
私もBunkamura ル・シネマでの公開を楽しみにしています