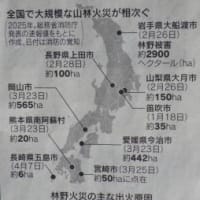旅先やレジャー施設などで身軽に動きたい。 そんなとき便利なのがコインロッカーです。
普段は目立たない存在ながら、登場から半世紀で機能は着実にアップしています。
「手荷物を預ける」にとどまらない実力派に育ってきているようです。
主要駅で増設が続くコインロッカー。 大きなスーツケースを預ける外国人も多くいる。
日本の安心・安全な街を象徴する光景だが、その原点はいつごろだったのだろうか?

東京五輪が開かれた1964年のこと。 シリンダー錠製造・販売の国産金属工業(現
アルファ、横浜市)が米社と組みコインロッカーの展開を始めたそうだ。
新宿駅に「セルフサービス(携帯品)一時預かり」と大きく書かれた“箱”の集合体が出現。
縦5段、横12列の小箱が並ぶ様子は近未来的に映ったに違いない??
当時の荷物預かり所といったら有人だったので、使い方がわからない人が多くいらして
説明係がいたという・・? (当時、私はもう東京にいましたが気づきませんでした)
普及に弾みがついたのは夏のプールだったという。 「必ずみな水着に着替えるので、
服をしまう所が必要だった」。 アルファロッカーシステム(横浜市)の“柳内社長”は
そう説明しています。 当然、夏しか需要がないが、くしくも世の中はスキーブーム
の幕開け期だった・・!
ロッカーのアフターサービスなど関連事業を手掛ける勇気屋エンタープライズ(東京・中央)
“内田取締役”は、夏の営業を終えたコインロッカーをスキー場へ運んだ当時の経験を
振り返る。 「神奈川県の葉山のプールから新潟県内のスキー場まで約300㌔。
箱を運ぶので『ハチミツ屋』と呼ばれていたものです」・・と。
70年の大阪万国博覧会などを経て、その後もコインロッカーは広がりを続けたそうだ。
沖縄の那覇空港にはサーフボードをまるごと預けられる超大型のロッカーも登場。
標高1400㍍の南アルプスにある山小屋にもロッカーが備え付けられています。
コインロッカーの仕組みを少し見てみましょう。 荷物を収め、紙幣を投入して鍵をか
ける・・。シンプルなようだが、実は奥深い。 駅のロッカーは当初、終電から始発
までは人の手で施錠していた・・が、60年代半ばに、終電を過ぎると翌日分の追加
料金が加算される「日送り」の仕組みができ、荷物を複数日預けられるようになった。
近年はICカードを鍵代わりに、認証や決済できるシステムや、駅構内の空きロッカー
を時間差なく確認できるサービスも始まりました。
「手荷物を預ける」という本来の用途を超えた使い道も出てきそうだ。 アルファロッ
カー社とKDDI、西武鉄道が実証実験中の「ラクトル」はその一例。 ネット通販
で買い物した食品や生活雑貨を、最寄駅のコインロッカーで受け取れるというもの。
郊外暮らしで帰宅が遅い人でも、地元の店の閉店時間を気にせずに買い物することが
できる。 預ける店と受け取る消費者を取り持つのはスマートフォンのアプリに届く
6桁のパスワード。 コインロッカーがICカードなどのデジタル技術に積極対応し
てきたことが役立った形のようです。 やり取りする商品は様々に広がる可能性があ
る。 通勤・通学で毎日朝晩使う駅に近い将来、多忙な現代人の時間を節約する魔法
の箱が現れるかもしれませんな~・・。
アルファロッカー社の柳井社長は「ニッチだが日本の社会に不可欠なインフラ。 付加
機能を取り込み、多くの人が使えるサービスを提供したい」と話しています。
コインロッカーの歴史は、まさに日本の「セルフサービス」化の流れと重なる。 誰も
が気軽に使える利便性は、様々なトラブルへの対応など、緻密なサポート体制によっ
て支えられてきました。 半世紀を歩んだコインロッカーからは、日本人のニッチで
もキッチリのサービス精神までも伺えるのではないでしょうか・・。
普段は目立たない存在ながら、登場から半世紀で機能は着実にアップしています。
「手荷物を預ける」にとどまらない実力派に育ってきているようです。
主要駅で増設が続くコインロッカー。 大きなスーツケースを預ける外国人も多くいる。
日本の安心・安全な街を象徴する光景だが、その原点はいつごろだったのだろうか?

東京五輪が開かれた1964年のこと。 シリンダー錠製造・販売の国産金属工業(現
アルファ、横浜市)が米社と組みコインロッカーの展開を始めたそうだ。
新宿駅に「セルフサービス(携帯品)一時預かり」と大きく書かれた“箱”の集合体が出現。
縦5段、横12列の小箱が並ぶ様子は近未来的に映ったに違いない??
当時の荷物預かり所といったら有人だったので、使い方がわからない人が多くいらして
説明係がいたという・・? (当時、私はもう東京にいましたが気づきませんでした)
普及に弾みがついたのは夏のプールだったという。 「必ずみな水着に着替えるので、
服をしまう所が必要だった」。 アルファロッカーシステム(横浜市)の“柳内社長”は
そう説明しています。 当然、夏しか需要がないが、くしくも世の中はスキーブーム
の幕開け期だった・・!
ロッカーのアフターサービスなど関連事業を手掛ける勇気屋エンタープライズ(東京・中央)
“内田取締役”は、夏の営業を終えたコインロッカーをスキー場へ運んだ当時の経験を
振り返る。 「神奈川県の葉山のプールから新潟県内のスキー場まで約300㌔。
箱を運ぶので『ハチミツ屋』と呼ばれていたものです」・・と。
70年の大阪万国博覧会などを経て、その後もコインロッカーは広がりを続けたそうだ。
沖縄の那覇空港にはサーフボードをまるごと預けられる超大型のロッカーも登場。
標高1400㍍の南アルプスにある山小屋にもロッカーが備え付けられています。
コインロッカーの仕組みを少し見てみましょう。 荷物を収め、紙幣を投入して鍵をか
ける・・。シンプルなようだが、実は奥深い。 駅のロッカーは当初、終電から始発
までは人の手で施錠していた・・が、60年代半ばに、終電を過ぎると翌日分の追加
料金が加算される「日送り」の仕組みができ、荷物を複数日預けられるようになった。
近年はICカードを鍵代わりに、認証や決済できるシステムや、駅構内の空きロッカー
を時間差なく確認できるサービスも始まりました。
「手荷物を預ける」という本来の用途を超えた使い道も出てきそうだ。 アルファロッ
カー社とKDDI、西武鉄道が実証実験中の「ラクトル」はその一例。 ネット通販
で買い物した食品や生活雑貨を、最寄駅のコインロッカーで受け取れるというもの。
郊外暮らしで帰宅が遅い人でも、地元の店の閉店時間を気にせずに買い物することが
できる。 預ける店と受け取る消費者を取り持つのはスマートフォンのアプリに届く
6桁のパスワード。 コインロッカーがICカードなどのデジタル技術に積極対応し
てきたことが役立った形のようです。 やり取りする商品は様々に広がる可能性があ
る。 通勤・通学で毎日朝晩使う駅に近い将来、多忙な現代人の時間を節約する魔法
の箱が現れるかもしれませんな~・・。
アルファロッカー社の柳井社長は「ニッチだが日本の社会に不可欠なインフラ。 付加
機能を取り込み、多くの人が使えるサービスを提供したい」と話しています。
コインロッカーの歴史は、まさに日本の「セルフサービス」化の流れと重なる。 誰も
が気軽に使える利便性は、様々なトラブルへの対応など、緻密なサポート体制によっ
て支えられてきました。 半世紀を歩んだコインロッカーからは、日本人のニッチで
もキッチリのサービス精神までも伺えるのではないでしょうか・・。