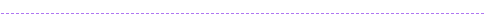江戸時代の初期の四国・土佐藩家老”野中兼山”は、
土佐藩の新田開発や港湾建設で有名な人だが、
失脚後、一族が長期間幽閉されたのもよく知られている。
幽閉されていたのは現在の宿毛市立宿毛小学校の校地。
校地内には記念碑や多くの説明板が建ち、
野中一族の功績や、一族の幽閉の史実を長く伝えていくという意思が伝わる。
宿毛小学校の説明板。↓
野中兼山一族の幽閉
野中兼山は江戸時代、土佐藩(今の高知県全域)の奉行で、藩内の政治のリーダーでした。
兼山は新田を開発したり、港を築いたり、お米の値段を調整したり、次々と新しい仕事を実行しました。
宿毛でも、河戸堰や宿毛総曲輪 (堤防)を築いたり、沖の島や山でおきた国境争いを解決しました。
しかし、兼山のやり方はとても強力だったので、各地で反発を生み、結局、奉行を辞めて隠居します。
そして その直後、四十九歳で死去してしまいました。
ところが、それでも反発の声はやみません。
兼山の政治が土佐藩の人々を苦しめたといって、兼山の子どもたちに、その罪を負わせることになったのです。
親の罪が子にもおよぶ時代でした。
子ども八人は宿毛に送られ、今の宿毛小学校のプールの場所に幽閉されました。
一番幼い貞四郎は、まだ二歳でした。
竹で囲まれた家での外には出られない生活の間に、子どもたちは成長し、そして次々に亡くなりました。
四女の婉は、兄、姉を失う悲しみを和歌を詠みます。
つらなりし梅の枝枯れゆけば のこる梢の涙なりけり
つらなる梅の立枝が枯れていくと、のこる小枝は涙を流すばかりだ。
約四十年という長い長い年月が過ぎ、男子の全員が亡くなると、
寛、婉、将の三人の女子だけが、ようやく釈放されました。
釈放された三人の内、婉は今の高知市朝倉に移って医者になったということです。
この婉の生涯は、高知県出身の大原富枝の小説『婉という女』で紹介され、大きな反響を呼びました。
・・・
旅の場所・高知県宿毛市桜町
旅の日・2018.10.3
書名・婉という女
著者・大原富枝 講談社 2005年発行
・・・

「婉という女」
第一章 赦免ということ
今日、安東家からお使者が見え、藩府からの赦免状を受けた。
お使者の帰ったあと、母上を中に、乳母、姉上、妹と相擁して泣いた。
八十を越えた母上と、六十五歳の乳母、姉妹たちもみんな四十をすぎた老嬢ばかり、
こうして相擁して泣いている涙も一人一人が別であった。
「野中婉、四歳にして獄舎に囚われ、九十歳の生涯をここに置く」
もしも墓碑銘を刻むことが許されたら、そう記して貰おう。
わたくしは遂に生きたことはなかったのだ。
門外一歩を禁じられ、
結婚を禁じられて、四十年間をわたくしたちはここに置かれた。
他人との面会を許されず、他人と話すことを許されないで、わたくしたち家族はここに置かれていた。
わたくしたち兄妹は誰も生きることはしなかったのだ。
ただ置かれてあったのだ。
四十年の間に、わたくしの兄姉は次々に死んでいった。
生き残った三人の姉妹のうち、姉上と妹は同腹のきょうだいであった。
二人はわたくしのように赦免を待ち望んではいなかった。
ほとんど迷惑に思っていた。
彼女たちはいった。
いまさら自由になって何としましょうぞ、 路頭に迷うばかりでございます。
このまま、生涯をここで終る方がようございます。
見たこともない新しい世界への不安と怖れは、勿論わたくしにもあった。
ましてこの四十をすぎた異腹の姉妹たちは、
もはや生涯を終っていた。
一度も生きることなく、彼女たちはすでに生涯を終っていた。

第四章 生きること
まず高知のお城や町を見たい、という母上のおのぞみで、駕籠は遠廻りしてゆくことになった。
城下にはいったのは日も暮れ方で、商いの家並もまだ灯は入れず、夕映えの反照で赤っぽい明るさの往来を、
慌しく人々が往き交うているのを、わたくしは心緊まる思いで眺めた。
井口の老人に出迎えられ、わたくしたちは駕籠を止めてお城を仰ぎ見た。
白堊三層の天守閣は、夕映えを背に淡紅色に 壁を染めて聳えていた。
権力と権威を誇示するためには、このような玲瓏な形式と結構の美しさが必要なのだ。
政治という怪物めいたものが生れるには、このような優美な高楼がなければならないのだ。
泰山先生とのおめもじは、ある日思いがけなく訪れた。
飄然と、まったく飄然と先生はその日お見えになったのだ。
「おお、お婉どのかー」
乳母と日毎薬湯をつくり、丸薬を練る。
越鞠丸と名づけて旧臣のものの行商に委せる。
一人二人、診察を乞う人もきて、いささかの銭や米、野菜などがわたくしに与えられる。
こうしてわたくしの生活の道も、ささやかながらなりたってゆくようであった。
帰国されてからの先生は、江戸の渋川先生、貝原益軒先生、安家博士などと、ご研鑽の
御状おとり交しに以前にもまして忙しく、講義も絶えてなくおめもじの機会はなかった。
--母上をお送りしてわたくしの毎日は一層自由を加えた。
貧しい病人を診てやり、惜しげなく薬をあたえ、のどかな生れつきの老いた乳母と二人、興のおもむくまま読み耽ることもできた。
享保五年が明け、そしてこの年も暮れた。
享保六年、宿毛から、妹、将女の死を告げるたよりが遥々と届いた。
涙もこぼれず、わたくしは乾いた眼にそれを読み、丹念に畳んでいった。
幽獄を出て十九年、ここでもまた、わたくしの周りには夥しく死が堆積した。
わたくしはそして六十一歳になった。
こうして、孤りここに生きている。これからも、生きてゆく・・・。