一度、奈良県の生駒山にある信貴山に行ってみたいものだと思っていた。
大阪から電車とバスに乗り継ぎ、やっとのことで信貴山の「朝護孫子寺」に着いた。広大な境内は山頂に「信貴山城跡」、
山門との間には、「本堂」をはじめ
「千手院」「本坊」「成福院」「玉蔵院」他の伽藍が並んでいた。
しかし圧倒的な印象を残したのは小さな建物「霊宝館」で、
そこに展示された国宝 「信貴山縁起絵巻」だった。
鉢が空を飛び、
米俵が舞い上がる、
童子が大空を駆けめぐる。
摩訶不思議なストーリーと躍動感。
信貴山に来てよかった、そう思った。

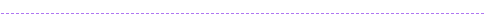
旅の場所・奈良県生駒郡平群町”信貴山”朝護孫子寺
旅の日・2021年12月1日
原作・宇治拾遺物語
原作者・不明
現代訳・「今昔物語 宇治拾遺物語」 世界文化社 1975年発行

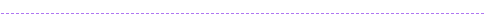
信貴山の縁起にまつわる事
これも昔の話だが、信濃の国に住む法師、なんとしてでも京へ上り、戒を受けようと志し、あれこれ算段の末、首尾よく、受戒できたのだった。
願いかなって、信濃へ帰ろうと思ったが、しかし心がすすまぬ、仏様のいない場所へもどるのは甲斐のない気がして、
東大寺の本尊の前にひれ伏し、どこか修行するにふさわしく、また、のんびり暮すことのできる場所はないものかと、
周囲ながめわたせば、西南の方角に山が、かすかに見えた。
あの山で、暮そうと考え、たどりついて、修行の明け暮れ過ごすうちおのずからちいさな仏像を授かった、
毘沙門様だった。
貧しいながら堂を建立申し上げ、お祀りして、 さらに修行に励んでいたのだが、
この山のふもとに、身分はいやしいが、たいへん裕福な人が住んでいて、常日頃、法師の食器は、ここへとんでいっては、なにがしの喜捨を受けてもどる。
しかし、金持は、すっかり鉢を忘れてしまい、喜捨をしないどころか、そのまま倉の戸を閉めて、帰ってしまったのだ。
そして、しばらくしたところ、この倉はひとりでにゆらゆらとゆれ動き、
「どうしたことだ、これは」人々さわいで見守るうち、さらにひどくゆれて、遂には地上から一尺ばかり浮き上り、
あれよあれよと、仰天して、みな見守るばかり。
やがて、鉢が倉からとび出し、おどろいたことに、鉢の上に倉をのせて、ゆらりと一、二丈持ち上げ、とび立ったから、さあ、大騒ぎ。
どこへとんで行くのか、見とどけようと、鉢の後を追い、弥次馬もつき従う。
鉢はかまわずとびつづけ、河内の、法師がもとへどしんと倉を投げ置いた。
この金持、法師に近づいて、未練がましく、
「これはたいへんな珍事でございます。どうか、返していただきたい」
というと、 法師は、
「丁度、物置きがひとつ入用だったのだ。
しかし、中のものは、そっくりお返しいたします」
と、法師が、鉢の上に一俵を置いて命じると、雁がとぶように、残りの俵もつづいて空中をとび、
千石の米俵の乱れとぶさまは、群雀の如く、金持はじめ、あらためて不思議さに恐れ入った。
・・・
このようにして、なお一心に修行をつづけるうち帝が御不例となり、
「河内の信貴に 近頃尊い法師がおられます。
ただ一人山中 にこもって修行なされたいへんな奇蹟をあらわす方、ある時は鉢をとばすなどなされ、しかも、それをほこりもせずひたすら仏に帰依し、困っているものを助けます。
かの法師を召して、お力をかりれば、さだめし御本復」と進言した。
帝の御不例を治してもらいたいとのたっての頼みに、
「それなら、ことさら参るまでもございません。 ここで祈禱たします」
帝もすこやかなお体にもどる。人々は、みなよろこび、いっそう法師を尊んだのだった。
この法師に一人の姉がいて、たいへん心配し、弟の後を追い上京し、東大寺、山階寺のあたりを、たずね歩いた。
しかし、誰も、弟の消息を知る人はなく、探しあぐね、東大寺の大仏の前に、夜を徹して祈りつづけ、暁ついまどろんだその夢に、仏があらわれて、
「たずねる僧は、西南の方角の山に居る、その、雲のたなびくあたりを探せ」とおっしゃる。
夢からさめれば、すでに夜は明けはなたれようとしていて、しかし姉は一刻も心せき、早く陽がのぼればと思ううち、本当に姉の気持を知ったかの如く、はやばやと 朝が訪れた。
そして、おつげ通りの方角に、山が見え、しかもかすかに紫の雲さえたなびいているから、うれしく心強く、たずねていくと、ちゃんと御堂があるではないか。
人の 気配をうかがって、「明蓮小院はいらっしゃいますか」 呼びかける。
「どなたですか」と、法師が表へ出れば、故郷の姉が、そこにいる。
「いったいどうしてここが分りました。こ れはおどろいた」と、とりあえずこれまでのいきさつを物語る。
「いえ、どんなにか寒く過しているだろうと、 これを持ってまいりました」姉はいいつつ、ふつうより 太目の糸で、ふっくらと暖かそうに編んだ胴着をひき出し、わたしたから、米も地位も土地も、いっさい無用と観じている法師も、姉の好意はよろこんでうけとった。
それまで法師は、紙衣一枚で冬さえ過ごし、寒さに耐えられぬ夜もあったけれど、この胴着を下に着て、以後はあたたかくくらし、なお修行をうむことなくつづけ、 また、この姉も、尼であったから、弟に従って山へこもり、仏に仕えることとなった。
信貴の本尊は、明蓮法師が、修行して、おのずと授ったあの毗沙門様であると、いわれている。
(巻八・第三)

・・















