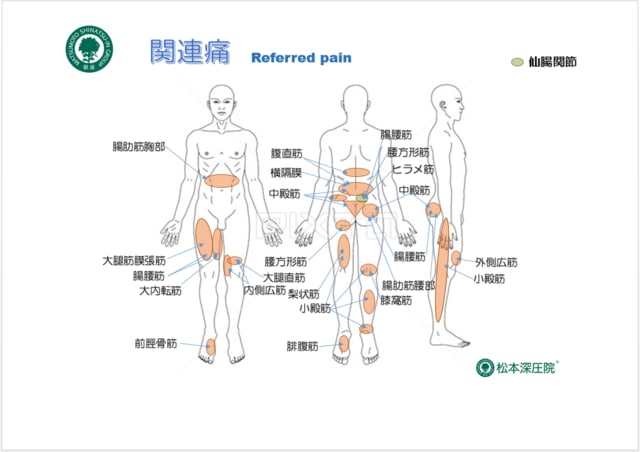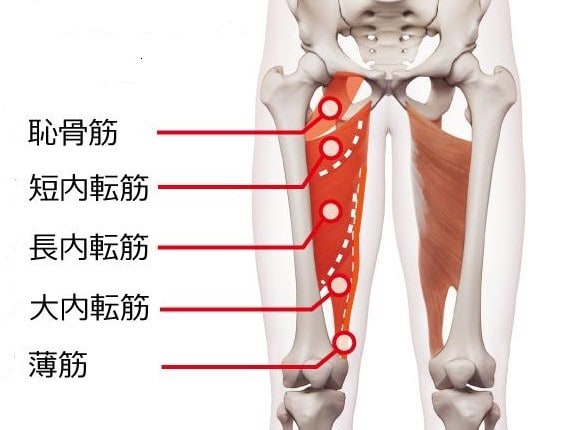🍓今まで説明した股関節痛に対する対策として手術療法は含んでいませんでしたが、最後に手術療法にも触れておきます。
私は手術をすることには反対ではありません。
しかし、レントゲンだけの診断で軟部組織に対する治療がなされないまま手術に踏み切ることには大反対です。
軟部組織、特に筋肉への治療のみで手術を避けられた方々と多くお会いしてきたていますので、まずは筋肉を正常化してみることにトライするべきだと考えています。
それでも、満足がいかない時には手術を受ければいいと思います。
股関節痛の程度には個人差が大きく、自分の我慢の限界を超える股関節痛を感じる方もいます。
そのような方は、手術の適応と考えますが、自分の我慢の限界を迎える前に股関節痛が改善に向かう方も意外と多いのです。
『手術の時期は患者さん自身が決めるもの。』という考え方が一般的です。
しかし、そう言いながら整形外科の先生が手術を勧めることが多いように感じます。
私は手術療法の利点も理解していますので、実際に私の担当する患者さんの25%は何らかの手術療法を受けています。
しかし、私は『手術した方がいいですよ。』と話すことはありません。
皆さんの中で、手術療法を受けようかどうか悩んでいる方も多いと思います。
多くの方は、股関節痛が強く出ていると『手術療法を受けようかな』と考え、股関節痛が治まると『やっぱりやめた。』と考え心が揺れています。
私は、『手術を受ける時期を逃して手術が困難になる』ことはないと考えていますし、私が名医と思う先生もそのように患者に説明しています。
経験が豊富で腕に自信のある整形外科医は『手術を受ける時期を逃して手術が困難になる』という言葉は使わないと私は考えています。
手術を受ける時期は、皆さんが『手術をしたい』と思うときだけです。
「先生、私手術をしようと思います。」
私は担当患者からこう言われた瞬間から手術に向かう考え方を話し、患者の満足のいく手術が受けられるよう病院や先生を紹介し、手術前後の経過を良くするための深圧を行います。










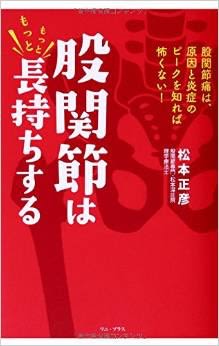



 半円まくら(特大)
半円まくら(特大)
 PGE2は痛み成分
PGE2は痛み成分 KL-1βは炎症成分
KL-1βは炎症成分 MMP‐1は軟骨成分分解酵素
MMP‐1は軟骨成分分解酵素