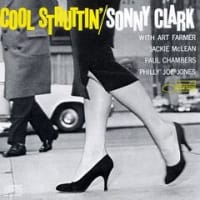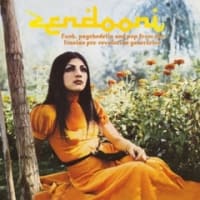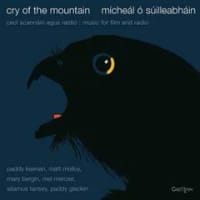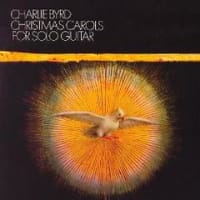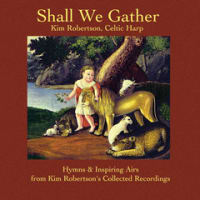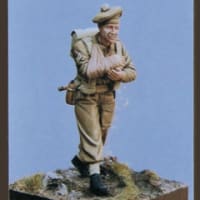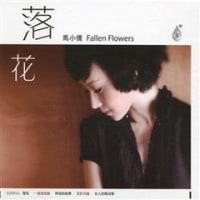”Souk System”by Gnawa Diffusion
ワールドもの方向では話題のグループと言うことでありますな、グナワ・ディフュージョン。
グループ名の”グナワ”は、かって北アフリカ在住のアラブ系住民に奴隷として使われていた黒人たちを指す言葉だそうな。とはいえ、このバンドがその種の人々の末裔によって構成され、ストレートにグナワの音楽を演じているわけではなく、その衝撃的な概念をバンド名に掲げることに意義を見出しているようだ。
バンドの中心人物は北アフリカ出身のなにやら高名な作家の息子というが、ともかく”グナワ”ではなくアラブ系の血筋に連なる人物である。十代で亡命中の父を追い、フランスに渡り、そのままその地で音楽活動を続けて来た。
バンドの歌は、アラブ音楽の要素とレゲのリズムが入り乱れるサウンドを伴いつつ、アルジェリア社会の矛盾、フランスに生きるアラブ系をはじめとした移民たちの置かれている過酷な現実、などに問いを突きつけているようだ。とは言うものの。CDに付されている収録楽曲の歌詞日本語訳などに目を通すと、その生硬な言葉の羅列には、ちょっとうんざりさせられるところがある。
まあ、青少年の頃には、この種の歌に接して熱くなったりするものです、「凄いんだぞ、彼らの政治的主張は!嘘っぱちなこの社会を鋭く突いているんだ!」とかね。
でも、生きて来た時代が時代で、その種の”運動”に関してはさまざまな幻滅を味わいつつ今日まで来たオジサンとしては、ちょっと辟易するところがあるわけだ。
その辺りで生じた、このバンドの音に対する疑問は、結局、アルバムを聞き終えても解消されることは無かった。
このバンドの純・音楽上の醍醐味というのは、砂漠にすむ蛇の如くにうねるアラビックな音楽要素が、世界の”抵抗音楽”の定番と化したレゲのリズムに乗って強引に突き進むところにあると思うのだが、そのスリリングな音楽のありように、どこか頭で音楽をやっている者の脆弱さもまた感じてしまうのだ。
”革命戦士たる音楽家”なんかより、能天気な恋歌を土着の音で野太く提示する銭金目当ての”バンドマン”連中の方が、その存在としてはよっぽど革命的なんだよな、いつも。そして、こんな事を言うと”反革命”のレッテルを貼られてしまうのもいつものことなんだが。
何ぞとぼやいていてもしょうがないのだが、彼ら、先に書いた”アラブ=レゲ”を、政治的主張なんかこっちにおいておいて、あくまで音楽的に研ぎ澄ましてみたらいいんじゃないかなあ。アラブの伝統的音楽を、都市型の悪意を秘めた現代に生きる音楽に再生させる道は、確かに開けて見えるのだから。
なんて事を言っても、頭に血を登らせた若き音楽戦士諸君には通じる話じゃないんだけどね、うん、私も青二才だった一時期、そんなだったからさ。それは分かっているんだけれど。