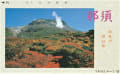日本の温泉シリーズは今まで、どちらかと言えばテーマ別に書いていたと思う。「十勝平野のモール泉」とか「温泉のあるクラシックホテル」とか。それも毎回では大変なので、今回からしばらく日本の各地の素晴らしい温泉宿を紹介していくことにしたい。それもあまり人が知らない、団体旅行では行かないような温泉を中心にしたい。だから「超有名秘湯」(鶴の湯温泉とか法師温泉など)は取り上げない。
北からと言うことで、北海道の銀婚湯温泉をまず書いてみたい。北海道には登別温泉、洞爺湖温泉、湯の川温泉など大きな温泉街と持つところも多いし、山の中にある一軒宿の秘湯も多い。支笏湖畔の丸駒温泉、帯広北方の然別峡かんの温泉など素晴らしい温泉だ。そっちも書きたくなるが、ここでは道南の「銀婚湯温泉」にした。
 (大浴場)
(大浴場)
名前が不思議だが、これは開湯が1924年(大正14年)5月10日で、その日が大正天皇の「25年目の結婚記念日」、つまり銀婚式の日に当たったからだという。だから、もうすぐ100年を迎える長い歴史を持つ宿なのである。名前から銀婚式に夫婦で訪れる客がいっぱいいるという。僕が行ったのは結婚10数年の時だったが、お湯も食事も素晴らしかったから、また25年目に行こうかと思ったけれど、その後一度も行けてない。
北海道に行くのは大変だけど、行くなら他に行きたいところがいっぱいある。団体旅行なら当然だが、個人で行く時も主要な観光地を短時間でまわることが多い。道南だと函館が中心になり、そこには湯の川温泉がある。ちょっと行った大沼にも温泉がある。銀婚湯温泉はちょうど函館と長万部の中間あたりの山の中にあって、周辺に有名観光地がないから通り過ぎてしまうエリアなのである。ホームページを見ると、函館本線の各駅停車しか泊まらない落部駅というところで下りれば、一人客でも送迎ありと出ているけれど、行きにくい場所である。

では一軒家の秘湯かというと、実は「上の湯温泉」(かみのゆ)という二軒宿の温泉郷となっている。もう一軒はパシフィック温泉ホテル 清龍園という宿である。でも広大な敷地に5本の独自源泉を持ち、森の中の秘湯と呼んでも間違いない宿だ。もう完全に都会を遠く離れた宿なので、風呂や食事のレベルはどうなんだろうと思っていた。ところがこれが素晴らしいお風呂で、しかも料理も美味しい。実に洗練された宿だったのに驚いた。

お風呂は内湯の大浴場の素晴らしさはよく覚えている。しかしホームページ上には森の中の「隠れ湯めぐり」が載っている。これは記憶がないんだけど、その後整備されたのか、それとも大雨の日で行かなかったのだろうか。なんともステキな風呂の写真が出ていて、2泊ぐらいしてノンビリしたくなる。「かけ流しシステム」として5本の源泉がどのように配湯されているのかがホームページに載っているのも貴重。お湯は透明なナトリウム泉がベースだが、とても柔らかな感じだった記憶がある。
何でも江戸末期の探検家松浦武四郎も来たり、あるいは箱館戦争の旧幕府軍も入った記録があるとか。車でも電車でも噴火湾の素晴らしい光景が望める。昔行ったときは「ケンタッキーフライドチキンの実験農場」があって寄った記憶がある。今は「ハーベスター八雲」という丘の上のレストランになっているようだ。函館と札幌の途中でもう一泊していくというのは、なかなか日程に余裕がないと出来ないと思うが、銀婚カップルでわざわざ行ってみる価値は大いにある。もちろんひとり旅でも、若くても老年でもいいわけだが。
北からと言うことで、北海道の銀婚湯温泉をまず書いてみたい。北海道には登別温泉、洞爺湖温泉、湯の川温泉など大きな温泉街と持つところも多いし、山の中にある一軒宿の秘湯も多い。支笏湖畔の丸駒温泉、帯広北方の然別峡かんの温泉など素晴らしい温泉だ。そっちも書きたくなるが、ここでは道南の「銀婚湯温泉」にした。
 (大浴場)
(大浴場)名前が不思議だが、これは開湯が1924年(大正14年)5月10日で、その日が大正天皇の「25年目の結婚記念日」、つまり銀婚式の日に当たったからだという。だから、もうすぐ100年を迎える長い歴史を持つ宿なのである。名前から銀婚式に夫婦で訪れる客がいっぱいいるという。僕が行ったのは結婚10数年の時だったが、お湯も食事も素晴らしかったから、また25年目に行こうかと思ったけれど、その後一度も行けてない。
北海道に行くのは大変だけど、行くなら他に行きたいところがいっぱいある。団体旅行なら当然だが、個人で行く時も主要な観光地を短時間でまわることが多い。道南だと函館が中心になり、そこには湯の川温泉がある。ちょっと行った大沼にも温泉がある。銀婚湯温泉はちょうど函館と長万部の中間あたりの山の中にあって、周辺に有名観光地がないから通り過ぎてしまうエリアなのである。ホームページを見ると、函館本線の各駅停車しか泊まらない落部駅というところで下りれば、一人客でも送迎ありと出ているけれど、行きにくい場所である。

では一軒家の秘湯かというと、実は「上の湯温泉」(かみのゆ)という二軒宿の温泉郷となっている。もう一軒はパシフィック温泉ホテル 清龍園という宿である。でも広大な敷地に5本の独自源泉を持ち、森の中の秘湯と呼んでも間違いない宿だ。もう完全に都会を遠く離れた宿なので、風呂や食事のレベルはどうなんだろうと思っていた。ところがこれが素晴らしいお風呂で、しかも料理も美味しい。実に洗練された宿だったのに驚いた。

お風呂は内湯の大浴場の素晴らしさはよく覚えている。しかしホームページ上には森の中の「隠れ湯めぐり」が載っている。これは記憶がないんだけど、その後整備されたのか、それとも大雨の日で行かなかったのだろうか。なんともステキな風呂の写真が出ていて、2泊ぐらいしてノンビリしたくなる。「かけ流しシステム」として5本の源泉がどのように配湯されているのかがホームページに載っているのも貴重。お湯は透明なナトリウム泉がベースだが、とても柔らかな感じだった記憶がある。
何でも江戸末期の探検家松浦武四郎も来たり、あるいは箱館戦争の旧幕府軍も入った記録があるとか。車でも電車でも噴火湾の素晴らしい光景が望める。昔行ったときは「ケンタッキーフライドチキンの実験農場」があって寄った記憶がある。今は「ハーベスター八雲」という丘の上のレストランになっているようだ。函館と札幌の途中でもう一泊していくというのは、なかなか日程に余裕がないと出来ないと思うが、銀婚カップルでわざわざ行ってみる価値は大いにある。もちろんひとり旅でも、若くても老年でもいいわけだが。