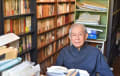2月9日になって、映画監督小沼勝の訃報が報道されたので、①に追加した。芸能界以外で一番知られた物故者は、プロ野球選手の門田博光(かどた・ひろみつ)だろう。1月24日に亡くなっているのが見つかった。74歳。1969年に南海ホークスに入団。2年目に打点王を獲得した。その後、一本足打法でホームランを量産し、通算567本は王、野村に次ぐ歴代3位の記録になっている。1988年には40歳にしてホームラン、打点で2冠を獲得しMVPとなり「中年の星」と呼ばれた。89年にオリックス、91年にダイエー(現ソフトバンク、元南海)に移籍し、92年に引退。名前は有名だったが、テレビなどで見た記憶はほとんどない。野球のテレビ中継が毎日あった時代だが、それはほぼ巨人戦オンリー。日本シリーズにも1回(南海時代に)出ただけ。88年の活躍も家でテレビを持ってなかったから見てない。引退後は指導者にならず評論家をしていた。
 (2006年、殿堂入り表彰時)
(2006年、殿堂入り表彰時)
歴史小説家の永井路子が1月27日に死去、97歳。歴史小説の多くが戦国か幕末かを舞台にするのに対し、永井作品は古代、中世を扱ったものが多かった。直木賞受賞作の『炎環』は源実朝暗殺事件を「裏に三浦氏あり」との仮説で描き、歴史学界にも影響を与えた。(現在は否定的な説の方が強いようだ。)その他、奈良時代の『氷輪』、平安初期の『雲と風と-伝教大師最澄の生涯』、日野富子を描く『銀の館』など多数。大河ドラマ『草燃える』(鎌倉時代の東国武士)、『毛利元就』の原作者。男性中心の歴史観に対し、女性の役割を評価する作品を書いた。また判りやすい歴史エッセイでも知られた。僕も何冊か読んでいるが、特に面白かったのは『悪霊列伝』。茨城県古河市で育ち、旧蔵書をもとに「古河文学館」を開館、また旧居を別館として公開している。
 (永井路子)
(永井路子)
詩人、児童文学者、フランス文学者で、宮沢賢治研究で知られた天沢退二郎(あまさわ・たいじろう)が25日死去、86歳。宮沢賢治に影響を受け学生時代から詩を書き、数多くの詩集を刊行した。『《地獄》にて』(1984)で高見順賞。さらに『光車よ!まわれ』『《三つの魔法》』シリーズなど児童文学でも評判になった。フランス文学者としては明治学院大学で教えるとともに、多くの翻訳を行った。アラン・フルニエ『グラン・モーヌ』(岩波文庫)は素晴らしかった。また『《中島みゆき》を求めて』などの著書もある。しかし、一番重要だと思う業績は、やはり宮沢賢治全集を作ったことだろう。弟の宮沢清六から生原稿を見せて貰い、何度も花巻に通って『校本宮澤賢治全集』(1973~77)をまとめ、その後新修、文庫版をへて、『新校本 宮澤賢治全集』(1995~2007)を完成させた。これによって賢治研究の基礎が作られたのである。
 (天沢退二郎)
(天沢退二郎)
政治運動家、著述家で、「新右翼」と言われた「一水会」の創設者、鈴木邦男が1月11日死去、79歳。「生長の家」の家庭で育ち、早大時代には生長の家系の右派学生運動で活躍。1969年に右派系学生運動の連合で委員長となったが、内部争いで1ヶ月で退任した。70年の三島由紀夫事件に衝撃を受け、72年に民族派団体「一水会」を設立した。75年に東アジア反日武装戦線を評価し、三一書房から『腹腹時計と〈狼〉』を刊行し論壇にデビューした。以後、新左翼系著名人などと知り合うが、21世紀になると非暴力の立場をはっきりさせた。また、反差別を掲げてヘイトデモ反対行動に参加した。周囲からは「右翼からリベラル派になった」などと評されたが、まあ、「反差別」や「死刑廃止」こそ日本の伝統だという思いはホンネなのだろう。何回か映画上映後のトークを聞いたと思うけど、本を読んだことはない。面白い人、勇気ある人ではあった。
 (鈴木邦男)
(鈴木邦男)
国際的に知られた数学者の佐藤幹夫が1月9日に死去、94歳。京大名誉教授。関数を極限まで一般化した「佐藤超関数」、微分積分を代数的に調べる「代数解析学」、概均質ベクトル空間の研究など、現代の数学、物理学に大きな影響を与えた。文化功労者。すごい人らしいんだけど、研究テーマのそれぞれを調べても、僕には難しすぎて全く意味不明。
 (佐藤幹夫)
(佐藤幹夫)
現代音楽の作曲家として知られた松平頼暁(まつだいら・よりあき)が1月9日死去、91歳。本職は生物物理学者で、立教大学教授を務めた。一方、作曲家松平頼則の子として生まれ、独学で作曲を学んだ。様々な様式に基づくシステム化された作曲を模索するとともに、一柳慧やケージの影響で偶然性の音楽も手掛けた。国際的な評価が高く重要な現代音楽家と言われている。
 (松平頼暁)
(松平頼暁)
「本の雑誌」創刊者で、本や競馬の評論でも知られた目黒考二が19日死去、76歳。本が読めないとの理由で次々と会社をやめ、ついには会社の同僚だった椎名誠らと1976年に「本の雑誌」を創刊した。実質的な編集長として多くの新人を発掘したことで知られる。また北上次郎名義で冒険小説やミステリーの評論を行い、1994年『冒険小説論 近代ヒーロー像100年の変遷』で日本推理作家協会賞、日本冒険小説協会大賞を受賞。藤代三郎名義で数多くの競馬関連本も出している。面白本に関するこの人の眼力は素晴らしいものがあり、刊行中の「日本ハードボイルド全集」(創元推理文庫)も楽しみにしていたので残念。
 (目黒考二)
(目黒考二)
1987年から95年まで、内閣官房副長官を務めた石原信雄が29日死去、96歳。竹下、宇野、海部、宮沢、細川、羽田、村山の7内閣を支えた。(当時は最長。現在は杉田和博、古川貞二郎に次ぐ3位。)この間は消費税導入、昭和天皇逝去、湾岸戦争、PKO法制定、非自民政権誕生、自社連立と戦後最大級の政治変動に見舞われた時期だった。退任後、95年の東京都知事選に立候補した。自社さ連立の村山政権時で自社など各党相乗りとなり、それに反発した青島幸男が当選してしまった。僕も当時は「各党相乗り」に反発して青島に入れたのだが、結果的には石原信雄知事が当選していたら、「現職2期目」は圧倒的に強いから、もう一人の石原(慎太郎)都知事は誕生しなかったのは間違いない。僕の人生にも大きな影響を与えていただろう。
 (石原信雄)
(石原信雄)
セコム創業者の飯田亮(いいだ・まこと)が7日死去、89歳。1962年に日本初の警備会社、日本警備保障を設立。1964年の東京五輪の警備を一手に担って飛躍し、テレビドラマ「ザ・ガードマン」のモデルになった。74年に東証二部、78年に一部に上場し、83年に社名をセコムに変更した。誰も手掛けていなかった分野を切り開いた戦後史の重要人物である。
 (飯田亮)
(飯田亮)
・阿部市次、2022年10月10日死去、99歳。松川事件元被告人で最後の存命者。一審で死刑判決を受けたが、61年の仙台高裁差し戻し審で無罪判決、63年に最高裁で確定した。
・石井昭男、2022年12月30日死去、82歳。78年に明石書店を創業し、人権問題の出版につくし、08年にマグサイサイ賞を受賞。
・金川千尋、1日死去、96歳。信越化学会長。90年から10年まで社長を務め、シリコンウェハー事業で世界最大手に育てた。
・仲尾宏、1日死去、86歳。歴史学者。在日コリアン・マイノリティー人権研究センター理事長。朝鮮通信使研究の第一人者で、著書に『朝鮮通信使 江戸日本の誠信外交』(岩波新書)などがある。
・河野一郎、6日死去、93歳。英文学者、翻訳家。東京外大名誉教授。カポーティ『遠い声、遠い部屋』、マッカラーズ『心は孤独な狩人』、シリトー『長距離走者の孤独』など、英米現代文学の紹介に務め、僕もずいぶん読んできた。
・岸義人、9日死去、85歳。化学者。世界で初めてフグ毒「テトロドトキシン」の人工合成に成功した。また乳ガンの抗がん剤「ハラヴェン」を開発するなどして、ノーベル賞候補と言われた。文化功労者。
・三枝佐枝子(さいぐさ・さえこ)12日死去、102歳。1958年に「婦人公論」編集長となった。(女性として初の商業誌編集長。)1973年に商品科学研究所所長、1978年に西武百貨店監査役。家庭と職業を「両立」させた先駆者だった。
・中山きく、12日死去、94歳。沖縄戦の元白梅学徒隊の生存者として、体験を語る活動を続けた。
・大村益夫、15日死去、89歳。早稲田大学名誉教授。朝鮮近代文学の研究で知られ、多くの翻訳を行った。
・石田穣一、17日死去、94歳。元東京高裁長官として、永山則夫の差し戻し審判決で死刑を宣告した。退官後に沖縄に移住し、那覇で死去。「ゆたか・はじめ」名義で鉄道趣味を生かしたエッセイも書いた。国内の鉄道全線を完乗しているという。
・上田誠也、19日死去、93歳。地球物理学者でプレートテクトニクス理論を広めたことで知られる。東大名誉教授。
・石井紫郎、17日死去、87歳。日本法制史研究者。中世・近世の土地制度を研究した。
・西原春夫、26日死去、94歳。刑法学者、元早稲田大学総長。「間接正犯」の研究で知られた。憲法学者西原博史(18年没)の父。
・カール・アレクサンダー・ミュラー、9日死去、95歳。超伝導酸化物の発見で、1987年ノーベル物理学賞を受賞した。
 (2006年、殿堂入り表彰時)
(2006年、殿堂入り表彰時)
歴史小説家の永井路子が1月27日に死去、97歳。歴史小説の多くが戦国か幕末かを舞台にするのに対し、永井作品は古代、中世を扱ったものが多かった。直木賞受賞作の『炎環』は源実朝暗殺事件を「裏に三浦氏あり」との仮説で描き、歴史学界にも影響を与えた。(現在は否定的な説の方が強いようだ。)その他、奈良時代の『氷輪』、平安初期の『雲と風と-伝教大師最澄の生涯』、日野富子を描く『銀の館』など多数。大河ドラマ『草燃える』(鎌倉時代の東国武士)、『毛利元就』の原作者。男性中心の歴史観に対し、女性の役割を評価する作品を書いた。また判りやすい歴史エッセイでも知られた。僕も何冊か読んでいるが、特に面白かったのは『悪霊列伝』。茨城県古河市で育ち、旧蔵書をもとに「古河文学館」を開館、また旧居を別館として公開している。
 (永井路子)
(永井路子)詩人、児童文学者、フランス文学者で、宮沢賢治研究で知られた天沢退二郎(あまさわ・たいじろう)が25日死去、86歳。宮沢賢治に影響を受け学生時代から詩を書き、数多くの詩集を刊行した。『《地獄》にて』(1984)で高見順賞。さらに『光車よ!まわれ』『《三つの魔法》』シリーズなど児童文学でも評判になった。フランス文学者としては明治学院大学で教えるとともに、多くの翻訳を行った。アラン・フルニエ『グラン・モーヌ』(岩波文庫)は素晴らしかった。また『《中島みゆき》を求めて』などの著書もある。しかし、一番重要だと思う業績は、やはり宮沢賢治全集を作ったことだろう。弟の宮沢清六から生原稿を見せて貰い、何度も花巻に通って『校本宮澤賢治全集』(1973~77)をまとめ、その後新修、文庫版をへて、『新校本 宮澤賢治全集』(1995~2007)を完成させた。これによって賢治研究の基礎が作られたのである。
 (天沢退二郎)
(天沢退二郎)政治運動家、著述家で、「新右翼」と言われた「一水会」の創設者、鈴木邦男が1月11日死去、79歳。「生長の家」の家庭で育ち、早大時代には生長の家系の右派学生運動で活躍。1969年に右派系学生運動の連合で委員長となったが、内部争いで1ヶ月で退任した。70年の三島由紀夫事件に衝撃を受け、72年に民族派団体「一水会」を設立した。75年に東アジア反日武装戦線を評価し、三一書房から『腹腹時計と〈狼〉』を刊行し論壇にデビューした。以後、新左翼系著名人などと知り合うが、21世紀になると非暴力の立場をはっきりさせた。また、反差別を掲げてヘイトデモ反対行動に参加した。周囲からは「右翼からリベラル派になった」などと評されたが、まあ、「反差別」や「死刑廃止」こそ日本の伝統だという思いはホンネなのだろう。何回か映画上映後のトークを聞いたと思うけど、本を読んだことはない。面白い人、勇気ある人ではあった。
 (鈴木邦男)
(鈴木邦男)国際的に知られた数学者の佐藤幹夫が1月9日に死去、94歳。京大名誉教授。関数を極限まで一般化した「佐藤超関数」、微分積分を代数的に調べる「代数解析学」、概均質ベクトル空間の研究など、現代の数学、物理学に大きな影響を与えた。文化功労者。すごい人らしいんだけど、研究テーマのそれぞれを調べても、僕には難しすぎて全く意味不明。
 (佐藤幹夫)
(佐藤幹夫)現代音楽の作曲家として知られた松平頼暁(まつだいら・よりあき)が1月9日死去、91歳。本職は生物物理学者で、立教大学教授を務めた。一方、作曲家松平頼則の子として生まれ、独学で作曲を学んだ。様々な様式に基づくシステム化された作曲を模索するとともに、一柳慧やケージの影響で偶然性の音楽も手掛けた。国際的な評価が高く重要な現代音楽家と言われている。
 (松平頼暁)
(松平頼暁)「本の雑誌」創刊者で、本や競馬の評論でも知られた目黒考二が19日死去、76歳。本が読めないとの理由で次々と会社をやめ、ついには会社の同僚だった椎名誠らと1976年に「本の雑誌」を創刊した。実質的な編集長として多くの新人を発掘したことで知られる。また北上次郎名義で冒険小説やミステリーの評論を行い、1994年『冒険小説論 近代ヒーロー像100年の変遷』で日本推理作家協会賞、日本冒険小説協会大賞を受賞。藤代三郎名義で数多くの競馬関連本も出している。面白本に関するこの人の眼力は素晴らしいものがあり、刊行中の「日本ハードボイルド全集」(創元推理文庫)も楽しみにしていたので残念。
 (目黒考二)
(目黒考二)1987年から95年まで、内閣官房副長官を務めた石原信雄が29日死去、96歳。竹下、宇野、海部、宮沢、細川、羽田、村山の7内閣を支えた。(当時は最長。現在は杉田和博、古川貞二郎に次ぐ3位。)この間は消費税導入、昭和天皇逝去、湾岸戦争、PKO法制定、非自民政権誕生、自社連立と戦後最大級の政治変動に見舞われた時期だった。退任後、95年の東京都知事選に立候補した。自社さ連立の村山政権時で自社など各党相乗りとなり、それに反発した青島幸男が当選してしまった。僕も当時は「各党相乗り」に反発して青島に入れたのだが、結果的には石原信雄知事が当選していたら、「現職2期目」は圧倒的に強いから、もう一人の石原(慎太郎)都知事は誕生しなかったのは間違いない。僕の人生にも大きな影響を与えていただろう。
 (石原信雄)
(石原信雄)セコム創業者の飯田亮(いいだ・まこと)が7日死去、89歳。1962年に日本初の警備会社、日本警備保障を設立。1964年の東京五輪の警備を一手に担って飛躍し、テレビドラマ「ザ・ガードマン」のモデルになった。74年に東証二部、78年に一部に上場し、83年に社名をセコムに変更した。誰も手掛けていなかった分野を切り開いた戦後史の重要人物である。
 (飯田亮)
(飯田亮)・阿部市次、2022年10月10日死去、99歳。松川事件元被告人で最後の存命者。一審で死刑判決を受けたが、61年の仙台高裁差し戻し審で無罪判決、63年に最高裁で確定した。
・石井昭男、2022年12月30日死去、82歳。78年に明石書店を創業し、人権問題の出版につくし、08年にマグサイサイ賞を受賞。
・金川千尋、1日死去、96歳。信越化学会長。90年から10年まで社長を務め、シリコンウェハー事業で世界最大手に育てた。
・仲尾宏、1日死去、86歳。歴史学者。在日コリアン・マイノリティー人権研究センター理事長。朝鮮通信使研究の第一人者で、著書に『朝鮮通信使 江戸日本の誠信外交』(岩波新書)などがある。
・河野一郎、6日死去、93歳。英文学者、翻訳家。東京外大名誉教授。カポーティ『遠い声、遠い部屋』、マッカラーズ『心は孤独な狩人』、シリトー『長距離走者の孤独』など、英米現代文学の紹介に務め、僕もずいぶん読んできた。
・岸義人、9日死去、85歳。化学者。世界で初めてフグ毒「テトロドトキシン」の人工合成に成功した。また乳ガンの抗がん剤「ハラヴェン」を開発するなどして、ノーベル賞候補と言われた。文化功労者。
・三枝佐枝子(さいぐさ・さえこ)12日死去、102歳。1958年に「婦人公論」編集長となった。(女性として初の商業誌編集長。)1973年に商品科学研究所所長、1978年に西武百貨店監査役。家庭と職業を「両立」させた先駆者だった。
・中山きく、12日死去、94歳。沖縄戦の元白梅学徒隊の生存者として、体験を語る活動を続けた。
・大村益夫、15日死去、89歳。早稲田大学名誉教授。朝鮮近代文学の研究で知られ、多くの翻訳を行った。
・石田穣一、17日死去、94歳。元東京高裁長官として、永山則夫の差し戻し審判決で死刑を宣告した。退官後に沖縄に移住し、那覇で死去。「ゆたか・はじめ」名義で鉄道趣味を生かしたエッセイも書いた。国内の鉄道全線を完乗しているという。
・上田誠也、19日死去、93歳。地球物理学者でプレートテクトニクス理論を広めたことで知られる。東大名誉教授。
・石井紫郎、17日死去、87歳。日本法制史研究者。中世・近世の土地制度を研究した。
・西原春夫、26日死去、94歳。刑法学者、元早稲田大学総長。「間接正犯」の研究で知られた。憲法学者西原博史(18年没)の父。
・カール・アレクサンダー・ミュラー、9日死去、95歳。超伝導酸化物の発見で、1987年ノーベル物理学賞を受賞した。