ここ最近、ネット上で大いに議論されている現象をご存知でしょうか。
私はこの現象についての知識、全くありませんでした。
「湯は水より早く凍る」現象議論沸く 大槻教授は批判(朝日新聞) - goo ニュース
そのNHKの番組を観ていないので何とも言えませんけれど、水よりもお湯が早く凍る現象を『ムペンバ効果』と言うらしく、これが科学か、反科学かという論争が起こっているそうでございます。
大槻教授のように否定的な立場をとる専門家がいる一方で、北大の前野教授のように肯定的に捕らえている専門家もいらっしゃる。科学者の間でも意見が分かれているところを見る限り、やはり追試をして調べた方がすっきりするんじゃないかなぁって思うのですが、このメカニズムの科学的な検証は非常に難しいのだとか。一見簡単に立証できるような気もするんですけどねぇ・・・。
科学的な検証が進みつつある鍼灸の世界においても、根本的に未検証となっている部分が存在致します。経絡や経穴(ツボ)の存在もそのひとつでございます。
経絡と呼ばれる部位は神経の走行に沿った部分が多く、いわゆる経穴(ツボ)の部位には神経や血管が集中しているという事は解明されておりますが、わかっているのはそこまで。解剖学的な器官として経絡や経穴があるという立証はなされておりません。
もっとも経絡や経穴、気というのは「機能や概念としての存在」だという考えが一般的であり、物質的な存在ではないというのは我々専門家にとっても当然の話でございます。現状でも臨床上の不都合はございませんし、これから先も解剖学的に経絡や経穴が立証されることはないでしょう。器官としての存在ではないのだから。
ところが今から47年前の1961年(昭和36年)、経絡や経穴を解剖学的に発見したという驚くべき学会発表がございました。
発表者は北朝鮮の医学者・キムボンハン(金鳳漢)氏。『経絡の実態に関する研究』という論文で、キム氏は経絡や経穴にあたる器官が存在すると論じ、染色した経絡や経穴を示して経絡を「ボンハン管」、経穴を「ボンハン小体」と名づけるという発表を行いました。
世紀の大発見とされたこのボンハン学説は、瞬く間に世界中の医学者の間で話題となりました。北朝鮮政府はキム氏の業績をたたえた『経絡の世界』という映画を作製し、記念切手を発行。昭和42年の第9回鍼灸経絡治療夏期大学でもこの映画が上映され、大きな議論を巻き起こしたという記録が残っております。
しか~し。
このボンハン学説を再現できた学者は誰ひとりとしていなかったのです。
再現性のないこの論文発表は捏造説が囁かれ、真剣に取り合われることもなくなり、結局医学的にはほぼ無価値とされてしまったのでございます。
それから44年の歳月が流れた2005年2月。東京電機大学で開催された「第19回生命情報科学シンポジウム」において、このボンハン学説をもう一度見直してみようじゃないかという動きがあったそうでございます。このシンポジウムでは1960年代に日本と韓国で検証されたデータや新しい検証データをもとにした議論が行われたらしいです。
冷静に考えてみれば、この再検証ってすごく馬鹿馬鹿しい事なんですよ。しかし馬鹿馬鹿しいと思いつつも、本当にニセモノなのかをしっかり検証する。これは研究職に就く方々の義務だと思いますし、こういう研究はもっと活発にやってもいいんじゃないかなぁって思います。
というわけで、馬鹿馬鹿しいとはわかっていても、あえてムペンバ効果のしっかりとした検証をやってみて欲しいなぁって。そんな風に思います。
・・・こういうのってどうしてもキワモノ的な扱いになっちゃうんだろうけどね、真剣にやればやるほど(^^;)
私はこの現象についての知識、全くありませんでした。
「湯は水より早く凍る」現象議論沸く 大槻教授は批判(朝日新聞) - goo ニュース
そのNHKの番組を観ていないので何とも言えませんけれど、水よりもお湯が早く凍る現象を『ムペンバ効果』と言うらしく、これが科学か、反科学かという論争が起こっているそうでございます。
大槻教授のように否定的な立場をとる専門家がいる一方で、北大の前野教授のように肯定的に捕らえている専門家もいらっしゃる。科学者の間でも意見が分かれているところを見る限り、やはり追試をして調べた方がすっきりするんじゃないかなぁって思うのですが、このメカニズムの科学的な検証は非常に難しいのだとか。一見簡単に立証できるような気もするんですけどねぇ・・・。
科学的な検証が進みつつある鍼灸の世界においても、根本的に未検証となっている部分が存在致します。経絡や経穴(ツボ)の存在もそのひとつでございます。
経絡と呼ばれる部位は神経の走行に沿った部分が多く、いわゆる経穴(ツボ)の部位には神経や血管が集中しているという事は解明されておりますが、わかっているのはそこまで。解剖学的な器官として経絡や経穴があるという立証はなされておりません。
もっとも経絡や経穴、気というのは「機能や概念としての存在」だという考えが一般的であり、物質的な存在ではないというのは我々専門家にとっても当然の話でございます。現状でも臨床上の不都合はございませんし、これから先も解剖学的に経絡や経穴が立証されることはないでしょう。器官としての存在ではないのだから。
ところが今から47年前の1961年(昭和36年)、経絡や経穴を解剖学的に発見したという驚くべき学会発表がございました。
発表者は北朝鮮の医学者・キムボンハン(金鳳漢)氏。『経絡の実態に関する研究』という論文で、キム氏は経絡や経穴にあたる器官が存在すると論じ、染色した経絡や経穴を示して経絡を「ボンハン管」、経穴を「ボンハン小体」と名づけるという発表を行いました。
世紀の大発見とされたこのボンハン学説は、瞬く間に世界中の医学者の間で話題となりました。北朝鮮政府はキム氏の業績をたたえた『経絡の世界』という映画を作製し、記念切手を発行。昭和42年の第9回鍼灸経絡治療夏期大学でもこの映画が上映され、大きな議論を巻き起こしたという記録が残っております。
しか~し。
このボンハン学説を再現できた学者は誰ひとりとしていなかったのです。
再現性のないこの論文発表は捏造説が囁かれ、真剣に取り合われることもなくなり、結局医学的にはほぼ無価値とされてしまったのでございます。
それから44年の歳月が流れた2005年2月。東京電機大学で開催された「第19回生命情報科学シンポジウム」において、このボンハン学説をもう一度見直してみようじゃないかという動きがあったそうでございます。このシンポジウムでは1960年代に日本と韓国で検証されたデータや新しい検証データをもとにした議論が行われたらしいです。
冷静に考えてみれば、この再検証ってすごく馬鹿馬鹿しい事なんですよ。しかし馬鹿馬鹿しいと思いつつも、本当にニセモノなのかをしっかり検証する。これは研究職に就く方々の義務だと思いますし、こういう研究はもっと活発にやってもいいんじゃないかなぁって思います。
というわけで、馬鹿馬鹿しいとはわかっていても、あえてムペンバ効果のしっかりとした検証をやってみて欲しいなぁって。そんな風に思います。
・・・こういうのってどうしてもキワモノ的な扱いになっちゃうんだろうけどね、真剣にやればやるほど(^^;)










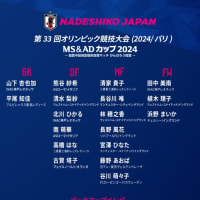















そしてうちの旦那さまはヤカンで沸かした熱々の麦茶をペットボトルに入れ、すぐに冷蔵庫に入れました。
ペットボトルがベコベコになってました。。。
うちのヒロコさんが見たら、あたしゃ確実に叱られます( ̄ω ̄)
実際そういう現象があり、まだ解明されていないという話だったので…条件などでいろいろ結果が変わってくるのかもしれないですね。
数学とかの難しい証明も、歴史的な過去の発掘も、氷を作るにあたってのいろんな解明も、一般人には全く無意味な事ですが、興味を持って研究、解明しようとする人ってすごいなぁ…と思います。
話は変わりますが、ツボとかに関してもまだわからない、というか器官としてハッキリしてない部分があるなんて知りませんでした!
これも、一般人としてはあまり気にならない部分だし…針を打ってもらって腰痛などを治してくれる先生がいるだけで嬉しいですけどね♪
東洋医学は現代医学や科学が発達する前に確立した医学なので現代医学の常識が通用しない部分も多々ありますし、経験的な医学なのでいわゆる科学的な解明が非常に難しい分野なんです。
A先生がやれば効果を得られるのに、同じ事をB先生がやると効かない。あるいはCさんには有効な治療が、同じ症状のDさんには無効となる場合がある。
これは技術の差だったり証(今でいう病名のようなもの)が違うために起こる現象なのですが、誰が誰に対してやっても同じ効果をコンスタントに得られるという治療法ではないんです。ここが西洋医学と東洋医学の決定的に違う部分なんですよね。
東洋医学はひとりひとりに合ったオーダーメイドの治療というわけです。
私は臨床が好きで、研究は苦手です。論文書いたり学会発表したりっていうのも正直やりたくない(^^;)
生涯、一治療家として患者さんと向き合いたいと願っています。