
4月より、母校のJ大学で日本古代史を担当することになりました。いろいろ事情がありまして、未だやや不安定な立場なのですが、力を尽くして後輩の指導に当たりたいと考えております。関係の皆さま、今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。
ところで、知り合いの方々は先刻ご承知のことと思いますが、私の研究は難解で分かりにくいといわれております。「もう少しわかりやすく」……よく聞く言葉ですが、私はこうした言説と戦い続けて(傲慢にも無視して?)きました。確かに、意味や論理の通らない文章は論外です。恰好をつけて漢字ばかり多いのもげんなりします。しかし、難解であることの何が悪いというのでしょう。学問というのは、難解であるがゆえに、問い続け考え続ける価値があるのではないでしょうか。難しければ難しいほど、自分なりの解答を発見できたときの喜びは、何にも増して大きいのではないでしょうか。分かりやすさを求めるのであれば、学問などやめてしまった方がいいと思います。「『話を簡単にしたがる人間』は総じて複雑な問題を長時間考察するだけの忍耐力を欠いた方であり、私はそんな人間を相手にしているほど暇ではない。現実が入り組んでいる以上、それを記述する言葉がそれに準じて入り組むことは避けがたいのである」とは、内田樹さんの至言(「憲法がこのままで何か問題でも?」内田他『9条どうでしょう』毎日新聞社、2006年、22頁)。また、高等教育において学生に簡単な道のみ指し示すのは、彼らから考える喜びを奪い、現実世界を埋め尽くす困難な課題へ立ち向かう力を弱体化させてしまうことに繋がります。ただでさえ、学生の想像力や思考力が低下しているというのに、それにこれ以上拍車をかけてどうするというのでしょうか。追求すべきは、いかに分かりやすく伝えるかではなく、いかに学生に考えさせるかです。講義や文章の工夫も、すべてそのためにあるべきと考えます。
……などと立派なことを書きましたが、これはあくまで決意表明で、すべてが完璧に実践できるわけではありません。ただ、理想としては常に掲げておきたいものです。
学生の皆さん、難問から目を背けず、一緒にいろいろ考えてゆきましょう。楽しいですよ。
上の写真は、ようやく改修工事の終わった私の研究室。まだ何も入っていなくて殺風景ですが、自宅に置いていた研究環境を別の場所に移動するというのは、なかなかに大変。しばらくはこの状態が続きそうです。ま、ゼミなどを行ううえで最低限の書籍は、持ってきておかないといけないですね。
ところで、知り合いの方々は先刻ご承知のことと思いますが、私の研究は難解で分かりにくいといわれております。「もう少しわかりやすく」……よく聞く言葉ですが、私はこうした言説と戦い続けて(傲慢にも無視して?)きました。確かに、意味や論理の通らない文章は論外です。恰好をつけて漢字ばかり多いのもげんなりします。しかし、難解であることの何が悪いというのでしょう。学問というのは、難解であるがゆえに、問い続け考え続ける価値があるのではないでしょうか。難しければ難しいほど、自分なりの解答を発見できたときの喜びは、何にも増して大きいのではないでしょうか。分かりやすさを求めるのであれば、学問などやめてしまった方がいいと思います。「『話を簡単にしたがる人間』は総じて複雑な問題を長時間考察するだけの忍耐力を欠いた方であり、私はそんな人間を相手にしているほど暇ではない。現実が入り組んでいる以上、それを記述する言葉がそれに準じて入り組むことは避けがたいのである」とは、内田樹さんの至言(「憲法がこのままで何か問題でも?」内田他『9条どうでしょう』毎日新聞社、2006年、22頁)。また、高等教育において学生に簡単な道のみ指し示すのは、彼らから考える喜びを奪い、現実世界を埋め尽くす困難な課題へ立ち向かう力を弱体化させてしまうことに繋がります。ただでさえ、学生の想像力や思考力が低下しているというのに、それにこれ以上拍車をかけてどうするというのでしょうか。追求すべきは、いかに分かりやすく伝えるかではなく、いかに学生に考えさせるかです。講義や文章の工夫も、すべてそのためにあるべきと考えます。
……などと立派なことを書きましたが、これはあくまで決意表明で、すべてが完璧に実践できるわけではありません。ただ、理想としては常に掲げておきたいものです。
学生の皆さん、難問から目を背けず、一緒にいろいろ考えてゆきましょう。楽しいですよ。
上の写真は、ようやく改修工事の終わった私の研究室。まだ何も入っていなくて殺風景ですが、自宅に置いていた研究環境を別の場所に移動するというのは、なかなかに大変。しばらくはこの状態が続きそうです。ま、ゼミなどを行ううえで最低限の書籍は、持ってきておかないといけないですね。











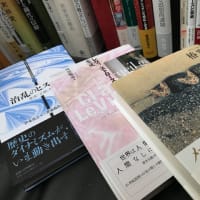
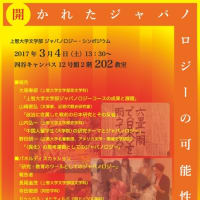
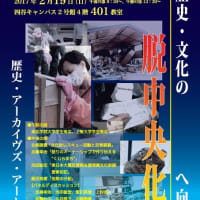
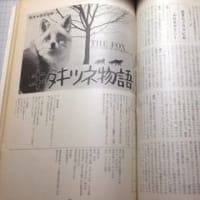
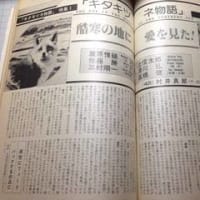
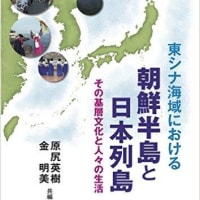

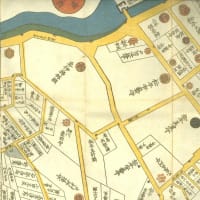







研究室、殺風景なのがむしろ羨ましい(笑)
ホント、我々同窓生、今回のこと心から嬉しく思っておりますのよ!
いまの学生たちが立ち向かうことになる現実は、今後もっと困難さを増してゆくように思います。しかし彼らにその耐性があるかどうか、少々心許ない気がします。Mさんが抱えていらっしゃる介護の問題など、逃げ出さずに引き受けてゆくことができるでしょうか……。
近年は介護支援施設も増え、負担の集中は回避されるようになってきましたが、私の母の世代には、老いた親の世話をするのは完全に〈嫁〉の仕事でした。母が寺の差配をしながら、家事と介護に明け暮れる姿は目に焼き付いています。鎌倉郊外はまだ伝統的な農家が多く、寝たきりの高齢者の自宅介護も少なくありません。月参りなどで伺ってみると、〈さよならまでの時間〉の過ごし方は、本当に人それぞれですね。しかし、当たり前のことですが、何らかの後悔は一様に残るものでしょう。「やることは全部やった」とすっきりしてみせるより、その後悔自体を抱え続けて自らの糧とし、また次の世代へも繋げてゆくことが大切なのだと思います。
〈忘却〉に抵抗するのも歴史学の役割のひとつですが、〈忘れたいこと〉を受けとめて生きてゆくのは苦しい。ぼく自身も、若い学生たちと、苦しさに耐える力を養ってゆきたいと考えています。研究室の方へも、また発破をかけにいらしてください。
〈個〉へ向けて発信し続けていると、様々な障害があるでしょう。「頷きあう共同体」からも謂われのない攻撃を受けることもあるでしょう。でも、学生にとって(もちろん我々にとっても)は、この作業こそが重要なはずです。世界は広い(ようで狭い、けどやっぱり広い)。大変でしょうが、頑張って下さい。帰国の際には、研究室覗かせて下さい。
不安もありますが、先達のお力を借りつつ、歩いてゆきたいと思います。中国にも早くゆきたい。
常勤になると、雑用が増えたりしがらみが増えたりする一方、学生と密に交流できたり、お金がかかる研究にチャレンジできたりするわけで、月並みですが「楽しむ」みたいな感覚がいいんじゃないかと思ったりします。
とは言え、私は新年度の業務ですでにヘロヘロです (^_^;; ○○センター長というのを今年度は2つもやらなければならない(涙)。大きい大学はうらやましいです。
もっとも、私の場合、研究していることを教えているわけではなく、研究と教育、雑用がある程度はなれているので、気が楽ではあります。ほうじょうさんの場合、しんどいかもしれませんね。
〈分かりやすさ〉至上主義云々の話でいうと、それ以前に今の学生には「靴をそろえて脱ごう」みたいなところからやんないとダメ、みたいな議論がかなりのリアリティを持ってたりしますからね (^_^;;
あの研究室でほうじょうさんと出会ったわけで、なつかしいです。
確かに、いまの学生には愕然とさせられることがありますね。某大学で講義終了後、教壇のところへやって来た学生に、「先生、ぼく先週出席してましたっけ?」と訊かれたときには、しばし言葉を失いました。もちろん、ちゃんとできる子も大勢いるんですけどね。
そうそう、もろさんと最初に会ったのは、梵一さんの研究室でした。確か『GYRATIVA』の創刊号が出てすぐですから、2000年ですか。ずいぶん昔のような気がするけど、まだ6年しか経ってないんですね。「広弘明集を読む会」……なんで途絶しちゃったんでしたっけ?