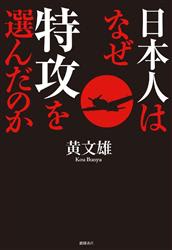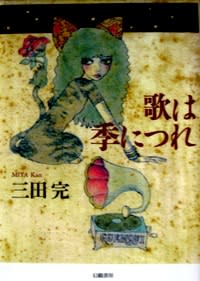【長谷川幸洋著、講談社発行】
新聞の長期低落傾向が続いている。国内発行部数は2000年の5370万部が2012年には4778万部に。10年ちょっとで10%以上も減少した。インターネットの存在感が高まる中、紙媒体の新聞は将来どうなるのだろうか。著者の長谷川氏は現在、東京新聞・中日新聞論説副主幹。本書は新聞を愛するが故の自戒の書といえよう。

「ジャーナリズムのデフレ敗戦」「新聞を出し抜くネット・ジャーナリズム」「ジャーナリストが生き残るためにすべきこと」など8つの章と「特別収録 大鹿靖明インタビュー」で構成する。大鹿氏は朝日新聞記者で、著書に「メルトダウン ドキュメント福島第一原発事故」(講談社ノンフィクション賞受賞)などがある。
タイトルの「2020年」は2回目の東京五輪開催の年。東京開催は昨年9月8日に決定し、テレビは発表の瞬間や「お・も・て・な・し」の場面を繰り返し放映した。ところが翌日、新聞は休刊日で朝刊がなかった(読売新聞は特別号外を宅配)。感動をもう一度と新聞受けをのぞいて肩透かしを食った読者も多いことだろう。休刊日は販売店の慰労が目的で、読者とは無関係のいわば内輪の事情による。
著者は「東京五輪が決まっても、新聞を発行しないで平気でいられる新聞は『読者のことを考えている』と本気で言えるのか」と問題提議。さらに、読者が休刊日で「新聞がなくても困らない」と実感したとすれば、「この体験はこれから2020年の東京五輪に向けて、じわじわと深い影響を与えるのではないか」と危惧し、「新聞大激動」の幕開けを告げるものとまで言い切る。
著者は各章の中で、官僚に取り入ってネタという餌をもらう〝ポチ記者〟を生む経済ジャーナリズムの構造的な問題や、記者クラブでの発表に頼り生データに当たらない記者の体質、情報の二次加工が不得意なマスメディアなどの問題点も指摘する。
2012年「週刊ポスト」が復興予算の流用問題を報じた。女性のフリーランス記者が霞が関の省庁が公表している予算の「各目明細書」をネットで読み込むことが特報のきっかけになった。著者が取材中、その記者から逆に問い返されたという言葉が印象的だ。「私が不思議に思っているのは、記者クラブにいる記者さんたちはみんな、私よりももっと多くの情報を持って……復興予算の流用だって知っていたかもしれない。それなのに、どうして報じられなかったのでしょうか」。
そう言えば、この復興予算流用問題以外にも佐村河内守氏の作曲者別人問題など、最近は週刊誌や月刊誌が書いた特ダネを新聞やテレビが後追いするケースが増えている。理化学研究所の「STAP細胞」論文不正疑惑も、最初に指摘したのは論文検証サイトで、それがブログやツイッターで広がって表面化した。長く再販制度や記者クラブなどで守られてきたオールドメディアの新聞にとって、低落傾向に歯止めを掛けるのはなかなか容易ではない。