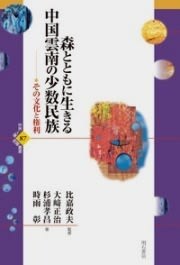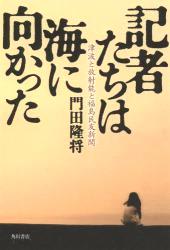【木下浩良著、朱鷺書房発行】
著者は1960年、福岡県柳川市生まれ。高野山大学文学部人文学科国史学専攻卒業、現在、同大学の図書館課長心得(司書)・密教文化研究所事務室長心得で、和歌山県高野町教育委員会副会長も務める。これまでに兵庫県竹野町史、養父町史、大阪府岬町史、和歌山県九度山町史、高野町史の編纂委員を歴任。

高野山東端に位置する奥之院にある墓地群は20万基とも30万基ともいわれる。本書はその中から自ら調査し確認できた戦国時代の武将とその夫人たち124人の石塔について、1人ずつ経歴と銘文を写真とともに紹介する。その多くは建立から既に400年。苔むし磨耗した銘文を読み取る作業の困難さは想像以上だろう。著者も「炎天下や極寒の雪降る中での調査は耐えがたいものであったが、新発見の石塔が見出されたりすると、一気にそれらを忘れさせてくれた」と述懐している。
高野山内の鎌倉時代から江戸時代草創期の慶長末年(1615年)までの有紀年銘の石造物は奥之院を中心に1969基が存在するという。最古のものは鎌倉中期の建長8年(1256年)銘の五輪塔。全体の半数強の1007基が五輪塔で、大名墓のほとんども五輪塔だった。そのほかは宝篋印塔、石室、石仏、石燈籠など。
本書では124人を奥之院入り口の一之橋から弘法大師の御廟に向かってほぼ順番通りに紹介する。意外なのはそのうち2割強の約30人を女性が占めること。著者は「高野山は女人禁制のイメージが強く、不思議に思われるかもしれないが、生前に女人禁制であったからこそ、せめて死後は奥之院の弘法大師のお傍で安らかに供養されたい、供養したいと願ったとしても、決して不思議ではない」とみる。
高野山最大で「一番碑」と称されているのが徳川2代将軍秀忠夫人お江の五輪塔(490.2cm)。基壇と合わせた高さは802.7cmもあり、基壇下部面の広さは8畳敷きほどもある。銘文から息子の駿河大納言忠長が1周忌に際し造立したことが分かる。「二番碑」は浅野家3代目の浅野長晟(ながあきら)夫人、振媛(ふるひめ)の五輪塔。「三番碑」は前田利長の五輪塔で、造立の奉行衆として4人の僧侶を列挙している点は他に例がなく、石材の産出地(攝州御影村)を明記している点も珍しい。
豊臣秀頼の五輪塔は高さ302cm、淀殿の五輪塔も295cmとともに3m前後と大きい。2人が自害したのは「大坂夏の陣」で大坂城が落城した翌日。だが両塔の造立日は落城の日になっており、銘文にはともに「御取次筑波山知足院」と刻まれている。この知足院の僧侶光誉は大坂冬の陣・夏の陣のとき徳川家康の陣で戦勝を祈願した〝陣僧〟。このことから著者は「家康が秀頼と淀殿の供養のために、その光誉に命じて奥之院に両塔を造立したのではなかろうか」と推測する。
伊達政宗の五輪塔も総高4m以上あり、その周りを殉死した家臣20人の五輪塔が囲む。上杉謙信と養子の景勝の墓所は江戸初期建築とみられる木造建築の霊屋で、中に2人の位牌が入っている。石田三成の五輪塔は総高267cmで、正面に「宗應逆修」と刻まれる。逆修(ぎゃくしゅ)は生前葬のこと。三成は「宗應」と称して30歳の時にこの塔を造り自身の葬式をしていたことになる。明智光秀のものと伝わる五輪塔は総高178cmで銘文がない。江戸時代中頃のもので「何度作り直しても破損するとの伝承がある」そうだ。
前田利家の石塔は高さ143.2cmの宝篋印塔。夫人まつは利家が病死すると芳春院として出家する。そして夫の供養のために石塔を造るとともに、そばに自身のため「為御逆修」と刻んだ同じ形の石塔を造った。2つの石塔からも生前の2人の仲睦まじさがしのばれる。高野山を攻めた織田信長の五輪塔もある。御廟橋の近くで総高230cm。「かつて敵対した武将であっても、供養のためには受け入れる高野山の懐の深さを垣間見る、貴重な石造物でもある」。
徳川3代将軍家光の乳母、春日局の五輪塔は弘法大師の御廟に近い燈籠堂のすぐ傍らに位置する。総高120cmで、前面には法名が刻まれた一対の石燈籠。亡くなる3年前の寛永17年(1640年)に逆修供養をした後に造立した。その場所からも将軍の権威を背景にした春日局の絶大な力の一端がうかがえるようでおもしろい。