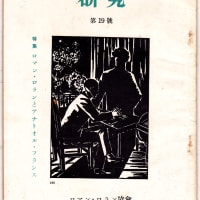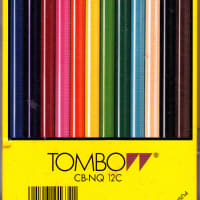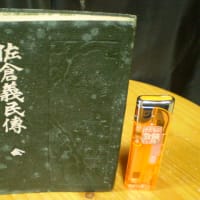朝日では、社説と声の欄が同じ紙面にある。声の欄は、考え方は違っても、その主張は短い文面ながら、わかりやすく伝わってくる。対して、社説、今日は、春闘についてだが、今日にかぎらず、いつの日も、何を言っているかわからない文面で、人に伝えるという文章の基本の姿でも、「声」に負けている。
さて、今日の声の欄に「今こそ読もうロランの小説」という投稿があった。
「年末から年始にかけて通読し、その素晴らしさの余韻にまだ浸っている。この傑作(ジャン・クリシトフ)が、より多くの人に読まれることを願う」という文面だ。58歳とある。なんと若々しいことか。
「ジャン・クリッストフ」は、よく若い頃なら読めるけど、あんな理想主義的な小説は、年取って経験を積むと、読めない、という人もいるようだ。
いや、ロマン・ロランだけでなく、ヘルマン・ヘッセや「チボー家の人々」なども、「昔、若い頃は感動した。あのころは若かった。でも、卒業した」という人もいる。特に文学通の人たちだろうか。今は、もっと難しいのを読んでいる。あんなものは、感傷的で、甘く、人生を知らぬ若い者だけが読める本だとでもいうのだろうか。こういう人たちとは友達にはなれない。
58歳になっても、「ジャン・クリストフ」に感動できる。年齢は関係ないだろう。読書の達人アランは晩年になって、「ジャン・クリストフ」を再読したが、感動は変わらなかった、といっていた。
それにしても、この時代に「ロマン・ロランを!」とは新鮮な驚きだった。こういう人も健在なのだ、とうれしくなった。
若い人は読んでくれるだろうか?なにしろ本屋さんに行ってもロマン・ロランの本を見つけるのも容易ではないのだから。これは、驚くべきことなのに。
言論、思想、出版の禁止なんて条例はどこにもないにもかかわらず、この国は自由な言論・思想・出版が消え、人々の精神の家畜化政策は大成功をおさめたのかもしれない。
さて、今日の声の欄に「今こそ読もうロランの小説」という投稿があった。
「年末から年始にかけて通読し、その素晴らしさの余韻にまだ浸っている。この傑作(ジャン・クリシトフ)が、より多くの人に読まれることを願う」という文面だ。58歳とある。なんと若々しいことか。
「ジャン・クリッストフ」は、よく若い頃なら読めるけど、あんな理想主義的な小説は、年取って経験を積むと、読めない、という人もいるようだ。
いや、ロマン・ロランだけでなく、ヘルマン・ヘッセや「チボー家の人々」なども、「昔、若い頃は感動した。あのころは若かった。でも、卒業した」という人もいる。特に文学通の人たちだろうか。今は、もっと難しいのを読んでいる。あんなものは、感傷的で、甘く、人生を知らぬ若い者だけが読める本だとでもいうのだろうか。こういう人たちとは友達にはなれない。
58歳になっても、「ジャン・クリストフ」に感動できる。年齢は関係ないだろう。読書の達人アランは晩年になって、「ジャン・クリストフ」を再読したが、感動は変わらなかった、といっていた。
それにしても、この時代に「ロマン・ロランを!」とは新鮮な驚きだった。こういう人も健在なのだ、とうれしくなった。
若い人は読んでくれるだろうか?なにしろ本屋さんに行ってもロマン・ロランの本を見つけるのも容易ではないのだから。これは、驚くべきことなのに。
言論、思想、出版の禁止なんて条例はどこにもないにもかかわらず、この国は自由な言論・思想・出版が消え、人々の精神の家畜化政策は大成功をおさめたのかもしれない。