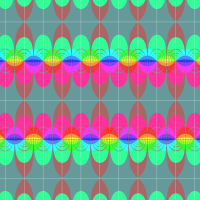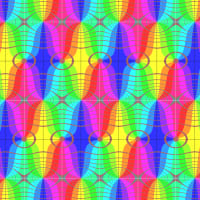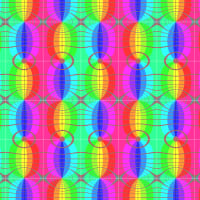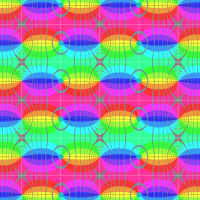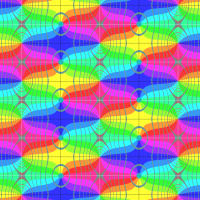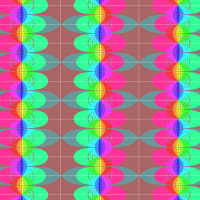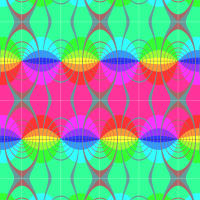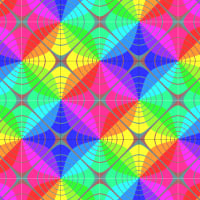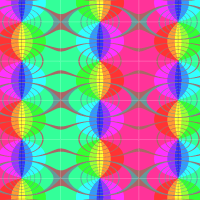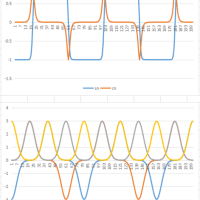微分幾何学の方は今回も表面上の追跡になりそうです。少しずつは進んでいる感じがするので、まあいいか、の感じ。
それと、別の本で共変ベクトルが1形式に変わりつつある理由が書いてあって、初めて見たので現在、勉強の方向を検討中です。
書名は言っておいた方が良いでしょう。
深谷賢治。解析力学と微分形式。岩波書店、2004年
今は新装版が手頃に手に入ります。中身は変わらないようです。
座標変換時にgrad, rot, divが妙なことになるみたいで、1形式が注目されているとのこと。1形式については以前にベクトル解析だったかテンソル解析だったか、翻訳本で新しい方法、として紹介されていました。ただし、同じ事なので従来法で勉強しても何ら差し支えない、とのこと。
なにしろ、ベクトル解析と言えばgrad, rot, divで、これにより輝かしい現代の技術社会が支えられているので、大成功のはずです。しかし座標変換ができないと、おそらくゲージ変換などで困難となるので一部では移行しつつあるとのこと。ええ、このあたりの業界事情は私には遠い世界なので間接的にしか分かりません。
で、上述の本で1形式は極性ベクトル、2形式は軸ベクトル、と書かれていたところで、最初は閉じてしまったことを思い出します。私はてっきり共変ベクトルと反変ベクトルだと思っていましたから。
多分、全くの外れでは無いと思います。ただ、共変ベクトルはコンデンサの扱いの感じ、反変ベクトルはその相棒のコイルの感じ、とは感じていましたから、それならば極ベクトル、軸ベクトルでしっくりくるか、と思い直して再度検討中、ということ。
ついでに3形式が擬スカラ、と書かれていて、こちらの正体はもう少し読まないと分かりません。
微分幾何学にもgrad, rot, divの式が出ていて、私の頭の中ではこの3者(微分形式、微分幾何学、ベクトル解析)の緩い関係がああでもない、こうでもない、と。
すっきり分かった気がしたら、あるいは途中経過でも面白いと思ったら、再びこの話題を取り上げます。