現在のミリオンライブのガチャのテーマが「冬の天体観測」で、目玉カードの一つが中谷育が望遠鏡を覗いている絵柄。この天体望遠鏡の製造元が自社の製品であることを特定し、ツイッターで反応したのがアイマスのまとめサイトで紹介されていました。
我が国屈指の光学機器メーカー、ビクセン社の「Vixen 天体望遠鏡 ポルタII経緯台シリーズ ポルタII A80Mf (39952-9)」だそうです。メーカーが特定したのだから間違いないでしょう。定番のエントリーモデル、の位置づけだそうです。定価は\59,400で、実売価格は4万円台みたいです。
なお、中谷育が手にしているのは「Vixen 天体望遠鏡用アクセサリー 微動ハンドル フレキシブルハンドル300mm」のようで、買うなら2本必要です。こちらはそんなに高価では無いです。月面観測用の減光フィルターも別売りです。
ということで、買ってみようかなと思われたPは多いと思います。結論から言います。天体観測に継続的に興味が続くような気がしたら、これは間違いの無い商品です。お買い得と思います。
ただし私、天体観測していたのは小学生から高校生までです。今も誠文堂新光社の天文年鑑は買い続けていますけど、単眼鏡やら双眼鏡でたまに天を見上げるくらいです。
何が見えるかというと、月面。そして像はかなり小さいですけど、主要な惑星(後述)。恒星はどんなに大きな望遠鏡でも点にしか見えません、色は分かります。
だったら、おもちゃ屋で売られている安価な学習用望遠鏡と変わらないではないか、と思う方もおられるでしょう。まあ、夏休みの宿題みたいな1シーズンで興味が失せるのなら、見た感じは同じと思います。
この望遠鏡の特徴は、扱いやすさにあると思います。屈折式だからほぼメンテフリー。気が向いた時にお出かけして、設置したらすぐさま観測開始できます。雲台と三脚ががっしりしているから、長時間の観測でも疲れにくいはずです。
星の位置は、スマホや3DSにアプリがあったと思います。その方向に手で向けて、ファインダーで狙って、ハンドルで追従させます。そう、天球って一日に1回転しているので、観測しているとすぐに視野から外れます。だから、ときどきハンドルを回さないといけない。これとは別に自動追従する望遠鏡も市販されていますけど、扱いはデリケートと思います。
ビクセン社は、私の印象ではアマチュア用望遠鏡や双眼鏡のメーカーで、外見が物々しくないのに、ものすごくしっかりした製品を提供するので、評判が高いです。ブランド物と言って良いです。それでも高価に見えるのは、光学系と雲台・三脚がしっかりしているから。
対物レンズは80mmアクロマートですから、二枚合わせの基本形。こんなのでも最近は透過率向上のためのマルチコートをするみたいです。接眼レンズが2種類付属していて、倍率と視野は、それぞれ46倍・64分、144倍・22分です。口径が80mmなので、これ以上の倍率の接眼レンズを使っても像がぼけるだけです。
「分」は角度の単位で、1度=60分。月の視直径が30分ほどで、手を伸ばした先の五円玉の穴の大きさほどだそうです。ずいぶん狭い範囲です。
ということで、月面は迫力の絵が見えるはずです。満月時などは明るいので、フィルターを使う必要があるでしょう。
惑星は最大の木星でも視直径は1分に満たず、小さく見えるだけです。でも、金星なら三日月のような満ち欠け、木星なら4つのガリレオ衛星、土星なら輪が明瞭に見えるはずです。昔の天文学者はこんな像を見ていたのかなと、想像が膨らみます。
恒星は前述したように点にしか見えないので、集合しているすばるとかが見栄えがします。アンドロメダ大星雲のような星雲系はぼうっと広がる光の集積にしか見えないと思います。
アマチュア向けの天文雑誌が複数刊行されているほどで、いったん興味を持ったら面白いですし、のめり込んだらものすごいことになります。この望遠鏡は機動性が高く、わずかの世話しか必要で無いので、たしかに入門にはぴったりだと思います。ただし、私はこの望遠鏡を使ったことはありません。買うのなら使った方のレビューを事前に見る方が良いと思います。
最新の画像[もっと見る]
-
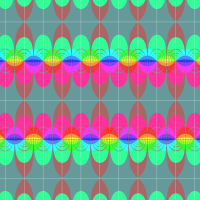 4145. 楕円関数、複素平面、上級編
2年前
4145. 楕円関数、複素平面、上級編
2年前
-
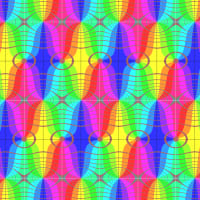 4145. 楕円関数、複素平面、上級編
2年前
4145. 楕円関数、複素平面、上級編
2年前
-
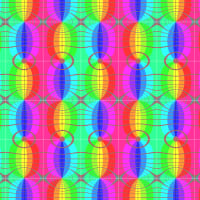 4145. 楕円関数、複素平面、上級編
2年前
4145. 楕円関数、複素平面、上級編
2年前
-
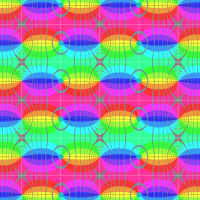 4145. 楕円関数、複素平面、上級編
2年前
4145. 楕円関数、複素平面、上級編
2年前
-
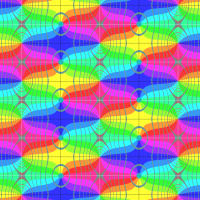 4145. 楕円関数、複素平面、上級編
2年前
4145. 楕円関数、複素平面、上級編
2年前
-
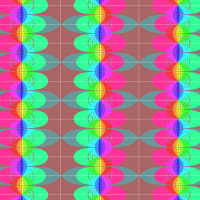 4145. 楕円関数、複素平面、上級編
2年前
4145. 楕円関数、複素平面、上級編
2年前
-
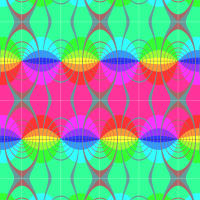 4136. 楕円関数、複素平面編
2年前
4136. 楕円関数、複素平面編
2年前
-
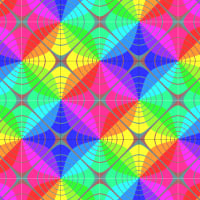 4136. 楕円関数、複素平面編
2年前
4136. 楕円関数、複素平面編
2年前
-
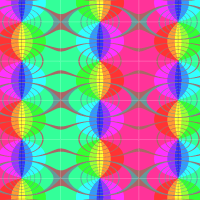 4136. 楕円関数、複素平面編
2年前
4136. 楕円関数、複素平面編
2年前
-
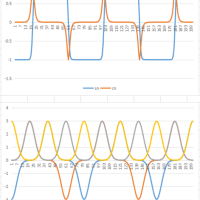 4120. 楕円関数、実数編、続き^4
2年前
4120. 楕円関数、実数編、続き^4
2年前













