■新幹線大爆破 (RCA)
いよいよ東京オリンピックが開催決定となれば、前回の昭和39(1964)年には未だ小学生だったサイケおやじにも様々な感慨が蘇っています。
それは東京の街の大改造が日本全国に波及していた事が実に大きくて、例えば古い建物や道路が壊され、日々次々に新しいものが作られていたという実感であり、特に東海道新幹線の開通は、ひとつの驚異と思えましたですねぇ~。
なにしろ「超特急」ですからっ!
東京~大阪が3時間!?
これは当時としては吃驚する他はないスピードでありました。
ところが、それを当たり前とする現実が直後にも継続進化していた我国高度成長の証であり、ついには昭和50(1975)年、それを破壊する映画「新幹線大爆破(東映・佐藤純弥監督)」が制作公開されたのですから、たまりません。
その強烈なカタルシスが日本だけでなく、世界的な大ヒットに繋がったことは、今や歴史と思うばかりです。
特に劇中、珍しくも高倉健=健さんが悪役、つまり新幹線爆脅迫事件の主犯であり、首尾よく大金をせしめて逃亡を図る終盤の流れでは、なんとか逮捕されませんように! と願う観客の気持が大勢を占めるであろう、その感情移入の根源が、高度成長社会から不条理に落ちこぼれた健さんに象徴される、当時の一般庶民の豊かになった社会の中の満たされない気持であったと思うのは、サイケおやじだけでしょうか?
しかも物語設定が、決して止まることの許されない新幹線高速列車、スピードが落ちれば仕掛けられた爆弾が爆発するという状況の中で、乗客や乗務員の焦りとジコチュウ噴出!
おまけに対応に追われる鉄道関係者や警察、そして政治家の自己保身と正義感のアンバランスな葛藤が、既に漠然とした前途を予感させていた当時の日本や世界の状況にアクセスしていた事は言うまでもありません。
いゃ~、ウケ狙いの大衆映画でありながら、後々まで如何様にも深読み出来る仕上がりになっているのは、名作のひとつの要件かもしれませんよ。
さて、そこで本日掲載のシングル盤は、その大ヒット映画「新幹線大爆破」からサントラ音源を抽出した1枚で、まずA面の「脱出へのパスポート」は不気味なスキャットが印象的に使われた、ちょいと地味なトラックなんですが、一方のB面「スーパーエキスプレス109」が、ジャズファンクの激熱演奏!
もう、初っ端からニューソウル全開のパーカッションとワウワウのリズムギター、ビシバシのドラムスにキメまくりのホーンリフが飛び出せば、快楽的なエレピや不安を煽るようなストリングスの響きも感度良好♪♪~♪ いゃ~、何度聴いてもグッと気持が高揚してきますよっ!
ちなみに劇伴を担当した青山八郎は幾分過小評価気味とはいえ、このトラックに参加しているスタジオ系ミュージシャン達の充実演奏を聴けば、納得の良い仕事だと思います。
さて、話は変わりますが、今回の東京オリンピック開催決定のキメ手となったのが、例の放射能汚染水問題に対する総理大臣の力強い対応宣言(?)とされますが、個人的には疑念を打ち消せません。
しかし総理大臣ともあろう御人が、あながちホラを吹いているはずは無いっ!
そう信じる他はないし、そう思いたいわけですよ。
逆に昨日、その原発事故に関連した訴訟において、菅直人や東電旧経営陣の不起訴が決まったという事については、これまた呆れた話です。
つまりオリンピックの東京開催が放射能汚染水問題で落選した場合、その犯人探しというか、責任を誰に押し付けるか?
その生贄予備軍にされていたのが、前述の顔ぶれだったと思うのは、サイケおやじだけではないでしょう。
ただし、不起訴になった彼等に責任が全く無いかと言えば、そんな事はありませんよねぇ~~~~~、絶対に!
問題は、どうにも納得出来ない胡散臭さが解消されていない現況と思います。
しかし同時に、些か使い古された言い回しではありますが、民主主義の日本においては、一度決めた事に対して、皆が一致協力するのが、あるべき姿という事です。
疑うことよりも、信じることが難しいのは、この世の真実のひとつかもしれませんが、それでも安心して新幹線に乗っている日々の安寧と同じように、福島の原発事故が収拾に向かうことを心から願っています。














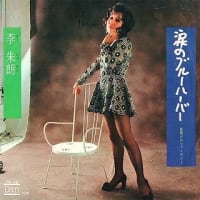

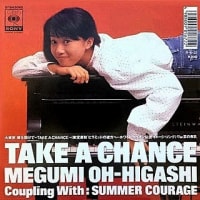








予告編を見ると、
http://www.youtube.com/watch?v=hw3DUS6EQfU
昭和を彩ったスターの方々が大挙出演されてます。皆さんお若い、お若い。この若さが、ストレートに昭和のエネルギーを感じさせてくれます。ところで。
この手の大作映画には必ず出てくる丹波哲郎さん、なぜかいつも「特別出演」という断り書きが付いてます。そもそも「特別・・」とはどういう意味なのでしょうか。今だに謎です。
毎度コメント&ご紹介、ありがとうございます。
さて、ご質問の件、言うまでもなく芸能界には「格」が厳然としてあり、映画のキャスティングにおける「序列」は常に気を使う作業(?)です。
特にクレジットロールでは、最初に主役、最後のトメに大物をもってくるのが慣例ですから、他に同格の俳優が出ている場合は、そのひとつ上か、真ん中に「特別出演」とか「友情出演」という肩書(?)を入れて、メンツを立てると言われています。
丹波哲郎は、まさにそうした「格」の筆頭であり、各社様々に大きな役を演じていますからねぇ~。
ちなみにスタア俳優は、場合によっては監督よりも権力があったのが、当時の撮影所システムであり、中には自分の都合でスケジュールを変える我儘も通用していたそうですよ。
もちろん同時に仕事に対するシビアさもあって、とりまき連中の大部屋組にも、それなりの役を付けるとか、そうやって映画作りの質が保たれていたというわけです。
「友情出演」というのも疑問でしたが同じような意味だったんですね。
音楽のアルバムで「appears by the courtesy of
○○○(会社名)」というのを良く見かけますが、レーベルの壁を越えて演奏やコーラスに特別参加するの意、と理解しておりました。そこから類推し、「特別出演」は、あるいは、映画会社の壁を越えて出演するの意、かと勝手に想像したりもしておりました。昔の俳優さんは、映画会社専属制、とも聞いておりましたので。カン違いを正していただき、有難うございます。
「格」の話で言うと、「友情出演」という断り書きは、「特別出演」の大物より、やや格の落ちる、中堅・若手の人気俳優さん(たとえば、松山ケンイチさん等)に用いられるような気がしております。正しいでしょうか。
こちらこそ、恐縮です。
所謂「五社協定」は映画全盛期の取り決めでしたが、既に当時から特定の映画会社と専属契約をせず、あるいはワンショット契約みたいな活動をやっていたスタアは存在していました。
それが昭和40年代末頃には実質的に消滅し、何よりも映画会社が経営不振でしたからねぇ……。
ちなみに専属契約の俳優は基本給があって、さらに出演作品毎にギャラが出ていたそうで、例えば東映だとクレジットロールの名前に「新人」と肩書が付くと、以降はギャラがもらえたそうですよ。
また東映京都では、既に役が付いている俳優でも、自分の出番以外に例えば「通行人」とか、そういう仕事もやるのが普通だったそうです。
ちなみに先日、某イベントで明かされた話では、ウルトラセブンの出演でダンは月に三万円、東宝専属のアンヌは十万円を越していた収入があったそうで、それが昭和42年ですから、吃驚でした。