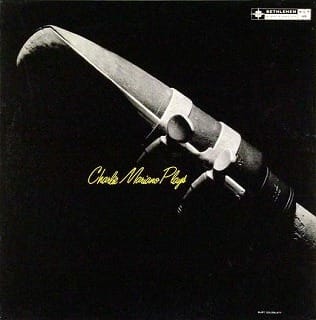■Opus De Jazz / Milt Jackson (Savoy)
いよいよ新年度、新しい職場で頑張る気概に満ちた人が目立ちますね。所謂フレッシュマンというところでしょうか、不景気な現状には、彼等のようなハッスルが必要だと痛感しております。
さて、これは遥か昔、私が社会人となって初めて買ったアルバムです。
そう、あれは、今は無くなってしまった銀座の有名中古店「ハンター」でゲットしたのが、つい昨日のようです。ジャケットは有名カラー版ではなく、地味なモノクロの別物デザインでしたが、アメリカプレスの盤そのものが分厚かったので、こちらを選んだわけです。値段も確か千円だったと記憶していますが、ちなみに、いっしょに売られていたカラージャケットの日本盤は千二百円でしたから、まだ給料を貰っていない自分には、当然の選択だったというわけです。
内容は言わずもがなの名盤ですから、ジャズ喫茶で何回も聴いていまいしたが、それでも欲しくなる魅力が、確かにあるんですねぇ~♪
録音は1955年10月28日、メンバーはミルト・ジャクソン(vib)、フランク・ウェス(fl,ts)、ハンク・ジョーンズ(p)、エディ・ジョーンズ(b)、ケニー・クラーク(ds) という名手揃いで、ブルースとバラードの真髄がじっくりと演じられています。
A-1 Opus De Jazz
オリジナルはホレス・シルバーが1953年11月に自作自演でブルーノートに吹き込んだピアノトリオのファンキー曲ですから、ミルト・ジャクソンにしてもお気に入りなのでしょう。このセッション以前の1954年6月にホレス・シルバーの助演を得て、ブレスティッジに名演を残していますが、やはり同曲の決定的なバージョンは、これでしょうね♪♪~♪
ミディアムテンポの弾むようなグルーヴは、ちょっと聴きには単調としか思えないケニー・クラークとエディ・ジョーンズの迷いの無いコンビネーションに支えられ、その軽やかなブルースフィーリングが、たまらない魅力になっています。
もちろん、これと同じようなノリは、ミルト・ジャクソンがレギュラーだったMJQでも演じられているのは確かです。しかしここでの演奏は、淡々とした中にも野太いグルーヴが感じられ、同時に奥深いジェントルな風情さえ滲んでくるのですが、その原動力はエディ・ジョーンズのしぶとい4ビートウォーキングとハンク・ジョーンズの素敵なピアノタッチじゃないでしょうか。それだけ聴いていても、グッと惹きつけられます。
そして演奏そのものの仕掛けが、これまたニクイほど! ヴァイブラフォン、フルート、ピアノがソロを回していくアドリブパートは、コーラスを重ねる度に切り詰められていき、終いにはソロチェンジの様相となるのです。
あぁ、このクールで熱い表現は圧巻ですねっ!
ミルト・ジャクソンは、これぞっ、モダンジャズのブルースを発散させますし、飄々としてシブイ表現のフランク・ウェスのフルートは、音色そのものがハスキーな感じで高得点♪♪~♪ さらにハンク・ジョーンズのピアノのジェントルな存在感も素晴らしいかぎりです。
オリジナルではホレス・シルバーが強烈にシンコペイトしていた、些かアクの強いテーマメロディのキモが、こうしてライトタッチで煮詰められていくところに、ジャズの面白さを感じてしまいます。
A-2 Opus Pocus
これもブルースですが前曲とは一転、ヘヴィなグルーヴが横溢した名演ですから、ミルト・ジャクソンはますますの本領発揮♪♪~♪ 粘っこいウォーキングベースに導かれ、全くの自然体でブルースリックを響かせるヴァイブラフォンのソウルフルな味わいは、本当に格別ですねっ♪♪~♪ まさにブレ無いファンキー&グルーヴィン!
そしてフランク・ウェスが、ここではディープなテナーサックスを披露してくれますから、嬉しさ倍増! コールマン・ホーキンス直系ともいうべきスタイルは、些か古臭いところが逆に高得点でしょう。というか、実はサブトーンも駆使したテナーサックスの不滅の魅力がたっぷりと味わえます。
さらに滋味豊かなハンク・ジョーンズの伴奏に趣味の良いアドリブソロも最高で、ファンキーなドロの中の清涼剤というには、あまりにも素晴らしすぎです。
B-1 You Leave Me Breathless
このアルバムの中では唯一のスタンダード曲で、落ち着いたスローテンポのバラード演奏ながら、流石は名人揃いとあって、セッションの中では一際輝く名演になっています。とにかくテーマ部分からして、各楽器の役割分担の妙、メロディフェイクの素晴らしさが堪能出来ますよ。
歌心の真髄を披露するミルト・ジャクソンのヴァイブラフォンは軽やかに舞踊り、フランク・ウェスのフルートはハートウォームな表現を大切にした健実な助演で好感が持てます。
そしてハンク・ジョーンズのセンスの良さは絶品♪♪~♪ 地味なところが逆に凄いという感じでしょうか、流石だと思います。
B-2 Opus And Interlude
ちょっとバラエティ番組のギャグオチのようなテーマメロディが、なかなかオトボケのブルースですが、アドリブパートは真正ハードバップの快適さが充満しています。そのミディアムテンポの淡々としたグルーヴは、このセッションならではの味わいでしょうねぇ~♪
ちなみに既に述べたように、その原動力となっているベーシストのエディ・ジョーンズは、フランク・ウェスと同じく、当時のカウント・ベイシー楽団ではレギュラーを務めていただけあって、生粋のブルースフィーリングとジャズのグルーヴをナチュラルに表現出来る名手として忘れ難い快演が、ここに記録されたようです。
それゆえに各人の持ち味が存分に披露されるアドリブパートは大充実! これがハードバップの素晴らしさです。
ということで、何れの曲も分かりきった楽しみに満ちた名盤だと思います。そして何度聴いても、決して飽きない傑作じゃないでしょうか。
今時期のウキウキした気分にもジャストミートだと思います。