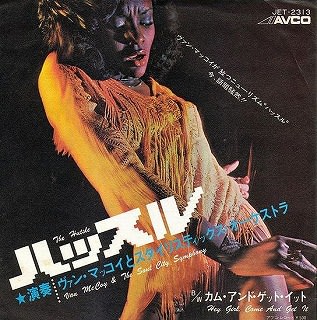■Sam Cooke Live At The Harlem Square Club, 1963 (RCA)

もちろんサム・クックは「ミスター・ソウル」と崇められる偉大な黒人歌手であることは、今や説明不要だと思います。
しかしサイケおやじは正直、何故サム・クックが「ミスター・ソウル」なのか? 恥ずかしながら長い間、それが全く理解出来ませんでした。
それでもサム・クックがオーティス・レディングやジョン・レノンやロッド・スチュアート等々、多くの凄い歌手から尊敬される存在であることは、日本で洋楽を聴いているサイケおやじにも知識としてはありましたし、実際に前述したボーカリストが素晴らしいカパーバージョンを吹き込んでいる事からして、サム・クックはやっぱりソウルの神様なのか!?
という漠然とした真実を確かめる事は、所謂ひとつの責務として、サム・クックの代表曲が入ったベスト盤LPを聴いてみたのですが、これがどうにも黒人らしさ、つまりソウルフルな感覚が薄く、しかもソフトなメロデイ優先主義の上手い歌手という印象だったんですねぇ……。
う~ん、これが「ミスター・ソウル」とは、これ如何に!?
今となっては完全に笑われてしまうんでしょうが、偽りの無い気持です。
しかしご存じのとおり、サム・クックはそのキャリアの初めにはゴスペル歌手としての成功があり、次いで1957年頃に大衆歌謡の世界へ転じた時、どういうわけか当時流行のR&Bスタイルではなく、反ロケンロールとも言うべき歌物スタンダードを吹き込んでいきました。
それが前述のベスト盤に収められていた「You Send Me」や「For Sentimetal Reasons」、そして「Wonderful World」等々の大ヒット曲に代表されるソフトな語り口を活かした名唱なんですが、そのあたりを「ミスター・ソウル」の真髄として聴くには、レコードという媒体は、あまりにも肩すかしでしょう。
実は後に知り得たことですが、ジャズやR&Bの黒人ボーカリストが大きな成功を収めるためには、白人マーケットにも売れる歌謡パラードをメインにする必要性があったようで、例えばビリー・エクスタインやナット・キング・コール、そしてロイ・ハミルトン等々が絶大な人気者であった事を鑑みれば、サム・クックのそうした路線も当然であったのです。
そしてもうひとつ、少なくともサイケおやじの世代はビートルズ以降の洋楽がリアルタイムのはずですから、基本的に強くて粘っこい黒人ピートやコブシには慣れきっているんでしょうが、当時のアメリカの白人少年&少女は当たり前の人種差別によって、本物の黒人音楽に接する機会が極めて少なかったはずですから、サム・クックが狙った白人ウケするレコードでさえも、相当に黒っぽく感じられたんじゃ~ないでしょうか?
とすれば、サム・クックのダンス系ヒット曲としては代表的な「Twistin' The Night Away」にしても、素っ気無いほどの歌いっぷりが妙にインパクトの強いものに感じられるのです。
ちなみにサム・クックが残したレコードでは、明らかに大人向けの歌謡パラードや歌物スタンダードで作られたLPに対し、シングル盤は十代向けというか、そういう恣意的な制作企画があったように思いますし、実際の巡業ステージでは白人御用達のナイトクラブとは別に黒人専用のドサ回りっぽいライプもやっていたのが定説で、おそらく「ミスター・ソウル」の真髄は後者にあったと思われます。
で、そんな漠然とした推察がぼんやりと浮かんでいた頃、それは1985年だったんですが、忽然として輸入盤屋の店頭に出ていたのが、本日ご紹介のライプアルバムでした。
A-1 Feel It
A-2 Chain Gang
A-3 Cupid
A-4 Medley:It's All Right - For Sentimental Reasons
A-5 Twistin' The Night Away
B-1 Somebody Have Mercy
B-2 Bring It On Home To Me
B-3 Nothing Can Change This Love
B-4 Having A Party
さて、ライプ盤の魅力とは、その一端であるにせよ、ファンが憧れのスタアのステージに接する興味と喜びであって、そういう需要と供給から実況録音が行われるわけですから、主役にとっては自らの人気を証明する絶好の機会でしょう。
サム・クックの場合も、1964年12月の突然の悲報により他界する以前、既に公式ライプアルバム「アット・ザ・コパ」と題されたLPを作っていて、これは同年7月、ニューヨークのナイトクラブ「コパカバーナ」に出演したステージを録った人気盤ながら、内容は白人客にアピールする目的を優先させたが如き、なかなか小粋にスイングする歌物が中心ですから、決して「ミスター・ソウル」の本領発揮を期待するとハズレます。
ところがご紹介の発掘ライプ音源は、1963年1月にマイアミの黒人客もOKというクラブでのライプレコーディングですから、その基本姿勢が違うという事でしょうか、実に生々しくも熱いブラックフィーリングが全篇に噴出しまくっているんですねぇ~~♪
しかも音質は、おそらく正規録音(?)であり、歌も演奏も観客の拍手やざわめきさえも、ソウルの闇鍋の如く、最高のゴッタ煮が美味しく楽しめるのです。
それはA面ド頭「Feel It」の幾分軽い肩慣らしから、続く「Chain Gang」では既に熱気全開という会場の雰囲気がピンピンに伝わって来る流れが圧巻! さらにスタジオバージョンでは甘さが目立って虫歯になりそうだった「Cupid」でさえも、ここでは粘っこいハードスイングになっているのですから、たまりません♪♪~♪
そして最初のハイライトが「It's All Right - For Sentimental Reasons」の極みのメドレーで、ゴスペルフィーリングをモロ出しにするサム・クックに呼応する観客のコーラスは、まさにコール&レスポンスを超越した魂の合唱ですよっ!
あぁ~、これを最初に聴いた時のサイケおやじは、心からの歓喜で震えてしまったですよ♪♪~♪
う~ん、サム・クックって、こんなに凄かったんだぁ~~!
これぞっ、「ミスター・ソウル」に偽り無し!
と、思わず熱くなってしまいましたが、もちろんサム・クックは闇雲にシャウトしているわけではありません。
持ち前のソフトな歌いっぷりと高音域に入っていく瞬間に聞かせてくれる絶妙のコブシ、如何にもゴスペル出身者らしい粘っこい説得力を前面に打ち出した節回し等々、それは今日の黒人ソウルミュージックでは当たり前の基本を自然体で演じているにちがいありません。
ですからお馴染みの「Twistin' The Night Away」がアップテンポで披露されても、スタジオバージョンで感じられたスピード感の軽さが、ここでは黒人音楽だけが持つ特有のトライヴ感に変質しているように思います。
いゃ~、このA面の流れ、本当に何度聴いても飽きませんねえ~~♪
しかしB面もさらに素晴らしく、抑えきれない(?)ゴスペル衝動が隠し様もない「Somebody Have Mercy」や「Nothing Can Change This Love」、お待たせしましたの大ヒット曲「Bring It On Home To Me」におけるネチネチした表現は、明らかに後の白人ロック歌手にも多大な影響を与えている事が確認出来るでしょう。
そしてオーラスの「Having A Party」が、これまた意外なほどの素っ気無さを逆手に活かした絶妙のクライマックスを出現させている感じですから、もう、会場は興奮のルツボ! 歓喜の喝采はもちろんの事、時折に雑音と思われる拍手は、おそらく録音マイクの傍にいたレコーディングエンジニアが我を忘れた行動じゃないかと推察されるほど、その場の雰囲気は狂熱に包まれていたわけです。
ちなみにバックの演奏はキング・カーティス(ts) のバンドがメインで、そこには弱冠二十歳のコーネル・デュプリー(g)、ジョージ・スタッブス(p,org)、アルバート・ガードナー(ds) 等々が、サム・クックの巡業用バンドの面々と最高のグループを演出提供しているのですから、たまりませんねぇ~♪ もちろん親分のテナーサックスも適所で任侠節を聞かせてくれますよ♪♪~♪
ということで、こんなにR&B本来の魅力を堪能させてくれるレコードが、なんとっ! 22年間もお倉入りしていたという、その信じ難い事実!
まあ、確かにサム・クックは生前、黒人公民権運動に深く関わり、自ら作った黒人意識高揚の曲を堂々と歌っていましたから、最期の瞬間となった射殺事件の真相も含めて、白人社会には長らくそっとしておきたい天才だったのかもしれません。
また黒人ミュージシャン全体の地位向上という大義名分を得て、自らの楽曲を管理する音楽出版社の設立やレコード会社との印税配分のゴタゴタ等々、あきらかに白人資本家にとっては、疎ましい一面を持った歌手でした。
それが白人と黒人の両方にウケていたという現実は、既に述べたとおり、双方のマーケットでスタイルやポリシーを使い分けていたという、些の狡さもあったからという分析は認めざるを得ないかもしれません。
しかしサム・クック本人は決して聖人君子ではなく、お金や女や酒でのトラブルも人間的な誘惑に負けての結果であることを知ってみれば、非常に親しみの持てる天才だと思います。
ということで、このLPは素晴らしく熱くて楽しい傑作盤!
出た当時から、ずぅ~~っと愛聴しているんですが、実は発売された頃はちょうどCDが実用化され、このアルバムも逸早くそれが輸入されていました。
で、友人から流行最先端のメディアとして聞かせていただいた同音源は、まさに仰天! その音質のクリアーさは無論の事、アナログ盤LPではカット編集されていた曲間の諸々がしっかり追加された完全版仕様になっていたんですねぇ~~!?
そのあたりは冷静に考察すれば、パッケージ化された同音源の曲の流れが実際のステージどうりであったのか? そういう分析も含めて、何かと疑問もあるわけです。
ただし、それはそれとして、そのCDバージョンで聴く事が出来た同アルバムのさらに凄い実態は、常に時代に遅れているサイケおやじにCDブレイヤー導入を決断させるきっかけのひとつになった事を付け加えておきます。
もちろん現在では、しっかりCDもゲットして、聴きまくっていますよ。
なにしろ何時如何なる時に聴いても、感動しますからねぇ~~♪
サム・クックの真髄、「ミスター・ソウル」と称された理由が、ここにあります!!
最後になりましたが、随所に滲み出るロッド・スチュアートっぽい節回しは無論、本末転倒!
しかし、続けてロッド・スチュアートが聴きたくなる衝動も抑えきれないのでした。