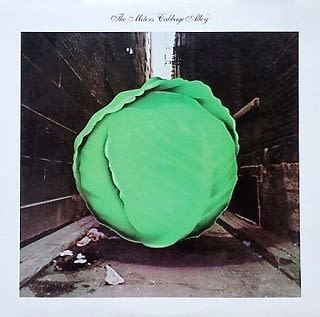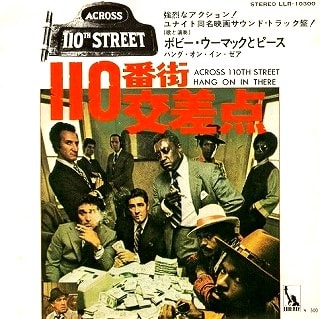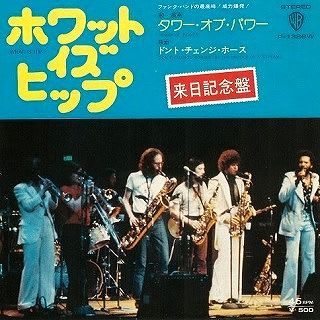■愛しすぎて / Otis Redding (Reprise / ワーナーパイオニア)
さて、汗ダラダラの真夏のソウルレビューといえば、オーティス・レディングが1967年にやってくれたモンタレー・ポップ・フェスティバルの熱唱熱演も忘れられません。
その模様はイベント全体が映画として撮影され、これまでに様々な仕様で公開されて来ましたが、もちろん音源も同様に多種出回っている中でも、圧巻だったのはジミヘンとオーティス・レディングのパフォーマンスであった事は歴史が認めるところですし、件の映像も音源も、あえて件の二人に特化したブツが人気を集めるのもムベなるかな!
本日掲載したシングル盤も、全くその中のひとつして、オーティス・レディングの魂の歌が堪能出来る1枚であり、殊更A面曲「愛しすぎて / I've Been Loving You Too Long」は、これ無くしては人生の意味も……!?
サイケおやじは、そこまで思い込まされる事も度々です。
ちなみにオリジナルは、もちろんオーティス・レディング自作自演による1965年のヒット曲なんですが、それはあくまでもアメリカの黒人マーケットでの成果であり、しかも最初はB面扱いだったと言われています。
で、それがモンタレー・ポップ・フェスティバルに集まるような白人の音楽ファンに知られるようになったのは、ストーンズが1966年12月にアメリカ優先で発売したライブアルバム「ガット・ライヴ・イフ・ユー・ウォント・イット!」にカバーバージョンを入れた事による功績が大きいと思われますが、実はストーンズの「愛しすぎて / I've Been Loving You Too Long」はスタジオ録音のテイクに歓声等々をオーバーダビングした疑似ライブという真相も、なかなか意味深でしょうか。
そして本家本元のオーティス・レディングが白人主体の大観衆の前に登場した事も、おそらくは芸歴の中で最初のギグだったとすれば、あくまでも自然体にありながら、やはり熱が入っていたのは否定出来ないように思います。
そのあたりは皆様も、前述の映像作品等々を楽しまれて、再び音源だけの鑑賞に浸るのを吝かとしない状況に証明されると言えば、いやはやなんとも、本日もサイケおやじの独断と偏見ではありますが……。
また、今となっては伝説になってしまいましたが、故・忌野清志郎がステージのキメ台詞にしていた「愛しあってるかぁ~~い?」の元ネタが、実はこのモンタレー・ポップ・フェスティバルでオーティス・レディングが「愛しすぎて / I've Been Loving You Too Long」を歌い始める前のMCの一節「We all love each other, right? Let me hear you say YEAH!」の日本語訳字幕であったという逸話も、なかなか眩しいですねぇ~~。
事実確認作業としては、昭和50(1975)年8月に放送されたNHKヤング・ミュージック・ショウにおけるモンタレー・ポップ・フェスティバルの映像が最良とされていて、それは現在出回っている公式映像ソフトでは、字幕が変わっているからなんですが……。
ということで、猛暑にギトギトの南部ソウルは、これまたひとつの我慢大会というよりも、自ら望んで激辛カレーを食するような、冒険的快感かもしれません。
サイケおやじは、例え愚行と言われようとも、好きです。