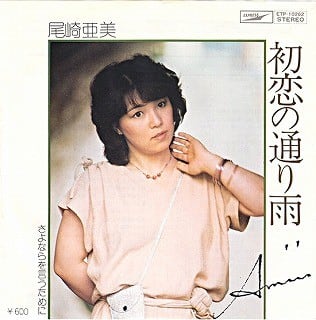■東京チーク・ガール / 河合夕子 (EPIC / SONY)

そりゃ~~ないぜっ!
と思わず呟く、あるいは嘆き節、時としては歓喜悶絶の瞬間ってのは、誰にだって必ずやあるはずで、サイケおやじにとっては本日掲載のシングル盤A面曲「東京チーク・ガール」を耳にした最初っから、丸っきり後頭部を突然に殴られるってのは、この事かっ!
そんな強烈な衝撃を覚えてしまったんですよっ!
なにしろイントロからしてドゥービー・ブラザーズが1979年にメガヒットさせた「What a Fool Believes」をシンセ主体のキーボードサウンドに焼き直しただけじゃ~なくて、楽曲主旋律までもが同じリフメロディで歌われていくんですから、全くのなんじゃ~~これっ!?
っていう松田優作のジーパン語録!!
で、これはラジオから流れて来たとはいえ、その声の主が河合夕子というシンガーソングライターという事は、この「東京チーク・ガール」は自作自演という狂言なのかぁ~~~!?
ところが、楽曲そのものの全体としての仕上がりは素晴らしく、弾んだリズムにファルセットを活かしたコーラス・アレンジも心地好く、これぞオンタイムの昭和56(1981)年にサイケおやじが求めていたサウンドにジャストミート!!
そして速攻でレコード屋を急襲し、ゲットしたのがこれというわけなんですが、クレジットを確認してみれば、やはり作詞作曲は河合夕子、そして編曲は水谷公生の名前があるものの、実は後に知ったところによれば、彼女の楽曲レコーディングには以前に愛奴に在籍し、浜田省吾のバックでも活躍していたギタリストの町支寛二の働きが大きかったそうで、以降に発売されていく彼女のアルバムのプロデュースも担当するのですから、要注意でしょう。
肝心の河合夕子については、これ以前も以後も、それほどプロフィールも知らないんですが、当時からテレビ出演も多かった記憶がありますし、ルックス的には平田隆夫とセルスターズのみみんあい、あるいは漫画のアラレちゃんの様でもあり、つまりは愛嬌フェイスの存在感と無意味に高揚感が素晴らしいパフォーマーという印象でしょうか。
それはサイケおやじの勘違いかもしれませんが、この「東京チーク・ガール」の気持ち良さは、見事なほどに希薄な歌詞のイメージとサウンドそのものの浮ついたノリと思えば、これからの季節には欠かせない魅力に満ちているはず?
結果的には河合夕子は数枚のアルバムやシングル盤を出しながら、何時しか表舞台からスタジオセッションの世界へ活動の場を移してしまい、今では音源の復刻も芳しくありません。
しかし、この「東京チーク・ガール」だけは忘れられていないインパクトがあるはずで、それが狂言だろうが、漫画だろうが、十人十色の感性には関係の無い話です。
唯そこに、気持ちの良い歌がある!
その真実はひとつと思うばかりです。