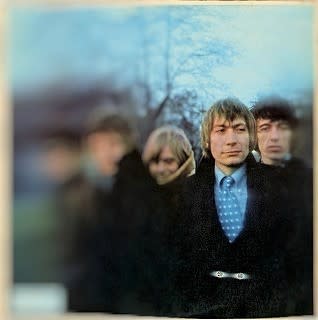■いつか誰か c/w フェニックス / ザ・ジャガーズ (フィリップス)

いゃ~~、昨夜の地震には仰天させられましたですねぇ~~!?!
ご無事でありましたでしょうか、皆様は?
その時刻、サイケおやじは所用で横浜の妹の家に居たんですが、かなりの被害が各所で予想され、帰宅事情も悪そうだったんで、そのまんま、妹の家に泊まって朝を迎えた次第です。
そして昨日は、もうひとつ、大きな激震がありました。
それは……、ソングライター&プロデューサーとしての仕事ばかりか、各方面での多才な活動により、我が国の文化・芸能界に絶大な功績を残した、すぎやまこういちの訃報でした。
しかも、他界されたのは先月末だったそうですが、昨日の公表というのが、弟子だった故・筒美京平の命日の1年後という、その運命の悪戯というには、あまりにも現世の運否天賦さえ感じてしまったほどです。
で、故・すぎやまこういちの偉大な業績については、とても語り尽くせるものではありませんが、個人的には芸能界の裏方としての活動の中で、スタア予備軍の温床とも云える、今や伝説の「野獣会」を立ち上げた事は、決して無視されるべきでは無いでしょう。
もちろん、その実態・実状について、サイケおやじの知っているところは限られてはいるんですが、とにかく「野獣会」は六本木周辺に集う遊び仲間のグループだったらしく、そこからは田辺靖雄、小川知子、大原麗子、井上順、中尾彬、等々が芸能界へスカウトされ、スタアになっていったんですが、元々は故・すぎやまこういちが当時、フジテレビで担当していたバラエティ番組への出演者を選抜するために集めたグループだったという真相があるらしく、それが昭和36(1961)年だったと云われています。
さて、そこで本日掲載したのは、昭和45(1970)年に発売された、これがジャガーズのラストシングルとされる1枚なんですが、そのジャガーズこそが、件の「野獣会」が音楽活動を始めた流れから結成されたバンドであり、もちろん当時は「野獣会オールスターズ」と名乗っていたそうですが、とにかくGS関連の楽曲にも多く関わってきた故人が、このシングル盤両面2曲で作編曲を担当したというのも、妙な因縁(?)を感じてしまいますねぇ……。
ちなみに作詞は、両面ともに阿久悠で、まずはA面「いつか誰か」はミディアムテンポのソフトロック歌謡に仕上がっているという事は、オーケストラも堂々と導入した、なんともアソシエイションがモロ出しの面映ゆさ (^^;
どうやら、例の万博の中のイベント用に作られた楽曲という説もありますから、これはこれで当時の流行を意識したものだったんでしょうが、肝心のジャガーズはGSブーム衰退の中で、メンバーも流動的となっていた時期で、岡本信(vo)、宮崎こういち(g)、佐藤安治(key)、森田巳木夫(b)、浜野たけし(ds) という面々がラインナップされてはいますが、サイケおやじは実際に当時のジャガーズのステージに接した事がありませんし、テレビ出演していたという記憶も薄いもんですから、その真の姿は知る由もありません……。
しかし、このレコードに収録された楽曲トラックは、既に述べたとおり、ソフトロック歌謡としては、如何にも「EXPO '70」な前向きなムードを今に伝えてくれる裏名作で、それはB面収録「フェニックス」でも、同じ味わいが全開 (^^)
このあたりの感覚こそが、ジャガーズというよりも、完全に故・すぎやまこういち!
――でありましょう (^^♪
穿ち過ぎかもしれませんが、後年の代表作「ドラクエ」あたりにも繋がる、壮大でありながら、個人主義をも大切にした音楽が提供されているんじゃ~ないでしょうか。
しかし、結果的に……、このレコードは売れず、ジャガーズもフェードアウトしてしまい、それでいて何故か中古屋の店頭にはゴロゴロ並んでいた時期がありましたから、デッドストックが相当にあったんでしょうかねぇ~~(^^;
このサイケおやじの私有盤にしても、それなんですよ (^^;
ということで、現在の日本で生活している我々にとって、「すぎやまこういち」という名前を全く知らない人は、ほとんど皆無でありましょう。
例え故人の業績の全てを把握していなくとも、我々の精神構造の中に自然と刷り込まれているのが「すぎやまこういち」の素晴らしい才能だと思うばかりです。
そして、衷心より、ご冥福をお祈りいたします。
合掌。