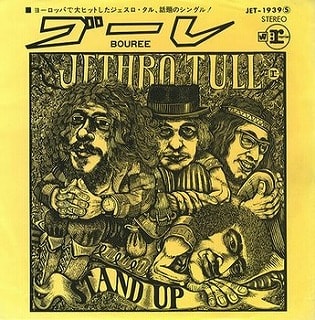■Dick's Picks Volum One / Grateful Dead (GDCD)

スタジオ録音よりは明らかにライプステージでの演奏に魅力を発揮出来るミュージシャンが確かに存在し、例えばグレイトフル・デッドは、その代表格かもしれません。
ですからライプアルバムも数多く出していますし、巡業公演から作られたブートもどっさり出回っていますが、それはグレイトフル・デッド側の寛容な姿勢によって、会場毎に決められた料金さえ払えば、ファンは堂々と録音出来る環境が許されていたからです。
もちろんグレイトフル・デッド本人達にしても、実は正式デビューした1967年以前から、自分達のステージのほとんどを録音していたという、実に几帳面なところがあって、ついに1993年頃は、その中から選んだ音源を自ら発売するという企画がスタート!
それが「ディックス・ピックス」と呼ばれるシリーズで、本日のご紹介は、とりあえず、その最初となった2枚組のCDです。
☆CD ONE
01 Here Comes Sunshine
02 Big River
03 Missiesippi Half Step
04 Weather Report Suite
05 Big Railroad Blues
06 Playing In The Band
☆CD TWO
01 He's Cone →
02 Truckin' →
03 Nobody's Fault But Mine →
04 Jam →
05 Other One →
06 Jam →
07 Stella Blue
08 Around And Around
既に述べたようにグレイトフル・デッドというバンドは、1960年代中頃からのサンフランシスコでサイケデリックロックの代表選手でしたから、アドリブどっさりの長尺演奏は得意中の得意でしたが、その側面というか裏側として、LSDという薬物による実験や各種ドラッグとの相乗効果による、所謂トリップを音楽で表現したり、あるいはそういう状態をさらに具象化していく狙いがバンドとしての存在意義だったことは諸説ありながらも、ある意味では外れていないと思われます。
ですからグレイトフル・デッドには、通称「デッドヘッズ」という熱心なファンが存在し、巡業の追っかけを長年やっている信者が大勢いるのです。
実は、これはちょっとヤバイ実情なのですが、グレイトフル・デッドのライプに常に大観衆が集まるのは、そこで良質のドラッグ類が容易く手に入るからだと言われています。
まあ、それはそれとして、とにかくグレイトフル・デッドのライプ演奏は、クセになる心地良さを秘めているのは間違いなく、例えそんなものに頼らなくとも、聴いているだけで音楽的な快楽を得られる大勢のファンの存在だって無視出来ないでしょう。
さて、このCDに聞かれるのは1973年12月19日、フロリダはタンパでのライプ音源で、これまで公式盤として出してきたライプアルバムと決定的に違うのは、ステージを極力、そのまま収録していることです。
ご存じのようにグレイトフル・デッドのライプは演奏時間が長く、それはアドリブパートや演奏の膨らみ具合により、決して毎回が同じではないところに魅力の一端があります。
それゆえに「ディックス・ピックス」のシリーズは今日まで、いろんな時代の壁を超え、かなりのボリュームになっていますが、その全てに聴きどころがあり、このひとつだけでは、とてもシリーズの存在意義を語ることなど不可能です。
しかし、この音源が残された時期のグレイトフル・デッドは、デビュー以来のワーナーから自分達のレーベルを設立しての最初のアルバム「新しき夜明け」を発表した直後とあって、タイトルどおりに気分一新の意気込みがあったように思われます。
メンバーはジェリー・ガルシア(vo,g)、ボブ・ウィア(vo,g)、フィル・レッシュ(b)、ビル・クルーツマン(ds)、そして特別参加のキース・ゴドショウ(p,key) の5人組だと推察出来ますが、その演奏は実に伸びやかな自然体♪♪~♪
繰り返しますが、グレイトフル・デッドのステージ進行は基本が同じでも毎回、その時の気分によって大きく変化していくのが常で、ここではまず前述の最新アルバム「新しき夜明け」に収録されていた「Here Comes Sunshine」がユル~く始まります。もちろん観客にはピカピカの新曲ということで期待と不安があるんでしょうが、演奏は何時しか浮遊感に満ちた展開となり、そこにはジェリー・ガルシアの不思議界ギターとも言うべき、所謂スペーシーなアドリブを中心に、各メンバーがジコチュウと協調のバランスを取りながら、グループとしての纏まりを追及していく構成が気持良いかぎり♪♪~♪
つまりライプの現場では、ひとつの楽曲がテーマとなってアドリブパートが膨らんでいくという、ジャズと同じ手法が繰り広げられているのです。
まあ、こうしたやり方は同時代のオールマン・ブラザーズ・バンド等々にも聞かれますが、例えばオールマンズが演奏の要所にキメのリフやお約束を盛り込んでいるのに対し、グレートフル・デッドはあくまでもナチュラルな姿勢というか、ある意味では成り行き任せの展開から起承転結を作り出しているように思います。
ですから、ひとつ間違えると、ユルユル過ぎて、素面では聴いていられないところも確かにあるんですが、虚心坦懐にグレイトフル・デッドの演奏に身を任せていれば、快楽の桃源郷は必ず現出するというのが、このグループのライプならではの素敵なところじゃないでしょうか。
この時期の演奏スタイルとしてはサイケデリックロックの残滓、カントリーロック、フュージョンとフォークソングのゴッタ煮、さらにR&R保守本流の躍動が、それこそ千変万化に消えては現れるメドレー形式が特徴的です。特に「CD TWO」では演目に「→」がわざわざ表記されているとおり、本当に美しき流れが堪能出来ますよ。
ちなみにグレイトフル・デッドに、どうしてこんな演奏が出来るのかはミステリアスな部分も多いのですが、おそらくはモダンジャズでは普通のモード手法の導入とか、暗黙の了解があってのことでしょう。素人には計り知れぬ奥行なんでしょうねぇ。
ただし、そんな理論的なことは関係なく、グレイトフル・デッドの演奏は不思議に心地良いですよ♪♪~♪
大まかに演奏をリードしていくのはジェリー・ガルシアのギターなんですが、そこへ執拗に絡んでいくボブ・ウィアのサイドギター、陰湿に暗躍するフィル・レッシュのペース、反応が適材適所に素早いビル・クルーツマンのドラミング、さらに的確な伴奏としぶとい演出をサポートするキース・ゴドショウのピアノは、繰り返しますが自然体でありながら阿吽の呼吸で纏まっています。
ちなみに、このシリーズの命名に関しては、主に音源管理をやっているスタッフのディック・ラトヴァラに因んだもので、倉庫が満杯になるほどのテープの山から、本人の好み優先で選んではCD化しているとか!?!
そういえば一時期、グレイトフル・デッドの優良ライプ音源が夥しく出回ったことがありましたが、それは件の倉庫の賃借料金が滞納された所為だったとか!?!
というように、書けば書くほど止まらなくなるのが、グレイトフル・デッドのミステリです。
幸いにも私は1990年に唯一度だけ、グレートフル・デッドのライプに接することが出来ましたが、まず会場には可愛らしい熊の人形とか、ステッカーやTシャツ等々の公認グッズがいろいろと売られていて、そのホンワカしたムードにサイケデリックな先入観を覆されました。
また前述したように客席には特別料金のプライベート録音エリアがあって、そこには各々が大袈裟なマイクを立てたり、昔ながらの巨大なオープンリール、あるいは最新のDATを駆使しながら、演奏が始まってもモニターばかりに気をとられている熱心なマニアが大勢いたことにも驚きました。
そして演奏は本当に長時間続き、会場はフリーエリア状態でしたから観客は立ったり、寝そべったり、もちろんラリルレロで踊っているやつも目立ちましたですね。しかし決して暴動なんかにはなりそうもない、非常に良い感じだったのが思い出に残っています。
グレートフル・デッドは長いバンドの歴史の中で、多くの演奏を残してくれましたから、最初はどっから聴いて良いのか迷われるかもしれませんが、個人的にはどれでも良いから、まずはライプ音源から楽しむことをオススメ致します。
ちなみに「ディックス・ピックス」のシリーズは、公式発売を想定したレコーディングではなく、サウンドボード直結のライン録音がメインなので、左右と真ん中から分離し、団子状になったサウンド作りになっていますから、観客の声援や拍手も控えめにしか聞こえませんので、臨場感は希薄です、
しかしそれゆえにライプの現場での一発勝負の生々しさは半端ではありません。当然ながら凡ミスも散見されますし、チューニングの狂いや時には楽器の不調といったハプニングが記録されていることもあります。
でも、それがグレイトフル・デットという魔法のバンドにあっては、全てが良い方向に作用していると感じるのは、サイケおやじの思い込みでしょうか……。もちろん、その日によっての演奏の良し悪しは確かにあって、あくまで個人的な基準としては、フィル・レッシュが好調だと、バンドのノリや創造力も高まっているように思います。
ということで、皆様にも、ぜひ、お楽しみいただきたいのが、グレートフル・デッドのライプです。ただし中毒性が強いですから、ご用心、ご用心。