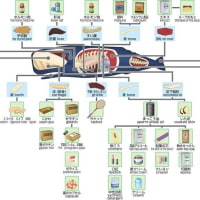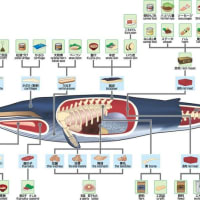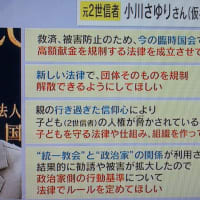2月1日(日):
時代の正体〈57〉わたしたちの国はいま(1) 思想家・内田樹さんに聞く 「よみがえる死者たち」2015.01.30 11:30:00
内田樹さん
私たちの国はいま「滅びる」方向に向かっている-。2015年が明けた1月1日、思想家の内田樹さんはブログにそうつづった。先の大戦の終結から70年、戦後民主主義が揺らぎ、経済成長の先行きに限界が見える中、日本はいま破局へ向かう途上のどの地点にいるのだろうか。
いま、世界的な現象として同時多発的に排外主義が跋扈(ばっこ)している。興味深いのは、ドイツ、フランス、日本という「敗戦の総括をうまくできていない国」において、それが顕著だということです。死者が死に切っていないせいで、「生煮えの死者」がよみがえっている現象のように私には見えます。
例えばフランスは、イスラム過激派によるテロは自分たちの「自由、平等、博愛」という民主主義の原理への攻撃だとしていますが、その言い分にはいささか無理があると思います。
フランスは戦勝国のような顔をして戦後世界に登場しましたが、事実上は敗戦国です。対独講和後成立したヴィシー政府は「自由、平等、博愛」の原理を一度捨て、「労働、家族、祖国」を掲げて、ナチスの後方支援をし、国内ではユダヤ人狩りをし、共産主義者やレジスタンス運動を弾圧しました。
でも、フランスはそうした過去を戦後きちんと総括していません。シャルル・ドゴール率いる自由フランスとレジスタンスが最終的にドイツ軍を敗走させたことをもって「フランスが勝利した」という物語を作り出した。そして、ヴィシー政府の官僚たちの多くは訴追されることもなく戦後フランス社会のエリート層を形成しました。
この「敗戦の否認」ゆえに、フランス人は自分たちが民主的な手続きを経て、自らの選択でファシスト政権を成立させたという歴史的事実に向き合うことをしていません。自分たちの国の政治文化のうちにそのような排外的・暴力的な要素が内在していることを認めない。
しかし、そうやって抑圧された政治的幻想は幽霊のように繰り返しよみがえってくる。それが「生煮えの死者」です。昨年6月の欧州議会選挙で、極右の国民戦線が第1党に躍進しましたが、別に前代未聞のことが起きたわけではありません。抑圧されていた過去がよみがえってきたのです。
■語らぬ戦犯
ドイツも事情は似ています。ドイツは戦争責任のすべてをナチスに押しつけて、ドイツ国民を免罪しようとした。
事実、ナチスに反対したドイツ人はたくさんいましたし、ヒトラー暗殺計画も繰り返し企てられました。だから、ドイツ国民とナチスは「別物」であり、戦争責任・敗戦責任はあげてナチスという一政党にあるという物語は戦後のドイツ人たちにとっては説得力を持つものでした。そうやって国民は部分的に戦争責任を解除された。
ドイツの歴代大統領は欧州各地を訪れるたびにナチスの犯罪を謝罪していますが、それはかつてドイツを強権的に支配していた独裁者の罪についての謝罪なのか、そのような独裁者を歓呼の声で迎えたドイツ国民の罪についての謝罪なのか、必ずしもはっきりとはしていません。
しかし、自己欺瞞(ぎまん)はいずれ破綻をきたします。フランスではアルジェリア戦争以来、反イスラムの政治的潮流は絶えたことがありません。ドイツもネオナチには厳罰で臨みますが、その一方でトルコ系移民は構造的に排斥されている。イタリアでもネオファシストの運動は戦後一貫して社会的影響力を失ったことがありません。
では、日本における敗戦の総括はどうだったか。戦争責任を追及した東京裁判は日本人自身によるものではありません。戦犯の指名も、罪状も、量刑も連合国軍総司令部(GHQ)の占領政策に沿う形で行われました。最終的に何人かがみせしめ的に処刑され、占領政策に利用できそうな人間は釈放されて政治家として戦後の「対米従属」戦略を担いました。「本当は何があったのか」についての調査は早々と打ち切られました。
戦犯たちの誰一人「戦争目的は何で、どのように戦争計画を立案し、どのように戦い、どのように敗れたのか」を戦争主体の立場から語ることができなかったからです。だから、私たちはいまだにあの戦争がなぜ始まったのか、本当はそのとき何があったのかを知らないままなのです。知らないまま一応つじつまのあった「敗戦についての物語」を採用して、それを信じているふりをしている。
■物語の破綻
日本を含めた敗戦国は、戦争と敗戦について、それぞれに物語を作りました。その作話に際して、恥ずべき事実や、受け入れがたい事実は隠蔽(いんぺい)されました。仕方がないといえば仕方がない。そのような事実に向き合うだけの精神力も体力も敗戦国民には望むべくもないからです。
戦後しばらくはどの国でもそういう物語は一定期間有効でした。でも、短期間に無理やり作った話ですから、いずれボロが出る。それが戦後70年たって噴出してきた。私はそう見立てています。
1980年代からの歴史修正主義や移民排斥や極右政党の進出や反イスラムは、この敗戦のときに作った物語の破綻として理解できます。敗戦の「物語」にうまく収まり切らないものが物語の隙間からしみ出している。「ガス室はなかった」とか「南京虐殺はなかった」といった主張をなす歴史修正主義者を駆り立てているのは、実は「忘れたことにしている話」がもたらす破壊への恐怖です。物語に収まりきらない歴史的事実が明かされることがどれほどの破壊力を持つかを彼らは実は知っているのです。
日本の戦争責任については東京裁判とサンフランシスコ講和条約でもう話は済んでいると言う人たちがいます。日韓条約を結び、日中共同声明も発表した。いまさら古い話を蒸し返すなと。しかし、戦争については「本当のところはどうだったのか」という問いがある程度時間がたつと、再び提出されてくることは避けがたいのです。国際法上戦後処理は済んだと言い張っても、そのときに不都合なことを隠蔽するために使った「物語」の賞味期限が切れてしまうと、塗り固めたはずの傷口からまた血膿(ちうみ)が噴き出してくる。
加害の事実は忘れやすいが、被害の事実は忘れられない。「僕らは忘れたから、君らも忘れてくれ」というロジックは通らない。「君たちは忘れてもいいけれど、僕らは忘れないよ」と加害の事実を記憶し続けるという構えでなければ隣国との和解は成立しないでしょう。
これから私たちはどうすればいいのか。日本人が敗戦のときに作った「物語」を一度「かっこに入れて」、あらためて「本当は何があったのか」という問いを冷静に中立的に主題化すべきだと私は思います。私たちはいわば弔われなかった死者たちの上に家を建てて住んでいます。だから、死者たちは繰り返し化けて出る。気の重い仕事ですけれど、私たちは家の床下から腐乱死体を掘り出して、彼らの死の経緯をもう一度語り直し、そして再び荼毘(だび)に付して魂の安らぎを願うしかないのです。
内田樹(うちだ・たつる) 神戸女学院大名誉教授、武道家、多田塾甲南合気会師範。神戸市で武道と哲学研究のための学塾「凱風館」を主宰。専門はフランス現代思想、武道論、教育論など。主著に「ためらいの倫理学」「街場の戦争論」「日本辺境論」など。
【神奈川新聞】
時代の正体〈58〉わたしたちの国はいま(2) 思想家・内田樹さんに聞く 「民主主義とカネの相性」2015.01.31 09:26:00
いま、「わが国は滅びる方へ向かっている」と口にしても、むきになって反論する人はそういません。ビジネスマンだって、もう経済成長がないことは分かっています。
一時だけ投資家たちがあぶく銭を求めて集まるカジノ資本主義的な事態はどこかの国でまだ何度か起こるでしょうけれど、しょせんはバブルです。歴史過程としての資本主義はもう末期段階を迎えている。そのことは口では経済成長を唱えている人だって分かっているはずです。
にもかかわらず、惰性に任せて「右肩上がり」の成長モデルに合わせて社会制度は改変され続けています。
教育、医療、地方自治、どれも経済成長モデルに最適化したかたちへの改変が強力に進められている。資本主義の仕組み自体、賞味期限が切れて終わりかけているのに、事態がさっぱり好転しないのは「いまのシステムが成長に特化したかたちになっていないからだ」「市場原理の導入が足りないからだ」と解釈する人たちが、終わりつつあるシステムに最適化するという自殺的な制度改革を進めている。
教育がそうです。学校教育法の改正で、大学は一気に株式会社化されました。教授会民主主義が事実上廃絶され、権限が学長に集中する仕組みになった。
株式会社のようにトップダウンで組織が運営され、経営の適否は単年度ごとに数値的に開示される。志願者数、偏差値、就職率、科研採択数、論文提出数、英語による授業時数、外国人教員数といった数値で大学が格付けされ、教育資源が傾斜配分される。営利企業と同じロジックです。
しかし、その結果、いま国公立大学全体の空洞化が急速に進行しています。すでに東大からも高名な教授たちが逃げ出している。当然だと思います。予算は削られ、労働負荷は増え、権限は縮小されたあげくに「さらなる改革努力を」と言われても、もう「笛吹けど」足が動きません。四半世紀休みなく続いた制度改革に教員たちはほとほと疲れ切っている。この後、日本の国公立大学の研究教育機関としての質は低下するばかりでしょう。
国内の大学の質の低下が進めば、国内での学歴では「使いものにならない」ということになる。当然、エリートを目指す人々は海外での学歴を求めるようになる。すでに富裕層は中等教育段階から子どもを海外の寄宿制インターナショナルスクールに送り出しています。その経済的負担に耐えられる富裕層にしかキャリアパスが開かれないのです。
医療も同じです。医療は商品であり、患者は消費者だという市場原理を導入したせいで医療崩壊が起きました。
どこでも超富裕層が最後に求めるのはアンチエイジング、不老不死です。そのためには天文学的な金額を投じることを惜しまない。それなら医療者は医療資源を超富裕層の若返りと延命のためだけに集中させた方が、きつくて安い保険医療に従事するより合理的です。経済格差がそのまま受けられる医療の格差に反映してしまう。米国では金持ちは最高級の医療を受けられ、保険医療や無保険者はレベルの低い医療に甘んじなければならなくなっている。
■株式会社精神
米国のように所得上位1%に国民所得の20%が集中するという格差拡大の流れは市場に委ねている限り、日本でも止まることはないでしょう。
そもそも株式会社は民主主義とは無縁のものです。
経営者が判断したことに従業員はあらがうことができない。当然にも、従業員の過半の同意を得なければ経営方針が決まらないというような企業はありません。すぐつぶれてしまう。従業員も経営判断の適否を判断する責任があるとは思っていない。経営判断の適否はすべてマーケットが判断してくれるからです。マーケットはビジネスにとっての最終審級です。だから、経営判断が民主的であろうと非民主的であろうと、そんなことはマーケットの決定には何も関与しません。
株式会社は右肩上がりを前提にしていますが、しかし、江戸時代までの日本では現状維持、定常再生産が社会の基本でした。
近代化を遂げた後も、久しく農村人口の5割を超えていた。農林水産業は自然が本来持つ生産力を維持するものです。自然は右肩上がりに無限にその生産力を上げるということがありません。何よりも生産力の持続可能性が重要だった。100年後の孫の世代のために木を植えるといった植物的な時間の流れに沿って、社会制度も設計されていた。そのような風儀は1950年代まで残っていました。
しかし60、70年代の高度成長期に農村人口が都市に移動し、サラリーマンが支配的な労働形態になりました。今の日本では株式会社のサラリーマンが標準的な人間ですから、「株式会社従業員マインド」で国家の問題も眺めるようになった。それはつまり植物的なゆったりとした時間の流れの中にはいないということです。四半期ごとの売り上げや収益に一喜一憂し、右肩上がり以外の生き方はありえないという思い込みが国民的に共有されている。
だから、もう成長はないという事実を突きつけられても、それを信じることができない。別のプランが立てられない。とりあえず昨日まで続けてきたことをさらに強化したかたちで明日も続ける。原発を再稼働し、リニア新幹線を造り、カジノを造りといったことをまた繰り返そうとしています。
もちろんそんなことをしても成長はない。それは学校が悪い、自治体が悪い、ついには民主主義が悪いというふうに責任転嫁される。それが現状です。
■歴史的転換点
振り返れば、関西電力大飯原発の再稼働は歴史的な瞬間でした。あのとき経済の論理に国民国家が屈服した。国土の保全と国民の健康かグローバル企業の収益増大かという二者択一で後者を選んだのです。
再稼働を要求した財界の言い分はこうでした。原発を止めたせいで電力価格が上がり、製造コストが上がり、国際競争力が落ちた。再稼働を認めないのなら生産拠点を海外に移す。そうなれば国内の雇用は失われ、地域経済は崩壊し、法人税収も減る。それでいいのか、と。この脅しに野田佳彦政権は屈した。
しかし、グローバル企業はもはや厳密には日本の企業とはいえません。株主の多くは海外の機関投資家、CEO(最高経営責任者)も従業員も外国人、生産拠点も海外という企業がどうして「日本の企業」を名乗って、国民国家からの支援を要求できるのか。
もう一度原発事故が起きたら、どうなるでしょう。彼らは自分たちの要請で再稼働させたのだから、除染のコストは負担しますと言うでしょうか。雇用確保と地域振興のため、日本に踏みとどまると言うでしょうか。そんなことは絶対ありえない。あっという間に日本を見捨てて海外へ移転してしまうでしょう。
利益だけは取るけれど、責任は取らない。コストはできる限り外部化するというのが「有限責任」体である株式会社のロジックです。
民主主義とグローバル資本主義は相性が悪い。民主主義と金もうけは残念ながら両立しません。そして昨年の総選挙の争点は、実は「民主主義とカネのどちらがいい?」という問いだったのです。その問いに日本の有権者がどう答えたのかはご存じの通りです。
【神奈川新聞】
時代の正体〈59〉わたしたちの国はいま(3) 思想家・内田樹さんに聞く 「国家の運営は無限責任」2015.02.01 12:30:00
3・11をきっかけにこの国は変わると思っていました。市場原理に任せて経済成長を目指すのは無理だと気づき、相互扶助の精神に基づいた、もう少し手触りが温かく、暮らしやすい世の中になっていくだろうと思っていました。メディアでもそういう論調が多かったように思います。
「絆」というのも決して薄っぺらな修辞ではなく、同胞は困っているときには助け合わなければいけないという「常識」がよみがえったように思いました。でも、震災半年後くらいから、そういう気分が拭い去るように消えて、「やっぱり金がなければ話にならない。経済成長しかない」という話にまた舞い戻ってしまった。
国土が汚染され、半永久的に居住不能になるかもしれないという国民的危機に遭遇したにもかかわらず、またぞろ懲りずに原発再稼働の話が持ち出されてきました。理由は「電力コストの削減」、それだけです。国民は「命の話」をしているときに、政府は「金の話」をしている。この危機感の希薄さに私は愕然(がくぜん)とします。
株式会社というのは18世紀の英国に発祥したまだ歴史の浅い制度です。その特徴は「有限責任」ということです。株式会社はどんな経営の失敗をしても、それが引き受ける最大の責任は「倒産」です。株券が紙くずになって出資者は丸損をしますが、それ以上の責任を社員(株主)は問われることがありません。
もう一つの特徴は「コストの外部化」ということです。金もうけに特化した仕組みですから、できるだけコストは「誰か」に押し付ける。原発を稼働させて製造コストをカットし、新幹線や高速道路を造って流通コストをカットし、公害規制を緩和させて環境保護コストをカットし、賃金を抑制して人件費コストをカットし、「即戦力」を大学に要請して人材育成コストをカットする。コストを最小化し、利益を最大化するのが株式会社の仕組みです。
東京電力がまさにそうです。福島第1原発で国土に深い傷を与え、10万人を超える人々が故郷に帰れない状態をつくり出しながら、誰一人刑事訴追されていない。日本国民は国土を汚染され、汚染された国土を除染するコストを税によって負担するというかたちで二重に東電の「尻拭い」を強いられています。
しかし、有限責任の組織体というのは、実際にはほとんど存在しません。米大統領だったジョージ・W・ブッシュがそうだったように、国家を株式会社のように経営したいと公言する政治家がいますが、彼らは国家は無限責任だということを忘れている。国家の犯す失政は「じゃあ、倒産します」では済まない。侵略戦争で他国民の恨みを買い、揚げ句に敗戦で国土を失うというような失政をした場合、その「ツケ」を国民は半永久的に払い続けなければならない。
沖縄が米軍基地で埋め尽くされているのも、北方領土が返還されないのも、中国や韓国から謝罪要求が終わらないのも、70年前の失政の負債が「完済されていない」と他国の人々が思っているからです。彼らが「敗戦の負債は完済された。もう日本には何も要求しない」と言ってくれるまで何十年、何世紀かかるかわからない。人間の世界は普通そうなのです。株式会社の方が例外的なのです。
■株式会社化
株式会社の仕組みを国家運営に適用できると主張している人たちが依拠しているのは「トリクルダウン理論」です。新自由主義者の言う「選択と集中」です。経済活動をしている中で一番「勝てそうなセクター(分野)」にある限りの国民資源を集中させる。そこが国際競争を勝ち抜いて、シェアを取って、大きな収益を上げたら、そこからの余沢が周りに「滴り落ちる(トリクルダウン)」という考え方です。韓国は「勝つ」ためにヒュンダイ、サムスン、LGといった国際競争力のある企業に資源を集中させて、農林水産業や教育や福祉のための資源を削りました。競争力のないセクターは「欲しがりません勝つまでは」という忍耐を要求された。
中国のトウ小平の先富論も同じものです。沿海部に資本と技術と労働者を集中させ、経済拠点を造りました。稼げるところがまず稼ぐ。その余沢が内陸部の貧しい地域にやがて及んでゆく。だから、今豊かな人間にさらに国富を集中することが、最終的に全員が豊かになるための最短の道なのだ、と。その結果が現在の中国の格差社会です。
安倍政権の政治もその流れに沿ったものです。安倍晋三自身は凡庸な政治家であり、特に際立った政治的見識があるわけではない。けれども、「すでに権力を持っている人間に権力を集中させる。すでに金を持っている人間に金を集中させる」という新自由主義的な経済理論と資質的に大変「なじみのいい」人物だった。合意形成も対話もしない。トップダウンで物事を決める。政策の適否は「次の選挙の当落」で決まるので、選挙に勝てば完全な信認を得たと見なしてよい。これはすべて株式会社のCEO(最高経営責任者)の考え方です。それがビジネスマンたちに選好されたのです。
■消えた議論
組織は一枚岩であるべきで、トップの指示に組織は整然と従うべきだというのは、いつのまにか日本の常識になってしまったようです。岡田克也氏が新代表に選ばれた民主党代表選の翌日のある新聞の社説ではこう書かれています。代表が決まった以上は党全体で岡田氏を盛り上げろと。党内でさまざまな議論があった以上、「議論をより深めて合意形成の道を探るべきだ」とは書かれていません。代表が決まった以上、そこに権限を集中させて、トップダウンに従うべきであり、そもそも民主党の支持率低下は党内の意見がまとまらなかったせいだ、と。
そんなことがいつから常識になったのか。自民党はかつて田中角栄と福田赳夫が「角福戦争」と呼ばれる15年に及ぶ党内闘争を展開してきました。日本政党史上「戦争」という名がついた党内闘争はこれだけしかありません。けれども、そのとき党内に意思一致がないことを否として、「自民党は一丸となれ」と説いたメディアがあることを私は記憶していません。むしろ党内派閥抗争が疑似的政権交代であったがゆえに自民党は長期政権を維持できたのだという話になっている。
党内の「戦争」はよいことで、党内不一致は悪いことだというメディアのダブルスタンダードを私はとがめたい。それはいつのまにか「政党もまた株式会社のような組織であるべきだ」という信憑(しんぴょう)を社説の書き手であるジャーナリスト自身が内面化してしまったということを意味しているからです。
市民レベルから対話と議論を積み上げて手作りした民主主義は日本にはありません。残念ながら、民主主義は連合国軍総司令部(GHQ)に与えられたものです。だからもろいのだと私は思います。身銭を切って守らなければ民主主義は簡単に崩壊する。
今、日本の諸制度から民主主義的なものが次第に放逐されつつあります。株式会社的な政治は一見すると効率的で、経済活動には有利なもののように見えます。けれども、繰り返し言いますが、株式会社は有限責任体であり、国民国家は無限責任体です。失政のツケは国民が何世代にもわたって払い続けなければならない。だから、すべての国民が、まだ生まれていない国民も含めて、国政の決定事項について「それは私の意思だ」という気持ちになれなくてはならない。
独裁政治の最大の欠陥は、独裁者が劇的な失政をした場合に、国民たちの誰一人その責任を取る気になれないということです。国として行った政策選択について「それは一独裁者のしたことであり、われわれ国民は関与していない」という言い訳が国内的には通じてしまう。これは国際的には通りません。そして、国民国家の失政は無限責任であるにもかかわらず、それを受け入れる国民主体が存在しないということになる。
国民主体というのは、先行世代の失敗をわがこととして引き受ける、あるいは同時代において自らは反対票を投じていても、合法的に選ばれた総理大臣がなしたことについては有責感を覚えるもののことです。しかし、独裁制では国民主体が立ち上がらない。
民主主義というのは効率的に物事を進めるための仕組みではありません。失敗したときに全員が自分の責任と受け止め、自分の責任の割り当てについては何とかしよう、と気持ちが向かうようになる仕組みのことなのです。
【神奈川新聞】
ついでに「内田樹の研究室」より:
2015.01.01
2015年の年頭予言
あけましておめでとうございます。
年末には「十大ニュース」、年頭には「今年の予測」をすることにしている(ような気がする)。ときどき忘れているかもしれないが、今年はやります。
今年の日本はどうなるのか。
「いいこと」はたぶん何も起こらない。
「悪いこと」はたくさん起こる。
だから、私たちが願うべきは、「悪いこと」がもたらす災禍を最少化することである。
平田オリザさんから大晦日に届いたメールにこう書いてあった。
「私は大学の卒業生たちには、『日本は滅びつつあるが、今回の滅びに関しては、できる限り他国に迷惑をかけずに滅んで欲しい』と毎年伝えています。来年一年が、少しでも豊かな後退戦になるように祈るばかりです。」
これから私たちが長期にわたる後退戦を戦うことになるという見通しを私は平田さんはじめ多くの友人たちと共有している。
私たちの国はいま「滅びる」方向に向かっている。
国が滅びることまでは望んでいないが、国民資源を個人資産に付け替えることに夢中な人たちが国政の決定機構に蟠踞している以上、彼らがこのまま国を支配し続ける以上、この先わが国が「栄える」可能性はない。
多くの国民がそれを拱手傍観しているのは、彼らもまた無意識のうちに「こんな国、一度滅びてしまえばいい」と思っているからである。
私はどちらに対しても同意しない。
国破れて山河あり。
統治システムが瓦解しようと、経済恐慌が来ようと、通貨が暴落しようと、天変地異やパンデミックに襲われようと、「国破れて」も、山河さえ残っていれば、私たちは国を再興することができる。
私たちたちがいますべき最優先の仕事は「日本の山河」を守ることである。
私が「山河」というときには指しているのは海洋や土壌や大気や森林や河川のような自然環境のことだけではない。
日本の言語、学術、宗教、技芸、文学、芸能、商習慣、生活文化、さらに具体的には治安のよさや上下水道や交通や通信の安定的な運転やクラフトマンシップや接客サービスや・・・そういったものも含まれる。
日本語の語彙や音韻から、「当たり前のように定時に電車が来る」ことまで含めて、私たち日本人の身体のうちに内面化した文化資源と制度資本の全体を含めて私は「山河」と呼んでいる。
外形的なものが崩れ去っても、「山河」さえ残っていれば、国は生き延びることができる。
山河が失われれば、統治システムや経済システムだけが瓦礫の中に存続しても、そんなものには何の意味もない。
今私たちの国は滅びのプロセスをしだいに加速しながら転がり落ちている。
滅びを加速しようとしている人たちがこの国の「エリート」であり、その人たちの導きによってとにかく「何かが大きく変わるかもしれない」と期待して、あまり気のない喝采を送っている人たちがこの国の「大衆」である。
上から下までが、あるものは意識的に、あるものは無意識的に、あるものは積極的に、あるものは勢いに負けて、「滅びる」ことを願っている。
そうである以上、蟷螂の斧を以てはこの趨勢は止められない。
自分の手元にあって「守れる限りの山河」を守る。
それがこれからの「後退戦」で私たちがまずしなければならないことである。
それが「できることのすべて」だとは思わない。
統治機構や経済界の要路にも「目先の権力や威信や財貨よりも百年先の『民の安寧』」を優先的に配慮しなければならないと考えている人が少しはいるだろう。
彼らがつよい危機感をもって動いてくれれば、この「後退戦」を別の流れに転轍を切り替えることはあるいは可能かも知れない。
けれども、今の日本のプロモーションシステムは「イエスマンしか出世できない」仕組みになっているから、現在の統治機構やビジネスのトップに「長期にわたる後退戦を戦う覚悟」のある人間が残っている可能性は限りなくゼロに近い。
だから、期待しない方がいい。
とりあえず私は期待しない。
この後退戦に「起死回生」や「捲土重来」の秘策はない。
私たちにできるとりあえず最良のことは、「滅びる速度」を緩和させることだけである。
多くの人たちは「加速」を望んでいる。
それが「いいこと」なのか「悪いこと」なのかはどうでもいいのだ。早く今のプロセスの最終結果を見たいのである。
その結果を見て、「ダメ」だとわかったら、「リセット」してまた「リプレイ」できると思っているのである。
でも、今のような調子ではリセットも、リプレイもできないだろう。
リプレイのためには、その上に立つべき「足場」が要る。
その足場のことを私は「山河」と呼んでいるのである。
せめて、「ゲームオーバー」の後にも、「リプレイ」できるだけのものを残しておきたい。
それが今年の願いである。
時代の正体〈57〉わたしたちの国はいま(1) 思想家・内田樹さんに聞く 「よみがえる死者たち」2015.01.30 11:30:00
内田樹さん
私たちの国はいま「滅びる」方向に向かっている-。2015年が明けた1月1日、思想家の内田樹さんはブログにそうつづった。先の大戦の終結から70年、戦後民主主義が揺らぎ、経済成長の先行きに限界が見える中、日本はいま破局へ向かう途上のどの地点にいるのだろうか。
いま、世界的な現象として同時多発的に排外主義が跋扈(ばっこ)している。興味深いのは、ドイツ、フランス、日本という「敗戦の総括をうまくできていない国」において、それが顕著だということです。死者が死に切っていないせいで、「生煮えの死者」がよみがえっている現象のように私には見えます。
例えばフランスは、イスラム過激派によるテロは自分たちの「自由、平等、博愛」という民主主義の原理への攻撃だとしていますが、その言い分にはいささか無理があると思います。
フランスは戦勝国のような顔をして戦後世界に登場しましたが、事実上は敗戦国です。対独講和後成立したヴィシー政府は「自由、平等、博愛」の原理を一度捨て、「労働、家族、祖国」を掲げて、ナチスの後方支援をし、国内ではユダヤ人狩りをし、共産主義者やレジスタンス運動を弾圧しました。
でも、フランスはそうした過去を戦後きちんと総括していません。シャルル・ドゴール率いる自由フランスとレジスタンスが最終的にドイツ軍を敗走させたことをもって「フランスが勝利した」という物語を作り出した。そして、ヴィシー政府の官僚たちの多くは訴追されることもなく戦後フランス社会のエリート層を形成しました。
この「敗戦の否認」ゆえに、フランス人は自分たちが民主的な手続きを経て、自らの選択でファシスト政権を成立させたという歴史的事実に向き合うことをしていません。自分たちの国の政治文化のうちにそのような排外的・暴力的な要素が内在していることを認めない。
しかし、そうやって抑圧された政治的幻想は幽霊のように繰り返しよみがえってくる。それが「生煮えの死者」です。昨年6月の欧州議会選挙で、極右の国民戦線が第1党に躍進しましたが、別に前代未聞のことが起きたわけではありません。抑圧されていた過去がよみがえってきたのです。
■語らぬ戦犯
ドイツも事情は似ています。ドイツは戦争責任のすべてをナチスに押しつけて、ドイツ国民を免罪しようとした。
事実、ナチスに反対したドイツ人はたくさんいましたし、ヒトラー暗殺計画も繰り返し企てられました。だから、ドイツ国民とナチスは「別物」であり、戦争責任・敗戦責任はあげてナチスという一政党にあるという物語は戦後のドイツ人たちにとっては説得力を持つものでした。そうやって国民は部分的に戦争責任を解除された。
ドイツの歴代大統領は欧州各地を訪れるたびにナチスの犯罪を謝罪していますが、それはかつてドイツを強権的に支配していた独裁者の罪についての謝罪なのか、そのような独裁者を歓呼の声で迎えたドイツ国民の罪についての謝罪なのか、必ずしもはっきりとはしていません。
しかし、自己欺瞞(ぎまん)はいずれ破綻をきたします。フランスではアルジェリア戦争以来、反イスラムの政治的潮流は絶えたことがありません。ドイツもネオナチには厳罰で臨みますが、その一方でトルコ系移民は構造的に排斥されている。イタリアでもネオファシストの運動は戦後一貫して社会的影響力を失ったことがありません。
では、日本における敗戦の総括はどうだったか。戦争責任を追及した東京裁判は日本人自身によるものではありません。戦犯の指名も、罪状も、量刑も連合国軍総司令部(GHQ)の占領政策に沿う形で行われました。最終的に何人かがみせしめ的に処刑され、占領政策に利用できそうな人間は釈放されて政治家として戦後の「対米従属」戦略を担いました。「本当は何があったのか」についての調査は早々と打ち切られました。
戦犯たちの誰一人「戦争目的は何で、どのように戦争計画を立案し、どのように戦い、どのように敗れたのか」を戦争主体の立場から語ることができなかったからです。だから、私たちはいまだにあの戦争がなぜ始まったのか、本当はそのとき何があったのかを知らないままなのです。知らないまま一応つじつまのあった「敗戦についての物語」を採用して、それを信じているふりをしている。
■物語の破綻
日本を含めた敗戦国は、戦争と敗戦について、それぞれに物語を作りました。その作話に際して、恥ずべき事実や、受け入れがたい事実は隠蔽(いんぺい)されました。仕方がないといえば仕方がない。そのような事実に向き合うだけの精神力も体力も敗戦国民には望むべくもないからです。
戦後しばらくはどの国でもそういう物語は一定期間有効でした。でも、短期間に無理やり作った話ですから、いずれボロが出る。それが戦後70年たって噴出してきた。私はそう見立てています。
1980年代からの歴史修正主義や移民排斥や極右政党の進出や反イスラムは、この敗戦のときに作った物語の破綻として理解できます。敗戦の「物語」にうまく収まり切らないものが物語の隙間からしみ出している。「ガス室はなかった」とか「南京虐殺はなかった」といった主張をなす歴史修正主義者を駆り立てているのは、実は「忘れたことにしている話」がもたらす破壊への恐怖です。物語に収まりきらない歴史的事実が明かされることがどれほどの破壊力を持つかを彼らは実は知っているのです。
日本の戦争責任については東京裁判とサンフランシスコ講和条約でもう話は済んでいると言う人たちがいます。日韓条約を結び、日中共同声明も発表した。いまさら古い話を蒸し返すなと。しかし、戦争については「本当のところはどうだったのか」という問いがある程度時間がたつと、再び提出されてくることは避けがたいのです。国際法上戦後処理は済んだと言い張っても、そのときに不都合なことを隠蔽するために使った「物語」の賞味期限が切れてしまうと、塗り固めたはずの傷口からまた血膿(ちうみ)が噴き出してくる。
加害の事実は忘れやすいが、被害の事実は忘れられない。「僕らは忘れたから、君らも忘れてくれ」というロジックは通らない。「君たちは忘れてもいいけれど、僕らは忘れないよ」と加害の事実を記憶し続けるという構えでなければ隣国との和解は成立しないでしょう。
これから私たちはどうすればいいのか。日本人が敗戦のときに作った「物語」を一度「かっこに入れて」、あらためて「本当は何があったのか」という問いを冷静に中立的に主題化すべきだと私は思います。私たちはいわば弔われなかった死者たちの上に家を建てて住んでいます。だから、死者たちは繰り返し化けて出る。気の重い仕事ですけれど、私たちは家の床下から腐乱死体を掘り出して、彼らの死の経緯をもう一度語り直し、そして再び荼毘(だび)に付して魂の安らぎを願うしかないのです。
内田樹(うちだ・たつる) 神戸女学院大名誉教授、武道家、多田塾甲南合気会師範。神戸市で武道と哲学研究のための学塾「凱風館」を主宰。専門はフランス現代思想、武道論、教育論など。主著に「ためらいの倫理学」「街場の戦争論」「日本辺境論」など。
【神奈川新聞】
時代の正体〈58〉わたしたちの国はいま(2) 思想家・内田樹さんに聞く 「民主主義とカネの相性」2015.01.31 09:26:00
いま、「わが国は滅びる方へ向かっている」と口にしても、むきになって反論する人はそういません。ビジネスマンだって、もう経済成長がないことは分かっています。
一時だけ投資家たちがあぶく銭を求めて集まるカジノ資本主義的な事態はどこかの国でまだ何度か起こるでしょうけれど、しょせんはバブルです。歴史過程としての資本主義はもう末期段階を迎えている。そのことは口では経済成長を唱えている人だって分かっているはずです。
にもかかわらず、惰性に任せて「右肩上がり」の成長モデルに合わせて社会制度は改変され続けています。
教育、医療、地方自治、どれも経済成長モデルに最適化したかたちへの改変が強力に進められている。資本主義の仕組み自体、賞味期限が切れて終わりかけているのに、事態がさっぱり好転しないのは「いまのシステムが成長に特化したかたちになっていないからだ」「市場原理の導入が足りないからだ」と解釈する人たちが、終わりつつあるシステムに最適化するという自殺的な制度改革を進めている。
教育がそうです。学校教育法の改正で、大学は一気に株式会社化されました。教授会民主主義が事実上廃絶され、権限が学長に集中する仕組みになった。
株式会社のようにトップダウンで組織が運営され、経営の適否は単年度ごとに数値的に開示される。志願者数、偏差値、就職率、科研採択数、論文提出数、英語による授業時数、外国人教員数といった数値で大学が格付けされ、教育資源が傾斜配分される。営利企業と同じロジックです。
しかし、その結果、いま国公立大学全体の空洞化が急速に進行しています。すでに東大からも高名な教授たちが逃げ出している。当然だと思います。予算は削られ、労働負荷は増え、権限は縮小されたあげくに「さらなる改革努力を」と言われても、もう「笛吹けど」足が動きません。四半世紀休みなく続いた制度改革に教員たちはほとほと疲れ切っている。この後、日本の国公立大学の研究教育機関としての質は低下するばかりでしょう。
国内の大学の質の低下が進めば、国内での学歴では「使いものにならない」ということになる。当然、エリートを目指す人々は海外での学歴を求めるようになる。すでに富裕層は中等教育段階から子どもを海外の寄宿制インターナショナルスクールに送り出しています。その経済的負担に耐えられる富裕層にしかキャリアパスが開かれないのです。
医療も同じです。医療は商品であり、患者は消費者だという市場原理を導入したせいで医療崩壊が起きました。
どこでも超富裕層が最後に求めるのはアンチエイジング、不老不死です。そのためには天文学的な金額を投じることを惜しまない。それなら医療者は医療資源を超富裕層の若返りと延命のためだけに集中させた方が、きつくて安い保険医療に従事するより合理的です。経済格差がそのまま受けられる医療の格差に反映してしまう。米国では金持ちは最高級の医療を受けられ、保険医療や無保険者はレベルの低い医療に甘んじなければならなくなっている。
■株式会社精神
米国のように所得上位1%に国民所得の20%が集中するという格差拡大の流れは市場に委ねている限り、日本でも止まることはないでしょう。
そもそも株式会社は民主主義とは無縁のものです。
経営者が判断したことに従業員はあらがうことができない。当然にも、従業員の過半の同意を得なければ経営方針が決まらないというような企業はありません。すぐつぶれてしまう。従業員も経営判断の適否を判断する責任があるとは思っていない。経営判断の適否はすべてマーケットが判断してくれるからです。マーケットはビジネスにとっての最終審級です。だから、経営判断が民主的であろうと非民主的であろうと、そんなことはマーケットの決定には何も関与しません。
株式会社は右肩上がりを前提にしていますが、しかし、江戸時代までの日本では現状維持、定常再生産が社会の基本でした。
近代化を遂げた後も、久しく農村人口の5割を超えていた。農林水産業は自然が本来持つ生産力を維持するものです。自然は右肩上がりに無限にその生産力を上げるということがありません。何よりも生産力の持続可能性が重要だった。100年後の孫の世代のために木を植えるといった植物的な時間の流れに沿って、社会制度も設計されていた。そのような風儀は1950年代まで残っていました。
しかし60、70年代の高度成長期に農村人口が都市に移動し、サラリーマンが支配的な労働形態になりました。今の日本では株式会社のサラリーマンが標準的な人間ですから、「株式会社従業員マインド」で国家の問題も眺めるようになった。それはつまり植物的なゆったりとした時間の流れの中にはいないということです。四半期ごとの売り上げや収益に一喜一憂し、右肩上がり以外の生き方はありえないという思い込みが国民的に共有されている。
だから、もう成長はないという事実を突きつけられても、それを信じることができない。別のプランが立てられない。とりあえず昨日まで続けてきたことをさらに強化したかたちで明日も続ける。原発を再稼働し、リニア新幹線を造り、カジノを造りといったことをまた繰り返そうとしています。
もちろんそんなことをしても成長はない。それは学校が悪い、自治体が悪い、ついには民主主義が悪いというふうに責任転嫁される。それが現状です。
■歴史的転換点
振り返れば、関西電力大飯原発の再稼働は歴史的な瞬間でした。あのとき経済の論理に国民国家が屈服した。国土の保全と国民の健康かグローバル企業の収益増大かという二者択一で後者を選んだのです。
再稼働を要求した財界の言い分はこうでした。原発を止めたせいで電力価格が上がり、製造コストが上がり、国際競争力が落ちた。再稼働を認めないのなら生産拠点を海外に移す。そうなれば国内の雇用は失われ、地域経済は崩壊し、法人税収も減る。それでいいのか、と。この脅しに野田佳彦政権は屈した。
しかし、グローバル企業はもはや厳密には日本の企業とはいえません。株主の多くは海外の機関投資家、CEO(最高経営責任者)も従業員も外国人、生産拠点も海外という企業がどうして「日本の企業」を名乗って、国民国家からの支援を要求できるのか。
もう一度原発事故が起きたら、どうなるでしょう。彼らは自分たちの要請で再稼働させたのだから、除染のコストは負担しますと言うでしょうか。雇用確保と地域振興のため、日本に踏みとどまると言うでしょうか。そんなことは絶対ありえない。あっという間に日本を見捨てて海外へ移転してしまうでしょう。
利益だけは取るけれど、責任は取らない。コストはできる限り外部化するというのが「有限責任」体である株式会社のロジックです。
民主主義とグローバル資本主義は相性が悪い。民主主義と金もうけは残念ながら両立しません。そして昨年の総選挙の争点は、実は「民主主義とカネのどちらがいい?」という問いだったのです。その問いに日本の有権者がどう答えたのかはご存じの通りです。
【神奈川新聞】
時代の正体〈59〉わたしたちの国はいま(3) 思想家・内田樹さんに聞く 「国家の運営は無限責任」2015.02.01 12:30:00
3・11をきっかけにこの国は変わると思っていました。市場原理に任せて経済成長を目指すのは無理だと気づき、相互扶助の精神に基づいた、もう少し手触りが温かく、暮らしやすい世の中になっていくだろうと思っていました。メディアでもそういう論調が多かったように思います。
「絆」というのも決して薄っぺらな修辞ではなく、同胞は困っているときには助け合わなければいけないという「常識」がよみがえったように思いました。でも、震災半年後くらいから、そういう気分が拭い去るように消えて、「やっぱり金がなければ話にならない。経済成長しかない」という話にまた舞い戻ってしまった。
国土が汚染され、半永久的に居住不能になるかもしれないという国民的危機に遭遇したにもかかわらず、またぞろ懲りずに原発再稼働の話が持ち出されてきました。理由は「電力コストの削減」、それだけです。国民は「命の話」をしているときに、政府は「金の話」をしている。この危機感の希薄さに私は愕然(がくぜん)とします。
株式会社というのは18世紀の英国に発祥したまだ歴史の浅い制度です。その特徴は「有限責任」ということです。株式会社はどんな経営の失敗をしても、それが引き受ける最大の責任は「倒産」です。株券が紙くずになって出資者は丸損をしますが、それ以上の責任を社員(株主)は問われることがありません。
もう一つの特徴は「コストの外部化」ということです。金もうけに特化した仕組みですから、できるだけコストは「誰か」に押し付ける。原発を稼働させて製造コストをカットし、新幹線や高速道路を造って流通コストをカットし、公害規制を緩和させて環境保護コストをカットし、賃金を抑制して人件費コストをカットし、「即戦力」を大学に要請して人材育成コストをカットする。コストを最小化し、利益を最大化するのが株式会社の仕組みです。
東京電力がまさにそうです。福島第1原発で国土に深い傷を与え、10万人を超える人々が故郷に帰れない状態をつくり出しながら、誰一人刑事訴追されていない。日本国民は国土を汚染され、汚染された国土を除染するコストを税によって負担するというかたちで二重に東電の「尻拭い」を強いられています。
しかし、有限責任の組織体というのは、実際にはほとんど存在しません。米大統領だったジョージ・W・ブッシュがそうだったように、国家を株式会社のように経営したいと公言する政治家がいますが、彼らは国家は無限責任だということを忘れている。国家の犯す失政は「じゃあ、倒産します」では済まない。侵略戦争で他国民の恨みを買い、揚げ句に敗戦で国土を失うというような失政をした場合、その「ツケ」を国民は半永久的に払い続けなければならない。
沖縄が米軍基地で埋め尽くされているのも、北方領土が返還されないのも、中国や韓国から謝罪要求が終わらないのも、70年前の失政の負債が「完済されていない」と他国の人々が思っているからです。彼らが「敗戦の負債は完済された。もう日本には何も要求しない」と言ってくれるまで何十年、何世紀かかるかわからない。人間の世界は普通そうなのです。株式会社の方が例外的なのです。
■株式会社化
株式会社の仕組みを国家運営に適用できると主張している人たちが依拠しているのは「トリクルダウン理論」です。新自由主義者の言う「選択と集中」です。経済活動をしている中で一番「勝てそうなセクター(分野)」にある限りの国民資源を集中させる。そこが国際競争を勝ち抜いて、シェアを取って、大きな収益を上げたら、そこからの余沢が周りに「滴り落ちる(トリクルダウン)」という考え方です。韓国は「勝つ」ためにヒュンダイ、サムスン、LGといった国際競争力のある企業に資源を集中させて、農林水産業や教育や福祉のための資源を削りました。競争力のないセクターは「欲しがりません勝つまでは」という忍耐を要求された。
中国のトウ小平の先富論も同じものです。沿海部に資本と技術と労働者を集中させ、経済拠点を造りました。稼げるところがまず稼ぐ。その余沢が内陸部の貧しい地域にやがて及んでゆく。だから、今豊かな人間にさらに国富を集中することが、最終的に全員が豊かになるための最短の道なのだ、と。その結果が現在の中国の格差社会です。
安倍政権の政治もその流れに沿ったものです。安倍晋三自身は凡庸な政治家であり、特に際立った政治的見識があるわけではない。けれども、「すでに権力を持っている人間に権力を集中させる。すでに金を持っている人間に金を集中させる」という新自由主義的な経済理論と資質的に大変「なじみのいい」人物だった。合意形成も対話もしない。トップダウンで物事を決める。政策の適否は「次の選挙の当落」で決まるので、選挙に勝てば完全な信認を得たと見なしてよい。これはすべて株式会社のCEO(最高経営責任者)の考え方です。それがビジネスマンたちに選好されたのです。
■消えた議論
組織は一枚岩であるべきで、トップの指示に組織は整然と従うべきだというのは、いつのまにか日本の常識になってしまったようです。岡田克也氏が新代表に選ばれた民主党代表選の翌日のある新聞の社説ではこう書かれています。代表が決まった以上は党全体で岡田氏を盛り上げろと。党内でさまざまな議論があった以上、「議論をより深めて合意形成の道を探るべきだ」とは書かれていません。代表が決まった以上、そこに権限を集中させて、トップダウンに従うべきであり、そもそも民主党の支持率低下は党内の意見がまとまらなかったせいだ、と。
そんなことがいつから常識になったのか。自民党はかつて田中角栄と福田赳夫が「角福戦争」と呼ばれる15年に及ぶ党内闘争を展開してきました。日本政党史上「戦争」という名がついた党内闘争はこれだけしかありません。けれども、そのとき党内に意思一致がないことを否として、「自民党は一丸となれ」と説いたメディアがあることを私は記憶していません。むしろ党内派閥抗争が疑似的政権交代であったがゆえに自民党は長期政権を維持できたのだという話になっている。
党内の「戦争」はよいことで、党内不一致は悪いことだというメディアのダブルスタンダードを私はとがめたい。それはいつのまにか「政党もまた株式会社のような組織であるべきだ」という信憑(しんぴょう)を社説の書き手であるジャーナリスト自身が内面化してしまったということを意味しているからです。
市民レベルから対話と議論を積み上げて手作りした民主主義は日本にはありません。残念ながら、民主主義は連合国軍総司令部(GHQ)に与えられたものです。だからもろいのだと私は思います。身銭を切って守らなければ民主主義は簡単に崩壊する。
今、日本の諸制度から民主主義的なものが次第に放逐されつつあります。株式会社的な政治は一見すると効率的で、経済活動には有利なもののように見えます。けれども、繰り返し言いますが、株式会社は有限責任体であり、国民国家は無限責任体です。失政のツケは国民が何世代にもわたって払い続けなければならない。だから、すべての国民が、まだ生まれていない国民も含めて、国政の決定事項について「それは私の意思だ」という気持ちになれなくてはならない。
独裁政治の最大の欠陥は、独裁者が劇的な失政をした場合に、国民たちの誰一人その責任を取る気になれないということです。国として行った政策選択について「それは一独裁者のしたことであり、われわれ国民は関与していない」という言い訳が国内的には通じてしまう。これは国際的には通りません。そして、国民国家の失政は無限責任であるにもかかわらず、それを受け入れる国民主体が存在しないということになる。
国民主体というのは、先行世代の失敗をわがこととして引き受ける、あるいは同時代において自らは反対票を投じていても、合法的に選ばれた総理大臣がなしたことについては有責感を覚えるもののことです。しかし、独裁制では国民主体が立ち上がらない。
民主主義というのは効率的に物事を進めるための仕組みではありません。失敗したときに全員が自分の責任と受け止め、自分の責任の割り当てについては何とかしよう、と気持ちが向かうようになる仕組みのことなのです。
【神奈川新聞】
ついでに「内田樹の研究室」より:
2015.01.01
2015年の年頭予言
あけましておめでとうございます。
年末には「十大ニュース」、年頭には「今年の予測」をすることにしている(ような気がする)。ときどき忘れているかもしれないが、今年はやります。
今年の日本はどうなるのか。
「いいこと」はたぶん何も起こらない。
「悪いこと」はたくさん起こる。
だから、私たちが願うべきは、「悪いこと」がもたらす災禍を最少化することである。
平田オリザさんから大晦日に届いたメールにこう書いてあった。
「私は大学の卒業生たちには、『日本は滅びつつあるが、今回の滅びに関しては、できる限り他国に迷惑をかけずに滅んで欲しい』と毎年伝えています。来年一年が、少しでも豊かな後退戦になるように祈るばかりです。」
これから私たちが長期にわたる後退戦を戦うことになるという見通しを私は平田さんはじめ多くの友人たちと共有している。
私たちの国はいま「滅びる」方向に向かっている。
国が滅びることまでは望んでいないが、国民資源を個人資産に付け替えることに夢中な人たちが国政の決定機構に蟠踞している以上、彼らがこのまま国を支配し続ける以上、この先わが国が「栄える」可能性はない。
多くの国民がそれを拱手傍観しているのは、彼らもまた無意識のうちに「こんな国、一度滅びてしまえばいい」と思っているからである。
私はどちらに対しても同意しない。
国破れて山河あり。
統治システムが瓦解しようと、経済恐慌が来ようと、通貨が暴落しようと、天変地異やパンデミックに襲われようと、「国破れて」も、山河さえ残っていれば、私たちは国を再興することができる。
私たちたちがいますべき最優先の仕事は「日本の山河」を守ることである。
私が「山河」というときには指しているのは海洋や土壌や大気や森林や河川のような自然環境のことだけではない。
日本の言語、学術、宗教、技芸、文学、芸能、商習慣、生活文化、さらに具体的には治安のよさや上下水道や交通や通信の安定的な運転やクラフトマンシップや接客サービスや・・・そういったものも含まれる。
日本語の語彙や音韻から、「当たり前のように定時に電車が来る」ことまで含めて、私たち日本人の身体のうちに内面化した文化資源と制度資本の全体を含めて私は「山河」と呼んでいる。
外形的なものが崩れ去っても、「山河」さえ残っていれば、国は生き延びることができる。
山河が失われれば、統治システムや経済システムだけが瓦礫の中に存続しても、そんなものには何の意味もない。
今私たちの国は滅びのプロセスをしだいに加速しながら転がり落ちている。
滅びを加速しようとしている人たちがこの国の「エリート」であり、その人たちの導きによってとにかく「何かが大きく変わるかもしれない」と期待して、あまり気のない喝采を送っている人たちがこの国の「大衆」である。
上から下までが、あるものは意識的に、あるものは無意識的に、あるものは積極的に、あるものは勢いに負けて、「滅びる」ことを願っている。
そうである以上、蟷螂の斧を以てはこの趨勢は止められない。
自分の手元にあって「守れる限りの山河」を守る。
それがこれからの「後退戦」で私たちがまずしなければならないことである。
それが「できることのすべて」だとは思わない。
統治機構や経済界の要路にも「目先の権力や威信や財貨よりも百年先の『民の安寧』」を優先的に配慮しなければならないと考えている人が少しはいるだろう。
彼らがつよい危機感をもって動いてくれれば、この「後退戦」を別の流れに転轍を切り替えることはあるいは可能かも知れない。
けれども、今の日本のプロモーションシステムは「イエスマンしか出世できない」仕組みになっているから、現在の統治機構やビジネスのトップに「長期にわたる後退戦を戦う覚悟」のある人間が残っている可能性は限りなくゼロに近い。
だから、期待しない方がいい。
とりあえず私は期待しない。
この後退戦に「起死回生」や「捲土重来」の秘策はない。
私たちにできるとりあえず最良のことは、「滅びる速度」を緩和させることだけである。
多くの人たちは「加速」を望んでいる。
それが「いいこと」なのか「悪いこと」なのかはどうでもいいのだ。早く今のプロセスの最終結果を見たいのである。
その結果を見て、「ダメ」だとわかったら、「リセット」してまた「リプレイ」できると思っているのである。
でも、今のような調子ではリセットも、リプレイもできないだろう。
リプレイのためには、その上に立つべき「足場」が要る。
その足場のことを私は「山河」と呼んでいるのである。
せめて、「ゲームオーバー」の後にも、「リプレイ」できるだけのものを残しておきたい。
それが今年の願いである。