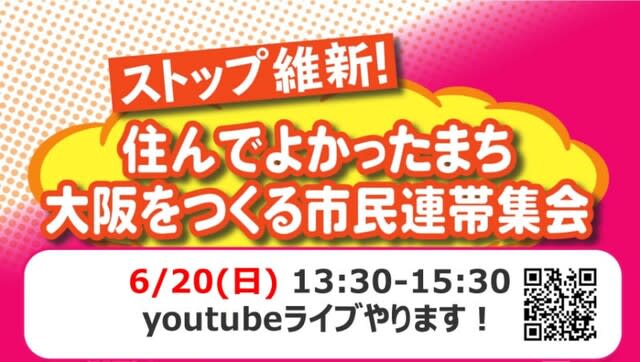150215 衆参両院の「テロ非難決議」を非難する!「テロの本質」を真面目に語る政治家はいないのか!
真面目に「テロの本質」を考えれば、その原因が、決して宗教の違いにあるのではなく、世界的に広がる富の偏在、極端な格差拡大、差別構造の継承、及びパレスチナ問題、それらによる<若者たちの絶望>にあることは、実は誰もがわかっていることだろう! それを「世界には凶悪なテロリストが大勢いて、こいつらを叩き潰せばテロが無くなる」なんて話に無理やりすり替えている。誰も、「テロの本質が、日本・世界の社会構造が抱える富の偏在・格差の拡大及びパレスチナ問題の<野放し状態>にこそある」という本質を語らないし、見させようとしない。そして、凶悪なテロリストへの恐怖ばかりを煽りたてている。これはまさにオーウェルの「一九八四年」の世界と同じだ。今回の国会の「テロ非難決議」に社民党・共産党まで加わっていたのには、あきれ果てた。「誰も本質を見ようとしない。」「武力で世界中の<絶望した若者たち>を封じ込めるべきではないし、不可能だ!」
秋原葉月さん「Afternoon Cafe」ブログから
※(1)「もちろん、普通の人間は戦争を望まない。しかし、国民を戦争に参加させるのは、つねに簡単なことだ。とても単純だ。国民には攻撃されつつあると言い、平和主義者を愛国心に欠けていると非難し、国を危険にさらしていると主張する以外には、何もする必要がない。この方法はどんな国でも有効だ」byヘルマン・ゲーリング
※(2)いつの時代も大衆をファシズムに煽動する手口は同じ。なのに同じ手口に何度も騙されるのは過去に学んでいないから。格差を広げ、セイフティネットを破壊し、冷徹な自己責任論が横行する社会を継続させるのは簡単だ。今よりもっと格差を広げ、セイフティネットを破壊する政策をとればよい。そうすれば人々に自己責任論がもっと浸透し、草の根から勝手に右傾化してくれる。
150329 タガ外せば歯止め失う 長谷部恭男・早稲田大学教授/「未来志向」は現実逃避 杉田敦・法政大学教授
杉田 先日ドイツのメルケル首相が来日しました。戦後ドイツも様々な問題を抱えていますが、過去への反省と謝罪という「建前」を大切にし続けることで、国際的に発言力を強めてきた経緯がある。「建前」がソフトパワーにつながることを安倍さんたちは理解しているのでしょうか。
/ /長谷部 そもそも談話が扱っているのは、学問的な歴史の問題ではなく、人々の情念が絡まる記憶の問題です。記念碑や記念館、映画に結実するもので、証拠の有無や正確性をいくら詰めても、決着はつかない。厳密な歴史のレベルで、仮に日本側が中国や韓国の主張に反証できたとしても、問題はむしろこじれる。相手を論破して済む話ではないから、お互いがなんとか折り合いのつく範囲内に収めようと政治的な判断をした。それが河野談話です。
/ /杉田 談話の方向性や近隣との外交について「未来志向」という言い方がよくされますが、意図はどうあれ、それが過去の軽視という「見かけ」をもってしまえば、負の効果は計り知れない。安倍さんたちは、未来を向いて過去を振り払えば、政治的な自由度が高まると思っているのかもしれません。しかし政治の存在意義は様々な制約を踏まえつつ、何とか解を見いだしていくところにあります。政治的な閉塞(へいそく)感が強まる中で、自らに課せられているタガを外そうという動きが出てくる。しかし、それで万事うまくいくというのは、一種の現実逃避では。
/ /長谷部 合理的な自己拘束という概念が吹っ飛んでしまっている印象です。縛られることによってより力を発揮できることがある。俳句は5・7・5と型が決まっているからこそ発想力が鍛えられる。しかし安倍さんたちは選挙に勝った自分たちは何にも縛られない、「建前」も法律も憲法解釈もすべて操作できると考えているようです。
/ /杉田 俳句は好きな字数でよめばいいのだと。
/ /長谷部 あらゆるタガをはずせば、短期的には楽になるかもしれません。しかし、次に政権が交代したとき、自分たちが時の政府を踏みとどまらせる歯止めもなくなる。外国の要求を、憲法の拘束があるからと断ることもできない。最後の最後、ここぞという時のよりどころが失われてしまう。その怖さを、安倍さんたちは自覚すべきです。 =敬称略(構成・高橋純子)朝日新聞『考論』
0015 オルテガ「大衆の反逆 (桑名一博訳;久野収解説)」(白水社イデー選書;1930)評価5
以下は、オルテガ所論の久野収による抜粋の抜粋である:///
オルテガによれば、政治のなかで「共存」への意志を最強力に表明し、実行していく政治スタイルこそ、自由主義的デモクラシーである。共存は、強い多数者が弱い少数者に喜んで提供する自己主張、他者説得の権利である。敵、それも最も弱い敵とさえ、積極的に共存するという、ゆるがない決意である。/その意味で、人類の自然的傾向に逆行する深いパラドックス(逆説)であるから、共存を決意した人類が、困難に面してこの決意を投げ出すほうへ後退したとしても、それは大きな悲劇ではあっても、大きな不思議とするには当たらない。/「敵と共存し、反対者と共に政治をおこなう」という意志と制度に背を向ける国家と国民が、ますます多くなっていく1930年代、オルテガは、「均質」化された「大衆」人間の直接行動こそが、あらゆる支配権力をして、反対派を圧迫させ、消滅させていく動力になるのだという。なぜなら、「大衆」人間は、自分たちと異類の非大衆人間との共存を全然望んでいないからである。略。///
「大衆」人間は、自分たちの生存の容易さ、豊かさ,無限界さを疑わない実感をもち、自己肯定と自己満足の結果として、他人に耳を貸さず、自分の意見を疑わず、自閉的となって、他人の存在そのものを考慮しなくなってしまう。そして彼と彼の同類しかいないかのように振舞ってしまう。/彼らは、配慮も、内省も、手続きも、遠慮もなしに、「直接行動」の方式に従って、自分たちの低俗な画一的意見をだれかれの区別なく、押しつけて、しかも押しつけの自覚さえもっていない。/彼らは、未開人―未開人は宗教、タブー、伝統、習慣といった社会的法廷の従順な信者である―ではなく、まさに文明の洗礼を受けた野蛮人である。文明の生み出した余裕、すなわち、贅沢、快適、安全、便益の側面だけの継承者であり、正常な生存の様式から見れば、奇形としかいいようのないライフスタイルを営んでいる新人類である。略。///
「自分がしたいことをするためにこの世に生まれあわせて来た」とする傾向、だから「したいことは何でもできる」とする信仰は、自由主義の自由の裏面、義務と責任を免除してもらう自由にほかならない。/われわれは自由主義の生みだした、この「大衆」人間的自由、自己中心的自由に対し、他者と共存する義務と責任をもった自由を保全しなければならないが、一筋縄でいかないのは、この仕事である。(160626:イギリスEU離脱について思うところ=もみ=)