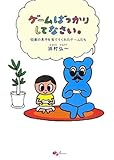今朝の「日経電子版」に「デジタル遺品」についての記事がありました。親戚が亡くなり、本人のスマホやパソコンが開けない、どのサブスクに入っていたかが分からない、などなど。デジタルならではの困ったことがいろいろあるそうです。
今年2月に亡くなった伯父の場合は、幸いデジタル関連で困ることが殆どありませんでした。本人も知らないで入っていた、スマホの通信料とは別途に払っていた月330円のサブスクは、携帯電話会社の方で止めることができました。10枚ほどあったクレジットカードは止められるものはすべて解約できました。ただ1つ、伯父の古いノートパソコンが残っていて、ずっと電源をオフのままにしています。妹がそのパソコンを欲しいというのですが、伯父のデータを抹消して引き継げるかどうかです。
母の場合もクレジットカードのローンはないし、デジタル関連のサブスクには入っていないし、株などもしていません。パソコンは勿論持っていませんし、スマホのPINは私が設定したので知っています。
問題なのは私自身。「日経電子版」と「Nikkei Asia」の購読料、「Amazonプライム」や「Microsoft 365」の年会費、「Nintendo Switch Online」の料金などなど…。こちらから解約の手続きをしない限り継続になってしまうものばかりです。
無料のものでも「X(旧Twitter)」とか「Facebook」などを止めないといけませんよね。ということは、「X」をしていることを母などに言わなくてはいけないのでしょうか。書きたい放題書いているし、それを見られてしまうと考えるだけで恥ずかしい…。
困ったことにクレジットカードの明細がデジタルでしか見られません。これは私本人でないとセキュリティの面から怖いのですが、亡くなったらどうなるのか。カードそのものは電話で解約できますが、サブスクの料金など明細がないと把握できずに困ることもあります。
せめてパソコンとスマホのPINをどこかに書いておくことだけはした方が良さそうですね。それらを知られないまま万が一私が亡くなったら、きっとサブスクの解約が困難でしょう。本人が亡くなっても、サブスクの料金は解約しない限り遺族が払わないといけないし、把握しないとかなり厄介ですね。
今年2月に亡くなった伯父の場合は、幸いデジタル関連で困ることが殆どありませんでした。本人も知らないで入っていた、スマホの通信料とは別途に払っていた月330円のサブスクは、携帯電話会社の方で止めることができました。10枚ほどあったクレジットカードは止められるものはすべて解約できました。ただ1つ、伯父の古いノートパソコンが残っていて、ずっと電源をオフのままにしています。妹がそのパソコンを欲しいというのですが、伯父のデータを抹消して引き継げるかどうかです。
母の場合もクレジットカードのローンはないし、デジタル関連のサブスクには入っていないし、株などもしていません。パソコンは勿論持っていませんし、スマホのPINは私が設定したので知っています。
問題なのは私自身。「日経電子版」と「Nikkei Asia」の購読料、「Amazonプライム」や「Microsoft 365」の年会費、「Nintendo Switch Online」の料金などなど…。こちらから解約の手続きをしない限り継続になってしまうものばかりです。
無料のものでも「X(旧Twitter)」とか「Facebook」などを止めないといけませんよね。ということは、「X」をしていることを母などに言わなくてはいけないのでしょうか。書きたい放題書いているし、それを見られてしまうと考えるだけで恥ずかしい…。
困ったことにクレジットカードの明細がデジタルでしか見られません。これは私本人でないとセキュリティの面から怖いのですが、亡くなったらどうなるのか。カードそのものは電話で解約できますが、サブスクの料金など明細がないと把握できずに困ることもあります。
せめてパソコンとスマホのPINをどこかに書いておくことだけはした方が良さそうですね。それらを知られないまま万が一私が亡くなったら、きっとサブスクの解約が困難でしょう。本人が亡くなっても、サブスクの料金は解約しない限り遺族が払わないといけないし、把握しないとかなり厄介ですね。