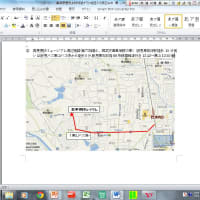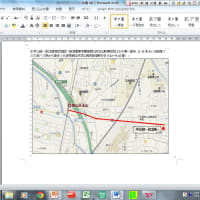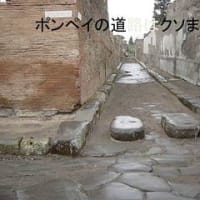多気北畠氏遺跡 第32次調査地現地視察

礎石が4基東西に並んでいる。担当者は柵列だと言うが、どうやって建てるのだろうか?判らん!!

一番の問題はこの石列。昨年この直ぐ西側で発見された石列(私は築地の基礎だと思っている)と1mも北にずれるという。ホント????配られた資料ですらずれているのとずれていないのがある。原因は「略測図だから」だそうだが、こんな大事なことを「略測」で報告するのは何故?不思議!
今日は朝から「多気北畠氏遺跡調査指導委員会」でした。9時から18時まで拘束されていたので、とても疲れました。この報告もいずれしなければいけないのですが(書いておかないといけないことが一杯あるのですが)、今日はまだ頭が整理できていないので、別にします。
ここのところずっと風邪気味なのですが、とてもとても忙しくて、これから先ももっともっと忙しくて・・・、まさに文字通り師走を実践しそうな勢いなのです。しかし、その師走前から既に助走が始まっていました。11月27日(今日多気)北畠氏遺跡調査指導委員会 28日亀山市史編集委員会 29日亀山市史古代史部会との個別協議 30日病院検査終了後歴博 12月1日歴博 12月3日講演会レジュメ提出 4日京都アスニーでの講演会 5日木簡学会 6日木簡学会 10日レジュメ提出2件 11日出前授業 12日四日市市歴博講演会 13日名張生涯学習講演会 19・20歴博研究会報告 24日~28日補講 アー死んでしまう!!
そんなこんなで、更新する気力も起こらない今日この頃なのですが、たまにはやっておかないと忘れられそうなので、助走期間の大宰府探訪をしばらく断続的にご紹介します。
11月20日から24日までYグチ大学のHY教授の科研費による研究会で大宰府とその周辺に展開する山城などを踏査する研究会に参加した。とても充実した研究会で、22日には各遺跡の調査担当者からの内容の濃い報告がなされ、熱心な討論が行われた。本来ならリアルタイムで報告するところだが、連日連夜の夜の宴でホテルに帰るとバタンキュ!!24日夜に津に戻ってきたのですがその後もハードスケジュールがぎっしり詰まり、やっと少しだけその報告を認める気力が起こってきたので書いてみることにする。
初日は本当は19日(木)なのだが、私は夕方まで授業があったのでやむなく二日目から参加した。初日は大宰府政庁やその周辺に展開する観世音寺、学校院地区、蔵司地区等々の中枢部を歩いたらしい。もっともこれらについてはこれまで大宰府の調査委員として何度も訪れていたので、今回はパスしても問題なかろうと判断もした。ただし蔵司地区は10月の委員会で現地を見学させていただいたのだが、その後発掘調査が進むということで、少し気がかりであった。ところが同行者に伺うと発掘はほとんど進んでいなかったということでホッとした。
二日目は太宰府の政庁周辺部で進む条坊の発見現場を歩いた。午前中は水城を中心に、午後は夕方暮れきるまで条坊を歩き回った。

水城へ至る官道を南から進んでいった。太宰府市教育委員会の丁寧な発掘調査によって、あちこちでこうした道路の確認調査が行われ、開発によって壊された時には看板が設置されている。
もちろんこれも以前に太宰府市教育委員会のNKさんのご案内で丁寧に歩いたところであり、その後の調査調査の進展により幾分か新しい成果が増えたものの、基本的な条坊の研究には影響がないということで、復習のつもりで歩いた。しかし新しい発想も得ることができた。感謝!!
案内者は今や太宰府条坊研究を一手に引き受けて先導するD教育委員会のIN氏である。近年の氏の研究によると太宰府条坊は基本的に90m四方の方眼を基準にしてその両側に道路敷きと宅地を割く分割型の条坊によって形成されているという。以前に訪ねたところも数多いのだが、どうしても自分の足で歩かないとその場のイメージを描きにくい。それにしても大半がマンションの一角にその痕跡を残しているに過ぎず、Iさんのご案内がなければ到底回れない遺構群であった。逆に言うと今回はIさんの御案内のお蔭で隅々まで回ることができた。感謝!!
最近の彼の持論は、90m方眼の地割りが7世紀段階からあったというものである。特に右郭と呼ばれる西側には7世紀代の遺物の集中する地域があり、今は宅地となっているところが多いが、かつては「通古賀」(とうのこが)等の地名研究からもこの地が筑前国の中心であったというのである。その地域を中心として.『周礼』考工記によるという説もある飛鳥の新城のような広大な条坊が整備されていたという。
「ウーン??なんぼiさんの説と言ってもそれはナインちゃうか!!」
こんなことを思いながら一緒に歩いた(詳しい説明や反論は22日の研究会の報告で)。要するに私は条坊が7世紀代には既に形成されていたという見解には従いかね流のだが、大宰府政庁を中心としてどの範囲にどんな遺構群があるのかを説明を聞きながら丹念に歩いた。

官道の跡がカラー舗装されて表示されている。こんな所をこの後次々と訪れることになる。
まだまだ先は長い。ひとまず今日はさわりだけで。
こいつをポチッと押して下さいね→