横浜の人は馬車道周辺も含め『関内』と呼びます。
もちろん、関内駅もあるからなのでしょうが、関内という呼び方の由来が紹介されていました。
横浜は言わずと知れた開港の街で、馬車道を含め、その開港場があった区域が『関内』です。

『関』は関門を意味しています。
開港場にあたる関門の内側(港側)が『関内』で、外側が『関外』と呼ばれました。
この『関内』と『関外』を分ける境目が、馬車道と伊勢佐木町の間にある吉田橋です。
吉田橋にある史蹟です。

吉田橋は、日本初めての鉄の橋とされています。
設計は、横浜公園にある胸像で紹介したリチャード・ブラントンです。

馬車道祭りでは馬とのふれあいコーナーもありました。

ポニーとの触れ合いは、子供たちに人気がありました。

歩道上に期間限定のワゴンセール「馬車道マルシェ」が開催されています。
マルシェとはフランス語で「市場」のことです。

馬車道に並行する道路上にある『馬車道十番館』です。
明治時代の西洋館を再現した赤レンガの洋館、馬車道十番館は、横浜を代表する老舗喫茶店です。
5階建ての馬車道十番館は、1階が喫茶室、2階が酒場、3階がグリル、4階と5階が宴会場になっています。

『馬車道十番館』の入口の横に、『牛馬飲水』と書かれた、昔の学校の水飲み場のようなものがあります。
大正時代は、陸上交通の主力は牛馬で、道路脇には給水のための牛馬飲水槽が設けられいて、ここの牛馬飲水槽は磯子区八幡橋際にあったものを移設したものです。

ここにもトッポが登場です。
馬車道通り沿いの横浜歴史博物館の前にも、『牛馬飲水』がありますが、あちらはレプリカのようです。

10年前のトッポの写真ですが、トッポパパがいつも写真を撮るので、カメラ目線は慣れたものでした。

『馬車道十番館』は、明治の先覚者でガス事業の創始者でもある高島嘉右衛門家の旧跡に当たります。
横浜開港の頃、海岸沿いに建てられた外国の商館は「一番館」「二番館」・・と呼ばれていました。
山手十番館は母体である、次回に紹介する『勝烈庵』の十番目の店として明治100年を記念して建てられたものです。
その後、「横浜十番館」として独立、馬車道十番館、別館馬車道十番館などを開館し、現在に至っています。

続く.....................................................................。
もちろん、関内駅もあるからなのでしょうが、関内という呼び方の由来が紹介されていました。
横浜は言わずと知れた開港の街で、馬車道を含め、その開港場があった区域が『関内』です。

『関』は関門を意味しています。
開港場にあたる関門の内側(港側)が『関内』で、外側が『関外』と呼ばれました。
この『関内』と『関外』を分ける境目が、馬車道と伊勢佐木町の間にある吉田橋です。
吉田橋にある史蹟です。

吉田橋は、日本初めての鉄の橋とされています。
設計は、横浜公園にある胸像で紹介したリチャード・ブラントンです。

馬車道祭りでは馬とのふれあいコーナーもありました。

ポニーとの触れ合いは、子供たちに人気がありました。

歩道上に期間限定のワゴンセール「馬車道マルシェ」が開催されています。
マルシェとはフランス語で「市場」のことです。

馬車道に並行する道路上にある『馬車道十番館』です。
明治時代の西洋館を再現した赤レンガの洋館、馬車道十番館は、横浜を代表する老舗喫茶店です。
5階建ての馬車道十番館は、1階が喫茶室、2階が酒場、3階がグリル、4階と5階が宴会場になっています。

『馬車道十番館』の入口の横に、『牛馬飲水』と書かれた、昔の学校の水飲み場のようなものがあります。
大正時代は、陸上交通の主力は牛馬で、道路脇には給水のための牛馬飲水槽が設けられいて、ここの牛馬飲水槽は磯子区八幡橋際にあったものを移設したものです。

ここにもトッポが登場です。
馬車道通り沿いの横浜歴史博物館の前にも、『牛馬飲水』がありますが、あちらはレプリカのようです。

10年前のトッポの写真ですが、トッポパパがいつも写真を撮るので、カメラ目線は慣れたものでした。

『馬車道十番館』は、明治の先覚者でガス事業の創始者でもある高島嘉右衛門家の旧跡に当たります。
横浜開港の頃、海岸沿いに建てられた外国の商館は「一番館」「二番館」・・と呼ばれていました。
山手十番館は母体である、次回に紹介する『勝烈庵』の十番目の店として明治100年を記念して建てられたものです。
その後、「横浜十番館」として独立、馬車道十番館、別館馬車道十番館などを開館し、現在に至っています。

続く.....................................................................。

















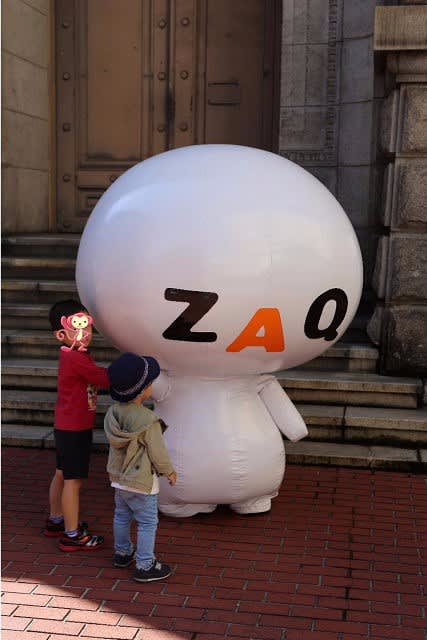










































































 青い目をした お人形は アメリカ生まれの セルロイド
青い目をした お人形は アメリカ生まれの セルロイド















































